第20回宮崎映画祭は台風接近のため、5作品をみただけであった。そのうちの三作品は時代の風を感じさせて関心を引いた。すはわち、映画が製作された時代を再訪させられ、終わった時代の意味を今、あらためて思い返され、そのうえで、現在をかんがえさせられるのであった。とくに1979年製作、長谷川和彦監督の東宝映画「太陽を盗んだ男」には、ぼく自身を根底からくつがえしてくれた70年代を再訪した思いにつつまれ、改めてその時代を思うのであった。
もっとも映画そのものは、三流の活劇でしかなく、ヒーローの沢田研二も彼を追う刑事役の菅原文太も、できの悪い脚本のせいか、凡庸な型にはまったキャラクターしか演じていなかった。大根役者としか見えなかった。ストーリー展開も、カーチェイス、ヘリコプター、自動小銃による銃撃戦、大爆発とどこかで見たシーンであった。それは、ハリウッド映画の焼き直しにみえ、ロケの撮影許可の限界内での撮影や、特撮の技術の稚拙さで、紙芝居じみてみえて、手に汗とにぎる興奮にいたらず、しらじらしさがつきまとうのであった。ゆえに三流といえるのである。この「太陽を盗んだ男」作品がもたらした時代感、ぼくはそれを70年代再訪といってみるが、これは予期しなかった映画ならではの時代再現をもたらすのであった。
画面を見始めるなり思えたのは、当時の街風景や、日常の暮らしのなんともいえない手触り感であった。街路に並ぶ商店、そこからみえる暮らし感が、素朴なのである。それを手触り感といった。それは人間くさい空間である。それにくらべると、現在はもう、国家や企業の権力や資本で、すみずみまでコントロールされ、個人の存在など芥子粒ほどの力しかないのではないかと、おもわされるかんじになってしまっている。それが、現在のぼくらの日常をおおっている疎外感である。まだコンピューターもパソコンも、インターネットも、無かった時代の暮らしは、これほど緩んでいたのであったのが、おどろきで見てとれたのである。
高校の物理の教師という主人公が、自分の部屋で、原爆をつくるという設定も、当時はそれほど違和感もなく、ありうろとおもえたのも、この時代相があったからであろう。沢田研二が演じるさえない教師が、ウランをどこから入手できたのかわからないが、それも超正確な球体にしていく。これをまるい金属容器に収め、まわり爆薬で囲む。爆薬に時限爆発想定をつける。爆発でウラン球は超球体のせいで、歪みの無い圧縮がくわわり、核分裂が起こり原子爆弾となるのだ。その工程が、ビニールシートのテントの張った中で、すすめられている。ようやく完成、緊張と疲労感でそばのベッドに倒れこむ主人公の飼い猫がでてきて、ウラン削り屑を舐めて死ぬ。ベッドで眺めている主人公、ビニールが放射能を防いでいるので安全というわけだ。福島原発の事故、その現場、その事後処理を知ったわれわれには、あまりにもばかばかしい原子爆弾製造である。だが、この設定を除くと、もう一点みえてくるものがある。これがなかったなら、およそ論じるに足らない映画であるが、この一点をみて、「太陽を盗んだ男」を論じざるをえなくなったのである。
この一点とは、この映画のふまじめさである。おおよそ70年代は、まじめすぎる時代であったともいえる。70年代の進歩的知識人、つまり学者、学生、文学者、芸術家のまじめさ、それは日本を革命しなければならぬという意識であった。60年安保も70年安保の反対闘争も国家権力で制圧されてしまい、革命もならず、その後革命の再起を図ろうという思考が論壇を賑わしていったが、効あるものもなく、78年8月には、論壇誌「展望」も終刊してしまった。その間、かれらは、革命の主題にかかわりつづけた。革命への道を、これまで歩いて来た道の上にあると信じて踏み外そうとしなかった。このまじめさがつづいていった。新しい料理をつくるのに、かって材料をこねくりまわすことで可能とする料理人の意識をすてられないまじめさがつついていったのだ。
この点からみれば、長谷川和彦監督の発想は、これらのまじめさをぶっちぎる憤りがみられるのである。まさに過去の材料の払い出しであった。それはぶち壊しであり、革命など、どうでもいいという視点である。撃たれても撃たれても不死身で追いかけてくる文太刑事を、ようやく殺害し、原子爆弾をふたたび取り戻した主人公は、これまでの「野球の完全中継」とか「ローリングストーンズ日本公演」とかの要求実現の材料とするのでなく、東京という国家の破壊に使用する気配を感じさせて映画は終わる。革命への情熱がテロリズムに変わりうるといったのは、マックスウエバーだが、情熱は臨界状況を超えると恐るべき反転をする。まじめさもだめだが、ばかげた発想もだめである。時代はそのことをかんがえさせる。今回の三作品をみると、やはりどうでもいい時代は終わりに近づき、あたらしい革命を模索できる時代がきつつあるのではないかと、おもえるのであった。
もっとも映画そのものは、三流の活劇でしかなく、ヒーローの沢田研二も彼を追う刑事役の菅原文太も、できの悪い脚本のせいか、凡庸な型にはまったキャラクターしか演じていなかった。大根役者としか見えなかった。ストーリー展開も、カーチェイス、ヘリコプター、自動小銃による銃撃戦、大爆発とどこかで見たシーンであった。それは、ハリウッド映画の焼き直しにみえ、ロケの撮影許可の限界内での撮影や、特撮の技術の稚拙さで、紙芝居じみてみえて、手に汗とにぎる興奮にいたらず、しらじらしさがつきまとうのであった。ゆえに三流といえるのである。この「太陽を盗んだ男」作品がもたらした時代感、ぼくはそれを70年代再訪といってみるが、これは予期しなかった映画ならではの時代再現をもたらすのであった。
画面を見始めるなり思えたのは、当時の街風景や、日常の暮らしのなんともいえない手触り感であった。街路に並ぶ商店、そこからみえる暮らし感が、素朴なのである。それを手触り感といった。それは人間くさい空間である。それにくらべると、現在はもう、国家や企業の権力や資本で、すみずみまでコントロールされ、個人の存在など芥子粒ほどの力しかないのではないかと、おもわされるかんじになってしまっている。それが、現在のぼくらの日常をおおっている疎外感である。まだコンピューターもパソコンも、インターネットも、無かった時代の暮らしは、これほど緩んでいたのであったのが、おどろきで見てとれたのである。
高校の物理の教師という主人公が、自分の部屋で、原爆をつくるという設定も、当時はそれほど違和感もなく、ありうろとおもえたのも、この時代相があったからであろう。沢田研二が演じるさえない教師が、ウランをどこから入手できたのかわからないが、それも超正確な球体にしていく。これをまるい金属容器に収め、まわり爆薬で囲む。爆薬に時限爆発想定をつける。爆発でウラン球は超球体のせいで、歪みの無い圧縮がくわわり、核分裂が起こり原子爆弾となるのだ。その工程が、ビニールシートのテントの張った中で、すすめられている。ようやく完成、緊張と疲労感でそばのベッドに倒れこむ主人公の飼い猫がでてきて、ウラン削り屑を舐めて死ぬ。ベッドで眺めている主人公、ビニールが放射能を防いでいるので安全というわけだ。福島原発の事故、その現場、その事後処理を知ったわれわれには、あまりにもばかばかしい原子爆弾製造である。だが、この設定を除くと、もう一点みえてくるものがある。これがなかったなら、およそ論じるに足らない映画であるが、この一点をみて、「太陽を盗んだ男」を論じざるをえなくなったのである。
この一点とは、この映画のふまじめさである。おおよそ70年代は、まじめすぎる時代であったともいえる。70年代の進歩的知識人、つまり学者、学生、文学者、芸術家のまじめさ、それは日本を革命しなければならぬという意識であった。60年安保も70年安保の反対闘争も国家権力で制圧されてしまい、革命もならず、その後革命の再起を図ろうという思考が論壇を賑わしていったが、効あるものもなく、78年8月には、論壇誌「展望」も終刊してしまった。その間、かれらは、革命の主題にかかわりつづけた。革命への道を、これまで歩いて来た道の上にあると信じて踏み外そうとしなかった。このまじめさがつづいていった。新しい料理をつくるのに、かって材料をこねくりまわすことで可能とする料理人の意識をすてられないまじめさがつついていったのだ。
この点からみれば、長谷川和彦監督の発想は、これらのまじめさをぶっちぎる憤りがみられるのである。まさに過去の材料の払い出しであった。それはぶち壊しであり、革命など、どうでもいいという視点である。撃たれても撃たれても不死身で追いかけてくる文太刑事を、ようやく殺害し、原子爆弾をふたたび取り戻した主人公は、これまでの「野球の完全中継」とか「ローリングストーンズ日本公演」とかの要求実現の材料とするのでなく、東京という国家の破壊に使用する気配を感じさせて映画は終わる。革命への情熱がテロリズムに変わりうるといったのは、マックスウエバーだが、情熱は臨界状況を超えると恐るべき反転をする。まじめさもだめだが、ばかげた発想もだめである。時代はそのことをかんがえさせる。今回の三作品をみると、やはりどうでもいい時代は終わりに近づき、あたらしい革命を模索できる時代がきつつあるのではないかと、おもえるのであった。











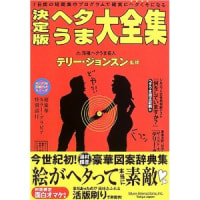












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます