初日(2013年8月24日)米映画「ムーンライズ・キングダム」を観た。その批評を書いてみたいのだが、安陪晋三首相がまたもスローガンを立ち上げ、大衆デマゴギーをしだしたのでこれを、取り上げて論じないかぎり他へすすめなく、動けないでいる。ここから始めたい。それは、首相のいつもの総動員体制のパーフォマンスである。今回は、わが国の各界を代表する(と、安陪首相が判断した)各分野の専門知識人を10人づつ諮問委員会として開催、その第一日が終わった。その模様をNHKや民間テレビが報道した。今後、各主題ごとに、6回開催されるというものだ。例のアベノミクスの命運を賭けた消費税増税の可否を問うものである。
この諮問委員会は、頭のいい、そして旬の(と、政権が選んだ)学者や経済人、その他の選良という者たちで、その頭数が数が多ければ多いほど、最良の結果がにじみ出るという、ワイン絞りの発想である。数は量となるが、絞って出るのは、間違いなくワインであり、金貨がでるわけではない。消費税を止めるか、影響を小さくするため、小出しにして、目的の8パーセントにするか、いきなり8パーセントとするかの回答だけに区分されていく。消費税というワインだけが滲み出るわけである。それが飲めるかどうか、飲めるはずだが、必要かどうか、ここが
問題だ。専門家や、選良でなくても、常識的に判断してみれば、消費税は増税しても景気減速、株価は下落、消費は冷え込む。消費増税を小細工で延期しても、財政政策への不信感で外国人ファンドは、ただちに日本国債の投売、価値の下がった国債の金利が高くなり、銀行金利も高くなり、景気は落ち込む。進んでも地獄、引いても奈落であると、想定できる。これこそ市場の現実的判断であると言われている。こういう状況の中で、安陪政権のやらねばならぬことは葡萄絞りをやっている場合かというのだ。首相自ら先頭に立つ、アベノミクスの反省であり、恥を恐れず軌道修正するか、破棄するかの英断的行動であろう。その上で、グローバルゼーションのなかで、日本だけの強国化をなりふり構わず実行して、アジア諸国の反発を買うよりも、仕立てに出る余裕、商人国家として、世界と日本の関係を再確認すべきであろう。商人はただで頭をさげているのではないのだ。これが経済戦略である。これを可能にしてきた日本国憲法の奇跡的力を、世界にも確認させ、日本国民も今こそ信じるべきではないのか。故に日本国内においては、国権の増大と自己権力の確立のための憲法改正を謀るのでなく、国民でなく、それぞれの個人、個人の自由と生存への強化を、実現すべきである。この基礎のうえにこそ消費税はあるのだ。だが、現況は闇雲に安陪スローガンの実現だけしか、方法はないかのようだ。そこは、もはや逃げ場のない茨の荒野、その踏破を、辻褄のあった逃げ道を学識経験者なら探せるという期待の諮問委員会は、もはやナンセンスである。かってケネディ政権、ジョンソン政権がベトナム戦争を継続・拡大への政策提言をしてきたのは、60年代米国を代表する最良の学者たちや文化人であった。一般に最良の最高の知の所有者と選ばれた者たちが、まちがった方向だけを示唆しつつけたのである。かれらのこの歴史的誤謬を、当時ニューヨークタイムズの記者であったデイヴィッド ハルバースタムが本「ベスト&ブライテスト」というドキュメントで、論文にしている。最良の選民であるがために、全体が見えない、権力の側に立ってしか、人間社会を把握できない偏向をもっていることえを、かれらの詳細な心理的動向、言説を記録、分析することで解き明かしている。今、わが国ではアベノミクスをめぐって、ベスト&ブライテストが、これから繰り返されていこうとしている。安陪スローガンを支える支点のひとつになることは間違いない。なぜ彼自身の外に支えが必要なのか、ぼくはこの行動こそ、安陪晋三首相の意識に潜む、彼自身も意識できない不安感であるのを、見る思いがするのである。
今はひどい時期である。このテレビ報道とどうじに、ぼくは幸運なことには、宮崎映画祭で、キネマ館の冷えすぎるエアコン(調整不可能という)を浴びながら映画を楽しみだしたという状況になった。ことしの映画祭は、まさに地球も日本もひっくりかえりそうな危機の年の映画祭であるのにである。その意味で第19回には総合タイトルに「Mのみらい」とあるのが、異様に目に付いた。これまでは総合タイトルにあまり意味を感じなかった。そう注意もはらわなかった。今回はちょっと違った。代表の臼井省司さんによるとMは movieのMであり、映画のデジタル化による変貌をもたらし、これからの未来への変化を見据えたいという意味もあるとある。つまりこの視点は、映画を見据える、きわめて具体的な行動につながっていると理解した。映画の変化を知る、これがひいては、映画祭を変貌させ、また宮崎の未来を開いていく可能性になる。市長の儀礼的挨拶(おそらく秘書課か広報課の職員の文章か)の「宮崎市の文化芸術の振興」とか「市民が主役の文化芸術活動の推進」とかいうスローガンでなくて未来を志向する小さな実行可能な現実が臼井さんには認められる。これがいい。
ではここで、本題に入ろう。「ムーンライズ・キングダム」はアメリカ北部の過疎地ニューイングランドの孤島の町で起きた少年と少女の恋物語である。冒頭からして、岩波絵本のページをめくるような感じにつつまれる。壁にかけられた子どもの絵画、縫いぐるみ、飛行機の模型、独楽、おもちゃの太鼓などに満ちた廊下や寝室、部屋へとカメラはパンすると、小学生低学年らしき子どもが、客間で今はもう消滅したレコードプレイヤーにSPレコードを架ける。と、それは交響曲の主題メロディーを、金管楽器、木管楽器、ピアノ、ハープ、弦楽器、ドラム別に、順番に演奏し、最後に全体でまとまるという音楽教材である。このクラシック音楽が、映画の導入部となっていた。なんでクラシック音楽なんだと思ったとたんに、はっと気づいたのは、美術、音楽、読書という欧米人の教養の基盤が、さりげなくならべられいることであった。加えて、自然は探求し、生きる絆としての開拓者の行動もあり、サバイバルの精神もくわえられる。ゆえに少年は本物の小銃をたずさへ、少女はサバイバルナイフを手にする。小銃は、追跡してきた仲間にむけて発砲され、少女はナイフでリーダの足を刺す。こういう教養の枠組み、行動の枠組みは、ごく自然であり、あらためて、ホワイト・アメリカンの意識にある行動原理におどろかされる。もちろん、これは伝統に帰れというような教訓的な映画ではない。教養を説く映画でもない。12歳の少年と少女が、駆け落ちをして結婚式を挙行するに至る、夢と希望実現へのスリルに満ちた冒険物語である。
監督も、ことさらアングロサクソン的教養などを、意図したとも思えない。そんなこととは関係なく、小さな恋が、性までを含めて昇華していく過程がどきどきするほど楽しい。少年はボーイスカウトの訓練キャンプから脱走し、少女は家庭と学校という日常から脱出する。二人は既成社会のくだらぬ規律からの脱走者である。12歳のヒロインがいい。彼女はいつも双眼鏡で、外部を観察する。双眼鏡をはずして真正面にグローズアップされる表情がすばらしい。何を見、何に気づいたのか、その青い深い沼のような目にひきつけられる。そこにあるのは、こどもとか大人とかでなく、世間並みの大人と比べて、人間として圧倒的存在感があるのだ。受けて立つ少年のほうは、行動的で勝つ具体的である。すでに訓練で身につけたサバイバル技術を駆使して追跡者を巻き、銃を発砲して戦い、二人の目的を成し遂げていく。まさに夢の冒険を重ねる。しかし、さらに困難なのは、二人にとって、性という領域の未踏の内面世界であった。その発見への冒険もつづくというわけである。いつの間にか追跡者のボウイ・スカウトの少年たちも、二人の勇気や愛を共感できるようになり、仲間となって二人を助け、大団円を迎える。まさに生きるとはなにかを自覚した少年・少女の物語である。その原動力にアングロサクソン的教養が流れている。それは、かれらにNDAとし生きているということに、きづかされたのであった。
さらに話をすすめるならば、そこが、ニューイングランドという町の孤島だということである。その場所は、現代アメリカの資本主義社会の対極的世界として、もう一つの主題をなしている。アメリカ資本主義の深刻な文明がもう一つの現実として、ニューイングランドを利用して、語られているわけである。それは経済効率の果てない追求が全社会を覆うアメリカがあることである。勝者が敗者か、合理化か旧態か、富裕か貧者か、スマホ、タブレット、インターネットのデジタル化、グローバル化、非能率な存在の粛清、職業の不安定、ライフラインの崩壊、均質・画一化、同じ風景と同じ生活、極小化されていく個の存在、絶望、犯罪、刑務所の増設とホームレスの増殖。終息のない経済的拡張への無限欲求で、ゴールのない終息のない人生だけがある。かくして人々の行動は、興奮的で、衝動的な一過性のみの繰り返しとなる。そのストレスの解決はない。理性的解決ではなく、抑圧のはけ口だけが、解決に錯覚される。社会は不正だ、それを圧倒する正義が、掲げられる。その正義とは、神に替わって、あらゆるものに刑罰を!!である。掲げられる国旗と道徳のスローガン。社会の隅々に不正を暴き出すモラルの喧伝。同性愛、堕胎、エロ本、売春、飲酒、麻薬、贅沢、死刑復活、ありとあらゆる法律違反、禁煙、躾、教育、電子機器、投資、日常での反社会的行動の抉り出し、あらゆる人々をコンプライアンスで厳格に処罰して、自分の欲求不満を満たしていく。その正義と愛国が叫ばれる。資本主義の猛威は、このような人々への抑圧を必然的にもたらしつづけていく。
その現実から一見別世界のニューアイルランドの孤島が、ある。映画を覆う、いささか懐かしいノスタルジックな風物だけが広がる、しかしノスタルジーが目的であろうか。たしかにそれはある。それを楽しめばすむのか、この映画はそんな甘さとはべつのものであるのだ。むしろ、現代アメリカ社会の絶望を、見るものの内面に月の出が照らしだすかのように見させるのだ。もっとも、そこには、かすかながら希望がないわけではない。映画のラストシーンには、ふたたび、クラシック音楽が流れる。キャストやスタッフ名のえんえんと流れる字幕にBGMとして流される。こんどは、一つ、一つの楽器が、メロディーを一節づつ演奏していく。そして最後にまとまって交響曲となる。そこで象徴されるのは、楽器はきわだつ個性をもつ個であり、それゆえに集まって交響曲を完成できるということである。つまりそメッセージは、自由と独立の精神であり、それがアメリカ人の遺伝子だと語られるがごとくである。
わが国は、今、どうなのか、ムーンライス・キングダムの示す個の自由と独立の遺伝子はあるのかどうか。わが国もまた資本主義社会なのである。
この諮問委員会は、頭のいい、そして旬の(と、政権が選んだ)学者や経済人、その他の選良という者たちで、その頭数が数が多ければ多いほど、最良の結果がにじみ出るという、ワイン絞りの発想である。数は量となるが、絞って出るのは、間違いなくワインであり、金貨がでるわけではない。消費税を止めるか、影響を小さくするため、小出しにして、目的の8パーセントにするか、いきなり8パーセントとするかの回答だけに区分されていく。消費税というワインだけが滲み出るわけである。それが飲めるかどうか、飲めるはずだが、必要かどうか、ここが
問題だ。専門家や、選良でなくても、常識的に判断してみれば、消費税は増税しても景気減速、株価は下落、消費は冷え込む。消費増税を小細工で延期しても、財政政策への不信感で外国人ファンドは、ただちに日本国債の投売、価値の下がった国債の金利が高くなり、銀行金利も高くなり、景気は落ち込む。進んでも地獄、引いても奈落であると、想定できる。これこそ市場の現実的判断であると言われている。こういう状況の中で、安陪政権のやらねばならぬことは葡萄絞りをやっている場合かというのだ。首相自ら先頭に立つ、アベノミクスの反省であり、恥を恐れず軌道修正するか、破棄するかの英断的行動であろう。その上で、グローバルゼーションのなかで、日本だけの強国化をなりふり構わず実行して、アジア諸国の反発を買うよりも、仕立てに出る余裕、商人国家として、世界と日本の関係を再確認すべきであろう。商人はただで頭をさげているのではないのだ。これが経済戦略である。これを可能にしてきた日本国憲法の奇跡的力を、世界にも確認させ、日本国民も今こそ信じるべきではないのか。故に日本国内においては、国権の増大と自己権力の確立のための憲法改正を謀るのでなく、国民でなく、それぞれの個人、個人の自由と生存への強化を、実現すべきである。この基礎のうえにこそ消費税はあるのだ。だが、現況は闇雲に安陪スローガンの実現だけしか、方法はないかのようだ。そこは、もはや逃げ場のない茨の荒野、その踏破を、辻褄のあった逃げ道を学識経験者なら探せるという期待の諮問委員会は、もはやナンセンスである。かってケネディ政権、ジョンソン政権がベトナム戦争を継続・拡大への政策提言をしてきたのは、60年代米国を代表する最良の学者たちや文化人であった。一般に最良の最高の知の所有者と選ばれた者たちが、まちがった方向だけを示唆しつつけたのである。かれらのこの歴史的誤謬を、当時ニューヨークタイムズの記者であったデイヴィッド ハルバースタムが本「ベスト&ブライテスト」というドキュメントで、論文にしている。最良の選民であるがために、全体が見えない、権力の側に立ってしか、人間社会を把握できない偏向をもっていることえを、かれらの詳細な心理的動向、言説を記録、分析することで解き明かしている。今、わが国ではアベノミクスをめぐって、ベスト&ブライテストが、これから繰り返されていこうとしている。安陪スローガンを支える支点のひとつになることは間違いない。なぜ彼自身の外に支えが必要なのか、ぼくはこの行動こそ、安陪晋三首相の意識に潜む、彼自身も意識できない不安感であるのを、見る思いがするのである。
今はひどい時期である。このテレビ報道とどうじに、ぼくは幸運なことには、宮崎映画祭で、キネマ館の冷えすぎるエアコン(調整不可能という)を浴びながら映画を楽しみだしたという状況になった。ことしの映画祭は、まさに地球も日本もひっくりかえりそうな危機の年の映画祭であるのにである。その意味で第19回には総合タイトルに「Mのみらい」とあるのが、異様に目に付いた。これまでは総合タイトルにあまり意味を感じなかった。そう注意もはらわなかった。今回はちょっと違った。代表の臼井省司さんによるとMは movieのMであり、映画のデジタル化による変貌をもたらし、これからの未来への変化を見据えたいという意味もあるとある。つまりこの視点は、映画を見据える、きわめて具体的な行動につながっていると理解した。映画の変化を知る、これがひいては、映画祭を変貌させ、また宮崎の未来を開いていく可能性になる。市長の儀礼的挨拶(おそらく秘書課か広報課の職員の文章か)の「宮崎市の文化芸術の振興」とか「市民が主役の文化芸術活動の推進」とかいうスローガンでなくて未来を志向する小さな実行可能な現実が臼井さんには認められる。これがいい。
ではここで、本題に入ろう。「ムーンライズ・キングダム」はアメリカ北部の過疎地ニューイングランドの孤島の町で起きた少年と少女の恋物語である。冒頭からして、岩波絵本のページをめくるような感じにつつまれる。壁にかけられた子どもの絵画、縫いぐるみ、飛行機の模型、独楽、おもちゃの太鼓などに満ちた廊下や寝室、部屋へとカメラはパンすると、小学生低学年らしき子どもが、客間で今はもう消滅したレコードプレイヤーにSPレコードを架ける。と、それは交響曲の主題メロディーを、金管楽器、木管楽器、ピアノ、ハープ、弦楽器、ドラム別に、順番に演奏し、最後に全体でまとまるという音楽教材である。このクラシック音楽が、映画の導入部となっていた。なんでクラシック音楽なんだと思ったとたんに、はっと気づいたのは、美術、音楽、読書という欧米人の教養の基盤が、さりげなくならべられいることであった。加えて、自然は探求し、生きる絆としての開拓者の行動もあり、サバイバルの精神もくわえられる。ゆえに少年は本物の小銃をたずさへ、少女はサバイバルナイフを手にする。小銃は、追跡してきた仲間にむけて発砲され、少女はナイフでリーダの足を刺す。こういう教養の枠組み、行動の枠組みは、ごく自然であり、あらためて、ホワイト・アメリカンの意識にある行動原理におどろかされる。もちろん、これは伝統に帰れというような教訓的な映画ではない。教養を説く映画でもない。12歳の少年と少女が、駆け落ちをして結婚式を挙行するに至る、夢と希望実現へのスリルに満ちた冒険物語である。
監督も、ことさらアングロサクソン的教養などを、意図したとも思えない。そんなこととは関係なく、小さな恋が、性までを含めて昇華していく過程がどきどきするほど楽しい。少年はボーイスカウトの訓練キャンプから脱走し、少女は家庭と学校という日常から脱出する。二人は既成社会のくだらぬ規律からの脱走者である。12歳のヒロインがいい。彼女はいつも双眼鏡で、外部を観察する。双眼鏡をはずして真正面にグローズアップされる表情がすばらしい。何を見、何に気づいたのか、その青い深い沼のような目にひきつけられる。そこにあるのは、こどもとか大人とかでなく、世間並みの大人と比べて、人間として圧倒的存在感があるのだ。受けて立つ少年のほうは、行動的で勝つ具体的である。すでに訓練で身につけたサバイバル技術を駆使して追跡者を巻き、銃を発砲して戦い、二人の目的を成し遂げていく。まさに夢の冒険を重ねる。しかし、さらに困難なのは、二人にとって、性という領域の未踏の内面世界であった。その発見への冒険もつづくというわけである。いつの間にか追跡者のボウイ・スカウトの少年たちも、二人の勇気や愛を共感できるようになり、仲間となって二人を助け、大団円を迎える。まさに生きるとはなにかを自覚した少年・少女の物語である。その原動力にアングロサクソン的教養が流れている。それは、かれらにNDAとし生きているということに、きづかされたのであった。
さらに話をすすめるならば、そこが、ニューイングランドという町の孤島だということである。その場所は、現代アメリカの資本主義社会の対極的世界として、もう一つの主題をなしている。アメリカ資本主義の深刻な文明がもう一つの現実として、ニューイングランドを利用して、語られているわけである。それは経済効率の果てない追求が全社会を覆うアメリカがあることである。勝者が敗者か、合理化か旧態か、富裕か貧者か、スマホ、タブレット、インターネットのデジタル化、グローバル化、非能率な存在の粛清、職業の不安定、ライフラインの崩壊、均質・画一化、同じ風景と同じ生活、極小化されていく個の存在、絶望、犯罪、刑務所の増設とホームレスの増殖。終息のない経済的拡張への無限欲求で、ゴールのない終息のない人生だけがある。かくして人々の行動は、興奮的で、衝動的な一過性のみの繰り返しとなる。そのストレスの解決はない。理性的解決ではなく、抑圧のはけ口だけが、解決に錯覚される。社会は不正だ、それを圧倒する正義が、掲げられる。その正義とは、神に替わって、あらゆるものに刑罰を!!である。掲げられる国旗と道徳のスローガン。社会の隅々に不正を暴き出すモラルの喧伝。同性愛、堕胎、エロ本、売春、飲酒、麻薬、贅沢、死刑復活、ありとあらゆる法律違反、禁煙、躾、教育、電子機器、投資、日常での反社会的行動の抉り出し、あらゆる人々をコンプライアンスで厳格に処罰して、自分の欲求不満を満たしていく。その正義と愛国が叫ばれる。資本主義の猛威は、このような人々への抑圧を必然的にもたらしつづけていく。
その現実から一見別世界のニューアイルランドの孤島が、ある。映画を覆う、いささか懐かしいノスタルジックな風物だけが広がる、しかしノスタルジーが目的であろうか。たしかにそれはある。それを楽しめばすむのか、この映画はそんな甘さとはべつのものであるのだ。むしろ、現代アメリカ社会の絶望を、見るものの内面に月の出が照らしだすかのように見させるのだ。もっとも、そこには、かすかながら希望がないわけではない。映画のラストシーンには、ふたたび、クラシック音楽が流れる。キャストやスタッフ名のえんえんと流れる字幕にBGMとして流される。こんどは、一つ、一つの楽器が、メロディーを一節づつ演奏していく。そして最後にまとまって交響曲となる。そこで象徴されるのは、楽器はきわだつ個性をもつ個であり、それゆえに集まって交響曲を完成できるということである。つまりそメッセージは、自由と独立の精神であり、それがアメリカ人の遺伝子だと語られるがごとくである。
わが国は、今、どうなのか、ムーンライス・キングダムの示す個の自由と独立の遺伝子はあるのかどうか。わが国もまた資本主義社会なのである。











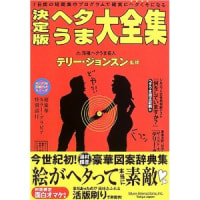












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます