映画をどう評価するかは、人それぞれであり、その価値は面白くてなんぼの世界で、自分にとって面白いかどうか、面白くなければ意味はない!!と、いうだけの話だ。しかし、面白さとはなに、と考え出すと、それこそまさに人それぞれの勝手で、その袋小路でつき当たって終わりになるようだ。面白い、面白くない、これ以上、語る必要もないのかもしれない。ただ、映画について何かを語りたいという感動や、興味は残ってしまうのも事実だ。その記憶にこげついおこげを剥がして、これがなんだと語りだすのが、ぼくのレビューということになるかもしれない。つまり、それはぼくの受けた「面白さ」を事後再確認するということになろうか。同時に記録として残すことにもなる。これは、気に入ったものを写真で撮る、所有欲に似ている。そうして、それからぼくが所有したおこげを人様に見せびらかしたい欲求に駆られるわけだ。
では、心に残ったものから語っていこう。まず、製作された1978年という時代、ぼく自身は、地方の同人誌作家として付かず離れずしていた、日本特有の純文学をいよいよ離れていった70年代だった。そのころの日本においては、高等文化の核でもあった純文学や演劇が、テレビ・漫画に席を追われだし、地すべりをあちこちで起こしだした時代であった。この田舎都市にもアングラ演劇や小劇場、ヒッピー・コミューンなど、アウトサイダーの芸術運動が、既成観念にボディーブローを加えだし、その効果もいくらかは、見え出しはじめていた。今でも前衛運動などに関わった団塊世代以前の年寄りたちのなかには、70年代の文化状況として、当時のベトナム反戦運動、学生運動などともに回想できよう。言ってみれば、70年代はネオカルチャーオープニングが、しだいに時代の変化の兆しとして、受け取られ始めた時代であった。もっともこの宮崎市では、時代の変化など、とんと芽生えるような空気など、なかったのでもあるが。
アメリカ映画「オプニングナイト」は、70年代の芸術論としても解釈できる。映画としても楽しめるのは請合えるが、この映画物語を芸術論として、分解してみるのも一興を添えるし、ここが、ぼくには「面白い」モノとして語ってみたい。
タイトルに「 SECOND WOMAN 」の英語を目にしたとき、すぐにボーヴォワール」の著作「第二の性」を連想できた。ついで彼女の著作「老い」を思いだしたのだ。彼女の存在は、フランスの実存主義哲学者サルトルの伴侶として、戦後の思想界を代表し影響を振るった美貌の哲学者、文学者、社会科学者として、当時はまだ人々の記憶にはあったと思う。問題は彼女の著作「老い」だが、この社会学的評論が、この映画のヒロインである女性の心理や葛藤、苦悩を処方箋のようにわからせてくれる。かんたんに本の内容を説明してみよう。
B5版、上下2段組の8ポイント活字でびっしり埋まった上下2巻で、700ページを越える大著であり、「第二の性」と並ぶ社会科学書の傑作というのが、発刊当時1972年のころの評価であった。この本の凄いのは、人の老いさらばえていく現実を、まさに実存哲学の手法を駆使して、宗教や、観念哲学を排除し、それぞれの老人の生きている現実を、冷静に自然科学の対象のように分析、論述していく内容である。対象とされた老人は、ギリシャ・ローマ時代から中世、ルネッサンス、19世紀の産業革命を経て、20世紀、戦後までの各時代を代表している哲学者、文学者、画家、音楽家、ひるがえって王や貴族、政治家、将軍、実業家、科学者などなどと膨大な分野に時間的にも分野的にも渉猟されている。索引で数えると478人である。この中で、ぼくが知っていたのは137人29パーセントであった。つまり3人に1人である。プラトン、アリストテレス、からはじまりチョーサー ラブレー、ミケランジェロ、シェイクスピア、ゲーテ、バルザック、ショーペンハウア、ホイットマン、マラルメ、プルースト、ジイド、トルストイ、フロイト、もうわかったとおもわれるが、ギリシャ・ローマ時代から白人文明を創造してきた天才たちのオンパレードである。かれら知ってる者137人が並ぶだけで圧倒されるが、他もこのレベルに近い時代、時代を代表する有名人だと思える。
ま、いうなれば、「知の巨人」族である。それも西欧文化・文明のまごうことなき創造家軍団である。その天才、巨人たちの「老い」が、実証的に論考されていくのだ。「老いさらばえた」姿として、現実存在つまり実存として、「人生の究極の意味」を剥き出しにされていくのである。ではそれはどんな姿なのか、かれらの人生の究極、ここではどん詰まりでの意味ともいえるが、その人生を、哲学者、文学者としてボーヴォワールは、どう提示したのであるか。彼女62歳の重評論である。
はしょって言おう。かれらの究極の人生は、過去の栄光からは想像もできない崩壊人生であるという事実が、一人また一人と曝け出されていく。ボーヴォワール女史は、まるでメスを振るう医者のように、かれらを解剖していく。たどり着いた最後の人生とは、なにか。その最終人間模様が、かたられていく。今、再読してみると、ある面では天才解剖の奇書ともいえる。
老後の性、あるいは恋について、これでもか、これでもかと、天才たちが演じてみせる人生は、精神というものが、どういうものか、驚異の意味をぶっつけてきた。たとえば、ビクトル・ユーゴ、70歳を過ぎて、女中ブランシュにほれこみ、自分たち夫婦の寝室の隣に女中部屋を作って彼女を住まわせた、そして、夜毎、彼女のヌードを盗視した。有名な音楽家の恋人もいたのだが、それはそれで、妻の目を盗んでは、幾夜も売春婦を求めて街をうろついた。妻や側近に止められたが、自分の抑制ができないと嘆いている。日記には、家族にわからぬ暗号をもちいて、売春婦や、ブランシュとのまともでないセックスの状況を書きつづけた。また覗きの快楽も絵として描いていった。晩年のトルストイも浮気をつづけていたが、妻ソフィの嫉妬、執拗きわまる追及、鉄道自殺、凍死自殺と走る激情を抑えねばならぬ日常が続いていった。ついにソフイアに絶えかね、知人の医師を伴って家出する。あとで、娘のシャーサが追いかけてくるがにここでは危ない、もっと遠くにとすすめられ、汽車に乗るが、次の夜に駅舎で死んでしまう。ゲーテは72才で、17才のウルリッケに夢中になる。一冊の詩集まで出すのだが、ついに医師に自分の性の可能性を相談して、ウルリッケに結婚を申し込む。だが息子や嫁に猛反対され、ウルリッケにも拒絶された。これが、ゲーテの最後の恋となった。あとは、世界に関心をうしない、無為のまま人生を終わる。その他、その他と、天才・巨人たちの驚異的な喜劇、悲劇のグロテスクなドラマを見ることができる。
ボーヴォワールは、男たちの性は勃起できなくなって終わりむかえるが、女の性は若いときも老年になっても、受け入れ可能で、まったく変わらない、終わりはないという。だが、相手に与える肉体がなくなるといっている。夫婦生活であっても、性の対象として、魅力を失うため夫は若い女性を求める。その嫉妬で、夫を束縛できても、夫の不満は消せず、性的魅力を失ってしまった妻も、夫の関心をえられず、激しい欲求不満にふたたび落とし込まれるだけだという。ボーヴォワール自身は、どうなのか。彼女の場合は、サルトルと、浮気までを含めて、お互いの自由を絶対束縛しない、その他を詳細な文書にして、サルトルと同棲に入った。だが、60代をこえると、サルトルの、終わることのない女関係がしだいに精神を揺るがし始める。ついに自分の最愛の弟子にサルトルが手をつけのを契機に、錯乱の気配がではじめた。彼女は弟子とレスビアンの関係となり、精神病院の入退院をくりかえしつつ、知的活動もできなくなり、1986年、78歳の人生を閉る。
ここで、オプニング・ナイトの冒頭に目を向けよう。そのシーンは舞台劇であり、劇のヒロイン役(ジーナ・ローランズ)は、夫の浮気を詰問するシーンである。まさに中年夫婦の危機の舞台が、「老い」の通りのように演じられている。しかし、それを演じるヒロインは、どうも身が入らない。その態度に演出家も、脚本家の女性も憤懣をおさえられなくっている。もうなんども同じ身のはいらぬヒロインの演技が繰り返されている。なぜか、映画はここから始まってくる。
では、心に残ったものから語っていこう。まず、製作された1978年という時代、ぼく自身は、地方の同人誌作家として付かず離れずしていた、日本特有の純文学をいよいよ離れていった70年代だった。そのころの日本においては、高等文化の核でもあった純文学や演劇が、テレビ・漫画に席を追われだし、地すべりをあちこちで起こしだした時代であった。この田舎都市にもアングラ演劇や小劇場、ヒッピー・コミューンなど、アウトサイダーの芸術運動が、既成観念にボディーブローを加えだし、その効果もいくらかは、見え出しはじめていた。今でも前衛運動などに関わった団塊世代以前の年寄りたちのなかには、70年代の文化状況として、当時のベトナム反戦運動、学生運動などともに回想できよう。言ってみれば、70年代はネオカルチャーオープニングが、しだいに時代の変化の兆しとして、受け取られ始めた時代であった。もっともこの宮崎市では、時代の変化など、とんと芽生えるような空気など、なかったのでもあるが。
アメリカ映画「オプニングナイト」は、70年代の芸術論としても解釈できる。映画としても楽しめるのは請合えるが、この映画物語を芸術論として、分解してみるのも一興を添えるし、ここが、ぼくには「面白い」モノとして語ってみたい。
タイトルに「 SECOND WOMAN 」の英語を目にしたとき、すぐにボーヴォワール」の著作「第二の性」を連想できた。ついで彼女の著作「老い」を思いだしたのだ。彼女の存在は、フランスの実存主義哲学者サルトルの伴侶として、戦後の思想界を代表し影響を振るった美貌の哲学者、文学者、社会科学者として、当時はまだ人々の記憶にはあったと思う。問題は彼女の著作「老い」だが、この社会学的評論が、この映画のヒロインである女性の心理や葛藤、苦悩を処方箋のようにわからせてくれる。かんたんに本の内容を説明してみよう。
B5版、上下2段組の8ポイント活字でびっしり埋まった上下2巻で、700ページを越える大著であり、「第二の性」と並ぶ社会科学書の傑作というのが、発刊当時1972年のころの評価であった。この本の凄いのは、人の老いさらばえていく現実を、まさに実存哲学の手法を駆使して、宗教や、観念哲学を排除し、それぞれの老人の生きている現実を、冷静に自然科学の対象のように分析、論述していく内容である。対象とされた老人は、ギリシャ・ローマ時代から中世、ルネッサンス、19世紀の産業革命を経て、20世紀、戦後までの各時代を代表している哲学者、文学者、画家、音楽家、ひるがえって王や貴族、政治家、将軍、実業家、科学者などなどと膨大な分野に時間的にも分野的にも渉猟されている。索引で数えると478人である。この中で、ぼくが知っていたのは137人29パーセントであった。つまり3人に1人である。プラトン、アリストテレス、からはじまりチョーサー ラブレー、ミケランジェロ、シェイクスピア、ゲーテ、バルザック、ショーペンハウア、ホイットマン、マラルメ、プルースト、ジイド、トルストイ、フロイト、もうわかったとおもわれるが、ギリシャ・ローマ時代から白人文明を創造してきた天才たちのオンパレードである。かれら知ってる者137人が並ぶだけで圧倒されるが、他もこのレベルに近い時代、時代を代表する有名人だと思える。
ま、いうなれば、「知の巨人」族である。それも西欧文化・文明のまごうことなき創造家軍団である。その天才、巨人たちの「老い」が、実証的に論考されていくのだ。「老いさらばえた」姿として、現実存在つまり実存として、「人生の究極の意味」を剥き出しにされていくのである。ではそれはどんな姿なのか、かれらの人生の究極、ここではどん詰まりでの意味ともいえるが、その人生を、哲学者、文学者としてボーヴォワールは、どう提示したのであるか。彼女62歳の重評論である。
はしょって言おう。かれらの究極の人生は、過去の栄光からは想像もできない崩壊人生であるという事実が、一人また一人と曝け出されていく。ボーヴォワール女史は、まるでメスを振るう医者のように、かれらを解剖していく。たどり着いた最後の人生とは、なにか。その最終人間模様が、かたられていく。今、再読してみると、ある面では天才解剖の奇書ともいえる。
老後の性、あるいは恋について、これでもか、これでもかと、天才たちが演じてみせる人生は、精神というものが、どういうものか、驚異の意味をぶっつけてきた。たとえば、ビクトル・ユーゴ、70歳を過ぎて、女中ブランシュにほれこみ、自分たち夫婦の寝室の隣に女中部屋を作って彼女を住まわせた、そして、夜毎、彼女のヌードを盗視した。有名な音楽家の恋人もいたのだが、それはそれで、妻の目を盗んでは、幾夜も売春婦を求めて街をうろついた。妻や側近に止められたが、自分の抑制ができないと嘆いている。日記には、家族にわからぬ暗号をもちいて、売春婦や、ブランシュとのまともでないセックスの状況を書きつづけた。また覗きの快楽も絵として描いていった。晩年のトルストイも浮気をつづけていたが、妻ソフィの嫉妬、執拗きわまる追及、鉄道自殺、凍死自殺と走る激情を抑えねばならぬ日常が続いていった。ついにソフイアに絶えかね、知人の医師を伴って家出する。あとで、娘のシャーサが追いかけてくるがにここでは危ない、もっと遠くにとすすめられ、汽車に乗るが、次の夜に駅舎で死んでしまう。ゲーテは72才で、17才のウルリッケに夢中になる。一冊の詩集まで出すのだが、ついに医師に自分の性の可能性を相談して、ウルリッケに結婚を申し込む。だが息子や嫁に猛反対され、ウルリッケにも拒絶された。これが、ゲーテの最後の恋となった。あとは、世界に関心をうしない、無為のまま人生を終わる。その他、その他と、天才・巨人たちの驚異的な喜劇、悲劇のグロテスクなドラマを見ることができる。
ボーヴォワールは、男たちの性は勃起できなくなって終わりむかえるが、女の性は若いときも老年になっても、受け入れ可能で、まったく変わらない、終わりはないという。だが、相手に与える肉体がなくなるといっている。夫婦生活であっても、性の対象として、魅力を失うため夫は若い女性を求める。その嫉妬で、夫を束縛できても、夫の不満は消せず、性的魅力を失ってしまった妻も、夫の関心をえられず、激しい欲求不満にふたたび落とし込まれるだけだという。ボーヴォワール自身は、どうなのか。彼女の場合は、サルトルと、浮気までを含めて、お互いの自由を絶対束縛しない、その他を詳細な文書にして、サルトルと同棲に入った。だが、60代をこえると、サルトルの、終わることのない女関係がしだいに精神を揺るがし始める。ついに自分の最愛の弟子にサルトルが手をつけのを契機に、錯乱の気配がではじめた。彼女は弟子とレスビアンの関係となり、精神病院の入退院をくりかえしつつ、知的活動もできなくなり、1986年、78歳の人生を閉る。
ここで、オプニング・ナイトの冒頭に目を向けよう。そのシーンは舞台劇であり、劇のヒロイン役(ジーナ・ローランズ)は、夫の浮気を詰問するシーンである。まさに中年夫婦の危機の舞台が、「老い」の通りのように演じられている。しかし、それを演じるヒロインは、どうも身が入らない。その態度に演出家も、脚本家の女性も憤懣をおさえられなくっている。もうなんども同じ身のはいらぬヒロインの演技が繰り返されている。なぜか、映画はここから始まってくる。











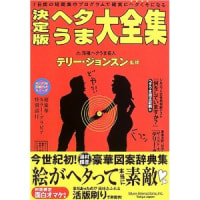












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます