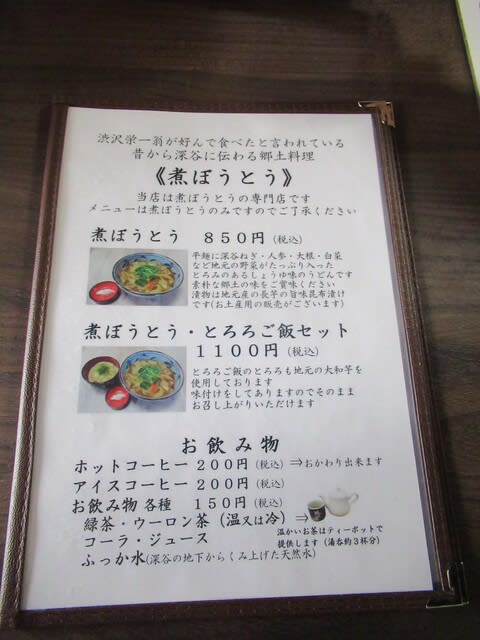文京区大和郷エリア以来、約1年振りの豪邸シリーズアップとなりました。
どうしてかというと、コロナ感染防止の緊急事態宣言により
都内への移動を真剣に自粛していた為であります。
今回の田園調布エリアで通算8エリア目になりますが、
この豪邸シリーズはスミダマンのほのぼの奮戦記の中で最も人気の高いシリーズであります。
そして今回田園調布エリアを選んだのは
渋沢栄一によってこのプロジャクトが立ち上げられたという
「渋沢栄一の足跡をたどる旅」に相応しいと考えたからであります。
では渋沢栄一シリーズ第2弾始まり始まり!



田園調布エリアの駅は東急東横線、東急目黒線の交差駅の田園調布駅になります。
そして地図的には大田区の最西端、世田谷区の最南端に隣接し、
西に多摩川が流れ、神奈川県川崎市との都県境に位置しています。
こじんまりしたお洒落な空気の流れる駅構内には
ベーカリー&カフェのお客の姿もあります。



改札口を出るとどことなく南欧の雰囲気に包まれた
ショッピングセンター「東急スクエアガーデン」が優しく迎えてくれます。
やはり低層の建物は人にとても温かみを感じさせる。


ただでさえ人の温もりを感じさせるスパニッシュ風の屋根に
ベージュ系の外壁のショッピングセンターの建物に
生きたグリーンの服装をまとわせるような花壇の植栽と花々。
駅を降りるなりいきなりこの風景は高級な気持ちにさせてくれる。



そしてこの建物が田園調布のランドマーク、復元された駅舎。
屋根がマンサードルーフで欧州中世の民家をモデルにしたもの。
2000年1月15日に駅のシンボルとして復元され、関東の駅百選に認定された。


噴水を中心とした西口ロータリー。
そこから広がる放射状及び同心円状の道路、街路樹の銀杏並木、そしてこの旧駅舎。
この周辺風景はまるで絵に描いたような美しさだ。


駅前の噴水公園があるロータリーのベンチの所には
アールの石に田園調布の由来についての長文が書かれている。
この碑は昭和34年秋、社団法人・田園調布会・会長名で出されたものだ。
それによると「約80万㎡のこの地域は渋沢栄一翁が田園都市に着目して
都会と田園との長所を兼ねた模範的住宅地を実現させようと
自ら老体を運んで土地を選定した所である。
そして大正7年に我が国初めての近代的大計画都市が実現した。
この都市全体を一つの公園のように明るく美しいものにする為、
建築の申し合せ、境界には花壇、低い生垣にするなどを厳格に実行した。
大正12年3月、当地に駅が設けられ田園調布という駅名に改められた…等々」が書かれている。


西口駅前にある木造の素敵な建物の2階に「PASTA RI」というイタリアンレストランがあり、
ここでランチをと思ったらなんと1時間45分待ちですって。
それでは田園調布の街巡りを先にと、とりあえず予約をして店を出た。
なお、1階にはお惣菜とお弁当のお店「DELI BREEZE」がある。


それではこれから豪邸巡りをスタートしましょう。
この道は駅を背にして左から2本目の放射線の道。
しばらく行くと交差している店の形が田園調布の最大の特色、
アールのゆるやかな曲線の道が見える。
このアールにすることによって道の先はすべて緑が見える潤いの造りになっている。

このお宅は大きすぎて全体を撮ることができませんでしたが、
おそらく最近建て替えられた和をベースにした
田園調布の建物では珍しいコンセプトの豪邸だ。


このように周囲の雰囲気に溶け込んだシックなRCの豪邸が続く。
両宅ともガレージが大きく複数台の車庫になっているのだろう。

こちらの豪邸は道路角地を活かしてかなり大きなアールのファザードの2種のタイル貼り。
とてもアピール度の強い邸宅だ。



大正14年、田園調布の開発に際し、武蔵野の旧景を保存し永く後世に残すために
田園都市(株)は街の一画の汐見台の土地を公園用の広場として残した。
この宝来公園は多摩川の沿岸旧荏原郡下沼部村の丘陵に位置し、
付近は亀甲山古墳を始めとする多くの遺跡に富んでいる。
園内には梅、桜をはじめ、クヌギ、シイなど約70種1,500本の樹木が繁り、
四季折々の自然の美しさは今も武蔵野の面影を残している。



この通りにはご覧のようなメルヘンチックな夢のある豪邸が並んでいて、
この一角をちょっと違った雰囲気の楽しい空気が流れていた。



それぞれ個性の違う豪邸で見応えがある。
特に3枚目の邸宅は重々しい石貼りの圧倒的存在感がある建物なだけに
逆に生け垣の優しさが生きている。
2枚目の豪邸はまだ新しい邸宅ではないか?
他の豪邸とは意匠のコンセプトが違い印象的な感じがした。
1枚目の豪邸はちょっと古い感じがしたが、門扉の存在感がすごい。

まだ植えたばかりか?
小さな生け垣だが糸杉のようで成長すると振り返りたくなるような生け垣になるのでは。

この邸宅の門扉のすごさには驚いた。
これだけでも威圧感がある。


こちらの豪邸の意匠はかなり違いがある。
上の邸宅はとてもオーソドックスなディテールだが、
下の邸宅は石貼りのアールの壁がすごいアピールをしている。
両邸宅とも素晴らしい。

田園調布に居住し、この街の開発を推進した渋沢栄一の子・渋沢秀雄によると
「田園調布の西側に半円のエトワール型を取り入れ、道路を造り、
街路樹を植え、広場と公園を整備し、庭を広くとり緑地の一部とし、
街全体を庭園のようにするなど良好な住環境をめざせ」と奮闘した。

なんと田園調布に外国大使館を発見。
アフリカのナイジェリア大使館だ。

この大邸宅だけを見ると、ここはアメリカか?と勘違いしてしまいそうな建物だ。
はたして住宅なのか、あるいは大使館等事務所系の建物なのかわからないが、
田園調布の中では異彩を放っていた豪邸だ。



荒っぽい表現だが丸と四角と長方形のそれぞれすごい豪邸が続く。



イギリスで提唱された田園都市構想をモデルに
日本有数の高級住宅地として開発された約30万坪のエリア。
日本で初めて庭園都市(ガーデンシティー)として計画的に分譲された地域で、
関東大震災後に都心から多くの人が移住してきた。




今回、田園調布の全豪邸を見たわけではないが、
この邸宅が一番すごく強烈なインパクトのある豪邸であった。
玄関の両サイド、石の擁壁の前には2つの枯山水の庭園を配し、玄関扉のすごいこと。
道路の角地にあり、圧倒的な存在感のある豪邸中の豪邸といった感じだった。
いったいどんな人が住んでいるのだろうか素朴にそう思う。


このすごい豪邸と張り合うかのように向い側にもまたすごい豪邸が建っていた。
昔(1980年代)漫才の星セントルイスが
「田園調布に家が建つ」のギャグネタでヒットしたが、
そんなレベルはすっとんでしまう程の豪邸が続いている。

駅が正面ストリートの左側一等地にあるケーキ屋さん「レピドール」。
2階はカフェになっている。
建物を見るととてもケーキ屋さんとは思えない素晴らしさだ。

こちらは線路沿いにある南欧地中海風の商業ビル。

その向かい側がバスターミナルになっている。

最後に田園調布の安心安全を見守っている駅前交番。
交番までもが南欧風のオシャレチックな造りに見える。
なお、参考に田園調布に住んでいる有名人は石原慎太郎、五木ひろし、
犬丸一郎(帝国ホテル)、牛尾治朗(ウシオ電機会長)、梅沢富美男、
曽野綾子、長嶋茂雄、鳩山由紀夫、中井貴一、鳥羽博道(ドトールコーヒー)。
かつて住んでいた人は渋沢秀雄、石川達三、石坂浩二、石坂洋次郎、
高峰三枝子、中内功(ダイエー)、霧島昇、小暮実千代、岡田真澄 等々。
錚々たる人達だ。