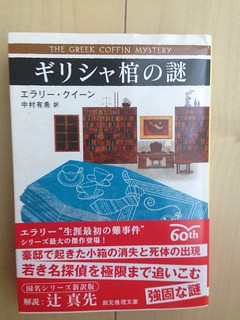ワンクッション置いて再びピーター卿シリーズ、第三作「不自然な死」(1927年)です。
本書は「誰の死体?」読了後にブックオフで見かけ108円で購入していました。
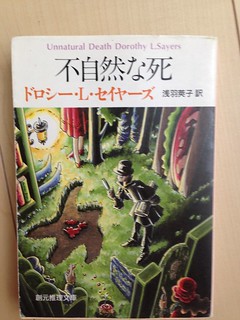
読みたいときにブックオフで見かける…「運命」でしょうか?(笑)
内容(裏表紙記載)
殺人の疑いのある死に際会した場合、検視審問を要求するべきか否か。とある料理屋でピーター卿とパーカー警部が話し合っていると、突然医者だという男が口をはさんできた。彼は以前、診ていた癌患者が思わぬ早さで死亡したおり検視解剖を要求したが、徹底的に分析にもかかわらず殺人の痕跡はついに発見されなかったのだという。奸智に長けた殺人者を貴族探偵が追つめる第三長編。
とりあえずの感想ですが...。
前作「雲なす証言」よりミステリー度は高いように感じましたが小説としては「雲なす証言」の方がよかったなぁという感想です。
ミステリー部分も犯人は序盤でほぼ特定されており「謎は」殺害方法がメインになるわけですが殺害方法は現代的に見ればあまりにも陳腐といえる方法です。
(一応伏線も張ってあるのでミステリー的にはフェアではあります。)
ピーター卿も作中で「殺害方法はなにかしらわるわけで最後に考えればよい」と語っていますが、解決すべきは「謎」は動機とアリバイになってきます。
「動機」の方も遺産がらみということは最初から提示されており、それをちょっとした小技で味付けていますがまぁあっさりしたものではあります。
アリバイの方ももそれ自体はわかればあっけないほど単純なです。
ただ犯人の動機は「遺産」という直接的なものだけでなく、罪意識が欠如していて人を殺すことを何とも思わない人間(”サイコパス”ですね)である犯人の特殊な性向が裏にあり、本当はこちらの不気味さを描きたかったんでしょうが…。
充分にはその不気味さを表現できているとは私には感じられませんでした。
またアリバイの方も「同性愛」(女性)の問題が取り上げられています。
作中、犯人とアリバイ協力者の関係もそうですが、最初の被害者であるドーソンとパートナーの関係も同性愛的な関係として描かれています。
サイコパス美女の同性愛など現代のマニア向けマンガや小説ではいかにもありそうな設定ですが、1920年代のイギリスという時代背景ではアケスケにどぎつく書くのははばかられる内容かとも思うのでその辺で物足りなく感じたのかもしれませんね。
ピーター卿自身「自分の趣味、道楽」で犯人を追いつめる行為に悩みがあって、作中で吐露しています。
この辺も犯人の情念とうまく絡み合うと面白そうなんですが….本作では「雲なす証言」ほど成功しているようには感じられませんでした。
(普通の意味では面白いのですが期待値が高いのでこんな表現になっています。)
さらに犯人(サイコパス-同性愛者)や自分の行為に悩むピーター卿の二人と、どこか相似形ながら全然異なる属性をもつ本作から登場のクリンプソン女史(「人の手紙なんか絶対読みませんよ!」と言いながらついつい読んでしまう女性かつ寡婦)を出して対比させているわけですが、そこもあまりうまく機能していないような...。
クリンプソン女史は単独で大活躍
「意欲」としては「雲なす証言」より上かと感じましたがが「ちょっと消化不良かなぁ」という感じを受けました。
ただし、問題提起は現代的ですし、人物を描く作者の筆力は前作同様確かで狂言回しとしてのクリンプソン嬢の活躍もとても楽しめます。
「普通に楽しい」ミステリーとしては、謎が深まる展開で活躍するピーター卿の大活躍も含め読み物としてはとても楽しめました。
↓よろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。
 にほんブログ村
にほんブログ村
本書は「誰の死体?」読了後にブックオフで見かけ108円で購入していました。
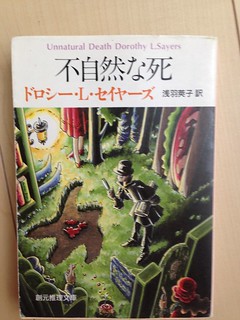
読みたいときにブックオフで見かける…「運命」でしょうか?(笑)
内容(裏表紙記載)
殺人の疑いのある死に際会した場合、検視審問を要求するべきか否か。とある料理屋でピーター卿とパーカー警部が話し合っていると、突然医者だという男が口をはさんできた。彼は以前、診ていた癌患者が思わぬ早さで死亡したおり検視解剖を要求したが、徹底的に分析にもかかわらず殺人の痕跡はついに発見されなかったのだという。奸智に長けた殺人者を貴族探偵が追つめる第三長編。
とりあえずの感想ですが...。
前作「雲なす証言」よりミステリー度は高いように感じましたが小説としては「雲なす証言」の方がよかったなぁという感想です。
ミステリー部分も犯人は序盤でほぼ特定されており「謎は」殺害方法がメインになるわけですが殺害方法は現代的に見ればあまりにも陳腐といえる方法です。
(一応伏線も張ってあるのでミステリー的にはフェアではあります。)
ピーター卿も作中で「殺害方法はなにかしらわるわけで最後に考えればよい」と語っていますが、解決すべきは「謎」は動機とアリバイになってきます。
「動機」の方も遺産がらみということは最初から提示されており、それをちょっとした小技で味付けていますがまぁあっさりしたものではあります。
アリバイの方ももそれ自体はわかればあっけないほど単純なです。
ただ犯人の動機は「遺産」という直接的なものだけでなく、罪意識が欠如していて人を殺すことを何とも思わない人間(”サイコパス”ですね)である犯人の特殊な性向が裏にあり、本当はこちらの不気味さを描きたかったんでしょうが…。
充分にはその不気味さを表現できているとは私には感じられませんでした。
またアリバイの方も「同性愛」(女性)の問題が取り上げられています。
作中、犯人とアリバイ協力者の関係もそうですが、最初の被害者であるドーソンとパートナーの関係も同性愛的な関係として描かれています。
サイコパス美女の同性愛など現代のマニア向けマンガや小説ではいかにもありそうな設定ですが、1920年代のイギリスという時代背景ではアケスケにどぎつく書くのははばかられる内容かとも思うのでその辺で物足りなく感じたのかもしれませんね。
ピーター卿自身「自分の趣味、道楽」で犯人を追いつめる行為に悩みがあって、作中で吐露しています。
この辺も犯人の情念とうまく絡み合うと面白そうなんですが….本作では「雲なす証言」ほど成功しているようには感じられませんでした。
(普通の意味では面白いのですが期待値が高いのでこんな表現になっています。)
さらに犯人(サイコパス-同性愛者)や自分の行為に悩むピーター卿の二人と、どこか相似形ながら全然異なる属性をもつ本作から登場のクリンプソン女史(「人の手紙なんか絶対読みませんよ!」と言いながらついつい読んでしまう女性かつ寡婦)を出して対比させているわけですが、そこもあまりうまく機能していないような...。
クリンプソン女史は単独で大活躍
「意欲」としては「雲なす証言」より上かと感じましたがが「ちょっと消化不良かなぁ」という感じを受けました。
ただし、問題提起は現代的ですし、人物を描く作者の筆力は前作同様確かで狂言回しとしてのクリンプソン嬢の活躍もとても楽しめます。
「普通に楽しい」ミステリーとしては、謎が深まる展開で活躍するピーター卿の大活躍も含め読み物としてはとても楽しめました。
↓よろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。