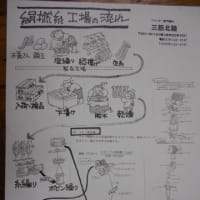「ワインダー巻きに入っている?ビリを消す装置なんてモノはないでしょうか?」
「シリンダー3~4本を給糸しているが、交換のときにビリが入るらしい?整経からの指摘があった」
確かに、その工場はダブル強燃機で撚りの強い糸を特長としている。その分、ワインダー作業は、
甘撚りやビリの巻き込みを防ぐために、専門の作業員をつけている。
以前の問題は、変形巻きを再度、仕上げ巻きにするために、コーン給糸のビリ発生を抑えたいとの事だった。
シリンダーキャップのテグスも使えないので、コーンの外周をテグスリングで押さえるビリ消し装置を
提案して、採用してもらった。しかし、今回は、仕上げコーンの中にビリ溜まり箇所があると言う??
さっそく、工場を尋ね、離れた処から、工員の手元作業を観察した。つなぎ部の撚り戻りを防ぐため
他の工場では見られない程の、糸たぐりもしている。スタート時も糸のたるみに気を付けながら、手順通りの
作業を行っていた。なんら、問題箇所や気抜き作業の兆候もない。
事故が起こっているからこそ、報告があるのだから、発見箇所から逆転して、発生箇所および原因、そして
対策を取らなければならない。その為には、「観察」こそが一番大切な作業となる。
事故糸がビームの中にあるのか?ワーパードラムに視られるのか?整経クリルからテンション装置、
長い糸道ガイド上で見られるのか?はたまた、センサーゲートでの状態は???
ワーパーが一旦停止した時の、糸の状態は問題ないか?観察する箇所はいっぱいある。
誰だって、自分が担当する場所で、事故が発生しているなんて、認めたくない。
一工場内だからイイ様なものの?これが、工場をまたげば大事になる。幡屋・染色屋・撚糸屋を含め、
自分の処ではない!と言い張る。今日、ラジオで聞いていたお役人の答弁とも似ている。
自分もワインダー事故ではないと信じたい。ワインダー事故での観察ポイントは解っているつもり。
だからこそ、整形担当者や織機担当者にも、今一度「観察」して欲しいと望む。
昔の先輩?に「失敗は宝、事故はチャンス」と聞いた。極論かも知れないけれど、事故多発交差点に
信号機が優先されるのと似ている。事故を隠してしまえば、いつまでたっても「改善」はない。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
ブログランキングに参加しています!1日1回クリックをお願いします!!
↓↓↓↓↓↓↓↓

「シリンダー3~4本を給糸しているが、交換のときにビリが入るらしい?整経からの指摘があった」
確かに、その工場はダブル強燃機で撚りの強い糸を特長としている。その分、ワインダー作業は、
甘撚りやビリの巻き込みを防ぐために、専門の作業員をつけている。
以前の問題は、変形巻きを再度、仕上げ巻きにするために、コーン給糸のビリ発生を抑えたいとの事だった。
シリンダーキャップのテグスも使えないので、コーンの外周をテグスリングで押さえるビリ消し装置を
提案して、採用してもらった。しかし、今回は、仕上げコーンの中にビリ溜まり箇所があると言う??
さっそく、工場を尋ね、離れた処から、工員の手元作業を観察した。つなぎ部の撚り戻りを防ぐため
他の工場では見られない程の、糸たぐりもしている。スタート時も糸のたるみに気を付けながら、手順通りの
作業を行っていた。なんら、問題箇所や気抜き作業の兆候もない。
事故が起こっているからこそ、報告があるのだから、発見箇所から逆転して、発生箇所および原因、そして
対策を取らなければならない。その為には、「観察」こそが一番大切な作業となる。
事故糸がビームの中にあるのか?ワーパードラムに視られるのか?整経クリルからテンション装置、
長い糸道ガイド上で見られるのか?はたまた、センサーゲートでの状態は???
ワーパーが一旦停止した時の、糸の状態は問題ないか?観察する箇所はいっぱいある。
誰だって、自分が担当する場所で、事故が発生しているなんて、認めたくない。
一工場内だからイイ様なものの?これが、工場をまたげば大事になる。幡屋・染色屋・撚糸屋を含め、
自分の処ではない!と言い張る。今日、ラジオで聞いていたお役人の答弁とも似ている。
自分もワインダー事故ではないと信じたい。ワインダー事故での観察ポイントは解っているつもり。
だからこそ、整形担当者や織機担当者にも、今一度「観察」して欲しいと望む。
昔の先輩?に「失敗は宝、事故はチャンス」と聞いた。極論かも知れないけれど、事故多発交差点に
信号機が優先されるのと似ている。事故を隠してしまえば、いつまでたっても「改善」はない。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
ブログランキングに参加しています!1日1回クリックをお願いします!!
↓↓↓↓↓↓↓↓