
「バジュランギおじさんと、小さな迷子」というインド映画が公開されたが、まあ素晴らしい。口のきけないパキスタンの6歳の女の子・シャヒーダーが、なんとか話ができるようにと、インドにある霊験あらたかなイスラム寺院にお参りに行く。その帰り道、電車を降りてしまったシャヒーダーは母親とはぐれ、電車はパキスタンに戻り、シャヒーダーはインドに取り残されてしまう。
じゃあ、シャヒーダーを国に帰せばいいだけで、話は簡単と思いきや、そうはいかない。隣同士で国境が接している国だが、簡単に行き来ができない。インドとパキスタンの根深い対立が、小さな女の子の帰還を次から次へと阻むのだ。インド映画お決まりの歌あり、踊りあり、笑いあり、涙あり。しっかり長尺でおなかいっぱいになる作りだ。
では、なぜ簡単にいかなかったのか?インドとパキスタンは、超仲が悪い!対立しているやばい状況であるからに他ならない。
いまさらながら、インドとパキスタンの関係をもっかい見直してみたくなったというわけです。勝手にやります。インドとパキスタンの関係。悪い癖ですが、根っこから掘り起こさないとならない性分なもんで、古代のインドから始まります。
インドは亜大陸といわれるほど、でっかい面積を占めている。ということは、気候も幅広く、「インドは暑い!」と一言では片付けられないくらいに広い。人間は水のないところでは生きていけないので、集住していたところは、川の周辺となる。世界の古代文明の一つ、インダス文明の発祥地、インダス川のほとりに人々は集まって暮らした。そのインダス文明の担い手になったのが、インドにもともと住んでいた、ドラヴィダ人といわれる民族である。モエンジョ=ダロに代表されるインダス文明は、整然としており、高度な都市文明を築いた遺構が残っている。ドラヴィダ人の高い知性が想像できる。
そこに侵入してきたのが、中央アジアに住んでいたアーリア人である。アーリア人は、一方がヨーロッパに、一方がインドに移動したので、インド・ヨーロッパ語族というわけのわかんない名称になっているが、特徴としては色が白いこと。そしてドラヴィダ人は色が黒かった。インダス文明が衰えた後にインドの担い手となったのが、色の白いアーリア人となった。このアーリア人を頂点として、色の白い順になぜか身分制度ができてしまう。カースト制だ。カースト制の基礎となる原則に、人々を分けるヴァルナというものがあるのが、この言葉の意味は、すなわち「色」だ。
頂点にいるのが「バラモン(司祭)」、次が「クシャトリア(王侯・戦士)」、そして「ヴァイシャ(市民)」、4つめが「シュードラ(隷属民)」だ。もちろん色の白い順。映画の中で、パワンが女の子を見て、「色が白いからバラモンだ!」といっていたのは、そんな所から来ている。そして、このヴァルナにも入れないのが、不可触選民といわれる階級の人々。上位のバラモンが指導者となって、太陽や風、雷などの自然の力に神が宿る考えこれを体系化したのがバラモン教であり、インド文化の基礎になっていく。インドや文化を総称してヒンドゥーというのだが、ヒンドゥー教の誕生はもうちょっと待ってください。
この身分制度に立ち向かったのは大勢いるが、なかなか破れない。かのお釈迦さまもその一人だったが、うまくいかなかった。仏教や不殺生で有名なジャイナ教などが生まれたが、やはりバラモンには勝てず、シヴァ神やヴィシュヌ神を崇拝するヒンドゥー教がまとまり、民間に定着していった。それが7世紀ころのことになる。
そこに加わるのがイスラム教である。同じ7世紀に誕生したイスラームは、どんどんと勢力を拡大し、西アジアからアフリカ、海を越えてヨーロッパのイベリア半島まで拡大した。そしてインドにも侵入し、北部を支配するようになっていった。16世紀から19世紀まで続くムガル帝国の王はイスラームであり、インド北部はイスラーム国家になる。すわ、戦争か?と思いきや、対立は起きない。ムガルの王はヒンドゥ―教徒と共存を図り、寛容な政策をとり、インドとイスラームを融合させた。インド=イスラーム文化が発達するのである。その代表がかの「タージ・マハル」だ。
17世紀の王、シャー=ジャハーンが愛妃のためにつくらせた墓で有名な「タージ・マハル」。丸い屋根や、4つの塔、壁にはアラベスクが刻まれているなど、代表的なイスラーム建築だ。しかし、徐々にイスラームとヒンドゥー教の対立が深まっていく。
その背景になるのは、あの国の存在である。今の世界の紛争の原因となっている国といえば、もちろんイギリスだ。大航海時代を経て、イギリスはアジアに進出を始めるが、その拠点となったのが、「東インド会社」だ。かのエリザベス女王の時である。この時から植民地化しようなどと思っていたわけではなく、新興国だったイギリスは、貿易をさせてもらう、という立場だった。しかし、帝国主義の進展により、イギリス・フランスなどの国は、アジアの植民地化に進んでいく。
その大きなきっかけになったのが、1757年に起こった「プラッシーの戦い」というイギリス対フランスのインドでの覇権争いである。当時のイギリスとフランスの戦いは世界各地で壮絶を極め、アメリカでのフレンチ・インディアン戦争や、ヨーロッパでの七年戦争も一連の戦争である。
フレンチ・インディアン戦争を描いた作品に「ラスト・オブ・モヒカン」がある。未見の方は、ぜひ。

さて「プラッシーの戦い」の勝利をきっかけに、イギリスは一気にインドの植民地化に着手する。イギリスは産業革命の真っただ中で、インドは、イギリス向けに原料となる綿花を栽培させ、インドの産業を壊滅させていく。かつてインドで盛んだった綿織物産業を壊滅させるために、織機を壊したり、技術者の腕を切り落とした、などという話がまことしやかに伝わっていたが、話が誇張されているのではないか、というが最近の説のようである。
しかし、インドの根幹をなしていた織物産業を駄目にしたのは間違いない。原料を安く買いたたき、製品を高く売りつける。綿花栽培を強制させられたインドでは、食糧不足に陥り、半端ない数の人々が餓死したといわれる。
もちろん、インドの人々が黙っていたわけではなく、たびたび反乱を起こしたが、そのたびに制圧され、さらに支配は過酷を極めた。その支配に利用したのが、宗教間の対立であった。この頃のイギリスのやってることをあげつらうと、真面目に反吐が出そうになるが、いかに効率よく支配するかの見本のようなやり口だ。
インドにはヒンドゥー教徒とイスラーム教徒(ムスリム)が共存していたが、ヒンドゥー教徒を中心に「インド国民会議」、ムスリムを中心とする「全インド・ムスリム連盟」が結成された。さて、イギリスは徐々に支配の範囲を広げていき、特に重要な地域は直接統治を敷いていった。もちろん、現地の人の不満は大きい。そこで、ヒンドゥー教徒とムスリムの対立をあおり、イギリスに目を向けないようにした。
「インド国民会議」は若干穏健で、目立った反英活動をしないと見越していたが、イギリスに対する反抗は強く、徐々に反英活動が活発化していく。そこでイギリスは、「インド国民会議」に対抗するために「全インド・ムスリム同盟」の活動を応援する。しかし、イギリスの思惑に反して、やはり反英運動に移行していく。
どちらも反英という立場では共通しているが、二つの組織を誕生させてしまい、それがのちのインドとパキスタンの対立に発展していってしまう。
「インド国民会議」に加わり、率いるようになっていったのはかのガンディーである。ガンディーはもちろんヒンドゥー教徒とムスリムを共存させる統一国家の形成を目指したが、「全インド・ムスリム連盟」はイスラーム教徒の国を作ることを譲らない。結局、1947年、ヒンドゥ―教徒の国と、イスラーム教徒の国をそれぞれ分かれて独立することになった。それがインドとパキスタンである。
しかし、インド国内にもまだまだムスリムはおり、もちろんパキスタンにもヒンドゥ―教徒がいた。彼らはそれぞれの国に迫害を逃れて民族大移動を始めたが、その際、多くが殺し合い、傷つけあってしまう。その対立を解消しようと奮闘したガンディーは、ヒンドゥ―教徒過激派に殺されてしまうのだ。
この辺は名作「ガンジー」に詳しく描かれています。

各々が独立してからも対立は解消するどころか、ますます溝が深まっています。カシミールの領有権やら、お隣の中国との絡みやら、どっちも核を保有してしまったもんで、超やばいと。そんなこんなの根深い対立が少女を苦しめてしまうという作りに、うまいなあ~と感心しました。宗教上の違いが、こんな大きな対立を生み出してしまうというのは、神様は絶対に望んでいないと思うのですがね~。
じゃあ、シャヒーダーを国に帰せばいいだけで、話は簡単と思いきや、そうはいかない。隣同士で国境が接している国だが、簡単に行き来ができない。インドとパキスタンの根深い対立が、小さな女の子の帰還を次から次へと阻むのだ。インド映画お決まりの歌あり、踊りあり、笑いあり、涙あり。しっかり長尺でおなかいっぱいになる作りだ。
では、なぜ簡単にいかなかったのか?インドとパキスタンは、超仲が悪い!対立しているやばい状況であるからに他ならない。
いまさらながら、インドとパキスタンの関係をもっかい見直してみたくなったというわけです。勝手にやります。インドとパキスタンの関係。悪い癖ですが、根っこから掘り起こさないとならない性分なもんで、古代のインドから始まります。
インドは亜大陸といわれるほど、でっかい面積を占めている。ということは、気候も幅広く、「インドは暑い!」と一言では片付けられないくらいに広い。人間は水のないところでは生きていけないので、集住していたところは、川の周辺となる。世界の古代文明の一つ、インダス文明の発祥地、インダス川のほとりに人々は集まって暮らした。そのインダス文明の担い手になったのが、インドにもともと住んでいた、ドラヴィダ人といわれる民族である。モエンジョ=ダロに代表されるインダス文明は、整然としており、高度な都市文明を築いた遺構が残っている。ドラヴィダ人の高い知性が想像できる。
そこに侵入してきたのが、中央アジアに住んでいたアーリア人である。アーリア人は、一方がヨーロッパに、一方がインドに移動したので、インド・ヨーロッパ語族というわけのわかんない名称になっているが、特徴としては色が白いこと。そしてドラヴィダ人は色が黒かった。インダス文明が衰えた後にインドの担い手となったのが、色の白いアーリア人となった。このアーリア人を頂点として、色の白い順になぜか身分制度ができてしまう。カースト制だ。カースト制の基礎となる原則に、人々を分けるヴァルナというものがあるのが、この言葉の意味は、すなわち「色」だ。
頂点にいるのが「バラモン(司祭)」、次が「クシャトリア(王侯・戦士)」、そして「ヴァイシャ(市民)」、4つめが「シュードラ(隷属民)」だ。もちろん色の白い順。映画の中で、パワンが女の子を見て、「色が白いからバラモンだ!」といっていたのは、そんな所から来ている。そして、このヴァルナにも入れないのが、不可触選民といわれる階級の人々。上位のバラモンが指導者となって、太陽や風、雷などの自然の力に神が宿る考えこれを体系化したのがバラモン教であり、インド文化の基礎になっていく。インドや文化を総称してヒンドゥーというのだが、ヒンドゥー教の誕生はもうちょっと待ってください。
この身分制度に立ち向かったのは大勢いるが、なかなか破れない。かのお釈迦さまもその一人だったが、うまくいかなかった。仏教や不殺生で有名なジャイナ教などが生まれたが、やはりバラモンには勝てず、シヴァ神やヴィシュヌ神を崇拝するヒンドゥー教がまとまり、民間に定着していった。それが7世紀ころのことになる。
そこに加わるのがイスラム教である。同じ7世紀に誕生したイスラームは、どんどんと勢力を拡大し、西アジアからアフリカ、海を越えてヨーロッパのイベリア半島まで拡大した。そしてインドにも侵入し、北部を支配するようになっていった。16世紀から19世紀まで続くムガル帝国の王はイスラームであり、インド北部はイスラーム国家になる。すわ、戦争か?と思いきや、対立は起きない。ムガルの王はヒンドゥ―教徒と共存を図り、寛容な政策をとり、インドとイスラームを融合させた。インド=イスラーム文化が発達するのである。その代表がかの「タージ・マハル」だ。
17世紀の王、シャー=ジャハーンが愛妃のためにつくらせた墓で有名な「タージ・マハル」。丸い屋根や、4つの塔、壁にはアラベスクが刻まれているなど、代表的なイスラーム建築だ。しかし、徐々にイスラームとヒンドゥー教の対立が深まっていく。
その背景になるのは、あの国の存在である。今の世界の紛争の原因となっている国といえば、もちろんイギリスだ。大航海時代を経て、イギリスはアジアに進出を始めるが、その拠点となったのが、「東インド会社」だ。かのエリザベス女王の時である。この時から植民地化しようなどと思っていたわけではなく、新興国だったイギリスは、貿易をさせてもらう、という立場だった。しかし、帝国主義の進展により、イギリス・フランスなどの国は、アジアの植民地化に進んでいく。
その大きなきっかけになったのが、1757年に起こった「プラッシーの戦い」というイギリス対フランスのインドでの覇権争いである。当時のイギリスとフランスの戦いは世界各地で壮絶を極め、アメリカでのフレンチ・インディアン戦争や、ヨーロッパでの七年戦争も一連の戦争である。
フレンチ・インディアン戦争を描いた作品に「ラスト・オブ・モヒカン」がある。未見の方は、ぜひ。

さて「プラッシーの戦い」の勝利をきっかけに、イギリスは一気にインドの植民地化に着手する。イギリスは産業革命の真っただ中で、インドは、イギリス向けに原料となる綿花を栽培させ、インドの産業を壊滅させていく。かつてインドで盛んだった綿織物産業を壊滅させるために、織機を壊したり、技術者の腕を切り落とした、などという話がまことしやかに伝わっていたが、話が誇張されているのではないか、というが最近の説のようである。
しかし、インドの根幹をなしていた織物産業を駄目にしたのは間違いない。原料を安く買いたたき、製品を高く売りつける。綿花栽培を強制させられたインドでは、食糧不足に陥り、半端ない数の人々が餓死したといわれる。
もちろん、インドの人々が黙っていたわけではなく、たびたび反乱を起こしたが、そのたびに制圧され、さらに支配は過酷を極めた。その支配に利用したのが、宗教間の対立であった。この頃のイギリスのやってることをあげつらうと、真面目に反吐が出そうになるが、いかに効率よく支配するかの見本のようなやり口だ。
インドにはヒンドゥー教徒とイスラーム教徒(ムスリム)が共存していたが、ヒンドゥー教徒を中心に「インド国民会議」、ムスリムを中心とする「全インド・ムスリム連盟」が結成された。さて、イギリスは徐々に支配の範囲を広げていき、特に重要な地域は直接統治を敷いていった。もちろん、現地の人の不満は大きい。そこで、ヒンドゥー教徒とムスリムの対立をあおり、イギリスに目を向けないようにした。
「インド国民会議」は若干穏健で、目立った反英活動をしないと見越していたが、イギリスに対する反抗は強く、徐々に反英活動が活発化していく。そこでイギリスは、「インド国民会議」に対抗するために「全インド・ムスリム同盟」の活動を応援する。しかし、イギリスの思惑に反して、やはり反英運動に移行していく。
どちらも反英という立場では共通しているが、二つの組織を誕生させてしまい、それがのちのインドとパキスタンの対立に発展していってしまう。
「インド国民会議」に加わり、率いるようになっていったのはかのガンディーである。ガンディーはもちろんヒンドゥー教徒とムスリムを共存させる統一国家の形成を目指したが、「全インド・ムスリム連盟」はイスラーム教徒の国を作ることを譲らない。結局、1947年、ヒンドゥ―教徒の国と、イスラーム教徒の国をそれぞれ分かれて独立することになった。それがインドとパキスタンである。
しかし、インド国内にもまだまだムスリムはおり、もちろんパキスタンにもヒンドゥ―教徒がいた。彼らはそれぞれの国に迫害を逃れて民族大移動を始めたが、その際、多くが殺し合い、傷つけあってしまう。その対立を解消しようと奮闘したガンディーは、ヒンドゥ―教徒過激派に殺されてしまうのだ。
この辺は名作「ガンジー」に詳しく描かれています。

各々が独立してからも対立は解消するどころか、ますます溝が深まっています。カシミールの領有権やら、お隣の中国との絡みやら、どっちも核を保有してしまったもんで、超やばいと。そんなこんなの根深い対立が少女を苦しめてしまうという作りに、うまいなあ~と感心しました。宗教上の違いが、こんな大きな対立を生み出してしまうというのは、神様は絶対に望んでいないと思うのですがね~。










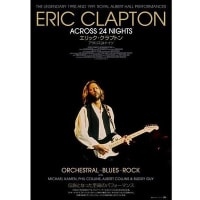









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます