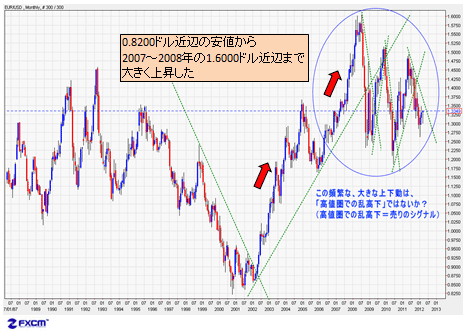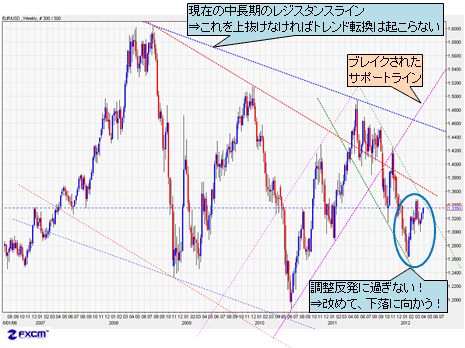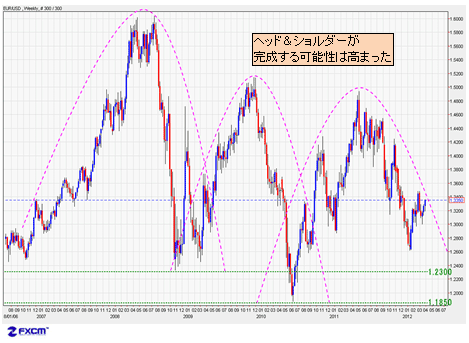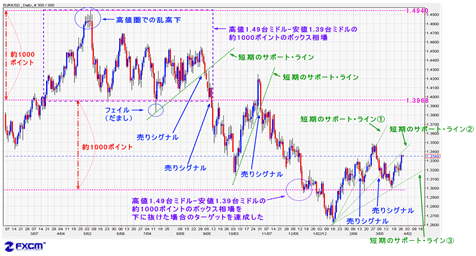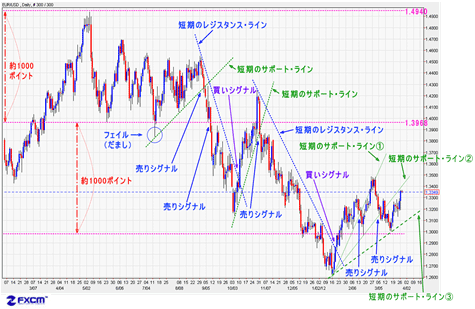2012年03月28日(水)東京時間 12:57 松田 哲
目先の相場では、FRB(米連邦準備制度理事会)のバーナンキ議長が「金融緩和は雇用の大幅拡大をもたらすために必要」と発言したことで、ユーロ/米ドルは、「ユーロ買い・米ドル売り」に反応している。マーケットで、米国の金融緩和政策が継続するとの期待が高まったためだ。
しかし、米国の金融緩和策が継続されることは、以前からバーナンキ議長が明言していることであり、新たな材料とは言い難い。
あえて言うならば、「米国の『QE3(第3次量的緩和策)』が、いずれ実施されるのではないか」といった期待が高まったということだろう。本当に実施されると、米ドルが余剰となるため、米ドル売りの材料となる。
つまり、目先の相場は、そういった思惑でフワフワとした値動きになっているように感じる。
■月足では、現在は「高値圏での乱高下」を見せている
個人的には、基本的な考え方を変える必要はないと考えている。以下、このところのコメントと同じ内容であることに、ご留意いただきたい(「欧州の『ごまかし』『詭弁』に惑わされるな!ギリシャ問題は小康状態のように映るだけ」など参照)。
大局で判断すれば「ユーロ売り」で戦うべきである。
(出所:米国FXCM)
まずは、ユーロ/米ドルの月足チャートからご覧いただきたい。
ユーロ/米ドルは、0.8200ドル近辺の安値から1.6000ドル近辺まで大きく上昇した。そして、1.6000ドル近辺で高値をつけてからは、安値は1.2000ドルレベル、高値は1.6000ドルレベルのゾーンで、大きく上下動を繰り返している。
この大きな上下動については、個人的には「高値圏での乱高下」だと判断している。いつもではないが、一般的には、この「高値圏での乱高下」は「売りシグナル」となる。
つまり、この大きな上下動は、いずれ、ネックライン(下限)を下に割り込むという示唆と推測している。当然ながら、1.2000ドル近辺のネックラインを割り込む場合は、その後に大きく下落するだろう。
■2007~2008年頃から、頻繁にトレンド転換が起きている
続いて、ユーロ/米ドルの週足チャートをご覧いただきたい。
ここで留意していただきたいのは、かなり長い期間の週足チャートを見ても、上記の月足チャートで見た「高値圏での乱高下」の部分だけしか表示されていないことである。
つまり、ユーロ/米ドルは、2007~2008年頃から現在にいたるまで、かなり激しく大きな上下動を繰り返しているということに注意が必要だ。
言い方を変えれば、2007~2008年頃から現在まで、かなり頻繁にトレンド転換が起こっているということだ。
通常は、これほど頻繁にトレンド転換は起こらない。現在の相場は、異常な状態なのである。
(出所:米国FXCM)
ユーロ/米ドルは2011年4月上旬に、赤の破線で示した中長期のレジスタンスラインを上抜け、その時点で「買いシグナル」を発した。赤の破線(細線)は赤の破線(太線)の平行線である。
だが、2011年5月5日以降は大きく急落し、中長期のレジスタンスラインとして、青の破線(太線)が改めて出現した。青の破線(細線)はその平行線である。
俯瞰(ふかん)して見ると、ユーロ/米ドルは2010年6月安値の1.18ドル台を起点に、ピンクの破線(太線)で示したサポートラインに沿って上昇した。なお、ピンクの破線(細線)はピンクの破線(太線)の平行線である。
結局、ユーロ/米ドルは、青の破線(太線)のレジスタンスラインとピンクの破線(太線)のサポートラインに挟まれて、大きな「三角保ち合い(ウェッジ)」を形成していたと言える。
そして、2011年9月9日に、このピンクの破線(太線)のサポートラインを下に割り込んだ。つまり、ピンクの破線(太線)を明確に下に割り込んだので、「売りシグナル」が点灯した。
ユーロ/米ドルはその後、「売りシグナル」のとおりに1.31ドル台まで大きく下落したが、2011年10月下旬に、ユーロ危機に対する包括案が合意に達したことを材料にして、1.42ドル台まで急騰した。
だが、大局で見れば、週足チャートに表示した青の破線のレジスタンスラインを上抜けない限り、トレンドは変わらない。
1.42ドル台まで急反発したものの、2011年10月31日に1.38ドル台まで急落したことによって、改めて「売りシグナル」を発したと考えている。
(出所:米国FXCM)
その後も下落が続き、1.26ドル台まで急落しており、シグナルどおりに動いたと言えるだろう。
目先では、1.26ドル台を見てから大きく反発上昇しているものの、今のところ、これは調整の反発に過ぎないと考えている。改めて、トレンドに従って下落するだろう。
なお、2011年5月5日以降の大きな下落について、右下がりではあるが、サポートラインを緑の破線(太線)で加筆した。緑の破線(細線)は、その平行線である。このサポートラインの傾き、スピードで下落していることをご確認いただきたい。
■「ヘッド&ショルダー」が完成する可能性が高まった!
続いても、ユーロ/米ドルの週足チャートをご覧いただきたい。
ユーロ/米ドルは中長期のチャートの形状から「ヘッド&ショルダー(※)」の可能性を考えていたが、1.18ドル台から大きく上昇しているので微妙になっていた。
だが、その後の値動きにより、今現在で見れば、「ヘッド&ショルダー」が完成する可能性が高まっていると考えている。
(※編集部注:「ヘッド&ショルダー」はチャートのパターンの1つで、天井を示す典型的な形とされている。人の頭と両肩に見立てて「ヘッド&ショルダー」と呼び、仏像が3体並んでいるように見えるため「三尊」と呼ぶこともある)
(出所:米国FXCM)
2011年5月4日の高値である1.4940ドルが右肩の高値となるケースを想定して、「ヘッド&ショルダー」の「3つの山」が示唆されている。
「ヘッド&ショルダー」は、それが完成した時点で粛々と対応すればよいのだから、現時点でも「ヘッド&ショルダー」を想定するのは時期尚早なのだが…。 完成するまでは、時期尚早の状態が続くこととなる。
「ヘッド&ショルダー」はネックラインを明確に割り込んだ時点で対応するべきで、「ヘッド&ショルダー」を作るかもしれないといった予見(予測)でポジションを取ると、失敗することがよくある。
しかし、当初考えていたパターンよりも、完成する時期は大きく先送りされたものの、「ヘッド&ショルダー」が完成する可能性は十分に高いと考えている。繰り返しとなるが、「ヘッド&ショルダー」は、それが完成した時点で粛々と対応すればよい。
なお、右肩の高値である1.49ドル台ミドルから、すでに大きく下落しているが、ここからネックラインの1.2300ドル、または、1.1850ドルを下に割り込む場合は、さらに急落する可能性が高くなる。すなわち、「売りシグナル」が点灯するということになる。
■結果的に、昨年7月の売りシグナルは「フェイル」だった
今度は、ユーロ/米ドルの日足チャートを、次のページでご覧いただきたい。
ユーロ/米ドルは2011年5月上旬に、高値を更新して上昇した。通常だと、高値更新は「買いシグナル」となる。
しかし、その際に高値圏での乱高下に映る値動きが見られた。必ずではないが、「高値圏での乱高下」は天井を示唆する場合がある。
結論から言えば、2011年5月のケースは、事前に察知したとおりに、「高値圏での乱高下」が天井を示唆していたことになった。
俯瞰(ふかん)すると、2011年3月頃から9月上旬までの間、下値が1.39ドル台ミドル、上値が1.49ドル台ミドルの「ボックス相場」を形成していたと言える。
下のチャートには、ピンクの水平線で「ボックス相場」の下値と上値を示し、約1000ポイントの「ボックス相場」を紫の破線で囲んで表示した。この「ボックス相場」の下値を明確に下にブレイクする場合は「売りシグナル」が点灯する。
その場合、「ボックス相場のセオリー」に従うと、ボックスの高値と安値の値幅分、ボックスの下値から約1000ポイント下落したところがターゲットになる。計算すると、ターゲットは1.2900ドル近辺となる。
(出所:米国FXCM)
実際のところ、日足チャートのように、2011年7月12日に1.3968ドルを割り込んだ。これにより「売りシグナル」が点灯し、1.3836ドルの安値をつけた。
だが、この時点では、ギリシャ問題に対する対症療法的な政策がなされたため、1.3836ドルから大きく反発上昇した。
結果的に、2011年7月中旬の「売りシグナル」の点灯は、典型的な「フェイル(だまし)」となった。
■「ボックス相場」を下抜けた場合のターゲットを達成した
「フェイル(だまし)」であるのか、否かは、後でわかることで、その時点ではわからない。だから、「フェイル(だまし)」であろうとも、ここは「売り」でついていくところだった。
こういったケースでは、ストップ・ロス(損切り)がついて実損が出るだろうが、それでよい。個人的には、こういったところで損を出さないと、利益も出せないと考えている。
日足チャートを見てのとおり、2011年7~8月の夏休み相場を経て、9月上旬に1.3968ドルを割り込み、その時点で「売りシグナル」を発した。
さらに、2011年7月12日の安値である1.3836ドルも割り込んだ。安値更新の時点で、再び「売りシグナル」を発したことになる。
1.3836ドルを割り込んでからも下落が続き、1.31ドル台まで急落した。しかし、ターゲットである1.29ドル台には届かずに反転した。
調整反発の上値メドとして、日足チャートに示した1.3968ドル(あるいは1.4000ドルレベル)を見ていたが、現地時間2011年10月26日に行われたEU(欧州連合)首脳会議で、ユーロ圏の債務危機打開に向けた包括策が合意に達したことを材料に、節目の1.4000ドルを上抜けた。
この時点では、売り方はいったん損切りを敢行し、改めて売り場を探すところだった。
大局での「ユーロ売り戦略」に変化はないが、最近のユーロ/米ドルは、欧州債務危機に関する材料で大きく振幅しており、無理をするのは危険だ。
ところが、日足チャートに示したように、緑の破線で示した短期のサポートラインを割り込み、「売りシグナル」を発した。
あまりにもアップダウンが激しく、右往左往するが、ここは「ユーロ売り」でついて行くところだった。
これだけ振幅が激しいのだから、改めて、1.41ドル台や1.42ドル台があれば、そこも売る覚悟がないと、1.38ドル台で売るのは難しい。ストップ・ロスは戻り高値である1.4246ドルよりも上に置く必要があった。
また、1.41ドル台や1.42ドル台、あるいは1.40ドル台でも売ることができるように、ポジションをコントロールするべきだ。
1.38ドル台で再度「売りシグナル」を発したが、ストップ・ロスは1.42ドル台に置かざるを得ず、かなり遠い。よって、1.42ドル台にストップ・ロスを置くにふさわしい水準でも売れるように、ポジションをコントロールするべきであった。
なお、ユーロ/米ドルは、2011年12月14日に節目の1.3000ドルを割り込み、1.2945ドルまで下落した。
これにより、下値が1.39ドル台ミドル、上値が1.49ドル台ミドルの紫の破線で囲んだ「ボックス相場」を下抜けた場合のターゲットを完全に達成したと判断している。
■大勢は「ユーロ安・米ドル高」のトレンドで変わらない
ギリシャなど欧州の不良債権問題には、いろいろと対応策が出ている。だが、関係各国や関係機関の思惑が一致せず、根本的な解決策とならないものばかりだ。
EU財務相会合では、ギリシャに1300億ユーロの追加支援を実行することで合意がなされた。これで、ギリシャは3月に期限を迎える国債の大量償還を乗り切れたため、この時点での国家破綻は避けることができた。
しかし、この時点の国家破綻を回避できただけで、何も問題は解決していない。
ギリシャ問題を解決できなければ、欧州の不良債権問題はイタリアや周辺国に拡大する可能性が高い。その旨、このコラムでも何度も記述してきたが、実際にイタリアや周辺国にも波及した。
基本的には、「ユーロ売り・米ドル買い」の方向でポジションを作るべきだ。
(出所:米国FXCM)
上の日足チャートに、青の破線で短期のレジスタンスラインを加筆した。ユーロ/米ドルは昨年10月下旬以降、この短期のレジスタンスラインに従って大きく下落していたが、目先では上抜けたので、「買いシグナル」を発した。
もし、高値圏で「ユーロ売り・米ドル買い」を行って、持ち値のよいポジションを持っていた場合は、いったん「利食いの買い戻し」を行い、次の「ユーロ売り」のタイミングを計るところであった。
だが、多少のリバウンド(反発上昇)があっても、大勢は変わらずに「ユーロ安・米ドル高」のトレンドである。だから、「ユーロ売り」で戦うべきである。
「値ごろ感でのユーロ買い」は、やらないほうがよい。そういった「アヤ狙いのユーロ買い」は目先でうまくいっても、悪いクセが残り、最終的には致命傷に至る。厳に慎むべし、と考える。
■引き続き、1.3500ドル近辺がレジスタンスとなっている
欧州の不良債権問題は根本的な解決策に向かっておらず、大きな流れ(大局)での「ユーロ安・米ドル高」のトレンドを変えることはできない。やるならば「ユーロ売り」である。
目先では、ユーロ/米ドルは1.26ドル台の安値をつけてから、調整反発をしている。リバウンド(反発上昇)を待っているときにリバウンドがないこともしばしばあるが、今回は調整反発が起きている。
ここで気をつけなければならないことは、事前には、リバウンドの大きさと時間は誰にもわからないということだ。
したがって、あくまでも個人的なカン(感覚)に過ぎないが、リバウンドしても上値のメドは1.3300ドルあたりで、1.35ドル台がマックスだと考えていた。
以前、このコラムでも解説したが、ユーロ/米ドルは700ポイントで「ボックス相場」を作るケースが多い。安値を1.26ドル台とすると、そこから700ポイント上は1.33ドル近辺であり、この水準が上限になる可能性が高いと考えていた(「ユーロ/ドル(EUR/USD)は[700ポイント]で変動する」など参照)。
しかし、実際のところは1.33ドル台前半を上抜けて、その時点で「買いシグナル」が点灯している。
それでも、1.3500ドル近辺のレジスタンスは、依然として有効である。
したがって、ユーロのショート派(売り方)は、1.35ドル台ミドルあたりにストップ・ロス・オーダー(損切り注文)を置いて、改めての「売り場探し」である。
このような調整反発局面で「売り」で戦う場合、便宜的なストップ・ロスを入れておき、ストップがついた場合には、改めて持ち値のよいところで売り直すといったテクニックが要求される。
対応が難しいのは十分に承知しているが、そういった対応をすべきだ。
■1.35ドル台ミドルにストップを置いて、少額でユーロ売り!
最後にもう一度、日足チャートをご覧いただきたい。その右端に、短期のサポートラインとして緑の破線を3本加筆した。
目先の相場では、リバウンド(反発上昇)の高値を更新して1.33ドル台をつけたことから「買いシグナル」が点灯したのだが、上値は2月下旬につけた1.3500ドル近辺にとどまり、そこでアタマを抑えられた格好だ。
引き続き、緑の破線で示した短期のサポートラインを下に割り込む場合は、「売りシグナル」が改めて点灯する。体制を立て直して、改めて「売り場」を探すところとなる。
1本目の「短期のサポートライン(1)」を割り込み、その時点で「売りシグナル」を発したが、今度は2本目の「短期のサポートライン(2)」が現れた。
その後、この2本目の「短期のサポートライン(2)」も割り込み、その時点で「売りシグナル」を発したのだが、再度、1.3000ドル近辺でサポートされて、3本目の「短期のサポートライン(3)」が現れている。
もちろん、この3本目の「短期のサポートライン(3)」を割り込む場合は、改めて「売りシグナル」が点灯する。
(出所:米国FXCM)
今のところ、戻り高値は2月下旬につけた1.34ドル台後半までで、1.35ドル台には乗せていない。戻り高値がいくらになるのか、事前には誰もわからない。
そのため、適当に1.35ドル台ミドルにストップ・ロスを置いて、少額で「ユーロ売り・米ドル買い」がよいと考えている。
そして、このストップ・ロスがつくようならば、改めて、そこから「売り場」を探すべきである。
なお、1.35ドル台に乗せてすぐの1.3500ドル近辺、あるいは、1.3520ドルといったところのストップ・ロスは近すぎる。1.3550ドルを超えたところにストップ・ロスを置くのがよい。
目先の相場では、1.3000ドル近辺でサポートされた格好になっているが、2本目の「短期のサポートライン(2)」を割り込んだことで、「売りシグナル」が持続した状態である。
ちなみに、この「売りシグナル」は1.3500ドルを上抜けると消滅する。だから、現時点のチャート分析での明確なストップ・ロスは、1.3550ドルを超えたところにすべきだと考えているのだ。
だが、現状レベルで「ユーロ売り・米ドル買い」で参入する場合、1.35ドル台ミドルのストップ・ロスでは遠過ぎる。そのように感じるのは理解できる。
したがって、100ポイント上や200ポイント上に、便宜的なストップ・ロスを置くといったテクニックを使うべきである。
「リスクを小さくして、リターン(期待利益)は大きくする」といった、自分にだけ都合のよいテクニックは存在しない。
(2012年03月28日 東京時間03:05記述)