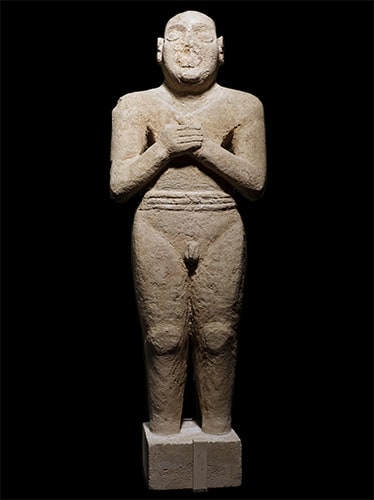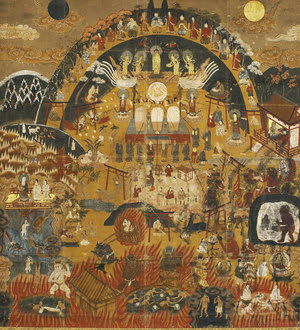アルフォンス・マリア・ミュシャ(Alfons Maria Mucha)(1860-1939)。チェコ語表記ではムハ。オーストリア帝国領モラヴィア(現代のチェコ)生れ。
(1)アール・ヌーヴォーの旗手(1895年、35歳)
ミュシャ、19歳、ウィーンで夜間のデッサン学校に通う。23歳、エゴン伯爵がパトロンとなる。25歳、ミュンヘン美術院に入学。28歳、パリにてアカデミー・ジュリアンに通う。
彼の出世作は1895年(35歳)、舞台女優サラ・ベルナールの「ジスモンダ」のポスターである。この作品は、パリにおいて大好評を博し、彼はアール・ヌーヴォーの旗手となる。
煙草用巻紙(JOB社)、シャンパン(モエ・エ・シャンドン社)、自転車(ウェイバリー自転車)などのポスター制作もおこなう。
ミュシャは、また、装飾パネルも多く手がける。連作『四季』(1896)など。
パリでの初期苦闘時代、ミュシャは雑誌の挿絵によって生計を立てた。次第に認められ、パリの大出版社、アルマン・コランの挿画家として活躍。最初に高い評価を得たのが、『白い象の伝説』の木版画33点(1894年)だった。

(2)万国博覧会ボスニア・ヘルツェゴビナ館の壁画装飾(1900年、40歳)
1900年、万国博覧会でボスニア・ヘルツェゴビナ館の壁画装飾を手がけたことがきっかけとなり、ミュシャはその活動を変える。作品制作のため、現地を訪れたミュシャは、オーストリア帝国支配下の現地の人々の窮乏ぶりに驚き、「僕は今まで何をやっていたんだ・・・」と思う。
そして後半生を、画業を通しスラヴ民族の意識高揚のために尽くそうと決意する。
彼の生まれ故郷チェコも、同じスラヴ民族として、繰り返し異民族であるゲルマン系民族の侵攻に苦しんだ。
(3)『スラヴ叙事詩』制作の3者契約(1909年、49歳)
愛国主義に目覚めたミュシャは、『スラヴ叙事詩』制作を決意する。それは、スラヴの諸言語を話す人々が古代は統一民族であったという「汎スラヴ主義」にもとづく。スメタナの組曲『わが祖国』(1882年初演)を聴いたことで、構想を抱いたといわれる。
パトロン探しと資金集めに、ミュシャは、1905年一旦、アメリカへ渡る。1909年、パトロンのチャールズ・クレイン、プラハ市と3者契約を締結し、チェコへ帰郷。『スラヴ叙事詩』制作に専念する。
(4)チェコスロバキア共和国成立と『スラヴ叙事詩』の発表(1918-9年、58-9歳)
第1次大戦後、1918年、オーストリア帝国が崩壊し、チェコスロバキア共和国が成立。ミュシャは、新国家のため紙幣、切手、国章などのデザインを無報酬で請け負う。
1919年、20点の絵画から成る連作『スラヴ叙事詩』が初めて展覧会で発表された。さらに、完全版が1928年に再度発表される。しかし彼が描いたアカデミックなスタイルの具象画は、「時代遅れ」とみなされ、評判は今ひとつだった。

(5)ナチスドイツによるチェコスロバキアの占領・解体とミュシャの死(1939年、79歳)
1939年春、ナチスドイツがチェコスロバキアを占領・解体すると、ミュシャは「愛国者」として逮捕される。ミュシャ(78歳)は厳しく尋問され、釈放の4ヶ月後、死去する。
『スラヴ叙事詩』は、彼の没後、長らく美術史から姿を消す。
(6)チェコスロバキア独立(1945年)&共産党政権(1948年成立)によるミュシャ黙殺
第二次大戦後、チェコスロバキアは独立を果たす(1945年)。さらに、1948年に共産党政権が成立。共産党政権は、愛国心との結びつきを警戒し、ミュシャの存在を黙殺した。
『スラヴ叙事詩』は、わずかに毎年夏、ミュシャの生まれ故郷にあるモラフスキー・クルムロフ城でひっそりと公開されるのみだった。
しかし、チェコ国民のミュシャへの敬愛は生き続け、プラハの春翌年の1969年には、ミュシャの絵画切手数種が制作された。
世界的には、1960年代以降のアール・ヌーヴォー再評価とともに、ミュシャは、改めて高い評価を受けた。
(7)ビロード革命による共産党政権崩壊(1989年)&『スラヴ叙事詩』がチェコ・プラハ市の市民会館へ戻る(2012年)
1989年、ビロード革命で共産党政権が崩壊。
1993年、連邦解消法に基づきチェコ共和国とスロバキア共和国が分離(ビロード離婚)。
ミュシャの『スラヴ叙事詩』の再評価が進み、2012年、チェコの首都、プラハ市の市民会館へ戻った。