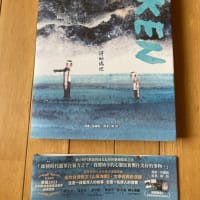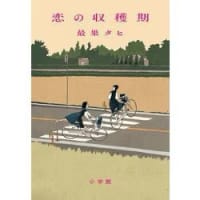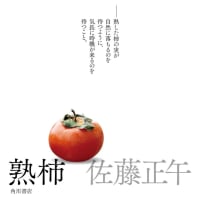待ちに待った映画だ。公開がなかなか決まらず、いったいどれだけ待たされるのか、気が気ではなかった。いくらなんでも公開されないだなんてことはあるまいとは思いつつも、ようやく公開が決まり、凄い量の試写会が今行われているようだ。松竹が自信を持って送る最新作である。できることならスマッシュ・ヒットを遂げてもらいたい。これは、それだけの力のある作品だから。
シナリオライターの大森寿美男の監督デビュー作である。数々の傑作映画の脚本を手掛け、満を持しての監督デビューだが、最初からこんなにもハードルの高い映画に挑み成功している。
これは中途半端な大作では意味がない。箱根駅伝を舞台にしたこの作品は、スケールの大きい作品でなくてはならない。それは何も大袈裟な仕掛とか、SFXとかを駆使したハリウッド大作とは違う。当たり前のことだ。この映画の命は、箱根駅伝をそのまま再現するところにある。それが出来なくてはありえない。
しょぼい映画にしてはならないのだ。スケール感は十分に保ちながら、彼ら10人の挑戦をリアルに捉えなくては成立しない。だからこれはとても困難な挑戦になる。だいたい原作となった三浦しをんの小説が素晴らしすぎるから、それをそのまま映画にするのは不可能に近い。
あれだけの膨大な分量である。10人のキャラクターをきちんと描き分け、その中から、彼らがありえない挑戦に挑み、それを成し遂げていく奇跡を納得のいく描写で見せなくてはならないのだ。2時間13分という長さは映画としては長い方だろうが、この小説を見せるにはあまりに短すぎる。はたして大丈夫なのか、心配だった。
だが、心配は杞憂に終わった。ちゃんとこのお話を映画として立ち上げている。前半の彼らがチームとして動き出し予選会を通過するまでが、コンパクトに、だがしっかりと描けていた。そりゃぁ原作のままにはならない。そんなことをしたら何時間あっても足りない。ポイントを外さず、必要なことだけをきちんと見せる。それだけで十分なのだ。だが、それは難しい。しかも、それだけでは誰も褒めない。勝負はそれからなのだから。
この映画の本題は箱根駅伝そのものなのだ。彼らが現実に箱根の舞台に立ち、正月の箱根を走り抜ける。その姿をきちんと撮ったなら、成立する。そして、そんなふうに思える映画にしなくてはならないのだ。それが与えられた使命である。
そこには、嘘があってはならない。彼らが、ただ走るだけの姿を追いかけるだけで、それだけで感動する。そんな映画にしなくてはならない。音楽で盛り上げて、とかなしだ。大仰なドラマもご法度だ。ただ、正攻法で攻めていく。ひたすらに走る。何も考えずに走り続ける。それだけで感動させるために、この映画はある。そこにはつまらない理屈とかはいらない。
大森監督と彼のスタッフはそんな困難を乗り越える。ただ、走るためだけに、この映画はあった。つまらない小細工はない。今この瞬間を生きる。この後どうなるかなんてわからないし、考える気もない。
ハイジ(小出恵介)はこの後、もう自由には走れないだろう。だが、そんなこと、どうでもいい。人生の残りをすべてこの瞬間と引き換えにしてもかまわない。生きていることの実感を摑むため、箱根の10区を走り抜ける。
区間新記録を達成し、再び走ることで生きていけるようになるカケル(林遣都)は、名誉だとか、栄光とか、そんなものではなく、本当の意味で走ることをハイジから教えられる。それは彼らがこの闘いを通してそれぞれが手にしたことだ。この奇跡が最初で最後の挑戦だった。寛政大学の陸上部のたった10人の軌跡は、この2時間13分の映画の中に、しっかり描かれてある。目撃せよ!
シナリオライターの大森寿美男の監督デビュー作である。数々の傑作映画の脚本を手掛け、満を持しての監督デビューだが、最初からこんなにもハードルの高い映画に挑み成功している。
これは中途半端な大作では意味がない。箱根駅伝を舞台にしたこの作品は、スケールの大きい作品でなくてはならない。それは何も大袈裟な仕掛とか、SFXとかを駆使したハリウッド大作とは違う。当たり前のことだ。この映画の命は、箱根駅伝をそのまま再現するところにある。それが出来なくてはありえない。
しょぼい映画にしてはならないのだ。スケール感は十分に保ちながら、彼ら10人の挑戦をリアルに捉えなくては成立しない。だからこれはとても困難な挑戦になる。だいたい原作となった三浦しをんの小説が素晴らしすぎるから、それをそのまま映画にするのは不可能に近い。
あれだけの膨大な分量である。10人のキャラクターをきちんと描き分け、その中から、彼らがありえない挑戦に挑み、それを成し遂げていく奇跡を納得のいく描写で見せなくてはならないのだ。2時間13分という長さは映画としては長い方だろうが、この小説を見せるにはあまりに短すぎる。はたして大丈夫なのか、心配だった。
だが、心配は杞憂に終わった。ちゃんとこのお話を映画として立ち上げている。前半の彼らがチームとして動き出し予選会を通過するまでが、コンパクトに、だがしっかりと描けていた。そりゃぁ原作のままにはならない。そんなことをしたら何時間あっても足りない。ポイントを外さず、必要なことだけをきちんと見せる。それだけで十分なのだ。だが、それは難しい。しかも、それだけでは誰も褒めない。勝負はそれからなのだから。
この映画の本題は箱根駅伝そのものなのだ。彼らが現実に箱根の舞台に立ち、正月の箱根を走り抜ける。その姿をきちんと撮ったなら、成立する。そして、そんなふうに思える映画にしなくてはならないのだ。それが与えられた使命である。
そこには、嘘があってはならない。彼らが、ただ走るだけの姿を追いかけるだけで、それだけで感動する。そんな映画にしなくてはならない。音楽で盛り上げて、とかなしだ。大仰なドラマもご法度だ。ただ、正攻法で攻めていく。ひたすらに走る。何も考えずに走り続ける。それだけで感動させるために、この映画はある。そこにはつまらない理屈とかはいらない。
大森監督と彼のスタッフはそんな困難を乗り越える。ただ、走るためだけに、この映画はあった。つまらない小細工はない。今この瞬間を生きる。この後どうなるかなんてわからないし、考える気もない。
ハイジ(小出恵介)はこの後、もう自由には走れないだろう。だが、そんなこと、どうでもいい。人生の残りをすべてこの瞬間と引き換えにしてもかまわない。生きていることの実感を摑むため、箱根の10区を走り抜ける。
区間新記録を達成し、再び走ることで生きていけるようになるカケル(林遣都)は、名誉だとか、栄光とか、そんなものではなく、本当の意味で走ることをハイジから教えられる。それは彼らがこの闘いを通してそれぞれが手にしたことだ。この奇跡が最初で最後の挑戦だった。寛政大学の陸上部のたった10人の軌跡は、この2時間13分の映画の中に、しっかり描かれてある。目撃せよ!