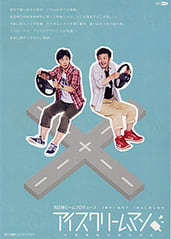
表面的には軽妙なドラマに見えて、その底に流れるドロドロしたものは、とても厭らしくて、重いドラマだ。地方にある合宿制の自動車教習所を舞台にした若者たちの人間模様が描かれる岩松了の92年作品。この作品は11年前に太陽族、岩崎正裕さんの演出により一度、見ている。あれとはまるでタッチの違う作品になる。それを期待して見た。
今回、横山拓也さんに求められたのは、「軽さ」である。そのために役者たちはいささかオーバーアクト気味に演じている。悪くはない。前半はなかなか快調である。笑って見ながら、徐々に本質に迫っていくうちに、その笑いは凍っていくことになる。ラストの事故死のエピソードに集約される残酷さがいかに生きてくるかが演出のポイントになる。
誰もが抱えるそれぞれの事情を表に出すことなく、内に秘めながら表面的なレベルで付き合う。もともと彼らは見ず知らずの他人でしかない。人生に於けるほんの数週間をなんとなく共に過ごし、もう2度と会うこともない。免許を取ること、という共通の目的はあるけど、接点はただそれだけで、それ以外の面で深く付き合っていく必要なんてないし、ここでの出会いが、一生の出会いにならないというわけではないけど、それは後々思うことで、ここにいる間、ここで友情を深めていくわけではない。
パブリック・スペースである宿泊所のロビーを舞台にして、当たり障りのない会話に終始する。よくは知らないもの同士が、遠慮しあいながらも、気がつけば自分たちのエゴをむき出しにして、話すくだらないやりとりは、それだけで醜い。しかも、そこに潜んでいるのは、性的な欲望だったりもして、若い男女が同じ場所で、寝泊まりしているわけだから、それぞれの内にいろんな感情が秘められていたりもするのは当然のことで、それを当たりさわりのないところで誤魔化しながら時を過ごしている。
人間関係の希薄さと、そこに潜む無神経な残酷さを軽やかなタッチで、描いていく横山さんの作風と、この作品の持つカラーは微妙にリンクしており、まるで横山さんのオリジナル新作を見ているような気分にさせられる。だが、かなりいい線までいくのだが、それがあと少しの所で、殺がれてしまう。終盤、芝居自体はテーマに向けて収斂していくにも関わらず、核心から遠ざかっていく気がするのはなぜか? それは、きっと岩松さんの求心力と、横山さんのそれが違うからだ。
この芝居の主人公は、この場に於いてニュートラルな位置にある早苗(物延結)である。彼女はこの宿泊棟の受付と彼らの世話を担当している管理者側の人間だ。芝居は、彼女の内的葛藤にすべてを集約させようとするのだが、あと一歩のところで、上手くいってない。彼女が抱え込もうとする闇を、芝居全体が支え切れていないからだ。群像劇の中に彼女の存在が埋もれてしまうのは、この作品にとって、プラスでもあり、マイナスでもある。とても微妙な問題だ。彼女の感情が爆発するシーンを敢えて作らないことで、その闇の深さを核心として据えることが可能だ。だがそれが、このままでは事故のインパクトの前では、薄まってしまう。台本と演出との齟齬が生じる。惜しい。
今の横山演出は岩松さんのように、簡単に答えを出そうとはしない。芝居は後半、どんどん重くなっていくが、それは横山さんのやり方ではない。これが彼の台本なら、この軽いトーンをラストまで貫いて、もっとフラットな芝居として見せるはずだ。それは彼の前作『トバスアタマ』を見れば、明らかである。今の時代は明確な答えを提示することを良しとしない情況にある。そこが、この芝居が書かれた90年代と00年代の違いであり、残念だが、この2010年という時代の気分をこの芝居は体現しない。その結果、本来なら、芝居が一気に盛り上がって行くところで、どんどん醒めていくという事態が生じてしまうこととなった。それは横山さんのせいではなく、あくまでも台本自体の問題であろう。とても優れた台本だからこそ、今の時代にはそぐわない。演出との齟齬は致命的である。
ただ、この作品との格闘を経由して、売込隊ビームは次で必ず凄いものを見せてくれるものと期待する。横山さんのリベンジはもうここから始まっている。
今回、横山拓也さんに求められたのは、「軽さ」である。そのために役者たちはいささかオーバーアクト気味に演じている。悪くはない。前半はなかなか快調である。笑って見ながら、徐々に本質に迫っていくうちに、その笑いは凍っていくことになる。ラストの事故死のエピソードに集約される残酷さがいかに生きてくるかが演出のポイントになる。
誰もが抱えるそれぞれの事情を表に出すことなく、内に秘めながら表面的なレベルで付き合う。もともと彼らは見ず知らずの他人でしかない。人生に於けるほんの数週間をなんとなく共に過ごし、もう2度と会うこともない。免許を取ること、という共通の目的はあるけど、接点はただそれだけで、それ以外の面で深く付き合っていく必要なんてないし、ここでの出会いが、一生の出会いにならないというわけではないけど、それは後々思うことで、ここにいる間、ここで友情を深めていくわけではない。
パブリック・スペースである宿泊所のロビーを舞台にして、当たり障りのない会話に終始する。よくは知らないもの同士が、遠慮しあいながらも、気がつけば自分たちのエゴをむき出しにして、話すくだらないやりとりは、それだけで醜い。しかも、そこに潜んでいるのは、性的な欲望だったりもして、若い男女が同じ場所で、寝泊まりしているわけだから、それぞれの内にいろんな感情が秘められていたりもするのは当然のことで、それを当たりさわりのないところで誤魔化しながら時を過ごしている。
人間関係の希薄さと、そこに潜む無神経な残酷さを軽やかなタッチで、描いていく横山さんの作風と、この作品の持つカラーは微妙にリンクしており、まるで横山さんのオリジナル新作を見ているような気分にさせられる。だが、かなりいい線までいくのだが、それがあと少しの所で、殺がれてしまう。終盤、芝居自体はテーマに向けて収斂していくにも関わらず、核心から遠ざかっていく気がするのはなぜか? それは、きっと岩松さんの求心力と、横山さんのそれが違うからだ。
この芝居の主人公は、この場に於いてニュートラルな位置にある早苗(物延結)である。彼女はこの宿泊棟の受付と彼らの世話を担当している管理者側の人間だ。芝居は、彼女の内的葛藤にすべてを集約させようとするのだが、あと一歩のところで、上手くいってない。彼女が抱え込もうとする闇を、芝居全体が支え切れていないからだ。群像劇の中に彼女の存在が埋もれてしまうのは、この作品にとって、プラスでもあり、マイナスでもある。とても微妙な問題だ。彼女の感情が爆発するシーンを敢えて作らないことで、その闇の深さを核心として据えることが可能だ。だがそれが、このままでは事故のインパクトの前では、薄まってしまう。台本と演出との齟齬が生じる。惜しい。
今の横山演出は岩松さんのように、簡単に答えを出そうとはしない。芝居は後半、どんどん重くなっていくが、それは横山さんのやり方ではない。これが彼の台本なら、この軽いトーンをラストまで貫いて、もっとフラットな芝居として見せるはずだ。それは彼の前作『トバスアタマ』を見れば、明らかである。今の時代は明確な答えを提示することを良しとしない情況にある。そこが、この芝居が書かれた90年代と00年代の違いであり、残念だが、この2010年という時代の気分をこの芝居は体現しない。その結果、本来なら、芝居が一気に盛り上がって行くところで、どんどん醒めていくという事態が生じてしまうこととなった。それは横山さんのせいではなく、あくまでも台本自体の問題であろう。とても優れた台本だからこそ、今の時代にはそぐわない。演出との齟齬は致命的である。
ただ、この作品との格闘を経由して、売込隊ビームは次で必ず凄いものを見せてくれるものと期待する。横山さんのリベンジはもうここから始まっている。
























