 父の回想録に「土手検」と呼ばれた町芸者の話がある。祖母がまだ娘だった頃、曽祖父が大江村の村長をやっていて、酒宴によく呼んだ町芸者が「土手検」と呼ばれて人気があったという。
父の回想録に「土手検」と呼ばれた町芸者の話がある。祖母がまだ娘だった頃、曽祖父が大江村の村長をやっていて、酒宴によく呼んだ町芸者が「土手検」と呼ばれて人気があったという。「熊本県大百科事典」によれば
――明治初期、寺原町(現壺川1丁目)に始まった町芸者は同町土手付近に住んでいたことから「土手券」と総称し、全盛時は市内各所に散在し、数々の人気芸者も生み、手軽で便利なことから一時隆盛を極めたが、これは「やとな」(雇い女の略。臨時に雇う仲居の女)の前身というべきものであろう。――
と説明されている。
「土手検」は昭和前期には消滅したと考えられ、その存在を知る人はもうほとんどいないと思われる。彼女たちがどんな芸を披露していたか知る由もないが、曽祖父の家で盛んに宴会が行われていたのは明治40年前後と考えられ、明治30年代前半に永田イネによって作られた「おてもやん」はかなり普及していたと考えられる。それはこの唄が「五足の靴」に登場することでもわかる。そして、その数年後に流行ったのが「自転車節」。熊本では「おてもやん」人気にあやかったのか、熊本弁の歌詞を付け加え、花柳界では「おても時雨」と呼んだ。おてもやんが山の向こうに住む恋人「彦しゃん」になかなか逢えない悲哀を唄うので「時雨(しぐれ)」と名付けたのだろう。この「おてもやん」と「おても時雨」は一対の唄として「土手券」たちによって唄われ、お座敷では人気を博したと思われる。
(備考)「券」または「検」は検番(券番)のこと。

















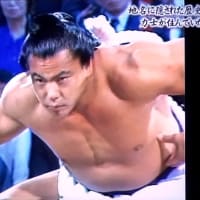
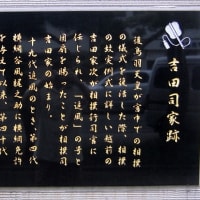

とても興味深く拝読しました。
私もそんなものを残したいです(笑)。
「おても時雨」(自転車節)も粋だと感じました。
ふと、映画「明日に向かって撃て」の自転車の曲乗りを思い出しました。
↓
https://www.youtube.com/watch?v=_VyA2f6hGW4
有難うございました。