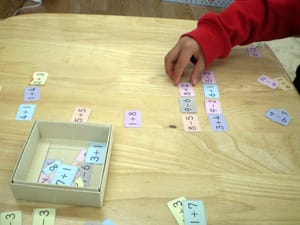糸山泰造著の「絶対学力」(文春ネスコ)に





人間は12歳までに様々な角度からものを見ること(抽象思考)が
できるようになる自然な成長プログラムを持っています。
ですから、そのプログラムに逆らって幼児期に先行学習や
パターン学習などをしていると手痛いシッペ返しをくらってしまいます。
幼児期にすべきことは、全ての時間を使って「ゆっくり、じっくり、
丁寧に」体験に裏付けされた豊かな言葉を習得させ、
「考える力」を付けてあげることなのです。
この力が育たないと具象思考から抽象思考へと
劇的に思考形態が変化する「9歳の壁」を突破することはできません。
いくら計算が速くても、表面的な言葉を多く知っていても
「9歳の壁」は乗り越えられないのです。






子育ても家庭学習もキーワードは「言葉」です。






という文章が載っていました。
幼児期は何はともあれ、親子でたっぷり会話をすることが、
大事ですね
そこで、過去記事のなかから、親子の会話の大切さについて触れた記事を
3つご紹介します。
4コママンガを使った 幼児のための作文指導(1)
絵本のインプット、アウトプットのバランスの話
☆
灘中の国語問題から 幼児教育を考える 2
また、何度か紹介させていただいているtoshi先生のブログに
小学校の国語の授業で、
子どもの考え表現する力をはぐくむ先生と生徒の会話の様子が
すばらしかったので紹介します。
子どもの話す力を引き出すための
とても良いヒントになると思います。





人間は12歳までに様々な角度からものを見ること(抽象思考)が
できるようになる自然な成長プログラムを持っています。
ですから、そのプログラムに逆らって幼児期に先行学習や
パターン学習などをしていると手痛いシッペ返しをくらってしまいます。
幼児期にすべきことは、全ての時間を使って「ゆっくり、じっくり、
丁寧に」体験に裏付けされた豊かな言葉を習得させ、
「考える力」を付けてあげることなのです。
この力が育たないと具象思考から抽象思考へと
劇的に思考形態が変化する「9歳の壁」を突破することはできません。
いくら計算が速くても、表面的な言葉を多く知っていても
「9歳の壁」は乗り越えられないのです。






子育ても家庭学習もキーワードは「言葉」です。






という文章が載っていました。
幼児期は何はともあれ、親子でたっぷり会話をすることが、
大事ですね

そこで、過去記事のなかから、親子の会話の大切さについて触れた記事を
3つご紹介します。
4コママンガを使った 幼児のための作文指導(1)
絵本のインプット、アウトプットのバランスの話
☆
灘中の国語問題から 幼児教育を考える 2
また、何度か紹介させていただいているtoshi先生のブログに
小学校の国語の授業で、
子どもの考え表現する力をはぐくむ先生と生徒の会話の様子が
すばらしかったので紹介します。
子どもの話す力を引き出すための
とても良いヒントになると思います。
くりあがり学習マシーンにつづき、
くりさがり学習マシーンです。
前回と同じ丸を10個書いた紙を2枚用意します。
11-2なら
まず、10のまとまりから、引きたい2を「ボトッ!ボトッ!」という
音とともに、
外へはじき出し、
「スルスルスル~」と落ち物ゲームのように、
もう片方の紙の1を移します♪
なぜ、マシーンなのか?
というと、こちらも、効果音やばかばかしいしぐさを加えると、
子どもがしつこくやりたがるからです
間違えた時、「どてっ!」とか言ってずっこけるのも、
子どもはものすごく好きで、それがしたいために、はりきって勉強します。
くりさがり学習マシーンです。
前回と同じ丸を10個書いた紙を2枚用意します。
11-2なら
まず、10のまとまりから、引きたい2を「ボトッ!ボトッ!」という
音とともに、
外へはじき出し、
「スルスルスル~」と落ち物ゲームのように、
もう片方の紙の1を移します♪
なぜ、マシーンなのか?

というと、こちらも、効果音やばかばかしいしぐさを加えると、
子どもがしつこくやりたがるからです

間違えた時、「どてっ!」とか言ってずっこけるのも、
子どもはものすごく好きで、それがしたいために、はりきって勉強します。

くりあがりの計算がすばやくできるようになるには、
頭の中で、10の合成と、あまった数のイメージが、
さっと浮かぶようにしておくことが大切です。

写真は「くりあがり計算マシーン」
ギーガチャン!ツツツ…
という音は、口でお願いします。
手動です♪
紙に10個丸を描いたものを2枚用意します。(5ずつ並べて)
こまはオセロでも、チップでもかまいません。
片方の紙に 9
もう片方の紙に 3
を置き、目で判断して、
9+3の答を言わせます。
その後、マシーンのスイッチを入れ(真似です)、
ギーガチャン!ツツツ…
10のまとまりと、あまりになるように
こまを動かします。
どうして、マシーンなのか?
というと、
単純にその方が子どもに受けるからです!

効果音やオーバーなしぐさを加えると、
子どもは何度でもやりたがります

頭の中で、10の合成と、あまった数のイメージが、
さっと浮かぶようにしておくことが大切です。

写真は「くりあがり計算マシーン」
ギーガチャン!ツツツ…

という音は、口でお願いします。
手動です♪
紙に10個丸を描いたものを2枚用意します。(5ずつ並べて)
こまはオセロでも、チップでもかまいません。
片方の紙に 9
もう片方の紙に 3
を置き、目で判断して、
9+3の答を言わせます。
その後、マシーンのスイッチを入れ(真似です)、
ギーガチャン!ツツツ…
10のまとまりと、あまりになるように
こまを動かします。
どうして、マシーンなのか?

というと、
単純にその方が子どもに受けるからです!

効果音やオーバーなしぐさを加えると、
子どもは何度でもやりたがります