東京子ども図書館の松岡享子さんが岩波新書から「子どもと本」を出された。

先週の日曜の読売新聞の書評で知った。
同新聞の編集委員の尾崎真理子さんの記事をまず読んでみよう!
----よき導き手になる知恵----------------------
かなり本好きの子でも、子供時代に読む本は500~600冊という。
気に入れば繰り返し読むから、<一冊一冊の持つ重みがおとなのそれとは比較にならぬほど大きい>。
だから、心底面白いと思う本に出会ってほしいし、その子の面白さの基準に沿って興味の幅を広げる導き手が、
親であれ、図書館員、教師であれ、誰かそばにいてほしい。
では、それらの人々にはどんな配慮が必要なのだろうか。
著者は1960年代に米国の公共図書館で児童室の取り組みを学び、
大阪市立中央図書館の勤務を経て、東京の自宅6畳間で家庭文庫を開設。
74年、子どもと読書を結ぶあらゆる活動の拠点として「東京子ども図書館」を創立した。
その人の知恵と提言が本書に結晶している。
同館が発行するブックリストは、昨今の世評や売れ行きに惑わされず、50年前に出た本も毅然として採録する。
なぜなら、奥付が示す何十刷という「古さ」ほど確実な、大勢の人に飽きず愛されてきた良書だという証明もないのだから。
もう一つ、信を置くのは「昔話」。その語り聞かせは子供が<思いっきり心を解放できる物語空間>であり、
<一生の読書の入り口>になるという。なぜ、子どもは残酷な結末でも平気なのか。心に多様な昔話を蓄えると、
後々人生の難問に立ち向かう力になるというのは本当か?
リュティや河合隼雄の至言を交えた解説から、長年の疑問も晴れた。
終章は一転、日本の図書館行政への言及となる。1953年に学校図書館法が成立し、施設は整ったものの、
導き手となる司書教諭不在の学校が今も多い。図書館員の身分は総じて不安定だ。
ひいてはそれが、便利な貸本屋としか認識しない利用者を増やし、
地域の図書館の質低迷につながった事情も浮かび上がる。
本書にあるのは理想論だろうか。しかし、この理想を貫いて40年、税金を1円も使わずに、著者は私立図書館を営んできたのだ。
--------------------書評おわり-----------
長年、子どもに本を通じて接してきた松岡さんだからこそ、
文に説得力がある。
特に第3章「昔話の持っている魔法の力」は白眉である。
「昔話は、今でも、子どもがこころの奥深くで求めているものを、
子どもによくわかる形でさし出しています。」
まさに言い得て、至言である。
皆さにも、一読をお薦めします。
今日のブログは、話題の本の紹介でした。
では、また。来週、このサイトでお会いしましょう!
今日、鹿児島で桜の開花宣言が出ました。
もう春ですね! みなさま、お元気で!

先週の日曜の読売新聞の書評で知った。
同新聞の編集委員の尾崎真理子さんの記事をまず読んでみよう!
----よき導き手になる知恵----------------------
かなり本好きの子でも、子供時代に読む本は500~600冊という。
気に入れば繰り返し読むから、<一冊一冊の持つ重みがおとなのそれとは比較にならぬほど大きい>。
だから、心底面白いと思う本に出会ってほしいし、その子の面白さの基準に沿って興味の幅を広げる導き手が、
親であれ、図書館員、教師であれ、誰かそばにいてほしい。
では、それらの人々にはどんな配慮が必要なのだろうか。
著者は1960年代に米国の公共図書館で児童室の取り組みを学び、
大阪市立中央図書館の勤務を経て、東京の自宅6畳間で家庭文庫を開設。
74年、子どもと読書を結ぶあらゆる活動の拠点として「東京子ども図書館」を創立した。
その人の知恵と提言が本書に結晶している。
同館が発行するブックリストは、昨今の世評や売れ行きに惑わされず、50年前に出た本も毅然として採録する。
なぜなら、奥付が示す何十刷という「古さ」ほど確実な、大勢の人に飽きず愛されてきた良書だという証明もないのだから。
もう一つ、信を置くのは「昔話」。その語り聞かせは子供が<思いっきり心を解放できる物語空間>であり、
<一生の読書の入り口>になるという。なぜ、子どもは残酷な結末でも平気なのか。心に多様な昔話を蓄えると、
後々人生の難問に立ち向かう力になるというのは本当か?
リュティや河合隼雄の至言を交えた解説から、長年の疑問も晴れた。
終章は一転、日本の図書館行政への言及となる。1953年に学校図書館法が成立し、施設は整ったものの、
導き手となる司書教諭不在の学校が今も多い。図書館員の身分は総じて不安定だ。
ひいてはそれが、便利な貸本屋としか認識しない利用者を増やし、
地域の図書館の質低迷につながった事情も浮かび上がる。
本書にあるのは理想論だろうか。しかし、この理想を貫いて40年、税金を1円も使わずに、著者は私立図書館を営んできたのだ。
--------------------書評おわり-----------
長年、子どもに本を通じて接してきた松岡さんだからこそ、
文に説得力がある。
特に第3章「昔話の持っている魔法の力」は白眉である。
「昔話は、今でも、子どもがこころの奥深くで求めているものを、
子どもによくわかる形でさし出しています。」
まさに言い得て、至言である。
皆さにも、一読をお薦めします。
今日のブログは、話題の本の紹介でした。
では、また。来週、このサイトでお会いしましょう!
今日、鹿児島で桜の開花宣言が出ました。
もう春ですね! みなさま、お元気で!













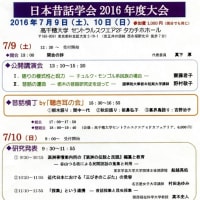






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます