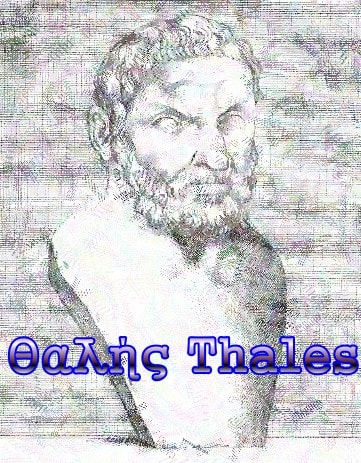アレクサンドリアの古代最大の図書館には、タレスとしてはレベルの低い『航海用天文誌』しか残されていない。少なくとも多くの広範な哲学者の証言によれば、タレスは膨大な著作を残したはずである。にもかかわらず、彼の真価を表す著作がなに一つ残されていなかった。それもこの図書館が焼き討ちされる前からである。
これは何を意味するのであろうか。犯人が誰かはわかっていない。いいだもも氏はプラトンを疑っている。いずれにせよ、当時、タレスを初めとした自然学者に対する焚書があったことは確かである。
栄光のギリシャ哲学者が、ソクラテス・プラトン・アリストテレスにのみ極限されたのは、彼らの偉大さばかりでなく、陰湿は政治的陰謀が働いていたことは容易に想像できる。
ただし、ディオゲネス・ラエルティオスやアリストテレス注解者のシンプリキオスは、タレスが著作をなにも残さなかったと書いている。
それと反対の証言もある。後10世紀に編纂された『スーダ』というギリシャ語語彙辞典では、タレスは多数の著作を残したとある。いずれが正しいのかは不明である。しかし、プラトンやアリストテレスによる激しい憎悪を考えれば、焚書の被害にタレスたちイオニア等東方に関係する先行者たちの著作が遭った可能性は、否定できないのである。

ヘロドトスは、タレスをミレトスの人とし、祖先はフェニキア人と推定した。通常、フェニキア人というとき、それはセム系人種を意味していて、ギリシャ人ではないという意味に使われる。これも真偽のほどは分からない。
ヘロドトスによれば、タレスはイオニア陥落前にイオニア人国家の改革を提言していた。全イオニア人が、イオニアの地理的中心であったテオス島に統一評議会を置き、その他の都市を各行政区にするという今日の中央集権国家を作ろうとしていた。
また彼が日蝕を予言したのは、リュディア軍とメディア軍との交戦中のことであるが、彼の知識はバビロニアの記録文書から得たとされている。バビロニアの神官たちは、宗教的な必要性から太陽回帰周行の知識が豊富で、少なくとも前6世紀には日蝕の地点確定能力ももっていたと考えられる。
とくに、イオニアが陥落した時のサルディスは国際都市であり、ギリシャの知識人たちが多数勉学のために訪問していた。タレスはこの地でバビロニア人たちから天文学と60進法を学んだとされている。ディオゲネス・ラエルティオスは、タレスこそが天文研究をした最初の人であり、日蝕と太陽の回帰を予告した最初の人であるとしているが、バビロン人から学んだことは確かだとされている。
タレスは、ピラミッドの高さを計測した最初の人でもあった。それは三角比を応用したものであった。直径が円を二等分し、二角挟辺が等しければその三角形は合同であるとか、対角線は等角であるとか、とにかく幾何学の定理をタレスはつぎつぎと確定していった。長距離の航海には北極星を目印とすべきだと航海士たちを指導したのもタレスである。それまでは、北極星のある小熊座ではなく、北斗七星のある大熊座をフェニキアの航海士たちは利用していたのである。星の測量器具もタレスの発明であった。
アリストテレスもまたタレスへの憎悪を隠さなかった。少し長くなるが、アリストテレスの『形而上学』A巻第3章から引用しよう。
「最初に哲学に携わった人たちの大部分は、もっぱら素材のかたちでのものだけを、万物の元のもの(始原)として考えた。すなわち、すべての存在する事物がそれから生じ、またそれへと消滅していくところのもの・・・その当のものを、存在する諸事物の基本要素であり、元のものである、と彼らは言っている。・・・このような哲学の創始者たるタレスは、水がそれであると言っている(大地が水の上に浮かんでいると主張したのも、そのためである)。彼がこうした見解をとったのは、おそらく、あらゆるものの栄養となるものが湿り気をもっていること、熱そのものさえ湿り気をもったものから生じ、それによって生きることを観察した結果であろう(ものがそれから生じる当のもの、それが万物の元のものにほかならない)。彼の見解は、こうしたことによるとともに、またあらゆるものの種子がしめった本性をもっていることによるものであろう。水こそが、湿り気をもったものにとって、その本性の元のものにほかならないのである」。
そして、アリストテレスはタレスを批判する。彼はなにも解決しなかった。彼は、大地を支える水を支える何らかのものをさらに見出さなければならなかったはずだからであると。
溜息が出てしまう。私の後代、私の理論を紹介する悪意ある人によって、このように低いところから私のオリジナルの理論が捏造され、揶揄の対象にされてしまうのであろうか。このような悪意の固まりのような文章に接すると、私は死ぬ前に私の著作のすべてを自ら焚書してしまおうか、という気持ちになってしまう。
このブログで少し前、「ウラノス」(天空)、「奈落の底」(タルタロス)、「オケアノス」(大河)を私は紹介した。それは動きのない静止した世界像であった。そこには変化と時間がなかった。プラトンのアテネでは、そうした枠組みから外れた考え方はすべて異端として廃絶された。光と闇、不老なる「クロノス」(時間)の水、そして「カオス」、「卵」、「無形の神」につながる「オルペリウス」の臭いをプラトンとアリストテレスは毛嫌いしたのである。
アリストテレスにとって、東方の異教徒の臭いをぷんぷんとさせているタレスは許せないものであった。アリストテレスは、自分の言う四つの原因のうち、素材という一つだけを始原とするタレスを侮蔑した。しかし、タレスは大地が水から立ち上がると考えたのであり、単に水が大地を支えていると考えたのではない。生成・発展・消滅のサイクルを問題にしたのである。けっしてアリストテレスが固着してしまった機械的静態論ではない。物質すべての相互作用を問題にしようとしたのである。
たとえば、水と熱とを対立させるのではなく、水にも熱があるとしたのである。このダイナミズムは東方のものである。光にしか生活を見ないアポロン的世界とは対照的なものである。
アリストテレスのタレスへの悪罵は、『魂について』第1巻にも現れている。
「より粗雑な人たちの中には、(魂は)水であると主張した者もいた。・・・彼らはすべてのものの種子が湿っているということから、そう信じたようである」。
アリストテレスにとって魂は血液と同じである。にもかかわらず、タレスは種子は血液ではないとして、人間の魂を否定したのである、という無茶苦茶な論法で、アリストテレスはタレスを糾弾したのである。
エジプトの神話は、大地が水の上で静止しているというものであり、バビロニア創造詩は、すべての陸地は海だったというものである。ヤーベは、水の上に大地を述べ広げた。こうした地下水脈を重視する東方の感覚をギリシャ本土の人たちは理解できなかった。オケアノスは大地の周囲を環流するだけのものだからである。オケアノスは地下には存在しない。
アレキサンダー大王が、東方の英知に感動して東方の学者をアテネに連れてきたが、そうした場面に直面したアリストテレスの屈辱はいかなるものであっただろう。思うに、ギリシャ哲学の専門家たちは、どうして、ギリシャ哲学が相次ぐ戦乱の中から生み出されたものであったという当たり前の史実について何も語らないのであろう。
どうして、政治家、実務家、国際的交流といった現実の生活の営みとの関係でギリシャ哲学を語らないのか。そのように称揚されても、ギリシャこそは、そしてそれを継承したローマこそは、奴隷社会であった。徹底的な差別社会であった。どうしてそれがポリスなのか。どうしてこのような初歩的なことすらこの世界では議論しないのか。いまの新古典派経済学が戦争について無言を守っていることとそれは通じるものである。
最近、すばらしい本が出た。トム・ホランド、小林朋則訳『ルビコン・共和制ローマ崩壊の物語』(中央公論新社)、本体3300円、税別)。
タレスにとって、水はアリストテレスが執拗に攻撃するような、単なる「素材」ではなかった。水は、彼にとって、無限定な広がりを示す観念であった。厳密な二分法を守るアリストテレスにとって、タレスもまた、水の「濃密化」という「希薄化」から事物が生み出されるという二分法を取ったものと理解したがり、無限定な、つまり、明確に定義できない発想などそもそもできなかったのである。
ディオゲネス・ラエルティオスは、タレスが「無生物と見えるものでも生きている。世界は神々に満ちている」と言ったと説明する。川も樹木も生気をもっている。霊を宿している。タレスは魂こそがものを動かすという。それは普遍的な意識と生命の源である。自己運動と変化の能力を魂がもつ。光と論理のみで世界を理解しようとして、それが新しい哲学だと自称し始めた青臭い、世間知らずの新興哲学者たちにタレスは、意図的にぶつかったのである。彼を突き動かしたものは、数学、とくに幾何学における神秘性への感嘆であった。まだまだ私たちの無意識の中にある未分化な思考法を、タレスは2600年も前に取り出して見せた。そして、案の定、合理的思考至上主義者である権威者によって抹殺された。