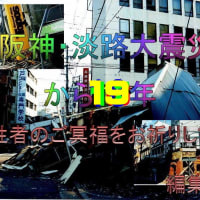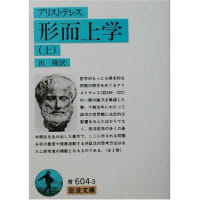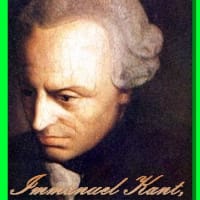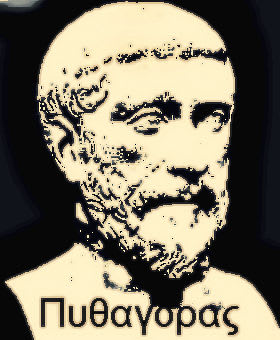
ソクラテス以前の哲学者の注解者として、プラトンは、多くの記述を残している。

しかし、プラトンの引用の仕方は、ほとんど例外なく、相手を揶揄したものであり、自分の正しさを示すべく、相手を過度に貶めるものである。以前にも指摘したが、とくに、ヘラクレイトスへの注解はひどい。そして、後世の人たちは、ソクラテス以前の哲学を、偏見に満ちたプラトンの目を通して見てきた。

そもそも、「ソクラテス以前の哲学」という括り方は、アリストテレスに由来する。
プラトンとアリストテレスは、自分たちの完成された哲学に辿り着く道筋としてしか、過去の哲学者を見ようとしなかった。
アリストテレスは、プラトンほどひどくはないが、それでも、過去の哲学者は未熟で、改めて学び直す必要のないものとして位置づけてしまった。
それは、例えば、経済学の世界に引き寄せて表現すれば、ウィリアム・ペティからポール・サミュエルソンまで、経済学は完成への道筋を歩んできたというジョセフ・シュンペーター(『経済分析の歴史』の記述)を彷彿とさせる。

はたして、そうであろうか。
人文学、社会学の世界では、直線的に進歩してきたと言えるのだろうか。昔の学問の方が優れていたという積もりはないが、現代に至るほど、言葉は饒舌になり、むしろ、本質的なものがぼやかされているのではないだろうか。
「底辺でのたうっている人たち」の哀しみを共有するという意識が、専門家ほど希薄になっているという情況を、私たちは直視すべきである。
こういえば、「情緒的な発言は慎んでもらいたい、データに基づく、科学的な理論で裏付けられた発言をしてもらいたい」と、私などはつねに叱られてきた。私は、口角泡を飛ばす議論は嫌いである。
その多くに、心がこもっていないからである。黙って、「分かってくれる人もいるはずだ」と、その都度、私は、つぶやいてきた。
目の前に生涯を託す職業に就けない若者たちが溢れているのに、労働問題の専門家たちは、労働形態が多様になった社会がきたとうそぶく。なにをいっているのか。誰が好きこのんでフリーターになりたいものか。誰が、非正規社員の方が気楽でいいと言えるのか。
私の住んでいる福井県は、共稼ぎ率が日本一だとか、貯蓄額が最高であるとか自慢されている。しかし、男性の賃金の低さには人々は目をつぶる。必要なことは賃金を上げることである。パートではなく、生涯打ち込める仕事を創り出すことである。
「消された伝統の復権」の執筆。孤独な作業である。しかも、ときどきではあるが、半畳を打たれる(*)。
(*)芝居で、役者に対する不満・反感を表すため、自分の敷いている半畳を舞台に投げうつ。芝居を見ていて、役者の演技を非難したりからかったりする。転じて、他人の言動に対し非難・揶揄(やゆ)などの声を発する。弥次る。
こうして、人に理解される前に挫折してしまうかも知れない。しかし、幸い、私の周囲には、少数ではあれ、若い人たちがこのブログを支えてくれている。彼らの善意を救いとして、「他者」への共感を訴え続けていきたい。
また、話が横道に逸れた。こういう私の悪弊について、協力してくれる若い人たちからよく叱られる。「確かに」と、自戒する。
話を元に戻そう。
きちんと評価せず、揶揄するばかりであるプラトンが、ひそかに憧れていた過去の哲学者もいた。後に、プラトンは、初期の自分の傾向を修正するが、それでも、若いときには、傾倒していた哲学者がいた。それが、ピタゴラスであった。
もとより、紀元前3世紀と紀元前6世紀というように、二人の生きた時代が大きく違うので、プラトンがピタゴラスを直接知っていたわけではないが、少なくとも、プラトンの『パイドン』(Phaedo)は、ピタゴラスの影響が見られる。
ただし、ここでも、ピタゴラスの説ではなく、プラトン的にアレンジされたものであるが、それでも、魂に関する終末論は、ピタゴラスへの傾倒なしには記述されようもなかったであろう。
そして、プラトンは、ピタゴラスの数論を弟子たちに勉強させたという研究もある(Ross, W. D., Plato's Theory of Ideas, Oxford, 1951, chs. IX-XVI)。『ティマイオス』(Timaeus)、『ピレボス』(Philebus)にそうした気配を見て取れる。
しかし、プラトン派、後の新プラトン派の人たちは、ピタゴラスをピタゴラスとして理解したのではなく、あくまでもプラトンに引き寄せて解釈したのであるといわれている。
ちなみに、アリストテレスは、ピタゴラスをプラトン的に解釈することには反対だったとされている。
「プシューケー」(ψυχη=魂)という言葉は、ピタゴラスのものとされている。
プラトンの『パイドン』 によれば、「生の原理」、「心」、「自己」という、順応性ある豊かな意味内容のある言葉として語られている。
イオン(Iôn=前490年頃~425年頃、アテネで活躍した悲劇詩人。自然学の著作もある)によれば、人間の魂は、死後に祝福されるはずであると、ピタゴラスは語ったという。
これは、ディオゲネス・ラエルティオス(Diogenês Laertios=キリキア地方、ラエルテ出身、後3世紀前半とされる)の『哲学者列伝』(Vitae et sententiae eorum qui in philosophia probati fuerunt )による(第1巻120節)。
「かの男は、その身は滅んだが、その魂は、かくも雄々しく気高さに秀でて、喜ばしい生を送っている。いやしくもピタゴラスは、まことの賢者であり、万人に優れていて、人の考えを知り抜き、学び尽くした人なので」。
「かの男」というのは、ペレキュデス(Perecydês=シュロイスの人。前550年頃、オルペウス教信者)。つまり、ペレキュデス(アテネの同名人=前5世紀頃とかレロスの同名人=前4世紀と混同しないように)というピタゴラス親派(オルペウス教とピタゴラスは不可分の関係にある)は、ピタゴラスの教えの通りに人生を歩み、ピタゴラスの予言の通り、肉体は死んでも、魂は幸福な生活を送っているというのである。
ヘロドトス(Hêrodotos=ハルカルナッソス出身。前485年頃~前420年の歴史家)の『歴史』(Historiae)でピタゴラスの名こそ出していないが、おそらく、ピタゴラスのことを言っているのであろう記述がある。
「人間の魂は不死であり、肉体が滅びると、そのつど生まれてくる別の生き物の中に入って、そこに宿るという説を唱えたのも、エジプト人が最初である。陸の生き物、海の生き物、飛翔する生き物と、ありとあらゆる生き物を巡ると、魂は再び、また生まれてくる人間の肉体に宿り、こうして魂が一巡するには3000年かかるという。ギリシャ人の中にも ─ 人によって、時代の後先ははあるが ─ これを自分の説のように用いた者がいる。私はそういう人たちの名前を知っているが、ここにはあかさない」(第2巻123節)。
愉快な記述である。
ヘロドトスという人は機知と諧謔(かいぎゃく)を喜んだ人なのだろう。「歴史学の父」が明るい人であったことは(内容の深刻さにもかかわらず)、救いである。明るさが、偉大な学者の資質なのだろう。学者は、人を深刻な姿に陥れるのではなく、人を救うために、時間が与えられているのである。そのためには、人を明るくさせなければならない。
まず、彼は、ギリシャの外部からくるものは、それが、インド、中央アジア、南ロシアからのものであれ、すべて、エジプトからきていると表現する。少なくとも、当時のギリシャ人はエジプトだけは尊敬し、東方の風物はすべて卑しいものと見なしたのであろう。アレキサンダー大王が、東方に惚れ込んだときのアレキサンダーの師、アリストテレスの失意を想像するだけで可笑しくなる。
ヘロドトスのいたずらは、エジプトを口実にして、ピタゴラスの考え方をギリシャ人に伝えたのである。ピタゴラスが、無知で傲岸なアテネ人たちに貶められないように、「私は知っているが、その人の名前はあかさない」といなしている。愉快な人である。
それはともかく、自信はないが、「歴史家」(ヒストリエー=ιστριη)の意味に関する私見を付け加えたい。「歴史家」(ヒシトリエー)とは、「探究の実践者」、「現場の証言者」のことであると私は思い込んでいる。
本稿の記述は、Kirk, G. S., Raven, J. E. & M. Schoield, The Presocratic Philosophers: A Critical History with a Selection of Texts, Second Edition, Cambridge University Press, 1957; G.S.カーク、J.E.レイビン、M.スコフィールド著、内山勝利・木原志乃・國方栄二・三浦要・丸橋裕、訳『ソクラテス以前の哲学者たち』(第2版)京都大学学術出版会、平成18年(恥ずかしながら、発行人に私の名前が記されている)、に大きく依拠している。

ただし、主張点のすべてがこの書ではなく、この書から鼓舞された私の私見にすぎない。誤りがあったとしても、原著者と翻訳者の責任ではない。

京都大学学術出版会の「古典叢書」のご愛読をお願いする次第である。

しかし、プラトンの引用の仕方は、ほとんど例外なく、相手を揶揄したものであり、自分の正しさを示すべく、相手を過度に貶めるものである。以前にも指摘したが、とくに、ヘラクレイトスへの注解はひどい。そして、後世の人たちは、ソクラテス以前の哲学を、偏見に満ちたプラトンの目を通して見てきた。

そもそも、「ソクラテス以前の哲学」という括り方は、アリストテレスに由来する。
プラトンとアリストテレスは、自分たちの完成された哲学に辿り着く道筋としてしか、過去の哲学者を見ようとしなかった。
アリストテレスは、プラトンほどひどくはないが、それでも、過去の哲学者は未熟で、改めて学び直す必要のないものとして位置づけてしまった。
それは、例えば、経済学の世界に引き寄せて表現すれば、ウィリアム・ペティからポール・サミュエルソンまで、経済学は完成への道筋を歩んできたというジョセフ・シュンペーター(『経済分析の歴史』の記述)を彷彿とさせる。

はたして、そうであろうか。
人文学、社会学の世界では、直線的に進歩してきたと言えるのだろうか。昔の学問の方が優れていたという積もりはないが、現代に至るほど、言葉は饒舌になり、むしろ、本質的なものがぼやかされているのではないだろうか。
「底辺でのたうっている人たち」の哀しみを共有するという意識が、専門家ほど希薄になっているという情況を、私たちは直視すべきである。
こういえば、「情緒的な発言は慎んでもらいたい、データに基づく、科学的な理論で裏付けられた発言をしてもらいたい」と、私などはつねに叱られてきた。私は、口角泡を飛ばす議論は嫌いである。
その多くに、心がこもっていないからである。黙って、「分かってくれる人もいるはずだ」と、その都度、私は、つぶやいてきた。
目の前に生涯を託す職業に就けない若者たちが溢れているのに、労働問題の専門家たちは、労働形態が多様になった社会がきたとうそぶく。なにをいっているのか。誰が好きこのんでフリーターになりたいものか。誰が、非正規社員の方が気楽でいいと言えるのか。
私の住んでいる福井県は、共稼ぎ率が日本一だとか、貯蓄額が最高であるとか自慢されている。しかし、男性の賃金の低さには人々は目をつぶる。必要なことは賃金を上げることである。パートではなく、生涯打ち込める仕事を創り出すことである。
「消された伝統の復権」の執筆。孤独な作業である。しかも、ときどきではあるが、半畳を打たれる(*)。
(*)芝居で、役者に対する不満・反感を表すため、自分の敷いている半畳を舞台に投げうつ。芝居を見ていて、役者の演技を非難したりからかったりする。転じて、他人の言動に対し非難・揶揄(やゆ)などの声を発する。弥次る。
こうして、人に理解される前に挫折してしまうかも知れない。しかし、幸い、私の周囲には、少数ではあれ、若い人たちがこのブログを支えてくれている。彼らの善意を救いとして、「他者」への共感を訴え続けていきたい。
また、話が横道に逸れた。こういう私の悪弊について、協力してくれる若い人たちからよく叱られる。「確かに」と、自戒する。
話を元に戻そう。
きちんと評価せず、揶揄するばかりであるプラトンが、ひそかに憧れていた過去の哲学者もいた。後に、プラトンは、初期の自分の傾向を修正するが、それでも、若いときには、傾倒していた哲学者がいた。それが、ピタゴラスであった。
もとより、紀元前3世紀と紀元前6世紀というように、二人の生きた時代が大きく違うので、プラトンがピタゴラスを直接知っていたわけではないが、少なくとも、プラトンの『パイドン』(Phaedo)は、ピタゴラスの影響が見られる。
ただし、ここでも、ピタゴラスの説ではなく、プラトン的にアレンジされたものであるが、それでも、魂に関する終末論は、ピタゴラスへの傾倒なしには記述されようもなかったであろう。
そして、プラトンは、ピタゴラスの数論を弟子たちに勉強させたという研究もある(Ross, W. D., Plato's Theory of Ideas, Oxford, 1951, chs. IX-XVI)。『ティマイオス』(Timaeus)、『ピレボス』(Philebus)にそうした気配を見て取れる。
しかし、プラトン派、後の新プラトン派の人たちは、ピタゴラスをピタゴラスとして理解したのではなく、あくまでもプラトンに引き寄せて解釈したのであるといわれている。
ちなみに、アリストテレスは、ピタゴラスをプラトン的に解釈することには反対だったとされている。
「プシューケー」(ψυχη=魂)という言葉は、ピタゴラスのものとされている。
プラトンの『パイドン』 によれば、「生の原理」、「心」、「自己」という、順応性ある豊かな意味内容のある言葉として語られている。
イオン(Iôn=前490年頃~425年頃、アテネで活躍した悲劇詩人。自然学の著作もある)によれば、人間の魂は、死後に祝福されるはずであると、ピタゴラスは語ったという。
これは、ディオゲネス・ラエルティオス(Diogenês Laertios=キリキア地方、ラエルテ出身、後3世紀前半とされる)の『哲学者列伝』(Vitae et sententiae eorum qui in philosophia probati fuerunt )による(第1巻120節)。
「かの男は、その身は滅んだが、その魂は、かくも雄々しく気高さに秀でて、喜ばしい生を送っている。いやしくもピタゴラスは、まことの賢者であり、万人に優れていて、人の考えを知り抜き、学び尽くした人なので」。
「かの男」というのは、ペレキュデス(Perecydês=シュロイスの人。前550年頃、オルペウス教信者)。つまり、ペレキュデス(アテネの同名人=前5世紀頃とかレロスの同名人=前4世紀と混同しないように)というピタゴラス親派(オルペウス教とピタゴラスは不可分の関係にある)は、ピタゴラスの教えの通りに人生を歩み、ピタゴラスの予言の通り、肉体は死んでも、魂は幸福な生活を送っているというのである。
ヘロドトス(Hêrodotos=ハルカルナッソス出身。前485年頃~前420年の歴史家)の『歴史』(Historiae)でピタゴラスの名こそ出していないが、おそらく、ピタゴラスのことを言っているのであろう記述がある。
「人間の魂は不死であり、肉体が滅びると、そのつど生まれてくる別の生き物の中に入って、そこに宿るという説を唱えたのも、エジプト人が最初である。陸の生き物、海の生き物、飛翔する生き物と、ありとあらゆる生き物を巡ると、魂は再び、また生まれてくる人間の肉体に宿り、こうして魂が一巡するには3000年かかるという。ギリシャ人の中にも ─ 人によって、時代の後先ははあるが ─ これを自分の説のように用いた者がいる。私はそういう人たちの名前を知っているが、ここにはあかさない」(第2巻123節)。
愉快な記述である。
ヘロドトスという人は機知と諧謔(かいぎゃく)を喜んだ人なのだろう。「歴史学の父」が明るい人であったことは(内容の深刻さにもかかわらず)、救いである。明るさが、偉大な学者の資質なのだろう。学者は、人を深刻な姿に陥れるのではなく、人を救うために、時間が与えられているのである。そのためには、人を明るくさせなければならない。
まず、彼は、ギリシャの外部からくるものは、それが、インド、中央アジア、南ロシアからのものであれ、すべて、エジプトからきていると表現する。少なくとも、当時のギリシャ人はエジプトだけは尊敬し、東方の風物はすべて卑しいものと見なしたのであろう。アレキサンダー大王が、東方に惚れ込んだときのアレキサンダーの師、アリストテレスの失意を想像するだけで可笑しくなる。
ヘロドトスのいたずらは、エジプトを口実にして、ピタゴラスの考え方をギリシャ人に伝えたのである。ピタゴラスが、無知で傲岸なアテネ人たちに貶められないように、「私は知っているが、その人の名前はあかさない」といなしている。愉快な人である。
それはともかく、自信はないが、「歴史家」(ヒストリエー=ιστριη)の意味に関する私見を付け加えたい。「歴史家」(ヒシトリエー)とは、「探究の実践者」、「現場の証言者」のことであると私は思い込んでいる。
本稿の記述は、Kirk, G. S., Raven, J. E. & M. Schoield, The Presocratic Philosophers: A Critical History with a Selection of Texts, Second Edition, Cambridge University Press, 1957; G.S.カーク、J.E.レイビン、M.スコフィールド著、内山勝利・木原志乃・國方栄二・三浦要・丸橋裕、訳『ソクラテス以前の哲学者たち』(第2版)京都大学学術出版会、平成18年(恥ずかしながら、発行人に私の名前が記されている)、に大きく依拠している。

ただし、主張点のすべてがこの書ではなく、この書から鼓舞された私の私見にすぎない。誤りがあったとしても、原著者と翻訳者の責任ではない。

京都大学学術出版会の「古典叢書」のご愛読をお願いする次第である。