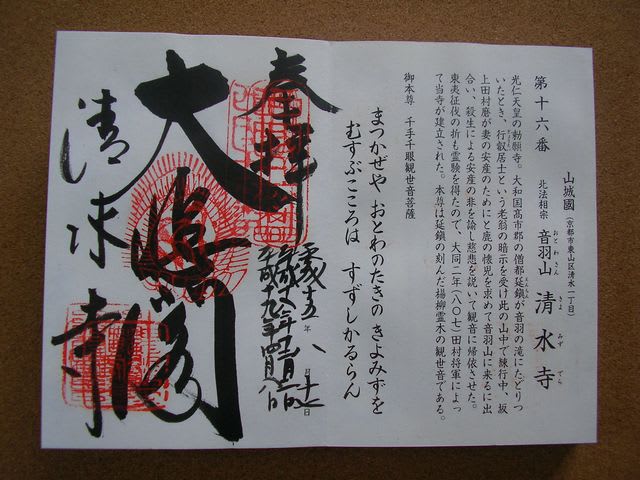コシアブラ
若芽のハカマをとって使います。
薄めの衣で天ぷらに→これが一番
もし和え物にするなら(2ℓぐらいの湯に小さじ一杯程度の重層を入れて)ゆでて水につけてアクを抜く、香りがいいので、からしあえとかごまあえがおススメです。
セリ
一つまみの塩を入れた熱湯でゆでて、水にとって冷やします。
おひたし、あえ物に。
そのままだったら「鍋ものや汁ものの実にして香りを楽しむのもいいよね」って。
ウチでは、ゆでて出し醤油をまわしかけて、香ばしく炒ったゴマをふりかけました。
ほろ苦いお味、ほんの少しが美味と教えていただきました、その通り!です。
トトキ(ツリガネニンジン)
「山でうまいものはオケラにトトキ里でうまいものはウリ、ナス、ナンキン」
ツリガネジンジンのカワイイお花からはこの食べれる若芽・若苗は想像できませんでした。
このツリガネニンジンの若苗トトキは
とりあえず、塩一つまみ入れた熱湯でゆで、水にとって冷まします。
それからです。
①細かくきざんで納豆と和え、ご飯の上にかけていただく。
②若苗の油いため
③おひたし、あえ物
④オムレツの具や卵どんぶり
さっそく①と④をお試し体験
①納豆とよく合います、ちょこっとの苦味が薬味の役目、ご飯にかけていただきました、イケますよ。
④卵と結構合います、ミンチ肉かハムのみじん切りを入れたらよかったかな?と、いやいやトトキと卵だけでいきましょう。
ちなみに、あのカワイイお花(ツリガネニンジン)も食べれます、そうです。
酢の物、サラダにイケるそうです。

さて、「山でうまいものはオケラとトトキ・・・・・」のオケラが山菜として知る人ぞ知る・・・・・
が、ホンモノに出会ったことがない、どんなんか試食してみたい気がします。
聞くところによりますと、山野の日当たりのよい場所に自生。
草丈は50㌢~1㍍くらい。茎は細くてかたい。
葉っぱのへりに鋭い鋸歯、裏には毛が生えてる。
秋に枝の先にアザミに似た白い花をつける。
ざっと、このような姿形であるそうな・・・・・(写真で見たイメージです)

(撮影:そよかぜさん)
春早く芽を出したオケラは綿毛をかぶっているが、伸びてゆくうちにこの毛がとれる、この頃が食べ時・・・・・なんですって。
お~い、オケラさぁん、どこに生えているん?
【おまけ】
鴨とセリは味がよく調和するので「鴨芹鍋焼き」が昔から有名で、
「なべ焼きの鴨と芹とは二世の縁」という江戸川柳もある、って教えていただきました。
「えっ!なんで?ですか?」ってお訊ねすると、
「これは、鴨と芹とは、生前水辺で暮らしていた仲やけど、今は、一つなべという意味なんよ」
4月22日の記事を削除いたしました。
その記事のコメントはこちらの方でご紹介させていただきます。
山菜摘み (キッカワ)
2010-04-22 22:58:56
すると「タラノメ」は一番人気のようですね。
天ぷらのうまさは格別
コシアブラも天ぷらがおいしいよね。
セリやトトキは、ほんの少しが美味
キッカワさん おはよう~~ (わんちゃん)
2010-04-23 09:13:37
ご覧いただき、ありがとうございます。
さっそく、これらのモン天ぷらとか、
あえ物にしていただきました。
お花の咲いてない時に摘むのですから、
見分けが難しいです
よくよく知ってる人たちにくっついていくのが一番ですね。
良かったです事・・。 (ショット)
2010-04-23 18:23:07
わんちゃんさん、山菜摘み?コシアブラ・・山に近いお蕎麦やさん等・・必ずシーズンにはコシアブラの天ぷらが・・。そして人気ですね・・美味しいって!!
楽しいですよね・・探しながらの散策撮影・・大好きです♪
画像からも察しますと・・とても柔らかく美味しかった事でしょうね・・。
( ゜▽゜)/こんばんわ (たま)
2010-04-23 22:08:47
山菜三昧のわんちゃん セロリ・・・苦手だね~
野菜はどちらかと云うと苦手な食べ物、
だからジュウサーにして飲む野菜にして何とかしのいでいます。
土瓶のこと、いい仕事してますね~お尋ね有難う・・・ネコちゃんがいるね~
ワンちゃんから~ネコちゃんへ・・・?(笑)
ショットさん こんばんわ~ (わんちゃん)
2010-04-23 23:50:43
>画像からも察しますと・・とても柔らかく美味しかった事でしょうね・・。
ハイ、レシピのレポートは次回に続きます・・・
と、いうことで。。。。。
そうそうコシアブラはてんぷらが一番かな・・・。
今しかない旬を楽しめますよね。
たまさん こんばんわ~ (わんちゃん)
2010-04-23 23:56:40
自家栽培の大きく成長したセロリをご近所さんから頂いた時は「う~~ん」でした。
まさか、わんこちゃんもネコちゃんも
我が家で一緒に暮らすなんてちょっと前なら思いもよらない事でした
それがね、もう10年にもなるんですよ。
「なぁんだ 一緒に暮らせば可愛いモンじゃ~ん・・・」って心境で~す。
名も知らぬ山野草 (道草)
2010-04-24 09:54:07
漉油(コシアブラ)・トトキ(漢字は無いみたいです)など、名前を聞いたことはない(知らない)けれど、いつかどこかで見た草花・・・そんな植物はかなりあるものです。蛇苺は昔は道端に幾らでもありましたが。近所の家の八重桜が、昨日一昨日の雨で散り始めました。「ふるさとの沼の匂ひや蛇苺」水原秋桜子。
Unknown (里伺)
2010-04-24 14:02:32
山も野も所有者があります。地元の方の生活の糧です。
遊び半分の山菜採りは止めましょう。地元の人々は嘆いていられます!
こんばんは (miu)
2010-04-24 20:52:12
わんちゃん、こんばんは~
ようやく春らしいお天気になりましたね。
山菜取りにお花の撮影と、とても楽しい一日でしたね。
山菜大好きです!
私の田舎では、こしあぶらは食べた記憶がないけど、こちらに来て天ぷらで食べた事はあります。
先日、田舎の母から取り立てのワラビに蕗にタラノ芽と送ってきたので、とても嬉しかったです♪