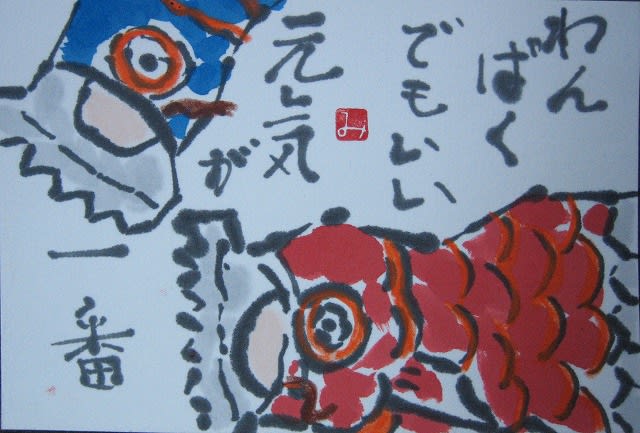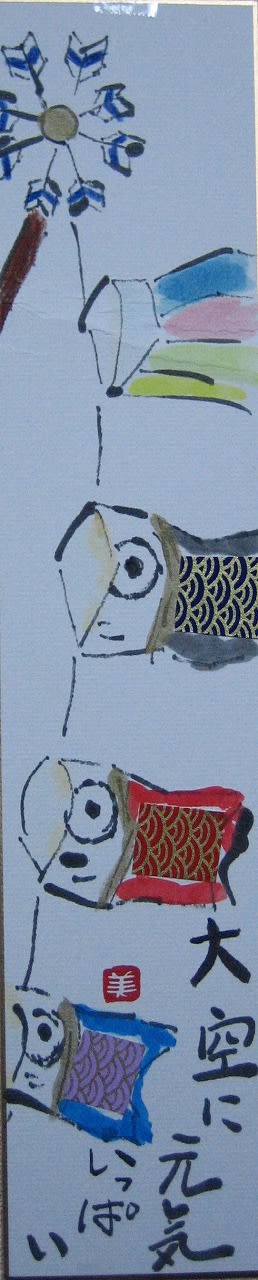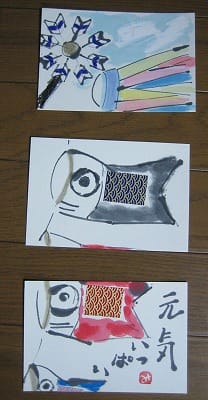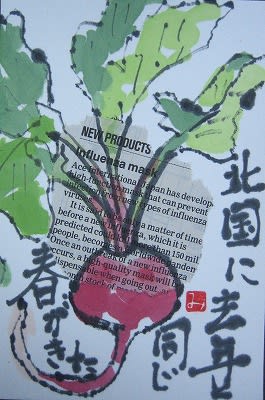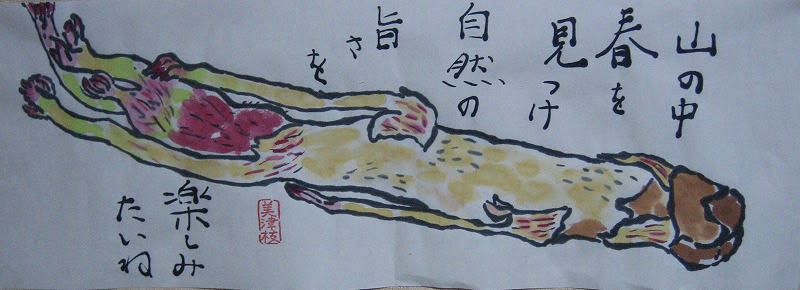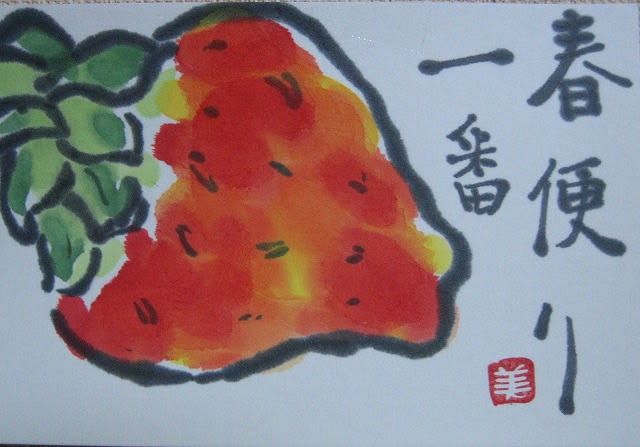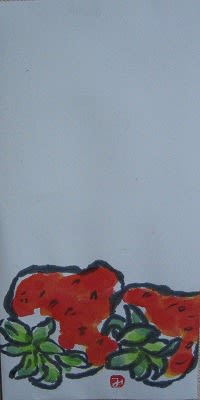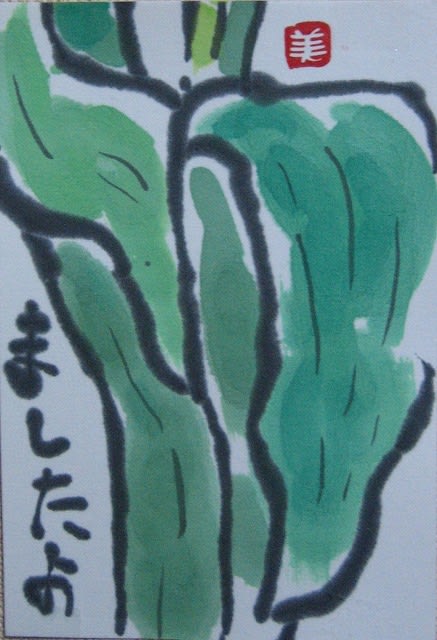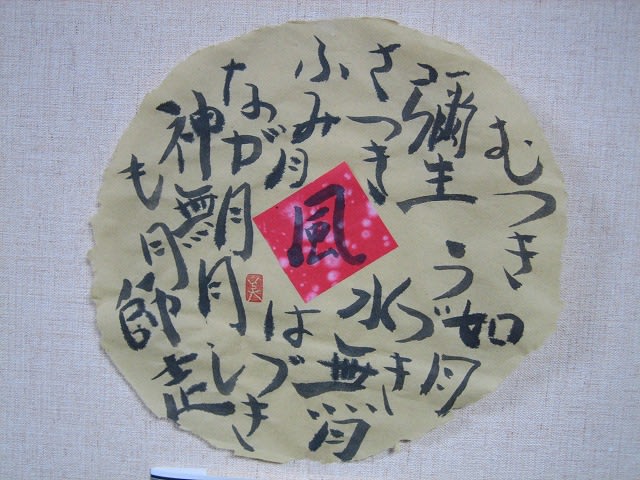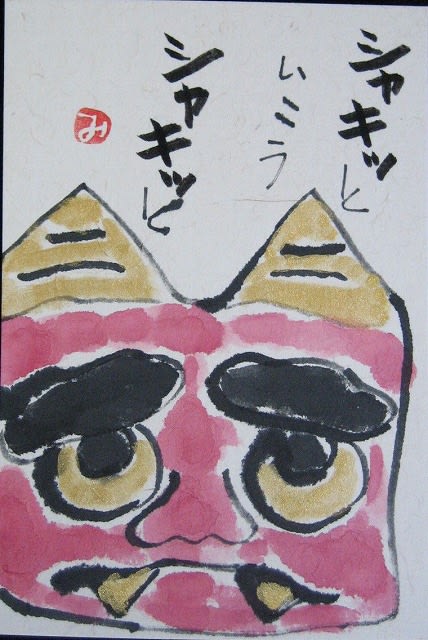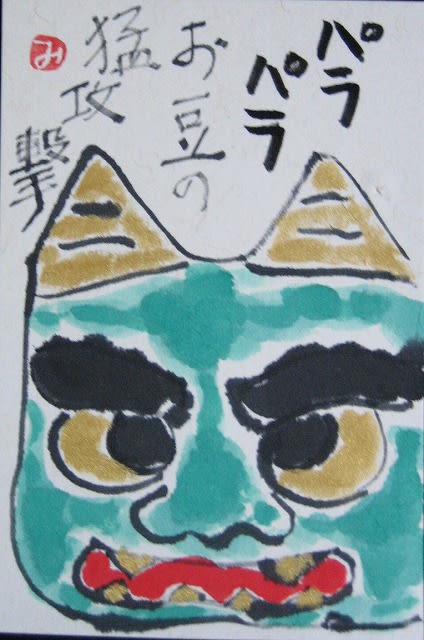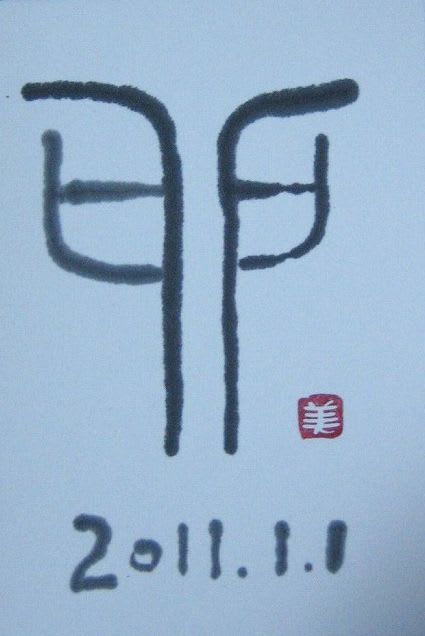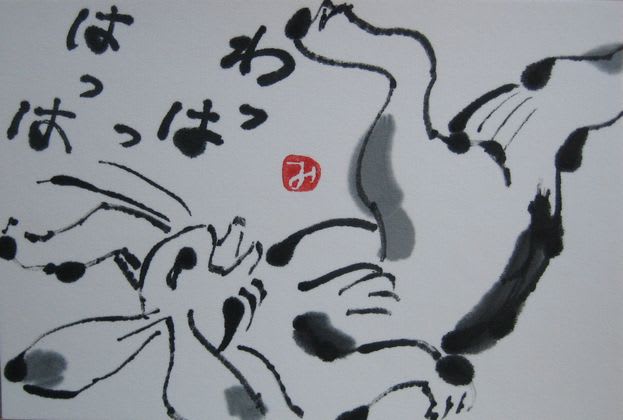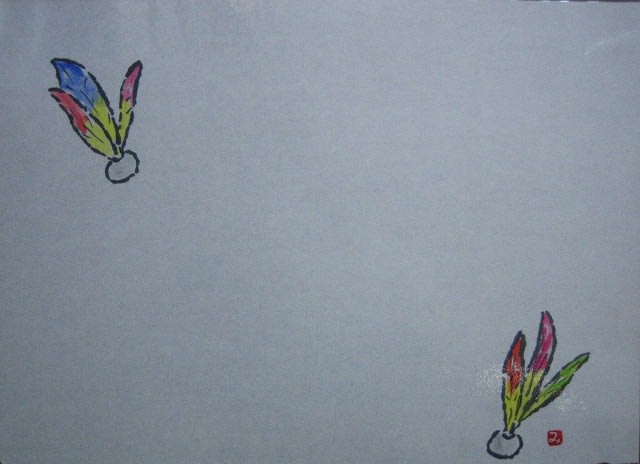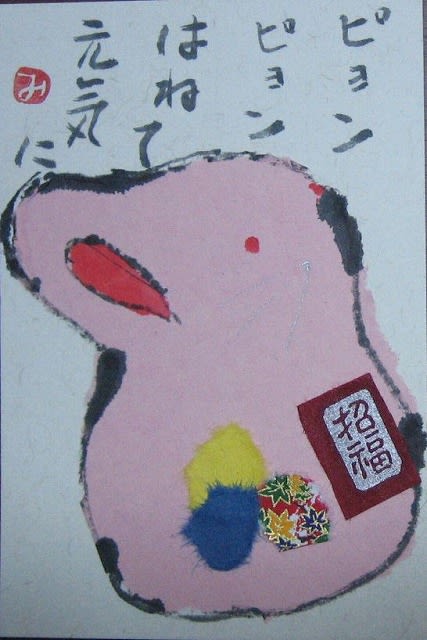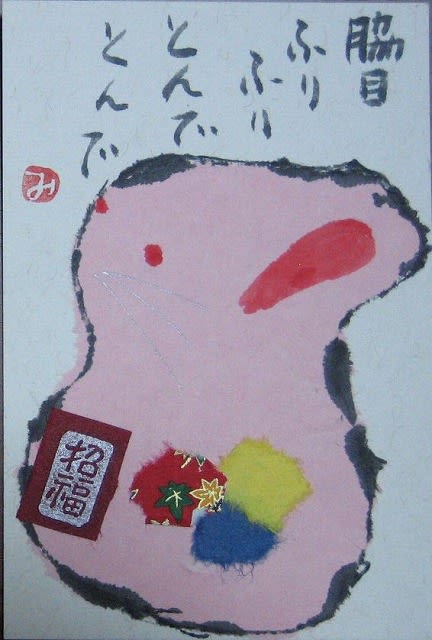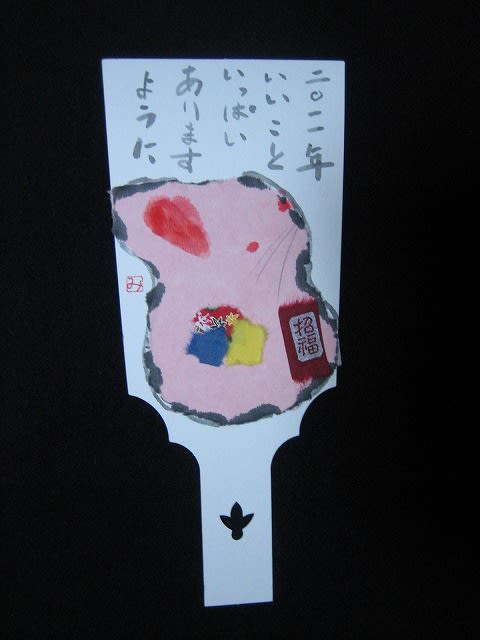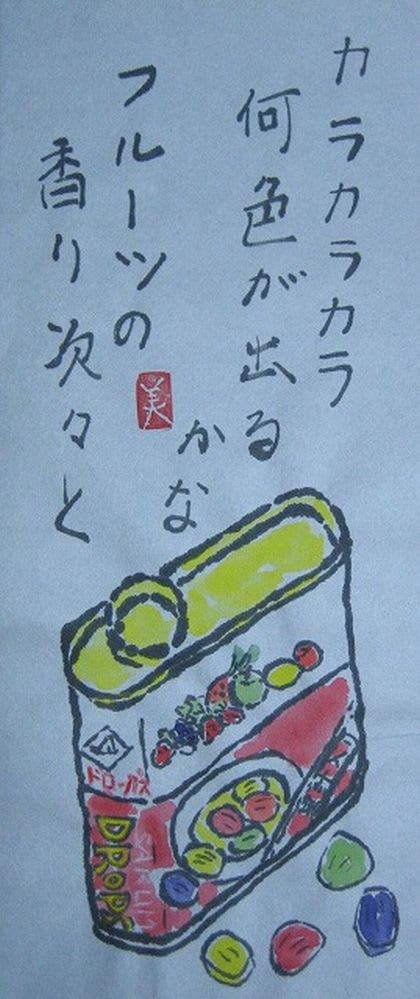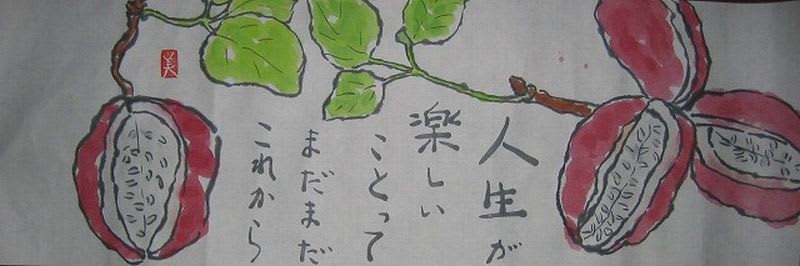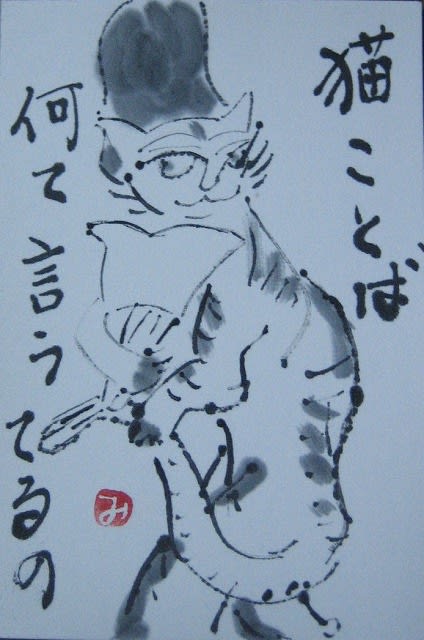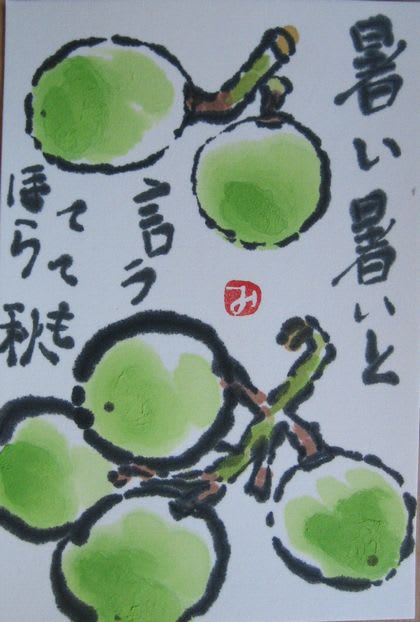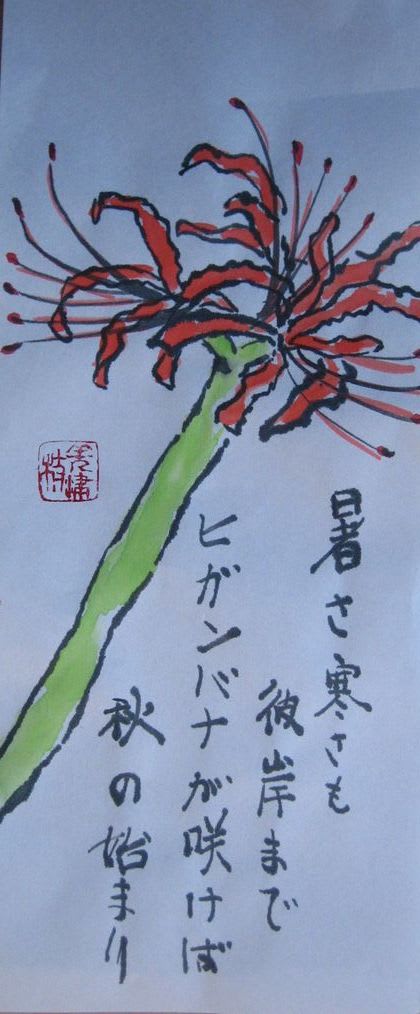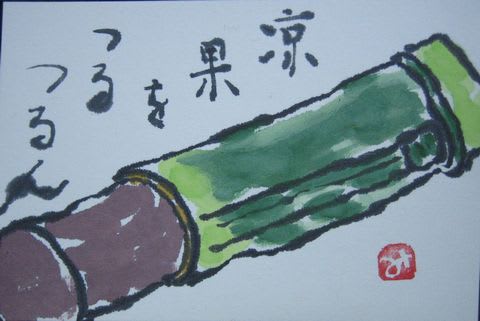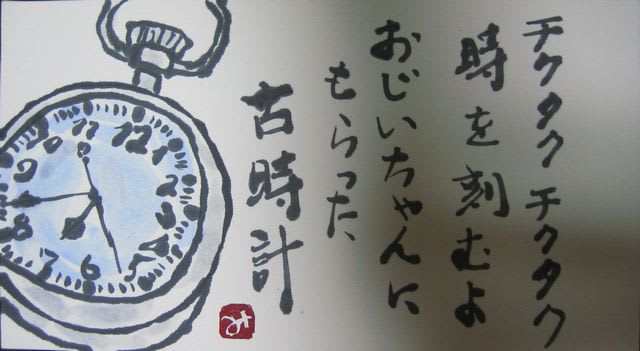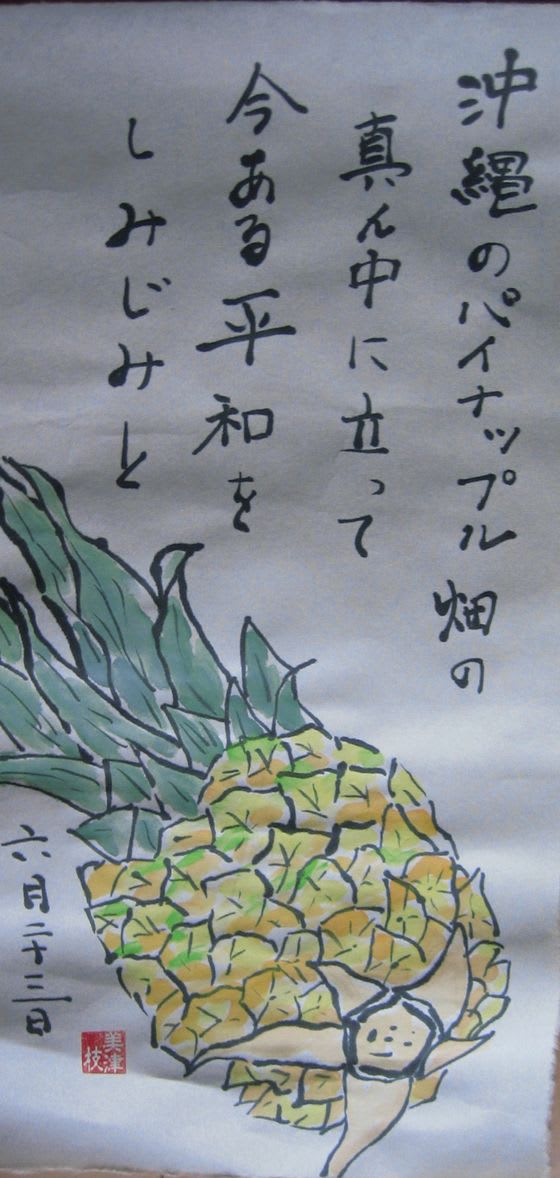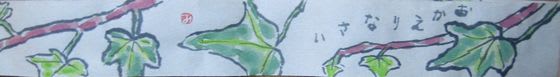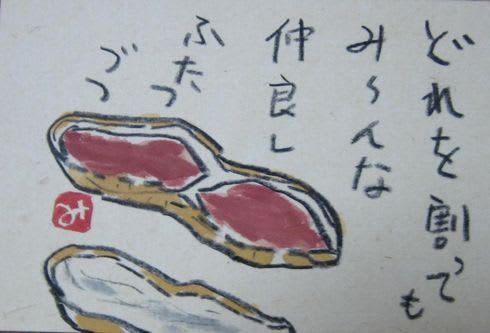【鬼の壁掛け】
鬼の壁掛けを作って描く
①鬼の顔を描く
②麻紙(ハガキ)に割り箸で描く
言葉で遊ぶ「くり返しことばを使う」
この白いのは、もともと、うさぎなんですよ、干支用にうさぎで・・・と、あったのを鬼に取っておきました。

ツノがありますね、眉はゲジゲジ、目はギョロッ、鼻は鷲鼻、口はグワ~ッと大きく開けてても閉じてても・・・
牙が多かっても少なかっても、自分の中に棲んでる鬼を描くみたいなカンジで~~
マジックで輪郭描いて、「いきなりマジックじゃぁ」と言う方は鉛筆で下書きを。
彩色は白残しとか何とかは別にして、ベタァ~と塗った方が良いですよ
目、ツノ、キバは金色。
鬼と言うと、赤、青、緑と、何色でもいいですよ、紫とか上朱(じょうしゅ)→朱色種でも。
線の際(きわ)を少しあけておくと、立体感が出ます。
ツノの黒い線は後で描く。



描き上げた鬼の顔を見ると、威嚇、なさけない、考え込んでると、意図しなくてもそんな表情になってしまったりして・・・
自分が描いた鬼とか、人が描いた鬼とか、いろんな鬼の表情を見てハガキに描いて、くり返し言葉で遊びましょう。
ぶつぶつ、がさがさ、なよなよ、ちょろちょろ、いらいら、いきいき、のろのろ、ごそごそ、こそこそ、わくわく、うろうろ、いきいき(みんなで、あんなんこんなんくり返し言葉を言いあいました)
鬼の目って黒目が上に寄ってますねぇ、睨みを効かせる「三白眼」と言いますね
「さぁ 鬼をハガキに描いてみますね、割り箸で描きます、グイグイグイッといきますよ」
鬼ってねみんなハガキの中にいれてしまわなくても良いですよ、大きく描いたら・・・
ツノから描いて顔は四角ばってが良いですね、
眉毛はごっつくて、目はギョロッと、グッグッグッと描いていきます
口はこう、ガァ~ッと開けて・・・
ググッと描いていきましょう。
彩色はハガキの場合、お面と違って、トントントンと塗っていきます、ペタァ~っと塗ってしまわないで白残しもたいせつですよ。
お面を隣の人と取っ替えてみましょう。
それぞれに表情もお顔の色も違うので面白いですよ。

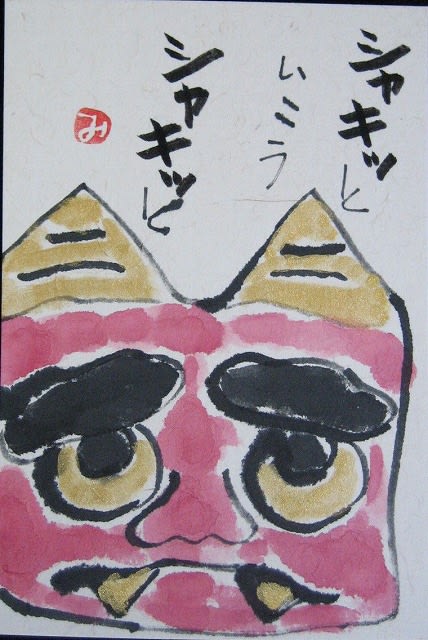
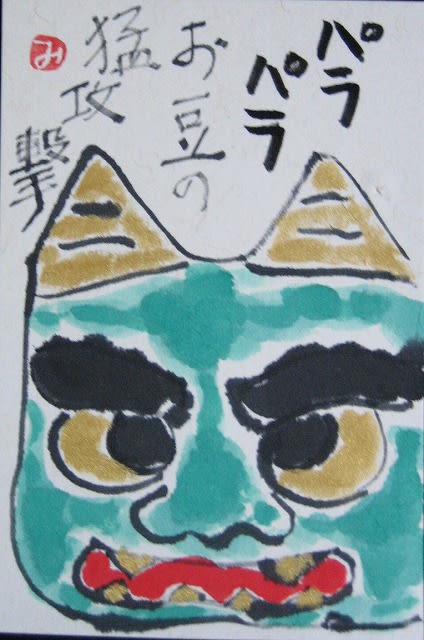
「節分の夜」 坂村真民
鬼やらいで追い出された
鬼の親子たちが
タンポポ堂に集まってくる
悉皆有仏性と
おっしゃったんだから
鬼にも仏性がある筈
よしよしといって
おこしやせんべいを出してやる
夜が明ければ
また行く処もあろう
お祭りだから
我慢するんだと
言いきかせ
鬼たちと
念仏をとなえる
↑道草さんからいただきました。
【蕪】

↑直径37㎝の笊に丸く水切りして貼り付けました
老灰紙を用意しました、あまり滲みはありません。
こちらにカブを用意してます、きれいなカブでシッポのあるのを描いて下さい
シッポが無いとカブじゃ無いですね。
売っているのは出荷の時にシッポを取ってしまうので、ウチの畑から抜いてきました。
薬をまかないので、虫が食べ放題になってます。
描くときはきれいな葉っぱでどうぞ・・・
虫食いを描くのも良いですね、多少はね、多少はね・・・ですよ。
カブの口から両方に楕円のように・・・
葉っぱなんですけどね、よく視ると真っ直ぐ生えているんじゃなくって、根元は少し広がってますね。
ハガキに描く場合は茎を短く葉っぱをすぐに描きます。
大きな紙の場合は茎を長く描けますが、葉っぱが重なってるところは、ええかげんで良いのですが、あんまりええかげんでもなんですので、やっぱりよく視て描いて下さいよ。
その場合、何本見えてるから、何本・・・と描かなくても良いです、しっかり見えてるところを描いて下さい
(カブの肌を塗る)老灰紙の場合、胡粉(こふん:白)をしゃ~っといきます、ベッタリ塗らないですよ。
首のとこ、若葉、白残しもちょっとね、
葉っぱの裏は薄めに表は濃いめに
しゃしゃしゃっと青草で。
「薄く切ってね、すし酢に漬けるんよ、蕪の甘酢即席漬けってカンジ・・・タカノツメの輪切りを少~し入れてね」とか
「その即席漬けにユズの皮の千切りを散らすと彩もいいよね」とか
「お出汁で、くつくつ煮て熱々をいただいたら、ぬくもるよね」とか、
「アクが無いので意外とシチューなんかにもイケるよ」とか
ここの絵手紙教室は先生はじめ生徒も全員主婦ですから・・・・・
【剥きかけのミカン】

↑ハガキ
こういうのん、やっぱりヘタから描きます
皮をむいてるので、むいてるカンジで。
グルッと描いてしまうと、味気ないので、ところどころ手を休めながら、ミカンは真ん丸じゃないので・・・
先に実からいきます、スジがありますね、
ちょっとなんか、皮にブツブツをいれましょう。
むいた内側、白いのがひび割れみたいなのがありますね。
皮の厚みも・・・
彩色にいきます
ヘタの切り口の中心は黄土、まわりは若葉+青草
むいたところは瑞々しいカンジをだすように。
白い筋があるのでベッタリ塗らないですよ、きれいなオレンジで。
皮は少し薄め、内側は薄~いオレンジ
オレンジの出し方は、皮は鮮光黄(せんこうき)→きいろ+上朱(じょうしゅ)→朱色
ヘタの周りがプクッとしたのがあれば、プクッと膨らんでね・・・
熱いミカンも美味しいよね、って話題に
子供のころ学校から帰ったら、祖母が火鉢でミカンを皮ごと焼いてくれてました。
掌にタオルで包んだ熱々のミカンを転がしながら、ふうふうしていただいたこと思いだしました。