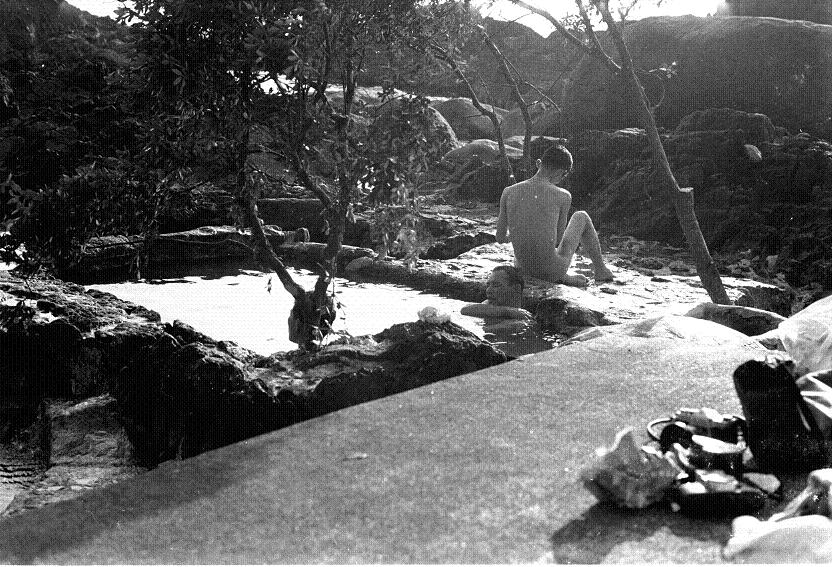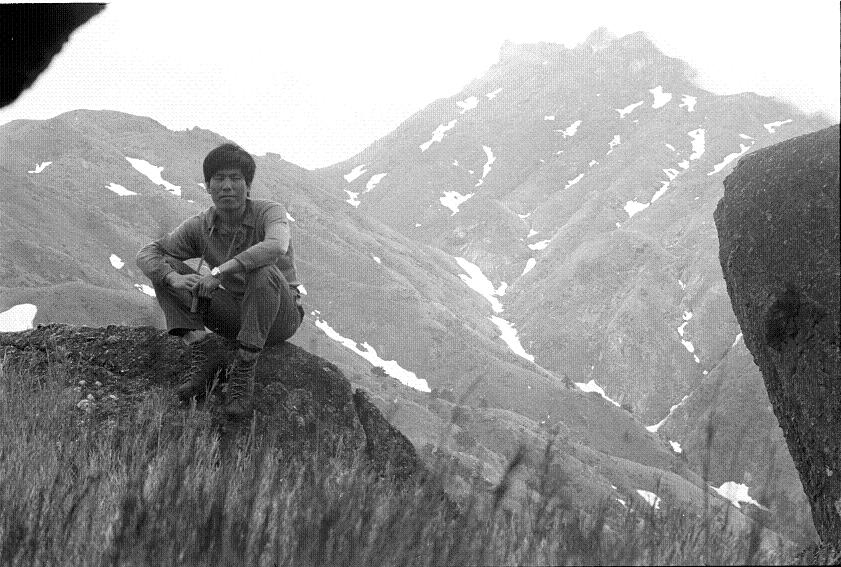撮影場所 岩手県久慈市山根町
久慈市から山間部に入った山根町の集落がNHK昼の番組に出てきた。
茅葺民家に常設の稲架やバッタリと呼ばれる水車がでてきた。
茅葺民家の出てきそうな時は録画予約をしておく。
東北の茅葺民家の情報は持ち合わせていなかった。
北山崎などの観光も終えて久慈市に泊まった。
走れば茅葺民家はあるだろうと思ったが県レベルの道路周辺はほとんどなかった。
山の中に入って初めて茅葺に出合えた。
NHKテレビに出てきた集落に行ったら稲を干していた。
何段にも積まれていた。どうして積むのか見ていたら稲の束の下に棒を入れ上の男性に渡していた。
竹の豊富なところは竹を組み一段掛け、山陰は竹の骨組みに何段も掛ける。
新潟県は杉の樹木に棒を渡し7段くらい掛ける。
東北は一般的に棒杭に稲を掛ける棒掛けが多い。
鉄道沿線や茅葺民家をバックに撮影されている。
ここ山根町には栗の木の稲架がある100年以上経過するが現役であった。
栗の木は腐れにくいので重宝されている。
写真 稲掛けをしている後ろに茅葺民家がある。
この地方はほとんどが草棟であった。

久慈市から山間部に入った山根町の集落がNHK昼の番組に出てきた。
茅葺民家に常設の稲架やバッタリと呼ばれる水車がでてきた。
茅葺民家の出てきそうな時は録画予約をしておく。
東北の茅葺民家の情報は持ち合わせていなかった。
北山崎などの観光も終えて久慈市に泊まった。
走れば茅葺民家はあるだろうと思ったが県レベルの道路周辺はほとんどなかった。
山の中に入って初めて茅葺に出合えた。
NHKテレビに出てきた集落に行ったら稲を干していた。
何段にも積まれていた。どうして積むのか見ていたら稲の束の下に棒を入れ上の男性に渡していた。
竹の豊富なところは竹を組み一段掛け、山陰は竹の骨組みに何段も掛ける。
新潟県は杉の樹木に棒を渡し7段くらい掛ける。
東北は一般的に棒杭に稲を掛ける棒掛けが多い。
鉄道沿線や茅葺民家をバックに撮影されている。
ここ山根町には栗の木の稲架がある100年以上経過するが現役であった。
栗の木は腐れにくいので重宝されている。
写真 稲掛けをしている後ろに茅葺民家がある。
この地方はほとんどが草棟であった。