私の出資馬、ドルフィンルージュがソエを発症しました。
ソエについては、『それほど重い病気ではなく回復後は競争能力にほとんど影響がない』ということを漠然と知ってはいるので、今回のドルフィンルージュの件もそれほど深刻には考えていません。
(先ほどの記事で書いたとおり、『いい休養』程度に思っています。)
ただ、そもそもソエとは何で、どんな治療法があるのか、本当に競争能力に影響はないのか、などなど、知っているようであやふやなところもあるので、念のために調べてみました。
“ソエ”とは、若駒に見られる“管骨骨膜炎(第三中手骨膜炎)”のこと。
読んで字のごとく管骨が骨膜炎を発症したということなのですが、どうやらその発症の正確な原因については今でも明らかになっていないようです。一般的には、成長し切っていない若馬に強めの調教などを課した場合、化骨不足の管骨背側面に過剰な力が掛かり、それが原因で管骨が炎症を起こしたものと考えられています。
ソエを発症した馬はとても脚を痛がる(跛行を起こす場合も多い)ので発見は容易です。従って、治療が遅れて症状が重くなるということは考えにくいのですが、一番の問題は、原因がはっきりしていないため、即効性のある治療法が確立されていないことです。
最近はあまり聞かなくなりましたが、ソエの治療法として有名なものに“焼烙治療”というのがありました。
これは、ソエを発症した馬の幹部に焼きゴテを当てて火傷をさせ、その火傷の回復過程がソエの良化を後押しすることを期待するという治療法です。ちょっと聞いただけでも、本当に効果があるの?と思ってしまいますが、昔からソエを発症した馬に対してこの方法が取られてきたのは事実です。
また、同じ考え方の治療法に、“ブリスター治療”というのがありますが、これは、焼きゴテで皮膚を焼く替わりに薬品を使って皮膚を爛れさせるというものです。正直言って、この方法も個人的には相当怪しいと感じてしまいますが、厩舎によっては今でもこうした方法を採用する場合があるようです。
“焼烙治療”や、“ブリスター治療”に科学的な根拠はないのですが、よく言われるのは、“お灸のようなもの”という説明です。ただ、お灸だとしても火傷をするほどのお灸など聞いたことがありませんし、それがソエの回復に効果があるという統計的なデータもないため、今ではこうした治療方法は姿を消しつつあります。
そして、現在主流になっている治療方法が“ショックウェーブ治療”というものです。
この方法は、ショックウェーブ(衝撃波)によって細胞を刺激し、新陳代謝に変化を起こさせることで新しい血管形成を促進させる治療法のことです。
競走馬の世界でショックウェーブが使われるようになったのはここ5、6年のことだと思いますが、2000年以前から人間に対する治療法として確立していたこともあり、“焼烙治療”や、“ブリスター治療”に比べると遥かに科学的かつ合理的で、臨床データも揃っています。
グローバルにいるドルフィンルージュも当然のことながら“焼烙治療”や、“ブリスター治療”ではなく、ショックウェーブと休養の組合せでケアして頂いていますが、現在のところはこの“休養とショックウェーブ治療の組み合わせ”というのがソエに対する最も効果的な処方箋ということのようです。
競争能力との関係についても、能力が高い馬はソエになりやすいとか、ソエから回復した馬はスピード能力が高まるとか、いろいろな言い伝えがあります。しかしながら、その手の話は全くの迷信のようです。(昔は若馬がソエに掛かると、厩舎で赤飯を炊く習慣もあったらしいですね。)
ソエは(比較的治りやすいとはいえ)病気ですから、発症しないに越したことはありません。(つまり、競争能力への直接的な影響で言えば、プラス方向に働くことはありません。)
ただし、ソエという、馬が人間に発信するサインを正しく理解して、早めの休養と適切な治療をえば、結果的にその馬の更なる成長を促すことに繋がり、ソエから回復したあとに予想以上の大成するということはあるかもしれません。
何だか長い説明になってしまいましたが、要するに、2歳馬のソエはあまり心配しても仕方がないということです。
ましてや、この時期の休養は将来のプラスになる可能性もありますから、ドルフィンルージュについても慌てずに成長を待ってあげたいと思います。
ソエについては、『それほど重い病気ではなく回復後は競争能力にほとんど影響がない』ということを漠然と知ってはいるので、今回のドルフィンルージュの件もそれほど深刻には考えていません。
(先ほどの記事で書いたとおり、『いい休養』程度に思っています。)
ただ、そもそもソエとは何で、どんな治療法があるのか、本当に競争能力に影響はないのか、などなど、知っているようであやふやなところもあるので、念のために調べてみました。
“ソエ”とは、若駒に見られる“管骨骨膜炎(第三中手骨膜炎)”のこと。
読んで字のごとく管骨が骨膜炎を発症したということなのですが、どうやらその発症の正確な原因については今でも明らかになっていないようです。一般的には、成長し切っていない若馬に強めの調教などを課した場合、化骨不足の管骨背側面に過剰な力が掛かり、それが原因で管骨が炎症を起こしたものと考えられています。
ソエを発症した馬はとても脚を痛がる(跛行を起こす場合も多い)ので発見は容易です。従って、治療が遅れて症状が重くなるということは考えにくいのですが、一番の問題は、原因がはっきりしていないため、即効性のある治療法が確立されていないことです。
最近はあまり聞かなくなりましたが、ソエの治療法として有名なものに“焼烙治療”というのがありました。
これは、ソエを発症した馬の幹部に焼きゴテを当てて火傷をさせ、その火傷の回復過程がソエの良化を後押しすることを期待するという治療法です。ちょっと聞いただけでも、本当に効果があるの?と思ってしまいますが、昔からソエを発症した馬に対してこの方法が取られてきたのは事実です。
また、同じ考え方の治療法に、“ブリスター治療”というのがありますが、これは、焼きゴテで皮膚を焼く替わりに薬品を使って皮膚を爛れさせるというものです。正直言って、この方法も個人的には相当怪しいと感じてしまいますが、厩舎によっては今でもこうした方法を採用する場合があるようです。
“焼烙治療”や、“ブリスター治療”に科学的な根拠はないのですが、よく言われるのは、“お灸のようなもの”という説明です。ただ、お灸だとしても火傷をするほどのお灸など聞いたことがありませんし、それがソエの回復に効果があるという統計的なデータもないため、今ではこうした治療方法は姿を消しつつあります。
そして、現在主流になっている治療方法が“ショックウェーブ治療”というものです。
この方法は、ショックウェーブ(衝撃波)によって細胞を刺激し、新陳代謝に変化を起こさせることで新しい血管形成を促進させる治療法のことです。
競走馬の世界でショックウェーブが使われるようになったのはここ5、6年のことだと思いますが、2000年以前から人間に対する治療法として確立していたこともあり、“焼烙治療”や、“ブリスター治療”に比べると遥かに科学的かつ合理的で、臨床データも揃っています。
グローバルにいるドルフィンルージュも当然のことながら“焼烙治療”や、“ブリスター治療”ではなく、ショックウェーブと休養の組合せでケアして頂いていますが、現在のところはこの“休養とショックウェーブ治療の組み合わせ”というのがソエに対する最も効果的な処方箋ということのようです。
競争能力との関係についても、能力が高い馬はソエになりやすいとか、ソエから回復した馬はスピード能力が高まるとか、いろいろな言い伝えがあります。しかしながら、その手の話は全くの迷信のようです。(昔は若馬がソエに掛かると、厩舎で赤飯を炊く習慣もあったらしいですね。)
ソエは(比較的治りやすいとはいえ)病気ですから、発症しないに越したことはありません。(つまり、競争能力への直接的な影響で言えば、プラス方向に働くことはありません。)
ただし、ソエという、馬が人間に発信するサインを正しく理解して、早めの休養と適切な治療をえば、結果的にその馬の更なる成長を促すことに繋がり、ソエから回復したあとに予想以上の大成するということはあるかもしれません。
何だか長い説明になってしまいましたが、要するに、2歳馬のソエはあまり心配しても仕方がないということです。
ましてや、この時期の休養は将来のプラスになる可能性もありますから、ドルフィンルージュについても慌てずに成長を待ってあげたいと思います。










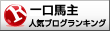

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます