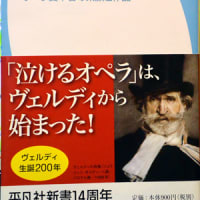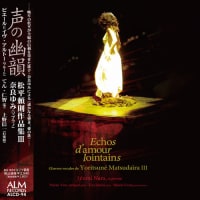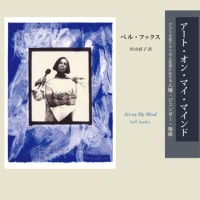北沢方邦の伊豆高原日記【139】
Kitazawa, Masakuni
ようやく遅咲きの白梅・紅梅が満開となり、コブシやモクレンの枝々の蕾も膨らみ切り、いまにも咲きそうだ。だいぶまえから咲き誇っているスイセンの花々は、まだ芳香を漂わせている。今朝(3月5日)ヴィラ・マーヤを開けに行くとき、半月以上も遅いウグイスの初鳴きを聴いた。春めいた陽射しとともに、心にほのぼのとした暖かさを喚起する。
いじめと自殺
ニューヨーク・タイムズ書評紙を読んでいると、アメリカでも子供の「いじめ(bullies)」が深刻な問題となり、何冊かの本が出ているようだ。だが私見によれば、この問題は大人の自殺の増加問題と深く関連した社会現象であり、先進諸国共通の病理であるように思われる。
戦前、私の子供のころにもいじめは存在していた。父の転勤やその死後の家庭の事情で、小学校を4校も転校したが、そのたびにいじめにあったことを覚えている。下校時校門に待ちかまえていた悪童たちに、「おまえは生意気だ」「転校生のくせに大きな顔するな」などと言いがかりをつけられ、殴る蹴るの喧嘩を展開したものである。多勢に無勢でいつもやられっぱなしであったが、東京に出たときは逆に数人の相手に鼻血をださせたりして勝ったことがある。
もちろん親にいいつけるなどは卑怯であり、恥とされていたし、また子供の喧嘩に親がでるのも大人の恥とされていたから、母も知らなかったか、知っていても黙っていたようだ。
だがこれは一種の通過儀礼であり、ひと月もしないうちに悪童たちとはとりわけ仲良くなり、遊び仲間となった。こうした陽気な喧嘩やその意味での暴力沙汰は、子供たちの集団生活でのある種の身体的ルールでもあり、また喧嘩や格闘も、医者に行くような怪我にいたることなどはけっしてなかった。
だが現在の「いじめ」はそのようなものとはまったく異なり、たんに陰湿であるというより、他者の人格や人権の抹殺を意図し、いじめの相手が自殺でもしようものなら、快哉を叫びかねないような病的なものである。またいじめにあったものが、簡単に自殺する内面の弱さも問題であり、両者は問題の盾の表裏であるといえる。
人間の性善説と性悪説
18世紀西欧でのルソーとホッブズの思想的対立以来、人間の性善説と性悪説はつねに対立を繰り返してきた。この伊豆高原日記【130】でも取りあげたが、スティーヴン・ピンカーやナポレオン・シャグノンらは近年の性悪説の代表である。『われらの本性のより良き天使たち』(2011年)という題名とは裏腹に、ピンカーは《ヒトはヒトにとって狼である》というホッブズを称揚し、近代の啓蒙思想と理性信仰がはじめてヒトの本性である悪を克服したとする。アマゾンの戦士ヤノマメ族に土産として銃をあたえ、麻疹ワクチンで逆に麻疹を流行させた(後者の疑惑は晴れたが)として悪名高いシャグノンは、ヤノマメの好戦性や攻撃性を「未開」の野蛮の典型とし(それも近年の生活環境の激変でそうなった可能性が高い)、性悪説を唱えている(これもルソーを皮肉る題名の本『高貴な野蛮人;二つの危険な部族─ヤノマメと人類学者ども─のなかでのわが生涯』 Noble Savages; My Life Among Two Dangerous Tribes─the Yanomamo and the Anthropologists. By Napoleon A. Chagnonのなかで)。
だが、たとえばわれわれ現生人類(Homo sapiens sapiens)はすでに数十万年生きているが、同じころ生存していたネアンデルタール人は、なぜ10万年しか生存できなかったのか? その答えはいくつかあるが、有力なひとつは、われわれが集団の絆が強く、つねに助け合い、自然との共生をはかってきたからである。人口の増加や環境の変化に適応して移住し、約二十万年かけて地球の主要部分に達したわれわれの祖先が、ヒトはヒトにとって狼であるような闘争社会に生きていたとしたら、このようなことはありえず、ネアンデルタール人同様いつか絶滅していたことであろう。
この一事をもってしても、ルソーの正しさは証明される。だが問題は、生活環境の変化、というよりも激変によって人間は性悪にもなりうることである。
近代人の脆弱性
ピンカーの主張とは逆に、啓蒙思想や合理主義以降の近代人は、精神的にきわめて脆弱になり、また経済的・物質的にはヒトはヒトにとって狼であるホッブズ的状況をみずから作りだしたといわなくてはならない。後者は訴訟社会といわれるように、国家が強制する法と秩序によってかろうじて安定が保たれることとなる。
ここで問題なのは前者である。すなわち、無意識や身体性のレベルでつちかわれる文化や本能的なルールより、意識や知識のレベルで獲得されるいわゆる理性的なものが優位にあるという教育や偏見にまみれ、自己のほんとうのアイデンティティが形成されないからである。人間はアイデンティティなしでは生きられないから、それに代わる偽のアイデンティティが形づくられる。国民というアイデンティティ、集団や組織や家族への帰属というアイデンティティなどなどであり、近年ではいわゆるソーシャル・ネットワークなどヴァーチャルなアイデンティティまでもが加わる。
だが、旧ソヴェト連邦や旧ユーゴスラヴィア連邦の解体時にみられたように、国家意識という偽のアイデンティティはたちまち消滅し、それに代わっていわゆる民族や宗教など別の疑似アイデンティティが紛争や葛藤をつくりだす。
戦前の古い共同体や郷土的文化──ナショナリストたちのようにそれらを復活させようとは毛頭思わないが──が解体され、明治近代化よりもさらに急激な近代化に邁進した戦後の日本では、この近代のアイデンティティ危機は他国より深刻であるといわなくてはならない。高度成長期にはまだ生活向上の期待で破綻することのなかったもろもろの偽アイデンティティも、格差社会の到来とそれによるひどい閉塞感のなかでは、もはやその疑似機能さえも果たすことはできない。欲求不満にもとづく攻撃性は自己より弱いものに向かい、上記のような「いじめ」となる。いじめを受けたものも、アイデンティティの脆弱さゆえに、それを跳ね返すような力をもつことはできない。子供だけではなく、大人の社会も同様である。鬱病や自殺の蔓延も、このことに根本原因がある。
それを救うのはなにか? 「アベノミクス」が招くにちがいない一層の格差の拡大と貧困層の増大は、状況をますます深刻にするだけである。そうではなくて、グローバリズム破綻後の状況にしっかりと適応するエコロジー的で持続可能な社会のヴィジョンを打ち立て、そのなかで身体性にもとづく新しい価値観や教育体系を創りだすことである。