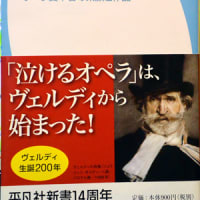おいしい本が読みたい●第十話 読点は語る
“彼女は切った、乱暴に、根元から、ひと房の長い髪を。
―それをとっといて下さいね! お別れです!“
ひょんないきがかりで再読することになった、フロベール『感情教育』のクライマックスシーンでの一節である。ほぼ二十年ぶりに再会した、初老のアルヌー夫人と年下のフレデリック、訪ねてきたのが彼女なら、別れの言葉を口にするのも彼女で、男は小説の最初から最後まで煮え切らない。場所は彼のアパルトマン、時は三月下旬のとある夕刻。目だけがはっきり見えるようなコスチュームで、日暮れ時を選んだのは、やはり相応の理由があるだろう。
わたしたちの身体のなかで、目はもっとも老化に抵抗すると言われる。薄暗がりのなかで、帽子をかぶったままの夫人の目を見る男は、二十年前の麗しの夫人を幻視する、おそらく彼女の計算どおりに。男は独身である。それでも何事も起こらないのが、軟弱男フレデリック・モローを主人公にすえたフロベールの新しさだった。
新しさついでに言えば、このクライマックスで物語が終わっていたなら、ある種の映画のラストシーンのような、それなりの余韻を残す効果があっただろうと思える。しかし作者はそうせず、フレデリックはもうしばらく無味乾燥な、さほど面白くもない人生を生きることになる。リアリズム文学の元祖と称される所以はこの辺にもある。
フロベールのこの小説の何が見事といって、読点と余白の使い方ほど見事なものはない。その好例が冒頭にあげた一節であった。余白については若干留保がいるかもしれない。というのは、作者が余白を計算に入れていることは明らかだけれども、彼が意図したのは初版の余白であって、わたしの眺めているポケット版では多少模様が異なるはずだからだ。
その点、読点は心配いらない。それにしても、さして長くないこの一文に読点が三個。副詞「乱暴に」とあいまって、この三つの読点が最大の効果を与える。ことばで名指すのではなく、ことばとことばの狭間の空白に、空白の息遣いのなかに、女の内面を封じ込めようとしたのだろうか。語りえぬものは、感じさせるしかないのだろうか。
この手の読点多用でいつも思い起こすのは、谷沢永一の文である。ただし、谷沢の場合は、フロベールのようにここぞというところで用いるのではなく、延々読点オンパレード文体で攻める、泣き落とし戦術に近い。引用は、親友だった開高健への挽歌とも言うべき『回想 開高健』(新潮社)の最終行。
“その、開高健が、逝った。以後の、わたしは、余生、である。”
むさしまる