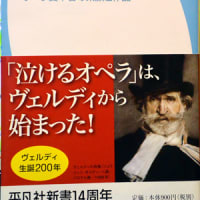おいしい本が読みたい●第二十一話
在日の…
「子供のころは、毎日毎日、ニワトリの卵を売って歩いていたな、アボジに仕事がなくてさ。あのころは、せつなかったよ」。いつか仕事の後で、ふだんは茶目っ気たっぷりの朴さんが、酔いに誘われたようにしんみりと言った。「そのせつなさを、後の人生に活かしたようにはみえねえぞ」。そうからかうと、妙におとなしく「へへへ…」と笑うばかり。
後にも先にも「せつない」過去を朴さんが語ったのはこのときだけだ。父親の出身地済州島のこと、「北」のこと、日本の政治のこと、ギャンブルのこと、酒と女はいわずもがな、話題は百般におよぶけれども、こちらが無理に追及しないかぎり、あの時代のことは触れたくなさそうな雰囲気が今もただよう。
あれもひとつのオーラル・ヒストリーなのか、そう得心したのは『在日一世の記憶』(小熊英二・姜尚中編、集英社)に手をつけたときだった。『砧を打つ女』(李恢成)の抒情、『血と骨』(梁石日)の泥臭、『Go』(金城一紀)の軽快などなど、いわゆる在日作家の受賞作品にはもともとわたしとウマの合う部分が多かった。けれども、これらのフィクションからこぼれ落ちていたものが、『在日一世の記憶』にある。そのなかのひとつが、文字を手にしていない在日女性たちの、表現手段を求める”切実さ”である。 ひとつの例として、「働いて、働いて、働いて」の姜必善(カン・ピルソン)さんの言葉に耳を傾けてみよう。おそらくすべてがここにあるのではないだろうか。
ひらがなカタカナを覚えたなあと思ったら、先生が「姜さん、名前稽古しよか」といわれましたんや。うれしいこと、うれしいこと。ひらがな、カタカナよりも自分の名前まず教えてもらいたかったんですが、恥ずかしゅうていわれへんでしたんや。 先生に「わたしの名前は“あらいあさこ”やけど、どないしてかきまんにゃ」というと、福西先生が、「本名、先覚えましょう」というてくれて初めて書きましたんや。ひらがな、カタカナ、自分の名前を書いて、いままで目が見えなかったんがパーッと見えてきた感じでした。
87歳で夜間中学に通う姜さんは、こうしてほとんど晩年に、書き言葉という表現手段の初歩を、手に入れつつある。それが両親の母語ハングルでなく日本語だということの意味は、わたしたちが考えるべきことだ。
むさしまる