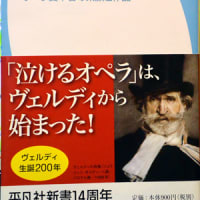おいしい本が読みたい●第十六話
昔のブラジルから本が届いた
いつ頃から興味をもったのか、何のきっかけでそうなったのか、自分でもよくわからないのだが、気がついてみたら机の周りに何冊か、こっちを見てごらん、と言わんばかりに自己主張をしてくる本がかたまっている。ラテン・アメリカの本たちだ。
いま自分のいる場所からもっとも隔たったところ。クレオール的文化への憧れ。そのあたりに興味の理由があるのかもしれないが、嫌いな理由は言い易くても、好きな理由はいわく言い難いことのほうが多い。
で、これまたなんとなく、学校の図書館の歴史関係の書架を眺めていて、おやこんな本が、と目に留まったのが、ジルベルト・フレイレの『大邸宅と奴隷小屋 -家父長制家族の歴史』(鈴木茂訳、日本経済評論社2005)だった。
原著の初版は1933年で、いかにも旧時代の著作ではあるけれども、今世紀になって訳されるだけの価値はある。ブラジルの家父長制というかプランテーションの歴史を、これだけ膨大な資料を踏まえて、巨細にわたって論じた書は、少なくとも日本のなかでは、他に見られないと思う。
惜しまれるのは、社会史の名著として名を残すだけの分析力と総合力をかねそなえ、さらに、学術的著作に欠如しがちなある種の熱情を投じていながら、その熱情がときとしてブラジル国民論に横滑りし、そこからナショナリズムへと昇華する道筋がほの見えることである。
昔日の大航海時代の先駆けから欧州の貧乏国へと落剝の身を晒すポルトガル、その末裔をもって任じるフレイレのブラジルは、世界恐慌をむかえた当時、まだまだアメリカに無条件の隷従を強いられる遅れた大国にすぎない。アメリカの大学に学んだフレイレには、だから、なおのこと自国(民)の可能性を信じてやまぬ思いは強かったろう。その点は加味してやらねばなるまい。
さて、わたしにとって大いなる収穫はふたつ。ひとつは、イザベラ・アジェンデ『精霊たちの家』のなかで、主人公が自宅中で先祖の亡霊としばしば出くわす、その理由の一半が理解できたことだ。作者イザベラはたしかに、その手の能力を有する特異な人である。彼女の他の著作をひも解けばそれは了解しうる。
しかし、別の与件も必要らしい。すなわち、イザベラがブラジルの伝統的家父長制にふさわしい家に育ったことなのだ。プランテーションでは敷地内の母屋(それがカザ・グランデ=大邸宅)に隣接して礼拝堂が配置され、そこに故人の亡骸も埋葬される習慣があったとフレイレは記す。つまり死者と生者がまさしく同居するのが家父長的家屋の伝統であって、イザベラの幻視も風土に根ざしたものともいえそうだ。
もうひとつの収穫は、土を食べる風習のこと。ガルシア・マルケス『百年の孤独』だと記憶するが、お姉さんが壁土をこっそり食べる悪癖を治せないでいるシーンがあった。また、飢餓に悩む現実のハイチで子供たちが泥のビスケットを齧っているとの報道もあった。かねて不思議な符合だと思っていたら、フレイレの記述に、土を食べる悪癖に染まった奴隷の幼児のことがでてきた。アフリカ人奴隷たちが自殺手段の一つとして用いたものが、「奴隷であると自由人であるとを問わず、広く子供たちも染まっている」奇妙な習慣となったらしい。ブラジルからコロンビア、ハイチへと、500年の植民地支配の重みは、やはり、いちばん脆弱な子供たちにのしかかるしかないのか。
それはそれとして、柳田国男の『遠野物語』にも、一人息子が大阪の戦に駆り出され、土を食っていた婆様の話がある(婆喰地(バクチ)という地名の由来話)。こちらは食べ物に困ったあげくというのでもない。
洋の東西は思わぬところで袂を分かたぬ。それを教えてくれたのも、フレイレであった。多謝。
むさしまる