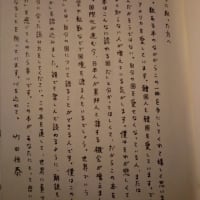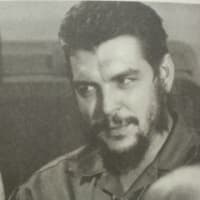曽野 綾子さんのエッセイ。
「新潮45」連載の「夜明けの新聞の匂い」の単行本です。
平成19年1月号から平成20年8月号までの記事が収められてをります。
曽野さんは作家といふことしか知りませんでしたが、ご自身はJOMAS
(海外邦人宣教者活動援助後援会)といふNGOの会長でもあられたのですね。
この連載記事を初めて読んだのですが、それで曽野さんのNGO活動も知つたり
日本人の修道女の方々で、アフリカの「所謂、ほんたふの僻地」といふやうな場所で医療活動をされてゐたりする方々がいらっしゃるのを知りました。
また、ユニセフなど国連の寄付機関への寄付金の使途不明金があることや
膨大な数の国連職員が世界各地で特権階級の生活をしてゐるといふのも知りました。
自分も、国連機関に寄付をするのは止めました。今まで信用してゐたのに・・・・
「国境無き医師団」からの寄付の御願いがポストに入つてゐたので、一度小額ながら寄付しましたら、また寄付の御願いが郵送されてきました。当時、地下鉄などに何枚も大判のポスターが貼つてあり、「この広告費はいくらなのだらう?」と思ひました。
何を信用してよいのかわかりませんが、自分は死んだら残つたお金は全額寄付に
するやうに「一筆」書くつもりです。
死んだらお金は不要となりますので(きつと)、必要な人に使つてもらいたいと思ひます。
自分の知らないことがたくさん書かれてゐて、学ぶことが多い一冊だと思ひます。
基本的に、自分の考へは曽野さんのお考へに賛成です。同意見のところが多かつたです。
戦後の「日教組教育の失敗」を曽野さんが記述されてをりますが、全く同意見です。
精神的にもひ弱で、教養の無い子供といふか人間が出来たのではないかと思ひます。
自分の場合、オーストラリアといふ「国外」に一定期間生活することで「日本人とは何か」「自分が日本人であること」「日本人であるために知つておかなければならないこと」等を感じ、学んだと思ひます。
しかし、日本だけにゐると、これが殆ど見えない。 「朱に交われば赤くなる」ではないけれど、最初から「赤」の一粒であれば、反対側の白地に行つてみないと「赤が何か」を感じるのは難しゐ。
今の日本、戦後50年で経済大国となり「苦労を知らない人たち」が増えたけれど
「電気も水も無い」地域といふのは今でも世界各地にあるはづであり・・・・
電気も水も無い=自力でなんとかしてゐる地域=二酸化炭素排出量少なし
電気も水もある=電力・原子力などを使用してゐる地域=一般に豊かと言はれてゐる=二酸化炭素排出量多し=温暖化誘発=途上国に被害
といふ構図も頭に浮かんで、「豊か」になつても「豊かになりすぎるのはいかがなものか?」とも思ひました。
考へることが沢山あつた、一冊でした。
「新潮45」連載の「夜明けの新聞の匂い」の単行本です。
平成19年1月号から平成20年8月号までの記事が収められてをります。
曽野さんは作家といふことしか知りませんでしたが、ご自身はJOMAS
(海外邦人宣教者活動援助後援会)といふNGOの会長でもあられたのですね。
この連載記事を初めて読んだのですが、それで曽野さんのNGO活動も知つたり
日本人の修道女の方々で、アフリカの「所謂、ほんたふの僻地」といふやうな場所で医療活動をされてゐたりする方々がいらっしゃるのを知りました。
また、ユニセフなど国連の寄付機関への寄付金の使途不明金があることや
膨大な数の国連職員が世界各地で特権階級の生活をしてゐるといふのも知りました。
自分も、国連機関に寄付をするのは止めました。今まで信用してゐたのに・・・・
「国境無き医師団」からの寄付の御願いがポストに入つてゐたので、一度小額ながら寄付しましたら、また寄付の御願いが郵送されてきました。当時、地下鉄などに何枚も大判のポスターが貼つてあり、「この広告費はいくらなのだらう?」と思ひました。
何を信用してよいのかわかりませんが、自分は死んだら残つたお金は全額寄付に
するやうに「一筆」書くつもりです。
死んだらお金は不要となりますので(きつと)、必要な人に使つてもらいたいと思ひます。
自分の知らないことがたくさん書かれてゐて、学ぶことが多い一冊だと思ひます。
基本的に、自分の考へは曽野さんのお考へに賛成です。同意見のところが多かつたです。
戦後の「日教組教育の失敗」を曽野さんが記述されてをりますが、全く同意見です。
精神的にもひ弱で、教養の無い子供といふか人間が出来たのではないかと思ひます。
自分の場合、オーストラリアといふ「国外」に一定期間生活することで「日本人とは何か」「自分が日本人であること」「日本人であるために知つておかなければならないこと」等を感じ、学んだと思ひます。
しかし、日本だけにゐると、これが殆ど見えない。 「朱に交われば赤くなる」ではないけれど、最初から「赤」の一粒であれば、反対側の白地に行つてみないと「赤が何か」を感じるのは難しゐ。
今の日本、戦後50年で経済大国となり「苦労を知らない人たち」が増えたけれど
「電気も水も無い」地域といふのは今でも世界各地にあるはづであり・・・・
電気も水も無い=自力でなんとかしてゐる地域=二酸化炭素排出量少なし
電気も水もある=電力・原子力などを使用してゐる地域=一般に豊かと言はれてゐる=二酸化炭素排出量多し=温暖化誘発=途上国に被害
といふ構図も頭に浮かんで、「豊か」になつても「豊かになりすぎるのはいかがなものか?」とも思ひました。
考へることが沢山あつた、一冊でした。