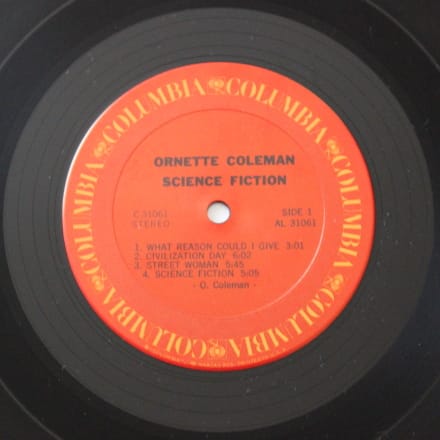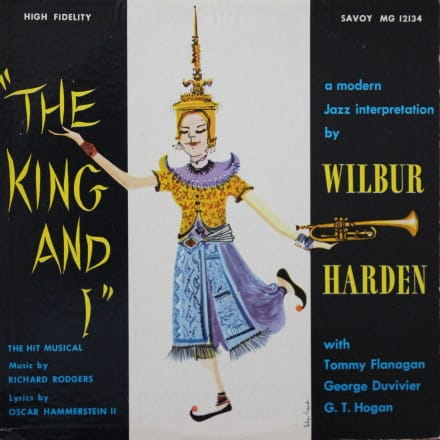Guttorm Guttormsen Kvartett / Albufeira ( ノルウェー Octave OCLP 03 )
グットルム・グットルムセンの第2作で、1979年7月にスタジオ録音されたもの。 同じワンホーンカルテットですが、今回はアルトも吹いています。
前作から4年ものインターバルを経てどうなっているかというと、前作よりも意識的に半歩ほど当時の主流派ジャズに近づいた雰囲気があります。
第1作は無理をせず自分たちの心象風景をありのまま綴ったような感じでしたが、こちらはかなり意図的にジャズに取り組んだ跡があり、そういう意味では
音楽家としての自意識が以前よりも強くなっている印象を受けます。 楽曲の中の起承転結がより明確になっているし、自分に与えられた小節数の中で
事前にかなり練習を重ねたようなフレーズを演奏しているので、かっちりとした感じがします。
アルトの演奏はかなりおぼつかないところがあって、運指が遅れたりリズムに乗りきれないところも多く、まだまだこれからというところです。
ピアノとドラムが前作とはメンバーが変わっており、ドラムは前作の人のほうが圧倒的に上手く、そのせいでこの作品は全体的にリズム感が少し
ぎこちない感じがします。 また、レーベルも変わった影響か、録音も少し貧しい仕上がりになっています。 今回はメンバー各人がオリジナルを
持ち寄った楽曲構成になっているので、曲ごとの雰囲気がバラバラで統一感が稀薄で、最後の曲なんかはまるでリターン・トゥ・フォーエヴァーの
アルバムに入っていそうな曲で、聴いていて思わず苦笑いしてしまいます。
プロとして自覚的な音楽をやろうとしたところは伝わってくるので立派だと思いますが、ここではまだその成果は出ていないなあ、というのが率直な
感想で、この後の作品をといきたいところですが、これ以降はアルバムがないようなのでどうなったのかよくわかりません。 北欧の演奏家はあまり
アルバムを出すことに執着しない人が多く、これが北欧のジャズの実像を把握しにくくしています。 ここで途切れてしまったのは、残念です。