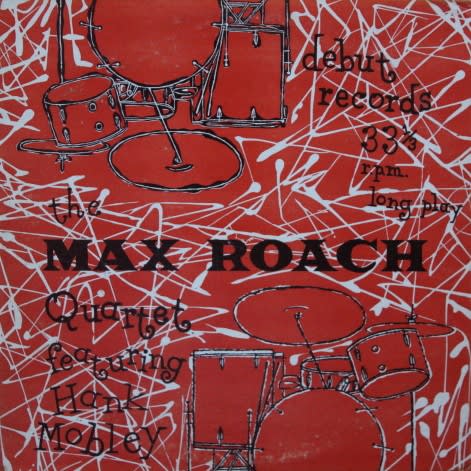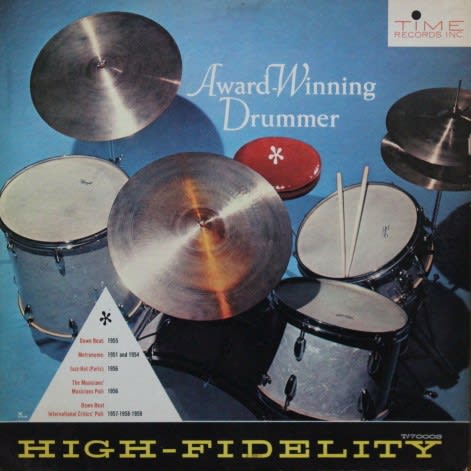Barry Harris / Breakin' It Up ( 米 Argo LP 644 )
バリー・ハリスの遅すぎるデビュー・リーダー作がチャーリー・パーカー集だったというのは、彼の音楽観をよく表していて、如何にもこの人らしい。
世に無数に存在するパーカー集の中でも、このアルバムが醸し出す雰囲気はパーカーの音楽が持っていた抒情的な側面を非常に上手く再現していて、
筆頭の出来の1つに挙げていい。 冒頭の "All The Thing You Are" が放つエレガントな芳香はパーカーが吹いた "Bird of Paradise" の雰囲気そのもの。
バリー・ハリスはピアノの技術で聴かせるのではなく音楽の建付けの上手さで聴かせる。 彼が言いたかったのはそういうことだったんじゃないだろうか。
"Embraceable You" ではデューク・ジョーダンが弾いたイントロのフレーズを踏襲していて、先人への敬意も忘れない。 ジョーダンとはまた一味違った
淡い情感で原曲の世界を描いていく。 パリで開かれる国際ジャズフェスティバルへ出演するために取ったパスポートをに因んで、"I Got Rhythm" の
コード進行を使って作った曲 "Passport" なんかも取り上げていて、マニアを喜ばせる選曲が嬉しい。 自作のブルースもいい塩梅で配置されていて、
捨て曲なしの内容が素晴らしい。
50年代に作られたピアノ・トリオのアルバムとしては、これは別格に好きだ。 このアルバムに漂う独特の風格は他の何にも代えがたいものがある。
その後リヴァーサイドと契約してたくさんのリーダー作を出せるようになったのは良かったと思うけれど、それらはどれもバリー・ハリスらしさは
希薄なような気がする。 バリー・ハリスらしい重いタッチでゆったりと歩を進めるこのデビュー作こそが、彼がジャズ界を渡り歩く際のパスポート
となったのはおそらく間違いない。 アーゴは地味なレーベルにも関わらず、そのアーティストの最良の姿を捉えることができた不思議な力があった。
地方都市に根を下ろすアーティストを大事にするというレーベルポリシーがその力を産み出していたのかもしれない。