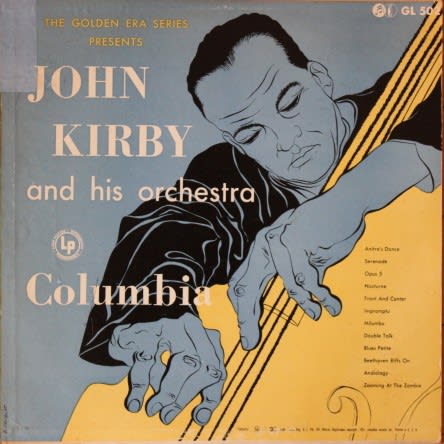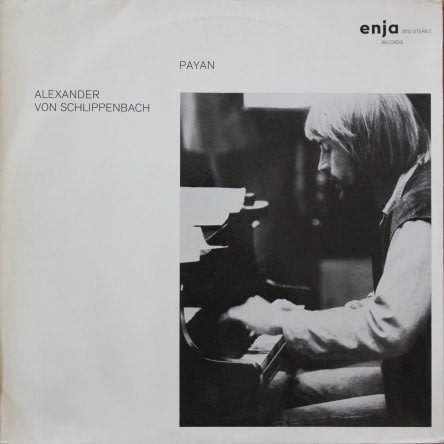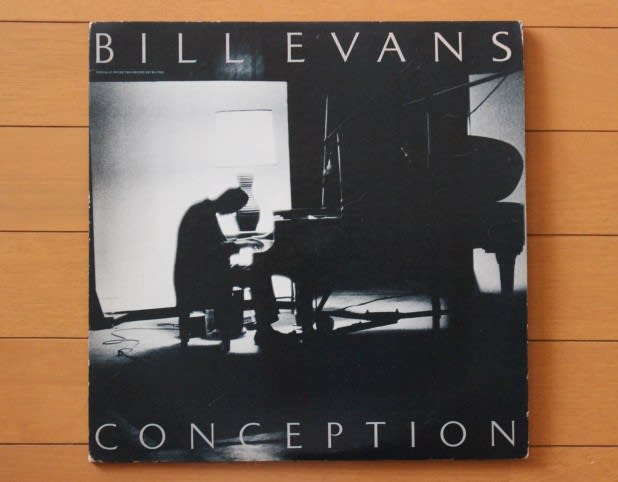Andrew Hill / Hommage, Nefertiti ( 日本 East Wind EW-8017, EW-8032 )
私に音楽の素晴らしさや猟盤の楽しさを教えてくれる数少ないブログの1つ、
Kanazawa Jazz Days のkenさんに教えていただいた、アンドリュー・ヒルの日本録音。
不遇に喘いでいた彼を日本の評論家とレコード会社が救い出した、実に素晴らしい作品たち。 70年代前半はまだ音楽を聴くような年齢ではなかったので、
この時期に作られた作品群は私にとっては未だに未知なる暗黒大陸であり、未聴の作品がたくさん残っている。 だからこうして小さな手がかりを辿りながら
猟盤する愉しさには格別なものがある。 週末の金曜日、DUに立ち寄るとまるで待ち構えていたかのように在庫があって、2枚ともワンコインだった。
アンドリュー・ヒルと言えば当然ブルーノートということで私も時々聴くけれど、それ以上この人を追いかけるようなことはなかった。 ブルーノートの諸作は
評論家には高く評価されてきたけれど、一般的には敬遠されることのほうが当然多い。 アルフレッド・ライオンは人気が出なかったことをとても残念がった
けれど、今振り返ってみるとこれは仕方がないんじゃないだろうか。 この人は元々は普通に主流派のジャズを演奏していたのに、ブルーノートに来た途端に
尖った音楽を始めて、その跳躍の大きさにはちょっと違和感がある。 "Black Fire" も "Point Of Departure" も嫌いではないんだけれど、やっぱり
ちょっと唐突過ぎる感じはするし、この人の内側から自然に湧き出てきたものというよりは先頭集団から遅れないように自分のペースを無視して走っている
ランナーを見ているような感じがする。 彼が当時広く支持されることがなかったのは、聴き手にそういう危なっかしさが伝わったからなんじゃないだろうか。
当時録音されたLP20枚分もの演奏の多くが未発表のままお蔵入りになり、表舞台からは消えざるを得なくなった不遇の時代、スイングジャーナルの編集長が
現地で彼に会い、その演奏を聴いて感銘を受けて日本のレコード会社に録音を勧めた。 その第1弾が "Hommage" というソロ演奏集になる。
針を落として音楽が鳴り始めた途端に、その魅力に憑りつかれた。 ピアノの音や打鍵のタッチの質感はデューク・エリントンを思わせるところがある。
硬質で重みがあり、数珠の紐が切れてテーブルの上で跳ねて飛び散るブラック・パールのように予測不能な軌道を描く。 でも、イメージしがちな難解さは
どこにもなく、こんなにわかりやすいピアノを弾く人なんだっけ?といい意味で予想を裏切られる。
壁1枚隔てた隣の部屋から聴こえてくるような共感し辛いかつての音楽の面影はどこにもなく、素のピアノ弾きの飾らない姿がある。 "Naked Spirit" なんて
まるでチャイコフスキーが描きそうな曲で、彼の "四季" の中に組み込まれていてもおかしくない。 そういうピアノ音楽の雫がボロボロと滴り落ちてくるような
感じなのだ。 だから、最後まで感激しながら聴き終えることができる。
それに何より、このレコードは音がいい。 ピアノの音の艶やかさと残響感がとても自然で、まさしくピアノ・ブラックと言いたくなるような色彩だ。
正直言って、初めて聴くピアノのレコードでここまで心の奥底深くまで届いてきたのは、ちょっと久しぶりだった。
もう1枚の "Nefertiti" はトリオによる演奏で、こちらも同じように音のいいレコード。 こちらはかなり印象派的な作品で、旋律で音楽を構成する
ことをせず、微かに残っている記憶を頼りに音を探りながら鳴らしていき、ディレイ気味に遅れて後追いで和声が構成されていくような音楽だ。
でも、リチャード・デイヴィスのアルコが印象的な曲があったり、と単調さはなく、どこかで聴いたことがあるような退屈さもなく、とても高度で深みのある
作品になっている。
金言に導かれて、アンドリュー・ヒルという音楽家のことを完全に見くびっていたことを思い知らされた週末になった。