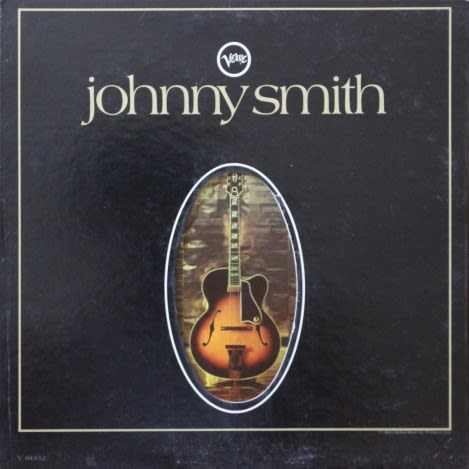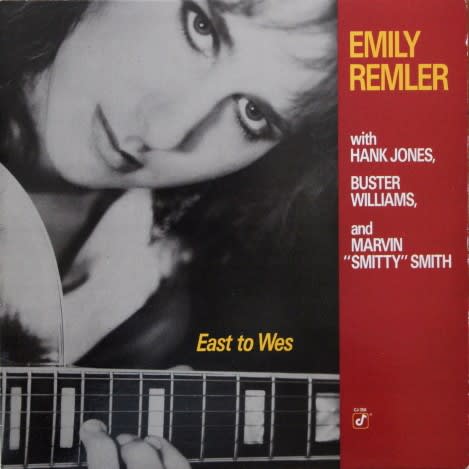Tommy Flanagan / Plays The Music Of Harold Arlen ( 米 Inner City Records IC 1071 )
安レコ漁りをしていると見たことのない、あるいは聴いたことのないレコードに出くわすことが多い。 だからこそ面白いのだが、それらの中には
初版も再発も無造作にミックスされていて、これはこれで目利きが必要になる。 このレコードは初めて見たもので、内容的には如何にも日本人好み
だなあと思って家に帰って調べてみると、オリジナルは日本のトリオ・レコードだった。 私はトミー・フラナガンにはあまり興味がなく、
作品の知識がほとんどない。
これはトリオ盤がリリースされた翌年にアメリカで出たものだが、ジャケットはこちらのほうがいい。 それにトリオ盤は聴いたことはないけれど、
このインナー・シティ盤はとても音がいい。
全編スタンダードで、どの曲も短めで品よくまとめている。 "Eclypso" のような硬質な作品も作れば、こういう売れ線もきちんとこなす。
上手いもんだなあ、と感心してしまう。 ハロルド・アーレンというシブい作曲家を取り上げるところはトリオ・レコードのセンスなんだろう。
よく出来ている。
注目は最後に収められたヘレン・メリルが歌う "Last Night When We Were Young" 。 彼女に1曲だけ歌わせる、という物足りなさの演出も
あざといくらい効いている。 さすがの素晴らしい歌で、この1曲のためだけに買う人も多いのだろう。
すべてが計算された、これはプロデューサーの技が光る1枚。