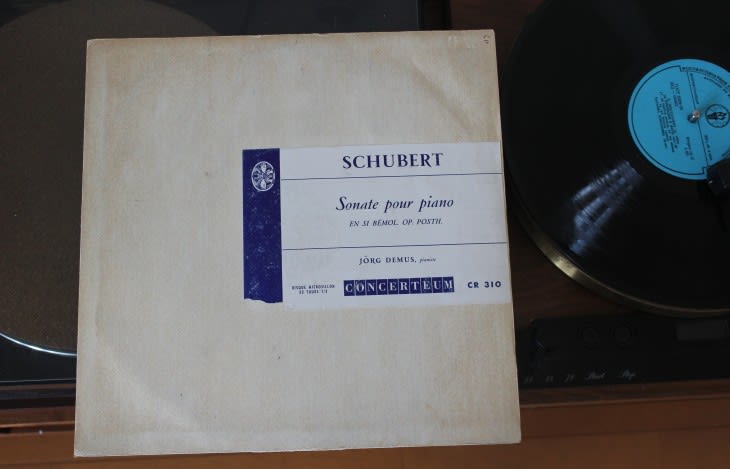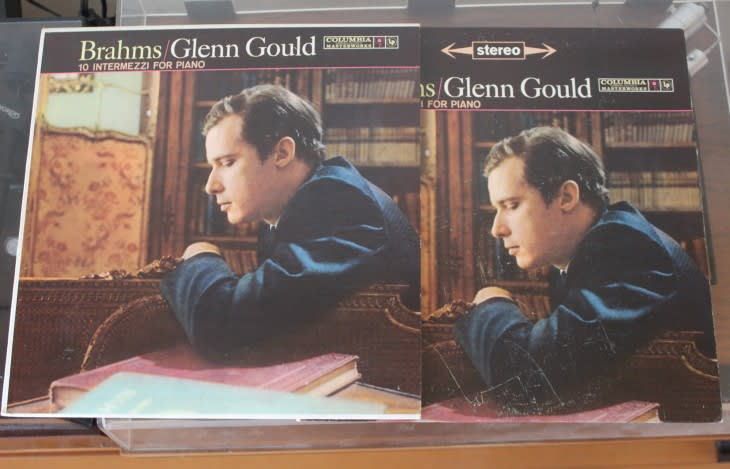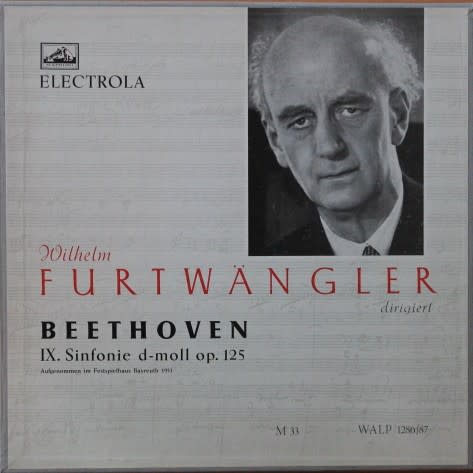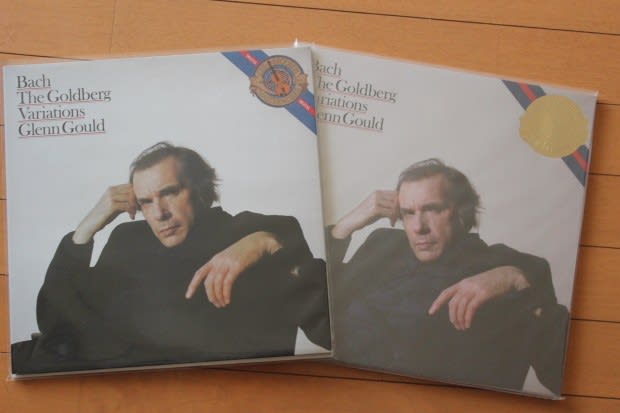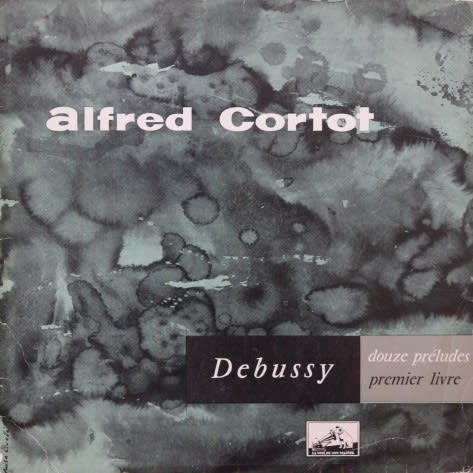Bolishoi Theatre Quartet / Reinhold Moritzevich Gliere String Quartet No.1, 2 ( 露 Melodiya M10-39653 )
ウクライナはリトアニア、ベラルーシと共に地理的にはロシアと東欧の間にあり、元々立ち位置としては微妙なところにあるせいで、
昔から正反対の価値観の狭間で揺れ動く定めにあった。こういう所で生きていくのは本当に大変だろうと思う。先週からこの週末にかけて
ロシアのウクライナ侵攻のニュースを見聞きしているせいで、この地域とジャズという音楽が結びつかず、レコードを聴く気分になれない。
TVニュースに出てくる専門家やネットに記事をまき散らす識者らの解説にどれだけ触れてもことの真相はまったくわからないし、
プーチンの気持ちもまったく理解できない。核とか第3次大戦という言葉を不用意に使う無神経さが不快だし、長い歴史の時間の中での
いざこざの結果としての出来事である以上、昨日今日の付け焼き刃的知識でどうにかなるような話でもないことから自身の無力さを
身に染みて感じて、出かけても気分は一向に晴れない。
ただ、それでもウクライナという国のことを理解しようと思い、この国と音楽はどういう関係なのかと調べてみると、グリエールが
ウクライナの出身だということが遅まきながらわかった。グリエールなら持っているはず、とメロディアのレコード群を探してみると
1枚出てきたので、この週末はウクライナのことを考えながらこればかり聴いていた。
ボリショイ劇場弦楽四重奏団が演奏する弦楽四重奏曲の第1番と2番。グリエールは室内楽もたくさん手掛けたが、実際にそれらを聴ける
レコードは少なく、これは貴重な記録である。グリエールは他の作曲家たちとは違って国外へ逃げることを良しとせず、ロシア革命の時代を
生き抜いた人だからその音楽遍歴は一筋縄ではいかないけれど、残した弦楽四重奏曲はベートーヴェンやロマン派の影響を強く受けた内容で
聴き易い。ボリショイ劇場管弦楽団のメンバーで結成されたこのカルテットもレコードが多くなく、こうして聴けること自体が貴重だ。
そういう奇跡的邂逅としての記録が残っていること自体が驚きだし、国営レーベルであるメロディアがグリエールのレコードを作っていた
ことを考えると、現在のこの状況がより嘆かわしく感じられてくる。