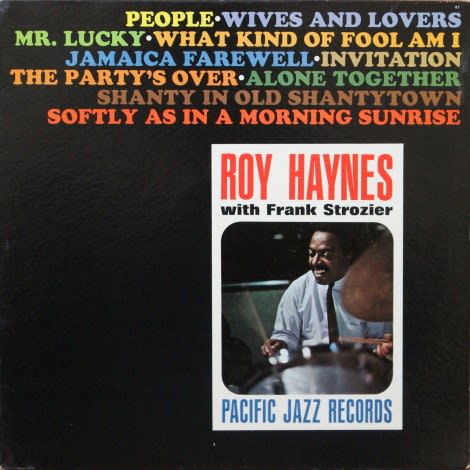Gerry Mulligan / Gerry Mulligan Quartet ( 米 Pacific Jazz PJLP-1 )
ジェリー・マリガンと言えばパシフィック・ジャズのアルバムイメージが強烈で、ウェストコースト・ジャズの中心人物だったかのような印象があるけれど、実際は違う。
彼はニューヨーク生まれで25歳まで東海岸で活動していた。 ギル・エヴァンスに編曲を学び、クロード・ソーンヒル楽団にスコアを提供するなどビッグ・バンドの
仕事が多く、その縁で映画音楽の仕事の声がかかり、1952年にロスへ行くが、1956年には東海岸に戻っている。 つまり、西海岸にはたった4年しかいなかった。
ロスで映画音楽の仕事をしながら夜はクラブでスモール・コンボの演奏をしていて、そこでまだ学生だったリチャード・ボックと出逢い、このレコード他に収められた
楽曲を録音して78rpmのSPと33rpmの10インチLPの2形態で発売したら "Bernie's Tune" がヒット、あっという間に人気グループになるが、麻薬の不法所持で
マリガンは逮捕され、バンドは1年もたたないうちに解散するという、まるでジェットコースターに乗ったかのような西海岸滞在だった。
音楽上の人格形成の若い時期にギル・エヴァンスの下にいたことがその後の彼の音楽観を決定付けていて、このピアノレス・カルテットも隙間の多いアレンジを
少ない楽器でスピード感を持たせて処理したことで成功している。 ウェストコースト・ジャズはこのレコードが生まれたことで本格的に立ち上がっていくけれど、
マリガンがここで演奏した音楽の礎になっているのはギル・エヴァンスの音楽観であり、その最初のダウンサイジング版だったマイルスの"クールの誕生"だった。
つまり、当時の西海岸に "ウエストコースト・ジャズ" を産み落としたのは、ギル・エヴァンスとその使徒であった2人の東海岸の若者だったということだ。
この10インチはこのレーベル・イメージである乾いた軽いサウンドとは違い、残響が効き冷気漂う奥行きを持った立体感のある音場感で再生される。
そのせいもあって、この後に展開される西海岸のジャズのイメージとは少し印象が異なる音楽になっている。 このピアノレス・カルテットはアレンジを
取り入れてはいても、演奏の主軸は各楽器のアドリブラインだ。 その手際よく整理されたアレンジとアドリブのコラージュを正しく継承した演奏家は
その後のこのレーベルの中では、チェット・ベイカーのグループを覗けば、結局のところ現れなかったように思う。