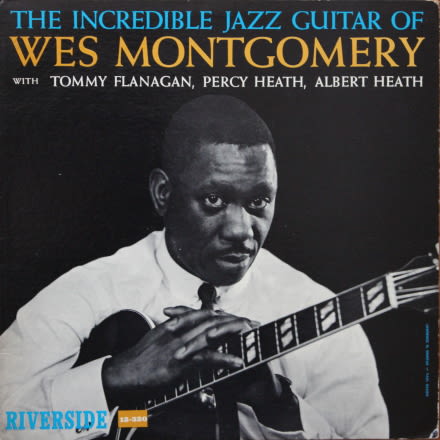Ornette Coleman / Paris Concert ( 日 Trio Records PA-7169,70 )
1971年の夏にパリで行われたコンサートの実況録音のテープを日本のトリオレコードがオーネット本人と販売契約を結んでリリースしたもので、
これがオリジナル。 当時のトリオレコードはこういう自社オリジナル作品を作ることに熱心で、例えばゲルハルト・ヘッツェルらウィーン・
フィルのメンバーを日本に招聘して室内楽の傑作を作るなど、重要な仕事をしていました。
2枚組のダブルジャケットは綺麗なコーティングが施されいてとてもコストをかけた質感の高い仕上がりで、エサ箱の中でもひときわ目立っていた
ので手に入れて聴いてみたのですが、これがあまりに素晴らしい内容で、びっくり。 元々トリオレコードが発売交渉をしていたのは別の演奏テープ
だったのに、発売直前になってオーネットが別の演奏テープを差し替えてこのレコードは作られており、本人としてはこちらの演奏のほうが
好きだったのでしょう。これは正しい選択だったと思います。
ヘイデン、ブラックウェルら常設メンバーにデューイ・レッドマンを加えたカルテットですが、オーネットらしい非常にしなやかで色香漂う演奏。
ライヴでこんな雰囲気を出せるということが驚異的。 多忙な時期の中で行った渡欧演奏だったので特に凝ったことは何もしておらず、普段着の
ままの演奏ですが、これが成熟した大人の音楽になっていて、聴いていた観客が演奏が終わるごとに溜め息を漏らしながら湧き上がるように拍手を
している様子が実に生々しく、その感動がリアルに伝わってきます。
この演奏旅行の後にCBSと契約を結んで傑作 "サイエンス・フィクション" を録音するわけで、その創作活動は充実していたようです。
デビュー当時から順番に聴いていくとその音楽はいろいろ変化しているのがわかりますが、その中で一貫して変わらないのが独特な質感の
"しなやかさ"。 だから、基本的にどの時期のレコードを聴いても大丈夫だし、長い活動の中で何度もピーク期を持っていますが、特にこの
70年代前半の演奏には強く惹かれるものを感じます。このアルバムが日本オリジナルということは誇らしい。 もっと評価されて然るべき。