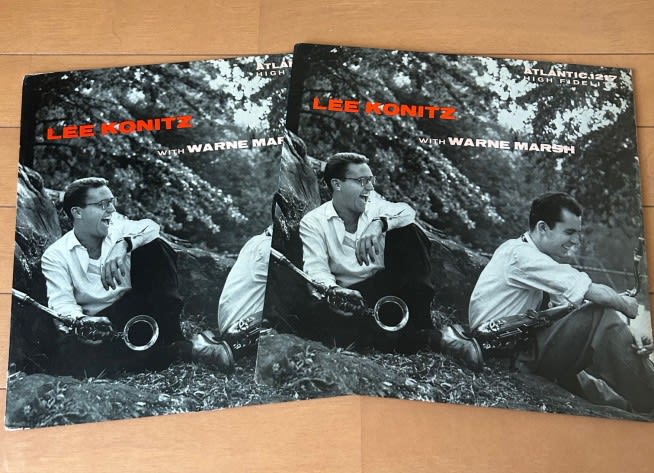Stan Getz, Gerry Mulligan, Harry Edison, Louis Bellson and The Oscar Peterson Trio / Jazz Giants '58 ( 米 Verve MG V-8248 )
ノーマン・グランツの巨匠趣味には困ったものである。ビッグ・バンドが華やかだった時代のスター・プレーヤーたちをメインに置いた彼のレコード
制作のポリシーは徹底していたし、その精力振りは驚異的だった。パーカーやパウエル、ビリー・ホリデイやスタン・ゲッツのレコードがたくさん
残ったのはよかったが、オスカー・ピーターソンやJ.A.T.P.のレコードが大量生産されたのはちょっとなあ、と思う。ピーターソンに全く興味のない
私からすればそれらは(申し訳ないけれど)無用の長物の山に過ぎず、見ていてうんざりさせられる。
彼は人種差別を受けていた非白人たちを支援するために "Jazz At The Philharmonic" と銘打った大きな劇場に観客を大勢集めてジャズを聴かせる
一大イベントを打ち上げて成功を収めた大興行主だったわけだけど、それと並行して大して儲からないレコード事業も行っていた。J.A.T.P.は資金
集めが目的だったから出演者は集客力のあるビッグ・ネームが集められ、そういうメンバーたちのレコードを熱心に作った。そこにはグランツの
趣味が色濃く反映されていて、そういう意味では彼の作ったレコードはどれも趣味性が高く、レコードとしての品質が高かったのは間違いない。
ただ、それらはニューヨークを中心にした東海岸の研ぎ澄まされた先鋭さとは別世界の、ある意味では弛緩した音楽だった。盛りの過ぎた大物
ミュージシャンをスタジオに集めてジャム・セッションをさせたが、そこには新しい音楽への志向はなく、よく言えば成熟した、裏を返せば退屈な
音楽の大量生産だった。それらはクラブなどでその場だけのものとして聴く分にはゴージャスで楽しかっただろうが、じゃあレコードとして家で
繰り返し聴いて楽しいかというと、残念ながらなかなかそうはいかない。買って帰って、盤質チェックを兼ねて1回通して聴いてみて、あとは
棚の肥やしとして場所だけとってしまう存在となりがちなんじゃないだろうか。
そんなわけで私はこのレーベルの初期のものは特定のアーティストしか聴かないし、大物を寄せ集めした企画ものはまったく聴かないのだけれど、
例外的にこのアルバムは中々出来がいいと思っている。やはりスタン・ゲッツの存在が大きく、彼が良かった頃の演奏が中心的存在となっている
ところが、このアルバムを他のアルバム群と一線を画す要素となっている。ゲッツがいるとやはり音楽はモダン寄りの感覚に近づくようになり、
退屈さから紙一重でうまく回避できているように思う。