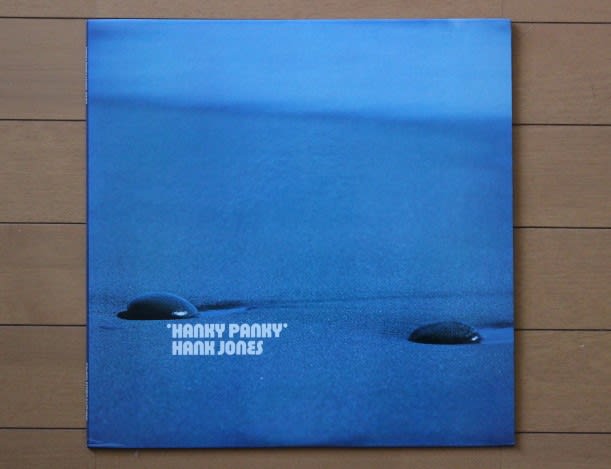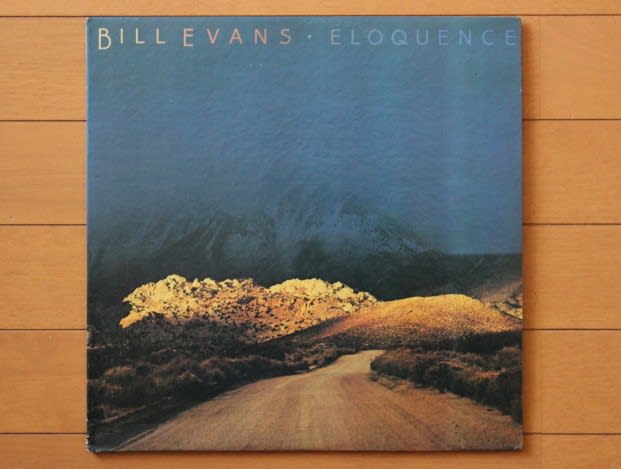Buddy Rich / Big Swing Face ( 米 Pacific Jazz PJ-10117 )
何と言う切れ味の良さ、ドライヴ感。 シャープで一糸乱れない管楽器群はケニー・クラークとフランシー・ボランのビッグバンドそっくりで、少し翳りが
あるところなんかもよく似ている。 ただ勢いよくて迫力があるというだけではなく、憂いのある表情も併せ持っていて、深みのある音楽であることが
すぐにわかる。 だからこそ、多くの称賛を集めたのだろう。 イェーイ、ノリノリだぜー、というようなアタマの弱いアホな話ではない。
バディー・リッチのこのバンドでの鬼教官ぶりは有名だけど、これだけ大勢の人を自分の思うように統率するにはそうせざるを得なかったんだろう。
TVで中学・高校の軽音楽部の奮闘物語なんかをよくやっているけど、そのノリはどう見ても体育会系のそれだし、汗と涙の根性物語になっている。
経験者によるとそれは一種異様な世界らしいけど、それでもそういうものに支えられていたのであろうことは容易に想像できる。
スイング・ジャズを大胆に発展させたモダン・ビッグ・バンドの音楽にはポピュラー音楽の要素がかなりたくさん取り込まれているので、実際はかなり汎用的な
内容で聴きやすい。 スイング・ジャズは見かけは単純で陽気な音楽に見えるけど、実はかなり純度の高いジャズ・ミュージックで専門性も高く、聴く人を
選ぶようなところがあるけど、モダン・ビッグ・バンドはそういうスイング・ジャズが持っていたある種の排他性みたいなものを取っ払ったわかりやすい音楽だ。
だから、もっと広く聴かれてしかるべきだと思う。 更にポピュラリティーだけではなく、楽器の数が多い分、複雑な味を愉しめる高級さもあるのだ。
このアルバムはライヴ演奏ならではの生き生きとした表情が素晴らしいけど、それ以上に収録された曲にいい曲が含まれているのが最大の魅力。
何と言っても、ボブ・フローレンスの "Willowcrest" に止めを刺すけど、リッチの娘が歌う "The Beat Goes On" もキャンディー・ポップを本格的な
ジャズに仕立てあげていて、1度聴くと忘れられない。 愉しいエンターテイメント性と極めて高度な音楽性が同居する画期的な仕上がりになっている。