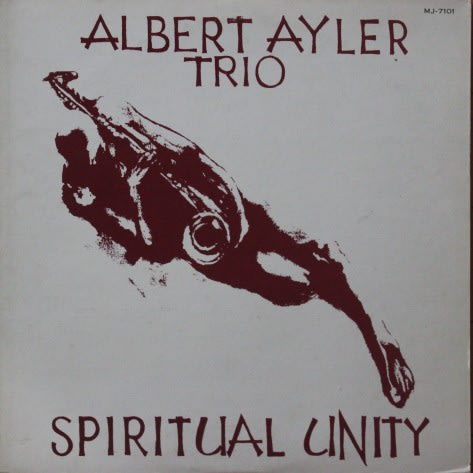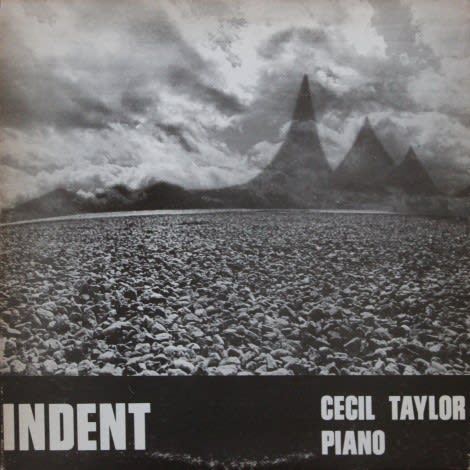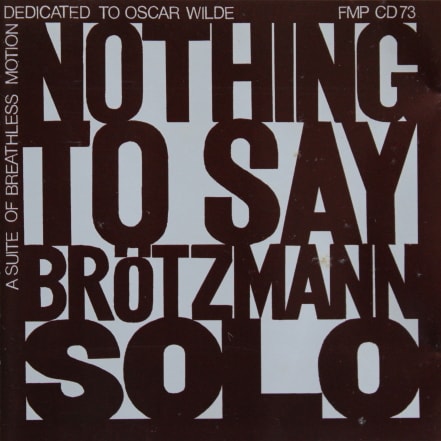トリオ 深海ノ窓 / 目ヲ閉ジテ 見ル映画 Blind Cinema 吉田野乃子 / Lotus
遅ればせながら、吉田野乃子さんの作品を聴くことができた。 心ある愛好家から静かに支持される、アヴァンギャルドなサックス奏者/作曲家である。
2006年から2015年までニューヨークで単身修行し、帰国後は北海道岩見沢を拠点に活動しているということで、まだまだ彼女についての情報は少ない。
先日30歳になったばかりの若さで、これからキャリアを積み上げていく人だから、そういう意味では同時代的に見守っていくことができる愉しみがある。
評判のいい "目ヲ閉ジテ 見ル映画" はピアノ、ベース、サックスのトリオ形式だが、硬質な抒情に貫かれた素晴らしい作品だ。 こういう言い方は不本意かも
しれないけど、ピアノが奏でる主旋律たちはまるで "風の谷のナウシカ" の中で流れていてもおかしくないような寂しげな美メロで、風景や映像を意識した
音楽になっているのはアルバムタイトルが示す通りだ。 そういう風景の中にそっと忍び込むようにサックスの旋律が鳴り始め、やがて高ぶった感情が
溢れ出るように激しい咆哮へと姿を変えていく。 そういう情感の生々しさが美しいヴィークルの上で移ろうように流れていき、これは心に深い印象を残す。
この音楽は作り物じゃなく、生きているなあ、というのが素直に感じられる。
"Lotus" はサックス1本だけで臨んだ本気度満点の作品で、無伴奏ソロだったり、オヴァーダブで複雑に編み込まれていたり、という渾身の1枚。
鳴っている音には只ならぬ強い想いが込められていて、生半可な気持ちで近づくと触れた途端にあっという間に弾き飛ばされてしまいそうな張りがある。
それはまるで、"ウォール・オブ・サクソフォン" だ。 ただ、それは例えばブロッツマンのような巨大な音の塊というのではなく、1曲1曲にその成り立ちの
ストーリーがあり、それが楽曲の中に埋め込まれている。 感情だけに任せた音楽ではない。 そこがかつての「日本のフリー・ジャズ」とは決定的に違う。
どちらかと言えば、この作品のほうが彼女の本音に近いんじゃないだろうか。
彼女のサックスの音色は重く硬質で少し濁りがある。 この「濁り」がとてもいい。 この音が聴きたい、と思わせる何かがある。
まあ、褒めてばかりじゃ何だから少し違うことも書いておくと、所々で硬さを感じるところがあると思う。 何というか、それは身体的な硬さのようなもので、
それが音楽を縛っているようなところがあるのを感じる瞬間があった。 これは時間が解決するのかもしれないけれど、これがほぐれた時にはどんな音楽が
出てくるのかなあと思ったりもする。
この時代に、しかも日本で、こういう音楽をやっていくことの困難さについては私の想像を絶するものがある。 彼女はこの難問をどう解決していくのだろう。
それをこれからも見守っていきたいと思った。 東京でライヴをやる時は観に行きたい。
今のところ、これらの作品を含めて、彼女のアルバムは自主製作でご本人に直接コンタクトして入手するしか手がない。 送られてきたCDには、手書きで
彼女のメッセージが書かれた小さなメモと、"Lotus" に関する彼女が書いた解説書が同封されていた。 それらを読みながら、アーティスト本人がこういうことを
しなければいけない音楽界の現状を恨めしく思った。 日本の資本はどうして志のある若い芸術家に手を差し伸べようとしないのだろう、というこれまで何度も
口にしたボヤキが、ここでもまた口をついて出てしまう。 尤も、「野乃屋レコーズ」という屋号は秀逸だけどね。