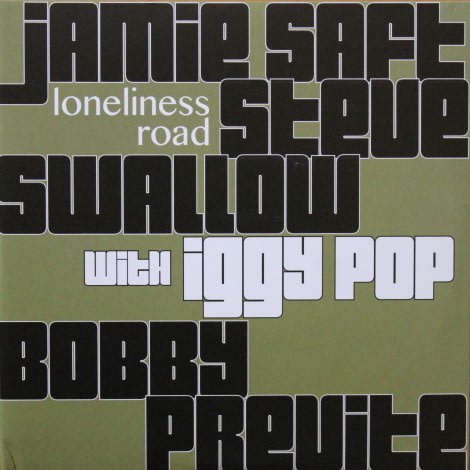Duke Ellington and his Orchestra ( 米 Columbia CL 1907 )
エリントン楽団がコロンビアからリプリーズに移籍する直前の1962年に録音、リリースされた。 タイトル通り、パリの夜の印象(エリントンがパリの夜を
どう過ごしたのかはよくわからないけれど)をテーマにした建付けになっているけど、まあ、あまりそういう雰囲気はこちらには伝わってこないように思う。
実際はニューヨーク録音だったそうだから、そういうことも影響しているのかもしれない。
コロンビア・LP時代のエリントンは硬派なファンやタカ派の評論家からはあまり評判がよくないらしい。 つまり、ポピュラー音楽寄りになり過ぎて、よくできた
演奏だが「本筋ではない(far from essential)」、と言われたりする。 まあ、そう言われればそうかもしれない。 原理主義的視線からはこういうのは
大衆に迎合した堕落に見えたりするのかもしれない。
でも、私はコロンビア時代のエリントンが好きだ。 このレコードはテオ・マセロがプロデュースしていて、片面に6~7曲を詰め込んでいる。 どの曲も2~4分と
短く刈り込んであり、曲調は明るく朗らかで屈託がない感じだ。 フランス人が作った曲やタイトルにパリという言葉が入っている曲を集めて、それらを
とても歯切れ良く、テンポ良く処理している。 かつては時々顔を出していた難解さのようなものは封印され、ここでは微塵もない。
でも、コロンビアのレコードはそういう一般大衆が聴いて楽しいようなものだけではなかった。 組曲形式の大作もあれば、歌手を招いて器楽的に歌わせたり、
特定の楽器にスポットを当てた演出をしたり、といろんな音楽上の試みをやってのけている。 それらの中には、意外に難解な音楽をやっているレコードも
ちゃんとあるし、最高のスタンダードを演ったものもある。 至る所で俗っぽいエリントンとサー・デュークが奇妙に同居していて、コロンビア時代の音楽は
彼の複雑な魅力に満ち溢れているのだ。
それにコロンビアは彼のレコードをとても丁寧に作った。 これもとても音質がいいレコードで、エリントンサウンドの魅力が十分に伝わってくる。