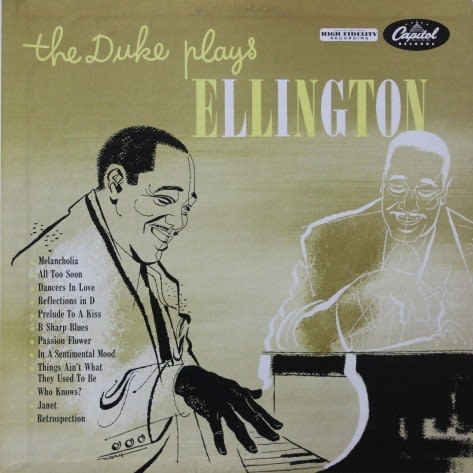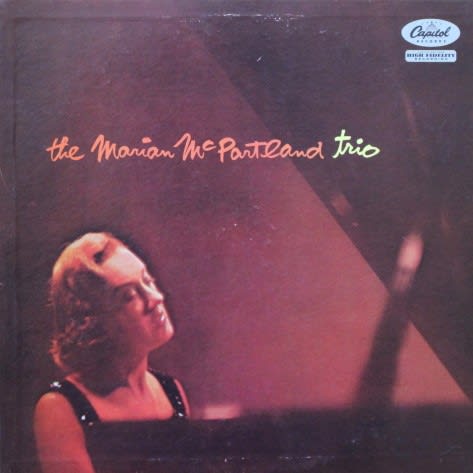Serge Chaloff / Blue Srege ( 米 Capitol Records T-742 )
1957年脊椎の癌で33歳という若さで亡くなったサージ・チャロフの記録は少なく、一番この人の実像がわかりやすく聴けるのが死の前年に
録音したこのアルバム。当然、この時点で既に身体は癌に蝕まれていただろうし、それ以前に最後には克服したとは言え、元々が重度の
へロイン中毒だったこともあり、身も心もボロボロだったはず。そんな彼の辞世の句がここには刻まれている。
バリトンを太い音で鳴らすのではなく、強弱の陰影をつけて吹くやり方はアート・ペッパーに似ており、バリトン界では他にはあまり例がない
吹き方だったように思う。バリトンという楽器にとってそれが効果的な吹き方だったのかどうかはよくわからないけれど、際立った個性では
あったと思う。ウディ・ハーマンの "フォー・ブラザーズ" としての名声がありながらも、その記録が十分に残らなかったのは残念だ。
スタンダードがメインのプログラムで、ワンホーンで緩急を付けた演奏はうまく纏まっており、よく出来ている。全体的にゆったりとした
恰幅のいい音楽で、なんともわかりやすい。昔はつまらない音楽だなと思っていたけど、こちらが枯れてくるとこのくらいがちょうどいいかも
と感じるようになってくる。聴く側の年齢によって、音楽の感じ方も変化してくる。
翌年には満を持してニューヨークへ移住するソニー・クラークもその個性が完成しており、いかにもソニー・クラークという演奏を聴かせる。
フィリー・ジョーとヴィネガーのリズム隊も盤石で、このトリオのおかげで音楽が筋の通ったものになっているのは明白。
ただ、クラークもフィリー・ジョーも重度のジャンキーで、このアルバムはそういう人たちによって作られているせいか、その音楽にはどこか
虚ろで物悲しい雰囲気が全編に漂っている。ジャズは50年代がピークだったけれど、薬物中毒と黒人差別という宿痾のせいで実際にアメリカで
活動していたジャズメンたちの演奏の多くがレコードとしては残されなかったのだろうと思う。そういう風にレコードとして残ったものは
実はほんの一握りのものだったということを考えると、ジャズとは失われた音楽だったのだと定義できるのかもしれないなと思う。