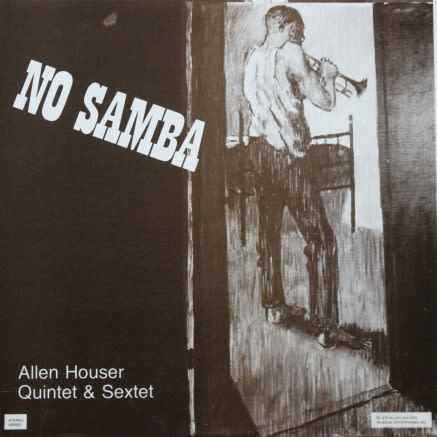Chet Baker Sings ( Brazil Hi-Fi Jazz 101 )
Pacific Jazz から出された "Chet Baker Sings" はこのレーベルとしてはよく売れたようで、World Pacificへ改名した後も同じジャケットデザインで
プレスされています。
ただ、Pacific Jazzレーベルのオリジナル盤であってもこのレコードはお世辞にもあまり音がいいとは言えず、そのことはレーベル側もどうやら自覚して
いたようで、ほどなくして疑似ステレオ盤が発売されます。 これが愛好家には評判が悪いようで、ジョー・パスのギターがオーヴァーダビングされて
いたり、1曲差し替えられていたり、左右のチャンネルに無理矢理楽器が片寄せされていたり、風呂場のような悪趣味なエコー処理が施されていたり、
ジャケットが酷いデザインへ変更になっていたり、と散々な言われようです。 やる気のないマニアの私はこの改悪ステレオ盤を聴いたことがないので
実際のところはどうなのかわからないのですが、意匠の素晴らしさでは他を大きく引き離していたこのレーベルもサウンド作りの面では弱点を抱えていた
のは間違いなさそうです。
初版のジャケットの裏面を見ると、ハイファイレコーディングであることやウェスタン・エレクトリック社の640AAというコンデンサーを使ってカスタマイズ
されたマイクをつかって録音されたことがわざわざ書かれているところから、レーベルとしては自信があった様子が伺えます。 私はオーディオ方面は
疎いので、ウェスタン・エレクトリックの名前くらいは知ってはいるものの、この機材がどのくらい優れたものなのかはよくわかりません。
はあ、そうなんですか・・・、という感じです。
別に庇うわけではありませんが、音がよくないとは言っても、聴いていて不快に感じるようなことはありません。 Pacific Jazzレーベルのマスタリングは
チェットの声を一番前面に出して、伴奏の楽器群をわざと後退させるようにしているので、楽器音の分離が悪く聴こえるし音圧も当然低いので音がよくない
という印象になってしまうのでしょう。 ヴォーカル作品なのでこういう建付けにするのは当然と言えば当然で、意志のある音作りです。
ただ、このブラジル盤を聴いてみると、疑似ステレオなんかにするくらいだったらこういうやり方もあったんじゃないのかな、と思います。
こちらの音は原盤のような奥行き感の演出こそありませんが、チェットの声や各楽器の音が薄皮を1枚剥がしたような明瞭になっていて、各楽器の
音の分離もよく、さらに音が消えていく際の自然な残響もきちんと生きています。
こちらもジャケット裏面にテクニカルデータに関するうんちくが書いてあり、Jorge Coutinho なるサウンドエンジニアがテレフンケンとアルテックの
コンデンサーを使っていることやらなんやらをポルトガル語で長々と書いてあって、オーディオへの無知に語学力の無さも加わって更に何のことやら
さっぱりわかりませんが、とにかく音質にはこだわってますよということが言いたいらしい。
でも、機材はもちろん大事なんでしょうが、マスタリングというのは本質的には人間がやる作業なんだから、エンジニアの音への見識や感性のほうが
遥かに大事なんじゃないんでしょうか。 World Pacific社もエンジニアを変えるなり、外部の著名なスタジオに委託するなり、もっと他にやり方が
あっただろうに、と思います。 評判のよくないステレオ盤も機会があれば聴いてみたいですが、縁がないのか、そちらはそちらでもしかしたら
稀少なのかよくわかりませんが、今のところ出会いがありません。