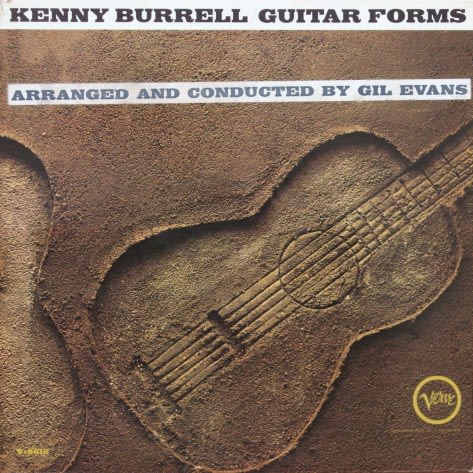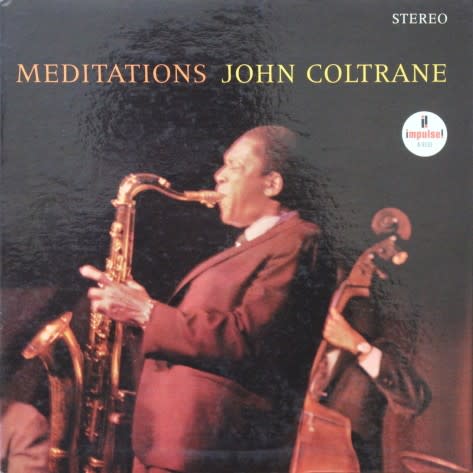Enrico Pieranunzi / Space Jazz Trio Vol.1 ( 独 YVP Music 3007 )
私がピエラヌンツィを知ったのは1996年に "The Night Gone By" が発売された時で、ちょうどその頃ティエリー・ラングにハマっていた
こともあって、同じ系統のピアノ・トリオということでずいぶん熱心に聴いた。当然の流れでユニオンのCDフロアに行って、他の作品も
あれこれ買い込んで聴いた訳だが、その時にこのスペース・ジャズ・トリオ関連のものがシリーズとして数巻並んでいた。
純粋なトリオ形式のものとしてかなり期待して聴いたのだけど、これらのCDの音が悪く(楽器の音がくすんでいて分離が悪く、デッドな音場)、
音楽の良さがまったく感じられなくて非常に落胆した。
そういうこともあって長い間このトリオのことは忘却の彼方へと消えていたんだけれど、当初はアナログも出ていたということを知って、
聴いてみるとこれがまるで別の作品のような音の良さで、ようやく溜飲を下げることができた。
この第1集は1986年のリリースで、制作にあたっては当然キースのスタンダーズのことが念頭にあっただろう。スタンダーズは世界のジャズの
潮流を大きく変えたグループだったため、欧州を中心にして雨後の筍のように同様のピアノ・トリオが生まれたわけだが、このトリオは
おそらくは差別化を図るためにスタンダードは演奏せず、オリジナル曲だけでアルバムを構成した。そして、スタンダードを演奏しなくても
同様の感銘を与えることができることをきちんと証明した。
硬質なダンディズムに溢れ、高度な音楽的コントロールがよく効いた素晴らしい演奏で、耽美的でロマンティシズムを信条とする
他のトリオ群から大きく距離をとった音楽が素晴らしい。禁欲的でありながらわかりやすく、耳に残るメロディーが散りばめられている。
スタンダーズの物真似はできても、このトリオへの追従は難しいだろう。