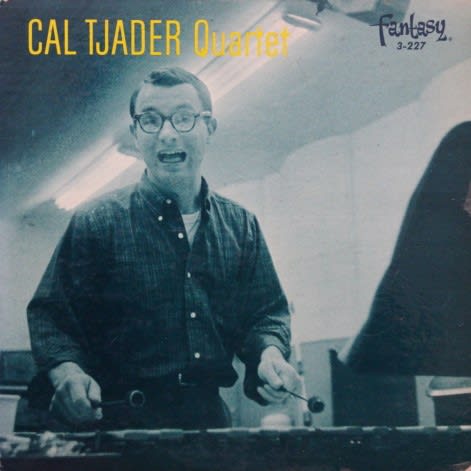ベニー・ゴルソンのブルーノート東京公演を観てきた。 6月29日(土)の1stセットで、17:00開演で1時間20分ほどの公演だった。 本当は金曜の夜の
公演に行くつもりだったが、老眼のせいでスマホ操作を誤ってしまったのだ。 金曜の夜には渡辺貞夫が観に来ていたようなので、惜しいことをした。


セットリストはこんな感じ。 それまでの公演よりも1曲少ないのは最終日でお疲れだったせいかもしれない。
1. Horizon Ahead ■メンバー
2. Whisper Not ベニー・ゴルソン(ts)
3. Tiny Capers マイク・ルドーン(p)
4. I Remember Clifford バスター・ウイリアムス(b)
5. Alone Together (ピアノ・トリオによる演奏) カール・アレン(ds)
6. Now's The Time (クロージング・テーマ)
今回はいい席が取れて、ステージど真ん中の正面に正対するシートだった。

17:00ピッタリに照明が落ちて、メンバーたちが客席の間を縫って登場。 こんな時間通りに始まるなんて、外タレの大物では珍しい。
黄金に輝くテナーを持ったゴルソンがスタッフに囲まれてゆっくりゆっくり歩いていく。 大丈夫かと見ているこちらがハラハラしたが、
ステージに上がったその姿は90歳とは思えない、もっと若い感じに見える。
この4人でHigh Noteレーベルに録音された近作のタイトル曲で始まり、「ディジー・ガレスピーのバンドで演奏していた頃、ボストンのクラブで
誰も人がいない時間にシートに座って30分ほどで書いた曲で、ディジーがすごく気に入ってくれてレコーディングもした」という紹介を経て
"Whisper Not" が静かに演奏された。 しみじみとした雰囲気に酔わされて、これは本当にいい曲だなと思った。
続いてクリフォード・ブラウンの想い出話に移り、「とにかく色んな才能が豊かで、奨学金で学校に通っていて、てっきり音楽の奨学金だろうと
思っていたら、何と数学の奨学金だったんだ、数学だよ?信じられない!」と言ってみんなを笑わして、そのブラウニーが作った曲です、という
紹介から "Tiny Capers" が演奏された。
そして、ブラウニーが死んだ夜の話へ。 ある日の深夜、演奏が終わった3:00am頃、ブラウニーは新婚だった友人リッチー・パウエルとその奥さんが
どうしても家に帰りたいというので、みんな疲れていたけれど車で帰ることにした、運転は若い新婦がしたが、その夜はフロントガラスから前方が
見えないくらい酷い土砂降りで、交差点を右折しなければいけなかったのに前がよく見えなくて道を直進してしまった、そしたら真横から車が・・・、
という話だった。 そして、"I Remember Clifford" が始まる。 ゴルソンの長めの無伴奏ソロから静かに3人が演奏に加わり、マイク・ロドーンの
抒情的なソロ・ピアノを挟んで、最後のゴルソンの無伴奏カデンツァで曲が終わる。 場内は途中のソロ終わりで拍手するのをためらってしまうほど
切なく物悲しい雰囲気に包まれた。
次の "Alone Together" はピアノトリオによるアップテンポのハードな演奏。 「クラシックの演奏家は何百回演奏しても毎回同じ音で演奏する、
でも我々ジャズミュージシャンは毎回違う演奏をするんだ」とまるで若い演奏家に向かって何かを諭すように話をする。
そして、クロージング・テーマである "Now's The Time" を演奏しながら、メンバー紹介をしてライヴは終了した。 「みなさんは本当に素晴らしい
観客です、このままマンハッタンへ連れて帰りたい」という挨拶の後、ゆっくりとステージを降りて、数人のスタッフが彼を気遣いながら周りを
囲み、4人は観客たちと握手をしながら楽屋へと戻って行った。
ゴルソンのテナーは見事なまでに枯れていて、早いパッセージなどは吹くこともないけれど、それはどこから聴いてもあのゴルソンの音色だった。
無伴奏のカデンツァではサブトーンと言えば聞こえはいいけど、音はかすれて吹くのもしんどそうだった。 それでも、それは紛れもなくベニー・
ゴルソンのテナー・サックスの音だった。
ピアノのルドーンもリズムによく乗る演奏で、バラードでは情感豊かな表情も素晴らしい。 カール・アレンは体重200キロ近くはあるんじゃないの?
というような巨漢で、そのリズムの安定感はハンパない。 そして、何と言ってもバスター・ウィリアムズのベースの素晴らしさ。 鉄壁のタイム感、
創造性豊かで歌心満点のソロは完璧で、久し振りにベースの演奏で感激させられた。
ゴルソンは自身の演奏以外ではずっと椅子に座っていたし、動作もゆっくりと緩慢で、そろそろ見納めなのかなと思った。 声や話し方は普通に元気で
闊達だったし、表情も生き生きとして明るかったけど、この先身体がどこまでついていくかはわからない感じがした。
でも、何とも言いようがないくらい、素晴らしいステージだった。 また来年も来てくれるなら、必ず行こうと思っている。
公演が終わって外に出るとまだ明るかったので、表参道から帰る途中下北沢で下車して、レコードをごそごそと漁って帰って来た。
何と楽しい土曜日だったことか。 毎週こうだといいのになと思うけど、なかなかそうもいかない。

公演に行くつもりだったが、老眼のせいでスマホ操作を誤ってしまったのだ。 金曜の夜には渡辺貞夫が観に来ていたようなので、惜しいことをした。


セットリストはこんな感じ。 それまでの公演よりも1曲少ないのは最終日でお疲れだったせいかもしれない。
1. Horizon Ahead ■メンバー
2. Whisper Not ベニー・ゴルソン(ts)
3. Tiny Capers マイク・ルドーン(p)
4. I Remember Clifford バスター・ウイリアムス(b)
5. Alone Together (ピアノ・トリオによる演奏) カール・アレン(ds)
6. Now's The Time (クロージング・テーマ)
今回はいい席が取れて、ステージど真ん中の正面に正対するシートだった。

17:00ピッタリに照明が落ちて、メンバーたちが客席の間を縫って登場。 こんな時間通りに始まるなんて、外タレの大物では珍しい。
黄金に輝くテナーを持ったゴルソンがスタッフに囲まれてゆっくりゆっくり歩いていく。 大丈夫かと見ているこちらがハラハラしたが、
ステージに上がったその姿は90歳とは思えない、もっと若い感じに見える。
この4人でHigh Noteレーベルに録音された近作のタイトル曲で始まり、「ディジー・ガレスピーのバンドで演奏していた頃、ボストンのクラブで
誰も人がいない時間にシートに座って30分ほどで書いた曲で、ディジーがすごく気に入ってくれてレコーディングもした」という紹介を経て
"Whisper Not" が静かに演奏された。 しみじみとした雰囲気に酔わされて、これは本当にいい曲だなと思った。
続いてクリフォード・ブラウンの想い出話に移り、「とにかく色んな才能が豊かで、奨学金で学校に通っていて、てっきり音楽の奨学金だろうと
思っていたら、何と数学の奨学金だったんだ、数学だよ?信じられない!」と言ってみんなを笑わして、そのブラウニーが作った曲です、という
紹介から "Tiny Capers" が演奏された。
そして、ブラウニーが死んだ夜の話へ。 ある日の深夜、演奏が終わった3:00am頃、ブラウニーは新婚だった友人リッチー・パウエルとその奥さんが
どうしても家に帰りたいというので、みんな疲れていたけれど車で帰ることにした、運転は若い新婦がしたが、その夜はフロントガラスから前方が
見えないくらい酷い土砂降りで、交差点を右折しなければいけなかったのに前がよく見えなくて道を直進してしまった、そしたら真横から車が・・・、
という話だった。 そして、"I Remember Clifford" が始まる。 ゴルソンの長めの無伴奏ソロから静かに3人が演奏に加わり、マイク・ロドーンの
抒情的なソロ・ピアノを挟んで、最後のゴルソンの無伴奏カデンツァで曲が終わる。 場内は途中のソロ終わりで拍手するのをためらってしまうほど
切なく物悲しい雰囲気に包まれた。
次の "Alone Together" はピアノトリオによるアップテンポのハードな演奏。 「クラシックの演奏家は何百回演奏しても毎回同じ音で演奏する、
でも我々ジャズミュージシャンは毎回違う演奏をするんだ」とまるで若い演奏家に向かって何かを諭すように話をする。
そして、クロージング・テーマである "Now's The Time" を演奏しながら、メンバー紹介をしてライヴは終了した。 「みなさんは本当に素晴らしい
観客です、このままマンハッタンへ連れて帰りたい」という挨拶の後、ゆっくりとステージを降りて、数人のスタッフが彼を気遣いながら周りを
囲み、4人は観客たちと握手をしながら楽屋へと戻って行った。
ゴルソンのテナーは見事なまでに枯れていて、早いパッセージなどは吹くこともないけれど、それはどこから聴いてもあのゴルソンの音色だった。
無伴奏のカデンツァではサブトーンと言えば聞こえはいいけど、音はかすれて吹くのもしんどそうだった。 それでも、それは紛れもなくベニー・
ゴルソンのテナー・サックスの音だった。
ピアノのルドーンもリズムによく乗る演奏で、バラードでは情感豊かな表情も素晴らしい。 カール・アレンは体重200キロ近くはあるんじゃないの?
というような巨漢で、そのリズムの安定感はハンパない。 そして、何と言ってもバスター・ウィリアムズのベースの素晴らしさ。 鉄壁のタイム感、
創造性豊かで歌心満点のソロは完璧で、久し振りにベースの演奏で感激させられた。
ゴルソンは自身の演奏以外ではずっと椅子に座っていたし、動作もゆっくりと緩慢で、そろそろ見納めなのかなと思った。 声や話し方は普通に元気で
闊達だったし、表情も生き生きとして明るかったけど、この先身体がどこまでついていくかはわからない感じがした。
でも、何とも言いようがないくらい、素晴らしいステージだった。 また来年も来てくれるなら、必ず行こうと思っている。
公演が終わって外に出るとまだ明るかったので、表参道から帰る途中下北沢で下車して、レコードをごそごそと漁って帰って来た。
何と楽しい土曜日だったことか。 毎週こうだといいのになと思うけど、なかなかそうもいかない。