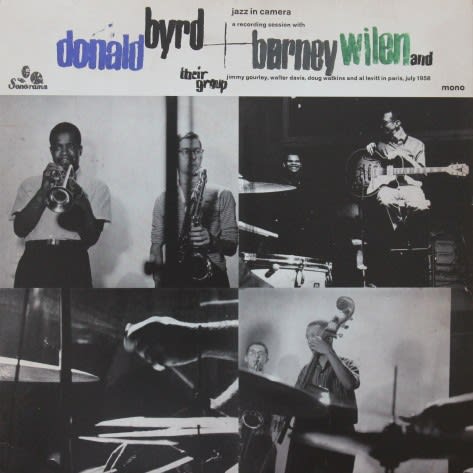Ernie Henry / Presenting Ernie Henry ( 米 Riverside RLP 12-222 )
この3ヶ月、ジャズのレコードは結局1枚も拾えず、正に緊急事態でこれが長引いている。最近はもうジタバタしてもしかたがない、と
諦めていて、ジャズからは少し距離を置いている。手持ちの少ないレコードを、たまにターンテーブルに乗せる程度の日々。
このアルバムも頻繁に聴くということもなく眠っていたが、こういう機会に久し振りに聴いてみた。
Matthew Gee のセッションへの参加でレコーディング・デビューを果たした翌日に、この自身の初リーダー作を吹き込んだ。
レコード番号も繋がっていて、ジャケットの雰囲気といい、Gee のアルバムとは双子のような印象がある。
ドーハムら、リヴァーサイドお抱えの手練れたちにしっかりと支えられながらの演奏で、音楽的には手堅く纏まっている。
層の薄いアルトサックス奏者の中で将来を嘱望されたが、交通事故で31歳で亡くなってしまったのは何とも残念だ。
ソロ・スペースはドーハムの方が長く、本人はまだまだ不慣れな感じで頼りないが、それでも独自の個性の片鱗は濃厚で、イニシアティブを
取っているのはドーハムだけど、うねるようなフレーズで懸命について行っている様子が微笑ましい。
この人はパーカーとドルフィーのちょうど中間辺りにいる。パーカーのアルトが紆余曲折を経てドルフィーへと発展しているのは明白だけど、
その過程が一般的には見えづらく、そう言われても・・・という感じがあるわけだが、この人がその間に立っていたんだということがわかれば、
黒人モダン・アルトの系譜が見えてくる。パーカーのように吹くことは誰にもできないけれど、一生懸命に真似ているうちに、なんかこんな
感じになっちゃいました、という側面があったんじゃないだろうか。
黒人モダン・アルト奏者は偶然なのか必然なのか、みんな短命で、その音楽が十分に熟す前にハード・バップの時代は終わってしまった。
その刹那的な風景の一コマがここにもある。傑作などでは全然ないけれど、それでも存在自体が貴重この上ない、そういうアルバムだろう。