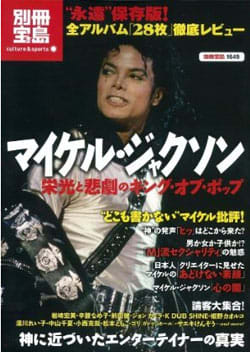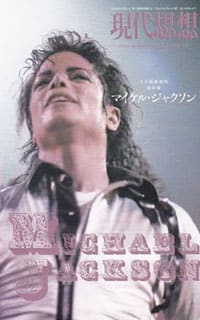スアド/著
スアド/著
松本百合子/訳
今日は久しぶりの本のお話。
少し読んだら気分が悪くなったほどの衝撃的な内容。
文庫化されたので購入しましたが、一気に読んでしまいました。
時代錯誤の因習、掟は21世紀の今でも世界に存在する。
女性に対しての男性による暴力、親がいとも簡単に女の子を殺すのです。
信じられませんが、これは一人の女性が命をかけて告発した真実の出来事です。
●ストーリー●
今から25年前の中東シスヨルダンの小さな村で生まれたスアド(仮名)は、幼い頃から働かされ、日常的に父親から虐待されていた。
17歳の時に恋をし、子供を身ごもるが、家族の名誉を汚した罰として義理の兄によって火あぶりにされる。
人道団体〈シュルジール〉で活動をしているジャクリーヌらによって奇跡的に救出され、ヨーロッパに渡る。
重度の火傷を負うが男性と結婚、子供にも恵まれるが、時折襲ってくる“鬱”と戦いながら、ジャクリーヌのすすめで本を出すことになる。
世界中の人たちにこの現実を知ってもらうために・・・
女性として生まれたばかりに奴隷として働かされ、家畜以下の生活を強いられる。
スアドの兄弟も14人いたはずが9人しかいない。
人知れず消えていく女の子、理由は家のためにならないから。
なんと生まれたばかりの女の子を母親が殺すのを目撃したスハド。
いつか自分も親によって殺されるのではないか・・・恐怖と隣り合わせの生活をしているのです。
驚くのは、成長するとともにスアド本人もここでは普通のこととして受け止めていることですね。
考える行為、選択する権利もない。
環境に慣れてしまい、女性は男性に服従するものと教えられてること。
そして年頃になれば恋もする。危険とわかっていてもこの思いは抑えられない。
だが不幸は訪れるのです・・・・その悪夢の中で未熟児で子供を産むのですが、運良く人道団体に助けられ、スアドはこの子供とともにヨーロッパに渡る。
子供は里親に預けられ、懸命に生きる彼女にすてきな男性が現れ、結婚そして二人の女の子が誕生。
第二の人生をおくるのですが、悲惨なやけどの跡、外を自由に歩けないストレス、そして火への恐怖で鬱状態に陥るスアド。
しかし、本を出版することになり、自分の忌わしい過去と向き合うことで、スアドの中で変化が生まれるのです。
「名誉の殺人」の数少ない生き残りとして、世界中の人たちにこの野蛮な行為を知ってもらうために勇気をもって彼女は証言したのです。
一生、魂の休まることはないだろうと思いますが、自分で運命を変えてやろうとする強さに感銘。
まるで中世の出来事のような、このような事件は現在も年に6,000件報告されてるそう。
これは明確な数字ではないですけど。
「名誉の殺人」(honor killing)と呼ばれる素行の悪い娘を家族が殺害する行為は、中東地域、アフリカ、インド、パキスタンなどに分布。
運良く世界中に逃げても親が追ってくることもあり(恐ろしいです・・・)
彼女らは息をひそめて暮らしているのです。
スアドももちろん名を偽り、顔も出せません。
あまりにも悲惨な行為に、憤りと地球上には我々の知らない因習がいっぱいあるということを知ったことですね。
そしてスアドは今は母親を許すことができるといっています。
今もあの土地にいたのなら、母親と同じことをするだろうと・・・
その土地が本来の常識を越えてしまうのでしょうね。
最後にスアドが言う。
自分を愛することができれば人も愛せる。
困難なことがあったら誰でもいいから人に話すこと。そして希望を持つこと。
スアドは日本での出版で来日をしています。
あとがきには日本のみなさんへの愛のメッセージが添えられていますよ。
いつかマスクをとったスアドが見られることを祈うばかりです。
人道団体シュルジール(本部:スイス)