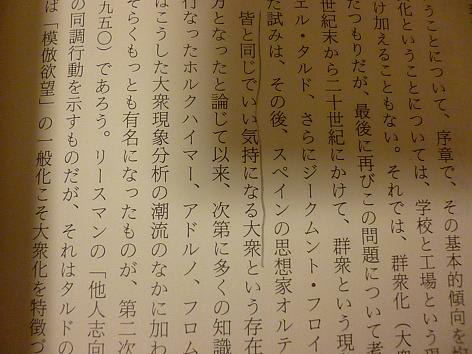肝臓を壊して以来、月一回、肝臓・頚椎ヘルニア等々心身を確認すべく順天堂に通っていたが、心の面での主治医であった貞子先生。医者にも、人事異動なるものがあるとは知らなかった。
3月に行くと、貞子先生は「転勤になることになって、本当は今までの経緯を知るじぶんが診察し続けたかったんですが。。。」
***
ということで、4月から新しい男性の主治医に変わった。
「声に出して読みたい日本語」を書いた斎藤孝さんに似た、若々しい先生だった。
先生は初対面に対して「具合はどうですか?」と、唐突に切り出した。
かたちんば「いつも思うのですが、ハローみたいに、どうですか?という質問に、じぶんは何をどう表現すれば良いか、が未だに迷って答えを出せないでいます。
クエスチョン&アンサーでいうと、どのような文脈でじぶんが何を語るかが、知らぬ同士のこの2人の会話には全くない。
その日本的曖昧さに対するいらだちが、実はわたしの内部で絶えないのですよ。
抗精神薬は、必ず診察を経ないといけない。そこには医者としての判断があるんでしょう。
でも、じゃあ、何を会話したか?と言えば”具合はどうですか?” ”まあまあです” ”はーい、いいですよ。お薬出しときますねえ。”。。。
はーい、いいですよ、とは、何がいいんですか?
あなたが数分の会話で、医者として何を判断されるのかが知りたい。
ましてや、初対面であり、そこには相互の文脈なり・合意形成がなければ、ほんとうは何もあなたは出来ないはずでは無いのですか?悪の権化=製薬会社の回し者じゃあ無いんでしょうから。裏カネもらっているわけじゃないんでしょうに。
教えて下さいよ。わたしは、ここでどんな文脈のどんな言語を語るのかを。語るべきなのかを。
目の前で血を流していれば、そこには対処方法があるべきですが、心はお互い見えない。
見えない中で、曖昧にコトを済ませて、あたかも診察のふりをしながら、大枚を医者が頂戴せしめるのには、じぶんは納得が行かない。」

そこから、本気での斎藤先生との会話が始まり、1時間話した。
彼は、そこまで言われたことがなかったのであろう。言葉をもつれさせながらも、真摯に2人の会話をした。
迷惑と思われようとも、じぶんは、えぐるような本質を語り合える仲にならねばならないと思っていた。
最終的に、お互いのゴールを決めようという話になった。
それは、例えば薬が無くても平気な姿だったり、日々障害と思えるような事態を超えられることだったり。。。
斎藤先生「そうは言えども、10分なりそこそこの時間しか無いのが実情ですから、そういったものを集約した書いた紙などを用意してもらえると、話しの焦点に向けて話が出来る。」
かたちんば「それはいつも用意していましたよ。」
斎藤先生「貞子先生には、それは話せなかったのですか?」
かたちんば「話しても、はーい、いいですよ、で終わり、クエスチョン&アンサーにはならなかったのが実情なんです。」
斎藤先生「まあ。。。あまり他の医師を批判するのはいけないので避けますが、じぶんとはそういう形を取りましょう。」
■Cocteau Twins 「あばらと血管(Ribbed and Veined)1985■