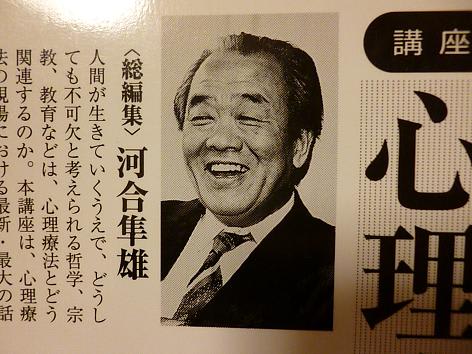昨夜、夜中に帰って、珍しく地上波テレビを回してみた。
地上波テレビを否定しつつも、大好きな山瀬まみちゃんが出ているNHKの「ためしてガッテン」をやっていて、深夜の夕食を摂りつつ見る。
不思議なめぐり合わせ、というものはあるもの。
悩ましい会議前の日に電車で「気がラクになる・・」本などという「ありがちな」「処世術」を引っ張りださねばならぬほど、精神がダウンしているときに、こんな番組にめぐり合う。
夜中やっているというのは再放送なのだろう。
中島らもさんが、かつて「その日の天使」というエッセイ(「恋は底ぢから」収録)で書いていたことを思い出した。
ジム・モリソンの詩で好きなセリフを引用して、その日その日には、かならず天使や神という者が居る・・・というエッセイだった。
仕事でぎゅうぎゅうずめ。
絶望感に打ちひしがれた冬の深夜の帰り道。
みけんにシワを寄せて悩む中、焼き芋屋さんが「お~いも~」と屋台を引きながら語る口調に思わず、ほっこりしてしまった。
これが、この日のボクの天使だった、というお話し。
めぐり合わせ、というのは不思議なものである。
***
昨夜の「ためしてガッテン」のテーマは「不眠ストレス緊張撃退 簡単トレーニング」なるもの。
昨夜の自分は、むしろ眠いし、早く眠らねばならない会議前夜。
自分の気持ちは「睡眠薬を飲めばじゅうぶんに眠れる」。
そんないつもの感じではあったが、明日をどう対処すべきか?には悩んでいた。いつも悩んでばかりいるが。
テーマとは若干ズレるが、参考になった。
というか、この番組自体よりも、その後検索して見つけた「健康増進法ブログ」というブログの記載内容に救われた感じ。
「ほっこり」などする余裕は無かったが、らもさん流に言えば、昨夜の「天使」だった。
下記は、そこからの引用であるが、悩める方々への「今日の天使」なり「救い」になれば・・・と思う。
ブログ・アドレス http://blog.livedoor.jp/webrich2-health/archives/2049697.html
以下要約引用する。
・・・「不安」は、無理に押さえ込もうとしたり、不安から目をそむける(酒の力を借りて逃れようとしたりする)と、巨大化する性質があります。
不安が強いのは性格のためではなく、脳のメカニズムのせいです。
例えば、大震災をキッカケに、地震が起きたらどうしよう、食料品が買占められたら、主人が大怪我をしたら、と不安感がだんだん募っていき、不眠になる人もいます。
・・・・・・普段、頭の中を客観的に見ているのですが、何か不安の種を見つけると警戒態勢に入り、不安感を生じさせます。
でも通常は20~30分でそれは消失します。
しかし、不安感を無理に押さえ込んだり、酒に逃げたりしていると・・・・・・より不安の種にフォーカスしようとします。
その結果、再度不安を感じる現実に直面したり、酒が切れると、脳の中で不安の種が以前に増して強調されてしまいます。
これがひどくなった場合に、元の冷静なモノの見方ができなくなり(不安を客観的に認識していた頃に戻れない)・・・・・・。
・・・・・・これが不安巨大化のメカニズムです。
・・・・・・仏教の修行の一つ、『座禅』が効果があります。
アメリカの研究論文では、座禅を続けていると、「内背側前頭前野」が分厚くなり、不安に強く対応できるようになるという結果が出ています。
座禅とは、カレーライスを見たら、”美味しそう”とか”腹が減った、食べたいなぁ”とか思わず、連想するのを止め、ただ”ああ、カレーなんだな”と素のままで受け止め、思考の連鎖を止めることなんだそうです。
しかし、座禅を勧めるのでは、「簡単脳トレ」ではありませんので、番組では、座禅の効果があっという間に身につく方法を伝授しました。
それは、早稲田大学・人間科学学術院の熊野宏昭教授が教える不安を流す方法です。
・軽く目を閉じ、小川と落ち葉を思い浮かべる。
・次に心の中に浮かび上がる思考(不安な事など)を落ち葉に乗せて川に流す。
・これを繰り返す。
ただこれだけです。
これを1日に10~15分、毎日続けます。
そうすると、1週間ほどで、不安が巨大化する不安症が消えていき、「何とかなるさ」という落ち着いた気持ちになれ、不眠の人も眠れるようになっていきます。
もう一つ、不安から抜け出すおまじないとして、「~と思った」というフレーズを不安な気持ちになった時につかうとよいそうです。
「また仕事で失敗して、俺ってダメだなぁ・・・」と落ち込んだ気持ちになったら、最後に「と思った」と付け加えます。
そうすると、心を客観視する力を鍛えることができ、不安にとらわれない性格になっていけるということです。
この「~と思った」は、熊野教授が実際の治療でも使っているメソッドだそうです。
以上が、今回の「ためしてガッテン」でしたが、不安や緊張におびえる時でも、それは手に負えない性格のせいではなく、脳の一定部位のメカニズムの機能低下のせいなんだと分かっているだけでも、安心できるのではないかと思います。
また、『困ったことは起こらない』というこの世のルールがあることも、知っておいてよいのではないでしょうか。
”心配なことは実際には9割以上の確率で起こらない”という法則です。
残り1割も現実には心配するより大事に至ることなく済んでしまうものです。
何故なら、自分の手に負えない事は自分の身には起こらないのが、この宇宙の法則だからです。 <引用終わり。
***
・・・・・・ということで、結果、なんとか「殺されずに」今日を越えることが出来た。
昨夜の「天使」に感謝。