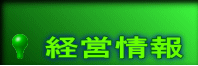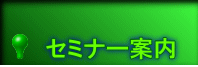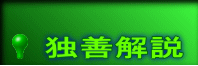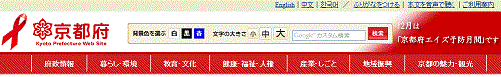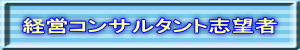時代の流れを時系列的に見ると、見えないものが見えてきます。

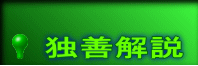

◆ 民間活力でアベノミクスはうまくいくか? 2013/06/09~16
安倍総理大臣が、経済の成長戦略において「民間の活力を引き出す」「10年後に一人当たりの国民総所得を150万円以上増やす」ことを表明しました。
私たちは、この安倍政権の民間の活力を高めるという成長戦略に期待を持っていいのでしょうか。
NHKの今井純子解説委員の番組で探ってゆきます。
◇1 なぜ成長戦略が注目されるか
昨今、日本経済が置かれている状況から見てみましょう。
安倍政権は、「第一の矢」と「第二の矢」を矢継ぎ早に打ち出しました。
第一の矢は「大胆な金融緩和」であり、第二の矢は「機動的な財政出動」です。
株高と円安の追い風を受けて、輸出や消費が増え、2013年1月から3月までのGDPの伸び率は、年率に換算してプラス3.5%と、高い伸びを示しました。
しかし、同期間における企業の設備投資は、2012年と比べて減少が続いています。サラリーマンの給与も、多くなるどころか、0.6%下回っています。
すなわち景気回復の恩恵を受けているのは、一部の大企業や資産家だけです。日本経済全体が力強く回復していると言える状況にはなっていないのです。
期待だけが先行して株高、円安になっていて、国民に広く恩恵が行きわたっている訳ではないのです。そのために、国民がアベノミクス
◇2 成長どころか乱高下
ここに来て株価が急落したりして、その影響で円安にもなったりしています。
1.株価は、先月半ばから、一転して、下落に転じています。
2.長期金利が上がったことで、住宅ローンの金利も上がっています。
3.円安の影響で、輸入品を中心に食品や電気代、パソコンなど幅広い製品やサービスで値上げが相次いでいます。特に、家計や中小企業にとっては、重い負担です。
このままでは、私たちの生活に景気回復の恩恵が回ってくる前に、個人消費が落ち込んでしまいかねません。そうなりますと、経済の足を引っ張ることになるでしょう。
景気の回復を持続させるには、「金融緩和」や「財政出動」に頼った期待先行の段階から、民間主導の力強い経済再生の段階へと早く橋渡しをしていかなければなりません。
そのためには、経済の構造改革を進めて、企業の活力を取り戻すという政府の決意と、そのための道筋を盛り込んだ「成長戦略」を確実に実行することが求められるのです。
◇第3回 成長戦略の中身
では、安倍政権の成長戦略は、国民の期待に応えるだけのホンモノの内容になっているのでしょうか。
今井解説委員は、その中味を3項目としてまとめています。
1.企業や産業、日本の立地の競争力を強化すること
2.医療・介護や農業などの分野で新しい市場をつくりだすこと
3.海外での利益を増やすこと
安倍政権では、第1項については、設備投資の増加と競争力の強化に向けて、次の3項目を挙げています。
1.古い生産設備を、最新の設備に買い替える企業を税金などで優遇すること
2.人が操作しないで、自動的に運転する車の開発に向けて、現在は認められていない公の道路での走行実験を認めるといった規制緩和を、個別の企業に対して認める制度をつくること
3.国が選んだ特定の地域で、大胆な規制緩和や税制優遇を検討する「国家戦略特区」を新たにつくる
私は、この3項は、目新しい政策でも何でもないと考えます。しかし、だからといって、全然ダメだと言っているわけではないですが、私の考えをご紹介します。
第1項は、スクラップ&ビルドをすることにより、買い換え需要を引き出そうとしている、目新しい手法ではありません。資源保護という観点では逆行することであり、それに税金優遇すると言うことでは、反対する人も多いでしょう。
第2項は規制緩和という手法です。国内で生産や開発をすることへの魅力を高めることで、民間の設備投資を増やそうというのです。自動運転というのは、実はカーナビが最初目指したことで、ITSの実現を目指そうとしています。すなわち、目新しい技術ではなく、それを前面に出して、3年間で10%の成長を目指し、リーマンショック前の水準に戻そうという、「成長」に値することではなく、ようやく元に戻るだけです。
第3項も規制緩和です。建物の容積率を緩和したり、インターナショナルスクールをつくりやすくしたりしています。「世界で一番ビジネスがしやすい環境をつくって、海外からの投資を呼び込む」と言っていますが、目論見通り行くのでしょうか。
◇第4回 戦略市場創造
安倍政権の成長戦略第2項は「医療・介護や農業などの分野で新しい市場をつくりだす」です。すなわち「戦略市場創造」と言え、次の2点を前面に出しています。
1.iPS細胞をつかった再生医療など最先端の分野で、医療開発や新薬の開発を、一元的に指揮する司令塔の機関を新たにつくること
2.インターネットを使った市販薬の販売を、原則として解禁すること
iPS細胞は、京都大学の山中伸弥教授のノーベル賞受賞でクローズアップされました。日本は、研究段階では最先端を行っている部分の多い医療や新薬開発関係ですが、実用化への段階が遅れています。
法改正などで、この分野でやるべきことも多いですし、分野を絞って集中的に促進していくことは重要です。この観点から、国が支援することは、その後押しをすることになります。
上記の第2項ですが、これは本当に国民にとって好ましいことでしょうか。市販薬は、大きく3分類されていますが、第一分類は、薬剤師などのアドバイスなしで、インターネットで購入することができるというのは、使い方を誤り、薬害に繋がることも懸念されます。
一方で、従来の法律では、わざわざ薬剤師のいる薬局まで足を運ばなければならない患者さんには厳しい規制です。それが緩和されることは結構なことです。
インターネット販売のやり方を工夫すべきですのに、手抜きの方策で人気とりのために実施するように思えます。
◇第5回 国際展開
安倍政権の成長戦略の第3項は「海外での利益を増やす」ことです。
海外での利益を増やすための戦略として、次の2項が挙げられています。
1.TPPなど、自由貿易協定を締結した国との貿易額の割合を、2018年までに、今の19%から70%に高める
2.インフラの輸出額を2020年までに今の10兆円から30兆円規模に拡大すること
第1項は、農業や保険などの業界におけます大反対の中、安倍政権が進めようとしています。
農業分野は、これまで国の手厚い保護を受けてきたこともあり、その既得権にしがみつき、製造業におけるような厳しい競争下における企業努力不足は否めません。その道の専門家によると、まだまだ経営努力をする方策があるように推測します。
一方で、食料というのは、絶対に死守すべき問題であり、その観点での考察が充分なされていないのが現状のように思えます。
国民健康保険という、世界で最も福祉面で進んだ制度が、TPPにより揺らぐ可能性を秘めています。その問題を解決できる秘策を政府は持っているのでしょうか、見出せると考えているのでしょうか。先が見えないままの現状は、大変不安です。
◇第6回 安倍政権の成長戦略の評価
成長戦略についての私見をこれまでに述べてきましたが、今井解説委員の考えを中心にご紹介します。
期限を定めて、多くの数値目標を掲げている点はわかりやすいと評価してもいいでしょう。
また、TPPへの参加など、抵抗が強くて、これまで決められなかった分野で決断をしています。また、依然、抵抗が強い規制緩和についても、国家戦略特区や、個別の企業の単位で、まず緩和を試してみるという、新しい試みが盛り込まれたりしています。
今井解説委員は、安倍政権の構造改革に踏み込もうという姿勢を評価しています。一方で、氏は、本当に狙い通りに、経済再生を果たせるのかとい観点で、私同様に疑問を感じています。
私の見方とは視点が異なる3点を挙げています。
1.目標達成の道筋が見えていない
2.政策の実効性
3.家計への還元
◇第7回 安倍政権成長戦略の問題点と実効性
先ず、今井解説委員は、問題点として3つ挙げていますが、その第1項「目標達成の道筋が見えていない」という点では、次のような意見を披露しています。
1.一点目は、目標を達成するための具体的な政策の中身が、まだ見えていないという点です。例えば、3年後に設備投資を10%増やすという目標はありますが、どのような税制面の支援を打ち出すのかは、これからです。
2.目玉のひとつ、国家戦略特区も、どのような規制緩和や税制優遇で、どういった特区をつくるのか。具体的な中味は、まだわかりません。
3.企業は、需要のある海外での設備投資は増やしても、人口が減っている国内での投資には、依然として慎重です。海外から、国内へと、投資の流れを変えていくには、相当思い切った税制改正や規制緩和を打ち出していくことが必要ではないでしょうか。
また第2項「政策の実効性」については、次のようにその問題点を指摘しています。
2点目の疑問点は、政策の実効性です。これまでにも、成長戦略は、毎年のようにつくられ、それなりの目標も書かれていましたが、大きな成果をだしたとは言えません。政府は、今回、成長戦略を定期的に点検して、追加的な対策をとっていく、としていますが、今度こそ、成長戦略をつくって終わりではなく、目標達成まで粘り強く対策をとり続けてほしいと思います。
安倍政権成長戦略の問題点第3項及び、今井解説委員のまとめは、次回に回します。
◇第8回 安倍政権成長戦略の「家計への還元」問題とまとめ
安倍政権の成長戦略における今井解説委員が考えている問題点の第3項と氏の考えのまとめを今回は紹介します。
まず、問題点第3項であります「家計への還元」について、氏は下記のように述べています。
3点目は、家計への還元です。
安倍さんは、家計が潤うことが大事だとして、10年後に一人当たりの国民総所得を150万円以上増やす考えを示しました。
しかし、国民総所得というのは、国の経済規模を示すGDPに、企業が海外から受け取る利益などを加えたもので、企業が利益をためこんでいても、一人当たりの国民総所得は増えます。
問題は、企業の利益をどう、私たちの家計に分配するかです。リーマンショックの前、企業が過去最高益をあげ続けたときも、企業は、利益を賃金には回しませんでした。
では、今後、どのように賃金を増やすのか、成長戦略からは、具体的な道筋は見えてきません。今回こそ、企業の利益が広く家計に還元されるよう、政府は、責任をもって、対応をしてほしいと思います。
この点については、GDIで150万円/国民という数値の出し方に、私は不満です。従来、GDP出見てきたのですから、それをGDP換算するとどうなるのかを示しませんと、単なる数字のマジックでしか過ぎず、結果的には国民の生活が楽にならないかもしれません。
なぜなら、インフレ誘導として2%がふくれあがり、GDIで表記することにより、海外資産等の数値が加算されますので、名目で150万円と言っても、実質で見る場合には、あまり現状より改善していないのではないかと、私は考えます。
最後に「まとめ」として、氏は下記のように述べています。
20年停滞していた日本経済の抜本的な構造改革を進めることは、簡単ではないでしょう。
しかし、今度こそ、うまくいきませんと、金融緩和と財政出動の、副作用だけが残ることになりかねません。
時間はあまりないかもしれません。
政府は、成長戦略の目標達成のための道筋、つまり、具体的な税制や規制緩和を早く示して、今度こそ、最後まで、きちんと実行してほしいと思います。
私は、氏のお考えを全面的に支持するわけではないですが、安倍政権が本当に本気で取り組めば、問題点を含んでいますが、日本経済は良くなると思います。
◆ 日本が進むべき方向
2013/06/07
大胆な金融政策を中心に日本の経済再生を図る「アベノミクス」の成果で、安倍総理の人気も高いです。
しかし、アジアなどの新興国では、こうした日本の金融政策による円安が通貨高を招き、輸出が伸び悩むなどの影響が出始め、円安への警戒感は強まってきています。
NHKの番組で、TICAD(アフリカ開発会議)に出席するために来日したアメリカのコロンビア大学のジェフリー・サックス教授とビズプラスサンデーの飯田香織キャスターのインタビュー番組を見た人も多いと思います。
持続的で安定した成長のために日本や世界各国はどのような経済政策を行うべきなのか、そのポイントを整理しました。
【バックナンバー】
◇1 黒田日銀総裁の金融政策の評価 2013/06/03
◇2 世界的な大規模金融緩和策 2013/06/04
◇3 “通貨安競争”は健全策か? 2013/06/05
◇4 政府や中央銀行が市場規制することができるか? 2013/06/06
◇5 日本は今後どうあるべきか 2013/06/07
サックス教授のお話から、それでは日本はどうすべきかを考えてみましょう。
彼は、日米においては経済政策があまりに短視眼的だと言っています。とくに日本においては、首相がころころと、政権変更がおきました。
アメリカでも政治のサイクルは長いとは言えません。連邦議会の選挙は2年おき、大統領選挙は4年おきにあり、深い構造問題を解決するには時間が足りません。
このような状況では、中長期的なビジョンでの政策が実現しにくくなります。
1.中国を世界経済にどう組み込んだら良いのでしょうか。
2.将来を担う子どもたちの「21世紀型の教育」をどうしたらよいのでしょうか。
3.気候変動の問題や原発の問題など、解決しなければいけない各種の問題にどのように取り組んだら良いのでしょうか。
これはほんの一例ですが、彼は、日本政府につぎのような点をアドバイスとして指摘しています。
1.人間にとってよりよい経済にするために、今後の根幹の問題は、人々の生活をどう向上させたら良いのでしょうか。
2.環境問題やエネルギー問題など、長期的な問題への取り組みます。重要なのは、短期的な問題に取り組みながら、長期的な問題に取り組むことです。
3.真の成長は、アジアやアフリカなどの新興諸国にありますが、こうした新興諸国の発展に日本はどのように寄与したら良いのでしょうか。持てる日本の能力を十分に発揮すべきです。
このような中で、TICAD(アフリカ開発会議)は、タイミング良く開催されましたと、
サックス教授はコメントしています。
昨年実施した中国の二番煎じのように私には思えますが、ウインウインの関係を構築する機会になれば良いと考えます。 <完>
◆ 日本が進むべき方向 2013/06/06
大胆な金融政策を中心に日本の経済再生を図る「アベノミクス」の成果で、安倍総理の人気も高いです。
しかし、アジアなどの新興国では、こうした日本の金融政策による円安が通貨高を招き、輸出が伸び悩むなどの影響が出始め、円安への警戒感は強まってきています。
NHKの番組で、TICAD(アフリカ開発会議)に出席するために来日したアメリカのコロンビア大学のジェフリー・サックス教授とビズプラスサンデーの飯田香織キャスターのインタビュー番組を見た人も多いと思います。
持続的で安定した成長のために日本や世界各国はどのような経済政策を行うべきなのか、そのポイントを整理しました。
【バックナンバー】
◇1 黒田日銀総裁の金融政策の評価 2013/06/03
◇2 世界的な大規模金融緩和策 2013/06/04
◇3 “通貨安競争”は健全策か? 2013/06/05
◇4 政府や中央銀行が市場規制することができるか? 2013/06/06
政府や中央銀行が、市場を規制することができるかどうか、サックス教授の意見です。
政府や中央銀行が規制するべきなのは金融機関です。
日銀がさらに今の金融緩和を推し進めるのであれば、金融緩和によって生じた、有り余りすぎる資金を使って金融機関がギャンブルのようなリスクをとる投資を行う危険があります。そこで金融市場がギャンブル化しないように細心の注意を払う必要があります。
アメリカで行われた金融分野の規制緩和は、犯罪にすらつながり、あきらかに間違えといえます。先般発生したようなウォール街での出来事が、東京でも起きないことを願っています。
【今後の掲載予定】
◇5 日本は今後どうあるべきか 2013/06/07
◆ 日本が進むべき方向 2013/06/05
大胆な金融政策を中心に日本の経済再生を図る「アベノミクス」の成果で、安倍総理の人気も高いです。
しかし、アジアなどの新興国では、こうした日本の金融政策による円安が通貨高を招き、輸出が伸び悩むなどの影響が出始め、円安への警戒感は強まってきています。
NHKの番組で、TICAD(アフリカ開発会議)に出席するために来日したアメリカのコロンビア大学のジェフリー・サックス教授とビズプラスサンデーの飯田香織キャスターのインタビュー番組を見た人も多いと思います。
持続的で安定した成長のために日本や世界各国はどのような経済政策を行うべきなのか、そのポイントを整理しました。
【バックナンバー】
◇1 黒田日銀総裁の金融政策の評価 2013/06/03
◇2 世界的な大規模金融緩和策 2013/06/04
◇3 “通貨安競争”は健全策か? 2013/06/05
韓国・タイなどの新興国は、日本をはじめとする先進国の金融緩和による、通貨高を背景に、最近、相次いで利下げに踏み切りました。こうした“通貨安競争”は、健全なことかどうか、サックス教授は次のように述べています。
先進国の金融緩和によって生まれた過剰な資金が、こうした国々に流れ込むのは当然のことです。
資金が流入した国の通貨は上昇します。その結果、その国の中央銀行は金融緩和によって対抗します。このため、世界的な金融緩和が起き、これは世界経済を刺激することになり、よいことです。
ただ、金融緩和によって通貨の過剰流動性が起きることは、さまざまなバブルを引き起こす可能性があります。
経済政策の運営の神髄ともいえるように、金融緩和にはある程度、慎重に進めるべきです。
つまり、一定程度までは健全ですけれども、その後は危険になるということです。
サックス教授は、境界線を見極めることの難しさを説いています。
【今後の掲載予定】
◇4 政府や中央銀行が市場規制することができるか? 2013/06/06
◇5 日本は今後どうあるべきか 2013/06/07
◆ 日本が進むべき方向 2013/06/04
大胆な金融政策を中心に日本の経済再生を図る「アベノミクス」の成果で、安倍総理の人気も高いです。
しかし、アジアなどの新興国では、こうした日本の金融政策による円安が通貨高を招き、輸出が伸び悩むなどの影響が出始め、円安への警戒感は強まってきています。
NHKの番組で、TICAD(アフリカ開発会議)に出席するために来日したアメリカのコロンビア大学のジェフリー・サックス教授とビズプラスサンデーの飯田香織キャスターのインタビュー番組を見た人も多いと思います。
持続的で安定した成長のために日本や世界各国はどのような経済政策を行うべきなのか、そのポイントを整理しました。
◇1 黒田日銀総裁の金融政策の評価
安倍総理と共に経済運営を担当している日銀の黒田総裁の金融緩和策を、サックス教授はどのように見ているのでしょうか。サックス教授の考えをまとめました。
デフレから脱却するために金融を大規模に緩和するというのは、正しい道だと思います。短期的には、円安をもたらし、日本経済を刺激します。
通貨の供給量を増やすことで、円を安くして輸出を増やし、企業の利益を増やすことで経済を成長させるのは、経済の基本です。本来であれば、とっくの昔からやるべきことでした。
【バックナンバー】
◇1 黒田日銀総裁の金融政策の評価
◇2 世界的な大規模金融緩和策
日米欧がこぞって大規模な金融緩和策をとっています。こうした金融政策は、世界経済にどんな影響を与えるか、サックス教授の意見です。
彼が強調したいのは、金融政策ですべての問題が解決できるわけではないということです。
金融政策でできることと言えば、日本の場合には1ドル=80円だった円相場を円安にすることです。個人的には110円が適正だ思っています。一層の円安は日本にとって望ましく、世界にとっても問題ありません。
金融政策は、構造問題を解決するわけではありません。
財政問題も、高齢化問題も、国際競争力の問題も、エネルギーの問題も、環境問題も解決しません。
アメリカでは、今、財政再建の議論が止まってしまっています。ヨーロッパでも、ユーロ圏の経済危機の結果、財政出動ができません。この結果、すべての経済政策の担当者は、すがるような視線を中央銀行に向けているのです。
【今後の掲載予定】
◇3 “通貨安競争”は健全策か? 2013/06/05
◇4 政府や中央銀行が市場規制することができるか? 2013/06/06
◇5 日本は今後どうあるべきか 2013/06/07
◆ インドとの原子力協定 2013/06/02
安倍総理とインドのシン首相の会談が東京で行われ、日本の原子力関連技術のインドへの輸出を可能にする原子力協力協定の交渉を進めていくことで合意しました。NHKの広瀬公巳解説委員の解説要約をご紹介します。
NPT・核拡散防止条約の枠外にあるインドとの協力をどこまですすめてよいのか。日本の原発を海外に輸出することの是非は十分に議論されたのか。
このような課題の中、12億の人口が電気を必要とするインドと高い技術力で新興国への進出を図ろうとする日本の立場をどのように融合させるかが問題です。
共同声明は、交渉が停滞していた原子力協定について「早期妥結にむけて交渉を加速する」と宣言しました。
原子力協定は核関連の物質や技術の移動を可能にするめに政府間で結ばれるもので妥結にいたりますと大規模なインフラ輸出に大きな可能性を開くものとなります。
核保有国であるのにNPTに入っていないインドは、今、国際的な核管理体制の中で、「特別扱い」をされている状態です。
インドに対し条件付きながら核燃料や原子炉などを輸出できるとしたのがアメリカとの原子力協力協定でした。インドに独自に核を開発させるよりも国際的な核管理の輪の中に取り込むべきだとするのがアメリカの立場でした。
これを受けNPTの加盟国のグループであるNSG・原子力供給国グループがインドへの核物質・技術の移転を認めるグループとしての方針を決定。つまり、インドを例外扱いする今の体制はインドが核を軍事目的には転用しないといういわば「インドへの信頼」を前提としているのです。
1974年の最初の核実験ではカナダから提供されていた原子炉から回収した使用済み核燃料を再処理しプルトニウムを抽出。核開発は平和目的であるとしていたインド政府の方針が、政権交代にともなって、強いインドを強調するものとなりました。
そもそもNPTは一部の国の核保有を追認するだけの不平等条約だというのが今も変わらぬインドの立場でインドはCTBT・包括的核実験禁止条約にも入っていません。このため、日本が原子力協定の交渉を進めるにあたっては、核物質や技術を軍事目的には転用されない、民生利用に限定される体制を確実にすることが必要です。
インド南部の海岸地帯にあるマドラス原発ではインド洋大津波の際に原発の施設の一部が浸水するトラブルがありました。このようなリスクにタイする回避策が伴わぬ原発輸出は、禍根を残しかねません。

 経営コンサルタント歴35年の経験から、
経営コンサルタント歴35年の経験から、