
だいぶ前にタイトルに惹かれて衝動買いし書架に眠っていた。それを取り出して読んでみた。深く考えること無しに「無宗教」と言いがちになることを、改めて問い直してみるのに役立つ書である。奥書を見ると、1996年10月に第1刷が発行され、2014年8月の第30刷となっている。たぶんその後も刷を重ねるロング・セラーになっている一冊だと思う。
第1章の冒頭が次の文で始まる。
”日本人のなかには「無宗教」を標榜する人が少なくない。
しかし本当に宗教を否定したり、考え抜いた上での無神論者はきわめて少ない。”
著者は、ズバリと日本人の宗教に対する一つの特徴を言い当てているように思う。このことを、著者は「宗教心」についての調査結果を引き合いに出し、裏付ける。著者は、どの調査を見ても、調査回答者全体の7割が「無宗教だ」と回答する一方で、その7割の75%が「個人的には無宗教」と回答しつつ、「宗教心は大切だ」と答えていると言う。
なぜ、この回答が生まれるのか? 「無宗教」という言葉に込める意味合いが、世界の多くの国々の常識と違うのだと著者は捉えていく。世界の常識では、無宗教と答えれば即無神論者と解され、胡散臭い人間と判断される。だから、海外では簡単に「無宗教」などと答えるなということにつながる。
著者は、日本人の言う「無宗教」は「特定の宗派の信者ではない」という意味に翻訳し、「むしろ宗教心は豊かなのである」(p8)と断言する。「無宗教」と「宗教心」が両立するのはなぜか? それを著者流に解き明かしたのが本書である。
この問題提起から、5章構成として、190ページほどで著者は持論を展開していく。一度立ち止まり、無宗教と宗教心という言葉をじっくり考えてみるのに役立つ。
第1章 「無宗教」の中身
第2章 「無宗教」の歴史
第3章 痩せた宗教観
第4章 日常主義と宗教
第5章 墓のない村 という章立てになっている。
著者は日本人の宗教心を分析する上で有効なツールとして、巧妙な概念区分で定義する。「創唱宗教」と「自然宗教」である。
創唱宗教:特定の人物が特定の教義を唱えてそれを信じる人たちがいる宗教
教祖と教典、教団の三者により成立する宗教
キリスト教、イスラム教、仏教、新興宗教などが該当する。
自然宗教:自然に発生し、無意識に先祖たちによって受け継がれ、今につづく宗教
著者は宗教をこのように区分しないから、混乱や誤解が生ずるのだと論じていく。
日本人においては、「創唱宗教」よりも「自然宗教」の方が優越していて、「自然宗教」の立場での宗教心を誰もが持っているのだという仮説を主唱していく。ご先祖や村の鎮守への敬虔な心を持っているという側面を指摘する。日本人にとっての自然宗教は、風俗や習慣になってしまった宗教なのだと言う。だから、初詣から始まり、春秋の彼岸、お盆、クリスマスまでの年中行事を繰り返し、違和感なく受け入れているのだと言う。「神道」は「自然宗教」を基盤として生まれた宗教であるが、著者の言う「自然宗教」そのものではないと識別している。
「創唱宗教」と「自然宗教」の区分は、「無宗教」と言いつつ「宗教心」を持っている日本人の有り様を、うまく説明していると思う。この説明、巧妙かつおもしろい。
本書は、著者のこの仮説について、読者の納得度を高めさせるための具体的な分析と論理構成の展開プロセスである。
第2章では、まず日本における「無宗教」感を助長した歴史的経緯を論じている。多くの場合、無意識であったとしても熱心な「自然宗教」の信奉者であり、「創唱宗教」に対しては無関心という意味での「無宗教」という意味合いと解釈するのが妥当と論じる。そういう日本人が形成されてきた背景はいずこにあるのか。
著者は中世人は神仏とともに生き、六道輪廻の苦しみから逃れることを求めた時代だが、その後儒教が導入されて、政策的に広がったことから、特定の宗派に対し無関心となり、「無宗教」の始まりとなったと言う。中世の「憂き世」ではなく、近世の「浮き世」意識に転換する。生産性の向上、経済的裏付けが、井原西鶴の描く享楽的人生観を肯定したとする。また、江戸時代の寺請檀家制度がイエの仏教を形成し、葬式仏教を生み出したと言う。本来の仏教にはない葬式仏教がすんなり受け入れられたのは「自然宗教」が根強く生きているからだと説く。自然に生まれた先祖崇拝観と葬式仏教が親和したからだということなのだろう。このあたりの経緯説明はわかりやすい。ナルホド感がありおもしろい。
第3章では、日本において宗教観が痩せた理由を指摘する。
1) 明治以降に、翻訳語として「宗教」という用語が生まれ、それは「創唱宗教」を意味し、宗教を「個人の私事」と位置づけた。「自然宗教」は排除され、分断されてしまった。「自然宗教」は宗教とはみなされないことになったと言う。
2) 明治政府は政策的に「神話」を国家原理に採用した。天皇崇拝の国教づくりである。「国家神道」は神道非宗教論として政策的に実行されていく。この「神道非宗教論」の成立に、浄土真宗が大きな役割を果たしたと著者は見ている。
この日本の近代国家のあり方が、「創唱宗教」と「自然宗教」の双方に極度の歪みや変質をもたらしたと言う。
3) 豊かな宗教観の試みは行われたが、「大逆事件」の発生により潰えてしまった。
著者はこの章で明治以降の国家と宗教の経緯並びに当時の論点を説明することにより、「『無宗教』は、近代日本の状況にあっては、明らかに身の安全を保障する言葉でもあったのだ」(p110)と結論づけている。
この辺りの歴史的状況について、私には初めて知る知識が多く、新鮮な感覚で読めた。
第4章で、著者は「無宗教」と「平凡」志向、日常主義との密接な関係を具体的な事例を取り上げて論じている。
1つは、信州の天竜川筋でかつて行われていた「サガ流し」行事、2つめは民俗学者柳田国男著『山の人生』の一節、、3つめは田山花袋の小説『重右衛門の最後』で描かれた人間の創り出す悪業、4つめは、きだみのるのムラについての記録作品に記されたムラの有り様、5つめは再び柳田国男著『日本の祭』に記された祭の祭礼化、6つめに曹洞宗の僧侶・鈴木正三著『万民徳用』の教え、これらの読み解きである。これら事例を通じて、日常主義の優位は、「17世紀以来の日本社会に共通した現象であった」(p163)と読み解いている。
最後の第5章は「『無宗教』が日本人の精神生活のなかでどのような位置にあるかをはっきりさせるためにも、墓を無用とする宗教心がどのようなものであるかを見ておこう」(p167)という意図からまとめられている。
著者は、沖縄の宮古島に付属する大神島のウヤガムの信仰を取り上げ、この島の「自然宗教」を紹介している。この島には「本土では希薄になったタマシイの信仰がまだ十分に生きている」(p173)と言う。そして、「この大神島の人々が『無宗教』を標榜する」(p177)と付け加えている。
著者は、「無宗教」という言葉にだまされてはならないということをあらためて強調している。
また、視点を変えて鳥取県青谷町の山根という和紙の里を紹介する。この里の篤信者足利源左を劇的に「回心」した人として、その生き方を紹介する。ここでは伝統の中で宗教心を形成した事例もあることに触れている。「無宗教」を強調しすぎないためということでもあろうと理解した。
「無宗教」という一語の意味は深い。そのことを考えるために役立つ本である。
四半世紀前の本だが、宗教の歴史の長さから受けとめれば、つい先日に出版された本とも言える。普段、深くは考えることのない言葉の意味を見つめ直してみようではないか。
ご一読ありがとうございます。
第1章の冒頭が次の文で始まる。
”日本人のなかには「無宗教」を標榜する人が少なくない。
しかし本当に宗教を否定したり、考え抜いた上での無神論者はきわめて少ない。”
著者は、ズバリと日本人の宗教に対する一つの特徴を言い当てているように思う。このことを、著者は「宗教心」についての調査結果を引き合いに出し、裏付ける。著者は、どの調査を見ても、調査回答者全体の7割が「無宗教だ」と回答する一方で、その7割の75%が「個人的には無宗教」と回答しつつ、「宗教心は大切だ」と答えていると言う。
なぜ、この回答が生まれるのか? 「無宗教」という言葉に込める意味合いが、世界の多くの国々の常識と違うのだと著者は捉えていく。世界の常識では、無宗教と答えれば即無神論者と解され、胡散臭い人間と判断される。だから、海外では簡単に「無宗教」などと答えるなということにつながる。
著者は、日本人の言う「無宗教」は「特定の宗派の信者ではない」という意味に翻訳し、「むしろ宗教心は豊かなのである」(p8)と断言する。「無宗教」と「宗教心」が両立するのはなぜか? それを著者流に解き明かしたのが本書である。
この問題提起から、5章構成として、190ページほどで著者は持論を展開していく。一度立ち止まり、無宗教と宗教心という言葉をじっくり考えてみるのに役立つ。
第1章 「無宗教」の中身
第2章 「無宗教」の歴史
第3章 痩せた宗教観
第4章 日常主義と宗教
第5章 墓のない村 という章立てになっている。
著者は日本人の宗教心を分析する上で有効なツールとして、巧妙な概念区分で定義する。「創唱宗教」と「自然宗教」である。
創唱宗教:特定の人物が特定の教義を唱えてそれを信じる人たちがいる宗教
教祖と教典、教団の三者により成立する宗教
キリスト教、イスラム教、仏教、新興宗教などが該当する。
自然宗教:自然に発生し、無意識に先祖たちによって受け継がれ、今につづく宗教
著者は宗教をこのように区分しないから、混乱や誤解が生ずるのだと論じていく。
日本人においては、「創唱宗教」よりも「自然宗教」の方が優越していて、「自然宗教」の立場での宗教心を誰もが持っているのだという仮説を主唱していく。ご先祖や村の鎮守への敬虔な心を持っているという側面を指摘する。日本人にとっての自然宗教は、風俗や習慣になってしまった宗教なのだと言う。だから、初詣から始まり、春秋の彼岸、お盆、クリスマスまでの年中行事を繰り返し、違和感なく受け入れているのだと言う。「神道」は「自然宗教」を基盤として生まれた宗教であるが、著者の言う「自然宗教」そのものではないと識別している。
「創唱宗教」と「自然宗教」の区分は、「無宗教」と言いつつ「宗教心」を持っている日本人の有り様を、うまく説明していると思う。この説明、巧妙かつおもしろい。
本書は、著者のこの仮説について、読者の納得度を高めさせるための具体的な分析と論理構成の展開プロセスである。
第2章では、まず日本における「無宗教」感を助長した歴史的経緯を論じている。多くの場合、無意識であったとしても熱心な「自然宗教」の信奉者であり、「創唱宗教」に対しては無関心という意味での「無宗教」という意味合いと解釈するのが妥当と論じる。そういう日本人が形成されてきた背景はいずこにあるのか。
著者は中世人は神仏とともに生き、六道輪廻の苦しみから逃れることを求めた時代だが、その後儒教が導入されて、政策的に広がったことから、特定の宗派に対し無関心となり、「無宗教」の始まりとなったと言う。中世の「憂き世」ではなく、近世の「浮き世」意識に転換する。生産性の向上、経済的裏付けが、井原西鶴の描く享楽的人生観を肯定したとする。また、江戸時代の寺請檀家制度がイエの仏教を形成し、葬式仏教を生み出したと言う。本来の仏教にはない葬式仏教がすんなり受け入れられたのは「自然宗教」が根強く生きているからだと説く。自然に生まれた先祖崇拝観と葬式仏教が親和したからだということなのだろう。このあたりの経緯説明はわかりやすい。ナルホド感がありおもしろい。
第3章では、日本において宗教観が痩せた理由を指摘する。
1) 明治以降に、翻訳語として「宗教」という用語が生まれ、それは「創唱宗教」を意味し、宗教を「個人の私事」と位置づけた。「自然宗教」は排除され、分断されてしまった。「自然宗教」は宗教とはみなされないことになったと言う。
2) 明治政府は政策的に「神話」を国家原理に採用した。天皇崇拝の国教づくりである。「国家神道」は神道非宗教論として政策的に実行されていく。この「神道非宗教論」の成立に、浄土真宗が大きな役割を果たしたと著者は見ている。
この日本の近代国家のあり方が、「創唱宗教」と「自然宗教」の双方に極度の歪みや変質をもたらしたと言う。
3) 豊かな宗教観の試みは行われたが、「大逆事件」の発生により潰えてしまった。
著者はこの章で明治以降の国家と宗教の経緯並びに当時の論点を説明することにより、「『無宗教』は、近代日本の状況にあっては、明らかに身の安全を保障する言葉でもあったのだ」(p110)と結論づけている。
この辺りの歴史的状況について、私には初めて知る知識が多く、新鮮な感覚で読めた。
第4章で、著者は「無宗教」と「平凡」志向、日常主義との密接な関係を具体的な事例を取り上げて論じている。
1つは、信州の天竜川筋でかつて行われていた「サガ流し」行事、2つめは民俗学者柳田国男著『山の人生』の一節、、3つめは田山花袋の小説『重右衛門の最後』で描かれた人間の創り出す悪業、4つめは、きだみのるのムラについての記録作品に記されたムラの有り様、5つめは再び柳田国男著『日本の祭』に記された祭の祭礼化、6つめに曹洞宗の僧侶・鈴木正三著『万民徳用』の教え、これらの読み解きである。これら事例を通じて、日常主義の優位は、「17世紀以来の日本社会に共通した現象であった」(p163)と読み解いている。
最後の第5章は「『無宗教』が日本人の精神生活のなかでどのような位置にあるかをはっきりさせるためにも、墓を無用とする宗教心がどのようなものであるかを見ておこう」(p167)という意図からまとめられている。
著者は、沖縄の宮古島に付属する大神島のウヤガムの信仰を取り上げ、この島の「自然宗教」を紹介している。この島には「本土では希薄になったタマシイの信仰がまだ十分に生きている」(p173)と言う。そして、「この大神島の人々が『無宗教』を標榜する」(p177)と付け加えている。
著者は、「無宗教」という言葉にだまされてはならないということをあらためて強調している。
また、視点を変えて鳥取県青谷町の山根という和紙の里を紹介する。この里の篤信者足利源左を劇的に「回心」した人として、その生き方を紹介する。ここでは伝統の中で宗教心を形成した事例もあることに触れている。「無宗教」を強調しすぎないためということでもあろうと理解した。
「無宗教」という一語の意味は深い。そのことを考えるために役立つ本である。
四半世紀前の本だが、宗教の歴史の長さから受けとめれば、つい先日に出版された本とも言える。普段、深くは考えることのない言葉の意味を見つめ直してみようではないか。
ご一読ありがとうございます。















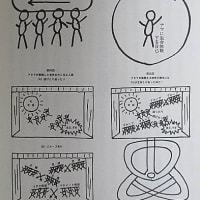




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます