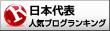「西野ジャパン、よくやった。感動をありがとう」という,日本中の称賛の中、それに抗うようですが、ベルギー戦での西野采配について、ないがしろにできない二つのテーマを、前回の書き込みに続いて指摘しておきます。
前回指摘したのは「相手チームの二枚替え」に対する、変幻自在の手当て。
今回指摘する、もう一つの問題点は、試合の最後の局面における細心の指示です。後半アディショナルタイム、まさにラストプレーに近い時間、本田圭佑選手のFKが相手GK・クルトワにセープされCKになった場面です。
最後のプレーで勝ちに行くということで、吉田麻也選手も昌司源選手もゴール前まであがりました。本田のCKがもっと細心の注意を払ったキックであれば、すんなりホイッスルがなったかも知れません。
ですから本田のCKには、イタリアの世界的名将・カペッロが「私が関係者としてあそこにいたらホンダを殴っている。なんで、あんなボールを入れるんだと」酷評しています。
それは別の問題ですが、やはりベンチからの細心の指示があってしかるべきでしょう。「吉田と昌司は上がらなくていい。上がっちゃダメだぁ」と。
よく「神は細部に宿る」といいます。ギリギリの細かいところにまで研ぎ澄まして対応しないと、得たいものは得られないということなのだと思います。
まして、相手は身体能力、技術ともに日本を大きく凌駕する世界ランキング3位、ここ1年以上無敗のチームです。こちらの戦術・采配に少しでもアバウトなところがあれば、スキを突かれると思って対応しなければなりません。
別に日本が勝てたはずだと思って言うつもりはありません。しかし、この2点、つまりベルギーの二枚替えに対する手当ての問題と、後半アディショナルタイムのCKの指示の問題、これは、明らかに反省点といえると思います。
おそらく、これからも、サッカー関係者の間では、何らかの形で議論のテーマになることでしょう。この書き込みが、その「たたき台」になればと思います。
西野監督自身は、ベルギー戦後の会見で「2点のリードをひっくり返された責任は選手にあるのではなく、明らかに指揮官の責任です。けれども、何が問題だったのか、まだ、わからないところです。時間をかけて考えてみます」と答えていました。
そのとおりだと思います。それは我々のような、よく見える立場の人間のほうが、かえって的確に指摘できることもあるのです。これをよく「岡目八目」といいます。
西野さんも、おそらく、今後じっくり自己分析することで、この二つが「足りなかった部分だ」と吐露する機会が出てくることと思います。
前々回の書き込みでは「何日かあとに代表選手が帰国します。(中略)そして日本中の人たちが「よくやった」「感動をありがとう」と言ってくれるシーンが見られると思います。もう少し、感動の余韻を味わえると思うと、これもまた楽しい限りです。」
と、西野ジャパンを称賛した自分です。つまり、ベルギー戦での采配の問題というのは、そこまで導いた西野監督の功績を何一つ打ち消すものではなく、ある意味「ないものねだり」なのです。
私は、前々回の書き込みで紹介した、夕刊フジのコラム・清水秀彦さんの、プロの指導者としての姿勢に共感していて、今回の検証事項というのは、やはり日本代表が前進していくために、ゆるがせにできない部分は、キッチリと検証する必要があるという立場での意見です。
ですから、日本中は「西野ジャパン、よくやった。感動をありがとう」と沸き立っていて、まったく構わないのですが、しかるべき立場の人たち、特に、今後の監督について議論すべき立場の人たちにとっては、なんとしても克服すべき課題だと言えるのかも知れません。
今日はこれぐらいにして、また。
前回指摘したのは「相手チームの二枚替え」に対する、変幻自在の手当て。
今回指摘する、もう一つの問題点は、試合の最後の局面における細心の指示です。後半アディショナルタイム、まさにラストプレーに近い時間、本田圭佑選手のFKが相手GK・クルトワにセープされCKになった場面です。
最後のプレーで勝ちに行くということで、吉田麻也選手も昌司源選手もゴール前まであがりました。本田のCKがもっと細心の注意を払ったキックであれば、すんなりホイッスルがなったかも知れません。
ですから本田のCKには、イタリアの世界的名将・カペッロが「私が関係者としてあそこにいたらホンダを殴っている。なんで、あんなボールを入れるんだと」酷評しています。
それは別の問題ですが、やはりベンチからの細心の指示があってしかるべきでしょう。「吉田と昌司は上がらなくていい。上がっちゃダメだぁ」と。
よく「神は細部に宿る」といいます。ギリギリの細かいところにまで研ぎ澄まして対応しないと、得たいものは得られないということなのだと思います。
まして、相手は身体能力、技術ともに日本を大きく凌駕する世界ランキング3位、ここ1年以上無敗のチームです。こちらの戦術・采配に少しでもアバウトなところがあれば、スキを突かれると思って対応しなければなりません。
別に日本が勝てたはずだと思って言うつもりはありません。しかし、この2点、つまりベルギーの二枚替えに対する手当ての問題と、後半アディショナルタイムのCKの指示の問題、これは、明らかに反省点といえると思います。
おそらく、これからも、サッカー関係者の間では、何らかの形で議論のテーマになることでしょう。この書き込みが、その「たたき台」になればと思います。
西野監督自身は、ベルギー戦後の会見で「2点のリードをひっくり返された責任は選手にあるのではなく、明らかに指揮官の責任です。けれども、何が問題だったのか、まだ、わからないところです。時間をかけて考えてみます」と答えていました。
そのとおりだと思います。それは我々のような、よく見える立場の人間のほうが、かえって的確に指摘できることもあるのです。これをよく「岡目八目」といいます。
西野さんも、おそらく、今後じっくり自己分析することで、この二つが「足りなかった部分だ」と吐露する機会が出てくることと思います。
前々回の書き込みでは「何日かあとに代表選手が帰国します。(中略)そして日本中の人たちが「よくやった」「感動をありがとう」と言ってくれるシーンが見られると思います。もう少し、感動の余韻を味わえると思うと、これもまた楽しい限りです。」
と、西野ジャパンを称賛した自分です。つまり、ベルギー戦での采配の問題というのは、そこまで導いた西野監督の功績を何一つ打ち消すものではなく、ある意味「ないものねだり」なのです。
私は、前々回の書き込みで紹介した、夕刊フジのコラム・清水秀彦さんの、プロの指導者としての姿勢に共感していて、今回の検証事項というのは、やはり日本代表が前進していくために、ゆるがせにできない部分は、キッチリと検証する必要があるという立場での意見です。
ですから、日本中は「西野ジャパン、よくやった。感動をありがとう」と沸き立っていて、まったく構わないのですが、しかるべき立場の人たち、特に、今後の監督について議論すべき立場の人たちにとっては、なんとしても克服すべき課題だと言えるのかも知れません。
今日はこれぐらいにして、また。