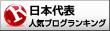前回の(その1)では、21歳にして日本代表で「別格の存在」となった中田英寿選手の足どりを振り返っておきました。
2006年6月22日、ドルトムントのホームスタジアムでのブラジル戦の終了ホイッスルが鳴ると、ピッチ中央に仰向けに横たわり、まるで精も根も尽き果てたかのように選手生活に幕を閉じた、中田英寿選手。
1993年、16歳の時から日本代表のユニフォームを身にまとって国際舞台に立ち続け、弱冠21歳にして日本代表の「別格の存在」となって9年のも長きにわたって日本代表を牽引してきた中田英寿選手。
中田英寿選手は、何故、それほど若くして「別格の存在」となり得て、何故、9年のも長きにわたって牽引し続けてこれたのでしょうか?
そのことに思う時、中田英寿選手の「心・技・体」のすべてが、まさに当時の代表選手たちに比べて1歩も2歩も先を行く高いレベルにあったからではないかと感じました。
つまり中田英寿選手は、早くから自らの「心・技・体」を鍛錬し続け、20歳代になろうかという頃には、そのすべてを高いレベルまで鍛え上げたが故、若くして「別格の存在」となり得たのであり、その後も「心・技・体」の鍛錬を怠らなかったが故、長きにわたって日本代表を牽引できたのだと思うのです。
今回は「早くから「心・技・体」を鍛錬し続けた中田英寿選手」について記録に留めておきたいと思います。それが中田英寿選手のことを後世に語り伝える上で、欠かせないと確信しています。
まず、その「心(しん)」。
中田英寿選手はメンタル面で、当時の他の選手より抜きん出ている点がいくつかあります。
一つは平常心というか、どんなことにも動じない、感情の起伏の少ない、強い精神力です。前回も書きましたが「W杯なんて一つの大会に過ぎない」と捉えるマインド自体が驚異的です。サッカー選手なら最高峰の舞台でプレーすることは夢でありも目標であるのが一般的な捉え方ですが、中田英寿選手はそうではありません。
そもそも、中田英寿選手は「「サッカーは人生のすべて」といった考え方でサッカーをやっているわけではない」と常々話している選手です。
たまたま、今のこの時期、サッカーでさまざまな経験を積めるし、自分も成長できるからサッカーをやっているだけ、といったフラットな気持ちでサッカーを捉えている人です。
そのことは平常心として肩に力の入らない精神状態をもたらしますが、反面、こだわりのない淡白な気持ちにも陥りやすいものです。シドニー五輪のベスト4を賭けたアメリカ戦、日韓W杯のベスト8を賭けたトルコ戦、中田英寿選手も悔しかったには違いないでしょうけれど、他の選手ほど悔しい気持ちには見えませんでした。
かと言って、すべての場面で淡々と、淡白にプレーする選手かと言えば違います。ジョホールバルの奇跡を生んだ獅子奮迅のプレーぶり、衝撃的なデビューを飾ったセリエA開幕戦のユベントス戦のプレーぶり、2001年コンフェデ杯準決勝・土砂降りの豪州戦で見せた地を這うようなFK、さらにはASローマがシーズン制覇を決めたユベントス戦で途中出場ながら1ゴール1アシストをあげたプレーなど、ここ一番に持てる力を出し切る集中力も、どんなことにも動じない平常心と強い精神力の延長上にあるメンタルだと思います。
どんなことにも動じない平常心、強い精神力は、特に対外的な発信の場面でも顕著です。
中田英寿選手は、実はとてもフレンドリーな人だということを、少しでも接点のある人ならば口を揃えて言います。
そのフレンドリーさは、身近な人だけに示されるものではなく、一国の首相などを相手にした場合にも、動じない平常心と精神力に支えられて発揮されます。
セリエA・ペルージャでプレーしていた時、欧州歴訪中の小渕恵三首相がイタリアを訪問しました。
その時、小渕首相とイタリアの首相との昼食会に、イタリアで活躍する日本人として中田英寿選手が単独で招待されました。
普通であれば、一国の首脳の昼食会に単独で出席するなど、ビビる以外の何物でもない体験でしょうけれど、中田英寿選手はまったく違いました。
臆することなく堂々と二人の首脳との昼食会をこなしたのです。彼がいかに動じない平常心と精神力を持った人かを物語るエピソードです。
けれども、多くのメディアを通じて発信される自分のことや、日本代表に関する喧騒にも似た報道に対しては、常にクールにというか、フレンドリーさとは無縁の、時として冷淡と思えるほど起伏の少ない姿勢を貫きます。
その姿勢は、メディア側から見ると「この年代で、そういう態度をとり続けるのは考えられない」とばかり、時にはバッシングの対象にしたり、時には記事の中で皮肉たっぷりな見出しをつけたりしてきました。
例えば、こういうことがありました。中田英寿選手は「ピッチの上では対等」という考え方が特に強い選手で、日本代表での練習でも試合でも、必要なコミュニケーションをとる際「さん」づけなどの敬称をつけることは決してしません。
これは試合中の瞬時、瞬時の状況の中で必要なことを伝えるのに、いちいち長い名前を呼んだりしない、スポーツ競技なら常識でもあり、ピッチ上では「ヒデ !」「カズ !」「ナナ !」などと呼び合います。
ところがキャプテン・井原正巳選手は「イハラ」と呼ばれていたのでしょう。ある時、中田英寿選手が大声で「イハラーー!」と指示を出している姿と音声がテレビカメラに捉えられました。マスコミはすぐ飛びつきました。
決して否定的な論調ではないにしても「中田選手は井原正巳選手を堂々と呼び捨てにして指示していました」というコメントがつけば「へぇ~、中田選手は平気でそういう言葉遣いをする人間なんだ」という印象をもたれる可能性は十分あるわけです。
ですから、中田英寿選手の胸の内、心の内を知り得ない一般人の多くがメディアの論調を真に受けて中田英寿選手のイメージを抱いていました。
そのことで、中田英寿選手がずいぶん損をしたのではないかとも思いますが、中田英寿選手は、それに頓着することなく「どうせメディアが勝手に作っているだけだから」と受け流してきました。
20歳代前半の青年が、メディアという巨大な力に対しても、なんら怯むことなく、臆することなく堂々とした姿勢を取り続けていたというのは、驚異的であり、他の同世代の選手たちと比べて、はるかに抜きんでたマインド、精神力の持ち主だということを示しています。
しかし、それほどに強靭な精神力の持ち主の中田英寿選手も、全国紙のインタビュー記事が発端となって、いわゆる右翼団体からの執拗な糾弾行為にさらされたことがありました。当時、若干21歳の青年に対するものです。
彼がいかに強靭とはいえ、糾弾行為から身の安全を確保するために取らざるを得なかった日々は、どれほど恐怖だったことか。事情を知らないメディアなどは、いい加減なことを書きたてました。しかし、彼は医師の診断で「極度のストレスが原因」と言われるほどの症状を呈するほどに追い詰められていました。
この時、中田英寿選手はフランスW杯のため日本を離れることができたため、致命的なことにならずに済みましたが、これが日本から離れられない状況がもっと続いたならと考えると、暗澹たるものがあります。
この「どんなことにも動じない平常心、強い精神力」は「非常に明晰な頭脳」と合わせ持っている、中田英寿選手の「資質」にほかなりませんが、それは、日本代表チームの一員として他の選手たちと同じ目線に立とうとする場合、自分の精神的強さ、頭脳明晰さがあまりにも抜きん出ているが故に、かなり他の選手たちと相和するのが難しいというハンディを背負うことになります。
チームの中で若い方に属する20歳代半ばまでは、自分がマイペースで他の選手たちとつるむことがなくても、せいぜい「変わったヤツ」と見られるだけで、そのハンディはさほど表面化しませんでしたが、20歳代後半、特に自分が自他ともにチームリーダーとして見られる、2006年ドイツW杯に向けたチームの中では、その強い精神力が邪魔をして、チームメイトから反発を買うことになっていきます。
すべからく団体競技のチームは、いわゆる「チームとしてまとまり」「チーム全員がお互いに助け合って」勝利にまい進することが基本であり、強いチームというのは「まとまり」や「互いに助け合う」マインドが他のチームより勝っているのが普通です。
そんな中で、リーダー格の選手に対する他の選手の意識が違う方向を向いていれば、いわゆるベクトルが合わないわけで「まとまり」や「互いに助け合う」マインドが他のチームより勝るのは難しくなります。
中田英寿選手の「心」の部分で唯一、残念なのは、そのあまりに強い精神力、平常心に加え、人とつるむことを好まないマイペースな性格が、チームの他の選手たちを遠ざける結果となったことです。
中田英寿選手は平塚に入団した理由の一つに「タテ社会ではないみたいだから」というチーム内の風通しのよさをあげ「ピッチの上では皆、対等」という考え方を貫いてきました。しかし、年月を経て、自分がチームの中で先輩と呼ばれる立場になり、若い選手たちから「こうして欲しい」と要求されたり「自分たちはこう思う」と意見される立場になった時、自分が若い時に望んでいた「タテ社会ではない関係」とか「ピッチの上では対等」といった考え方で、後輩選手たちにも接したかどうか・・・。
逆に「ヒデさんはタテ社会の先輩」であり「ヒデさんの前では対等たり得ない」と思われるようなふるまいになっていなかったのかどうか、もし、そうだとしたら、若き日に先輩たちに対して行なっていたふるまいがブーメランのように自分に返ってきたのではないかとすら思ってしまいます。
それでも中田英寿選手は、彼なりに全力を尽くしています。2006年ドイツW杯の第一戦・豪州戦に逆転負けした後、次戦クロアチア戦を3日後に控えた夜、中田英寿選手は選手だけの夕食会を提案して実現させています。
日本代表の歴史には、選手だけのミーティングや食事会で徹底的に議論を戦わせたことがターニングポイントとなって、チームが劇的にまとまり快進撃を続けたケースが幾つかあります。
中田英寿選手もそうした「チームとしてのまとまり」を取り戻したい一心で提案して実現した夕食会だったに違いありません。
でも結局それは夕食会以上のものにはなりませんでした。中田英寿選手と他のすべての選手、その間に生じた溝は埋まることなく大会は終わりました。
ブラジル戦終了後、ピッチ中央に仰向けに横たわった中田英寿選手のもとに近づく選手が一人としていなかったという現実が、その溝の深さを物語っていました。
これは「ないものねだり」なのかも知れませんが、もし中田英寿選手が、その食事会で、自分の思いをすべてさらけ出し「まとまって戦いたい」「そのために自分がどうすればいいか教えて欲しい」といった趣旨のスピーチでもしていたらと思います。
中田英寿選手ではなく「中田英寿氏」となった今、聡明な氏のことですから、いろいろと思うところはあると思います。けれども、当時の自分の考え方やふるまいを、決して後悔することはないと思います。
中田英寿選手が自ら発信したインターネットでの記録は、「nakata.net」という書籍になっています。欧州のサッカーシーズンである秋から春まで毎にまとめられているのではないかと思いますが、05-06、すなわち現役生活最後となったシーズンの本を読んでみますと、2005年11月16日に国立競技場で行われたアンゴラとの試合について、とても興味深い記述があります。
少し引用します。「実は今回ほど、やっていて虚しさや寂しさを感じた試合も初めてだと思う。
特に、後半の途中、試合中なのにもかかわらず、まるで俺自身が第三者かのように試合を感じた瞬間があった。
その時、観客席をふっと見上げたら、両ゴール裏のサポーター席を除いた正面スタンドとバックスタンドは、まるで誰も試合を楽しんでいないかのように静けさが漂っていた。
そして、その視線をグラウンド上に落としてみた。そしたら案の定、ピッチの上にも同じような静けさが漂っていた。試合中にもかかわらず・・・・。
それを見た瞬間、恥ずかしながら俺はそのピッチ上の状況を打開する術が、思い浮かばなかったし、何のために試合をやっているのか混乱してしまった。そして、他の選手たちは一体どういう気持ちでやっているんだろうか、何を目的でサッカーをやっているんだろうか、と考えてしまった。
チームとしてこの試合で何をやりたいのか、それぞれ個人として何をやりたいのかが見えなかったんだよね。
〈中略〉
日本代表が今のレベルからもう一つ上のレベルに行くには、相手が強い時や跡が無いような厳しい状態の時に、出来るサッカーを常時やる "集中力と精神面の強さ"を手に入れるだけでいいと思う。
それは、本当に個人個人の気持ち次第。
味方に要求できる強さ、味方を信じて走れる強さ、味方を助ける声を出せる強さ、そんなちょっとした強さが今の日本代表に一番欠けている事だと思う。」
以上が引用部分ですが、この日の記述について編集者のコメントだと思いますが、「翌年7月3日のメールには『半年前に引退を決意した』と綴られているが、引退決意は実はこのころから徐々に本格的なものに固まりつつあったのかもしれない」というコメントがついています。
今回のテーマである「21歳にして日本代表の別格の存在となった中田英寿選手の「心・技・体」」のうち「心」の部分は、そのあまりに強靭な精神力、他を寄せ付けないマイペースな性格ゆえに、自分のサッカー人生の集大成にしたかった最後の大会にきて、チームメートの共感を得られないという破綻をきたしてしまいました。
引用した記述にもあるように、中田英寿選手が指摘している「日本代表に欠けている点」は、まさに「もっとも」なことです。ですから、何年経過しようが、後年の中田英寿氏は、何一つ悔いがないわけです。
当時も、このことに異論を挟む代表選手はいなかったと思います。
にもかかわらず、実際は、他の選手たちに、その思いは伝わりませんでした。
中田英寿選手も、さきに引用した日の最後にこう記述しています。
「ただ、これらはすべて他人が助けてくれる事ではなくて、自分で変えるしかないのだけれど・・。」
つまり、中田選手の思いが伝わらなくても、それは仕方のないこと、各自が自分で変えるしかないことなので、変わらなければ仕方のないこと、と思い定めていたようで、あとは自分が現役を辞めることしか選択の余地がないと心に決めたのだと思います。
さて、中田英寿選手の「心」の部分の大きな特徴として「どんなことにも動じない平常心、強い精神力」について述べてきましたが、もう一つの特徴は「非常に明晰な頭脳」です。その具体的な要素として「語学力」「研究心」「先見性」があげられます。
まず「語学力」。私たちが舌を巻いたのは、セリエA・ペルージャに移籍して現地で開いた最初の記者会見です。現地の記者から「何かイタリア語で一言」と問われ、即座に流暢なイタリア語で「もうお腹がすいたので勘弁してよ、パスタでも食べにいきたいな」と返したのです。
21歳のサッカー青年が、実は大変な勉強家で、イタリア語会見に耐えられるだけのボキャブラリーを習得していたことを、まざまざと知った場面でした。
「研究心」でも、数々のエピソードがあります。中学時代に中田英寿選手にサッカーを指導した方は、何かを教えた時、他の選手からはさほど質問が出なくとも中田英寿選手だけは、先生があきれるほど質問してきたといいます。自分が納得いくまで探求する、その姿勢も彼の持つ資質です。
その「自分が納得いくまで探求する」姿勢は、Jリーグ入りした時、そして欧州挑戦を決めた時のクラブ選びでも如何なく発揮されました。
山梨・韮崎高校からJリーグ入りする際、(その1)でもご紹介したとおり当時の12クラブ中、11クラブから誘いを受けるという高評価の中、横浜M、横浜F、ベルマーレ平塚の練習にそれぞれ参加しています。
中田英寿選手は、選ぶ基準を明確に持っていました。それは「自分が活きるポジションですぐ試合に出られる可能性があるクラプ」というものでした。その結果、平塚を選んだわけです。「タテ社会ではないみたいだから」つまり、先輩の言うこと、目上の人が言うことが絶対みたいなチームではなさそうというのも中田英寿選手の判断の決め手だったようです。
そして欧州挑戦を決めた時の選択基準もほぼ同じでした。当時、欧州のビッグクラブといわれるチームからのオファーも幾つかありました。
サッカー選手であればビッグクラブの一員になることは、W杯でプレーすることと同様、夢であり目標です。しかし、中田選手は「ビッグクラブの一員になっても、すぐ試合に出られなければ意味がない」という考えのもと、例え小さなクラブでも、自分をキチンと評価してくれて試合に出られる可能性の高いクラブ、ということでセリエAに昇格したばかりのペルージャを選んだのです。
このように、自分がキチンとして基準を持ち、それに合うクラブを納得いくまで調べて、確認して、その上で決めるという確固たる姿勢を、若くして貫いたことが、彼の成功の大きな要因だと思います。
選ぶクラブがビッグクラブで「常勝軍団」であることなど、彼にとっては不必要だったようですが、それは逆に、そういうクラブの一員が持つ「勝者のメンタリティ」を涵養する機会を得られなかったのではないかという、ある意味の「悲劇」でもあったのではないかと当ブログは指摘しておきたいと思います。
日本に来た大物外国人選手、あるいは指導者の中で、ジーコやドゥンガ、あるいはベンゲルといった人たちはサッカープレーヤーの持つべき大切なマインドに「勝者のメンタリティー」をあげています。
「勝者のメンタリティー」を分かりやすく言えば、それは「負け犬根性を持つな」「勝負には絶対勝つんだ」というマインドをチームを構成するすべての選手が共有していなければ、試合には勝てないんだ、ということのようです。
そして、「勝利」を重ね続けているビッグクラブ、常勝軍団と呼ばれるクラブには、長い間に培われてきた、その「勝者のメンタリティー」が備わっており、どのクラブも、そこを目指していくべきだ、ということのようです。
中田英寿選手が選んだクラブは、対照的に、まだ「勝者のメンタリティー」が備わっているとは言い難いクラブだったと思います。
そこで自分が常に試合に出続け、スキルと経験を積むことはできたと思いますが、チームがタイトルを取るとか、王者と呼ばれることはありませんでした。
「どんなことにも動じない、感情の起伏の少ない平常心」のところでも書きましたが、シドニー五輪のベスト4を賭けたアメリカ戦、日韓W杯のベスト8を賭けたトルコ戦、中田英寿選手も悔しかったには違いないでしょうけれど、他の選手ほど悔しい気持ちには見えなかったのは、この「勝者のメンタリティー」と無縁ではないのではないか、そう思えてならないのです。
中田英寿選手の持つメンタリティーの3つ目の要素「先見性」で特筆すべきは、当時のアスリートとして初めてといえる「インターネットを通じた独自の情報発信を始めた」という点です。
自分の公式サイトを開設して、情報発信するというスタイルはサッカー選手のみならず、当時の日本のスポーツ界を見渡しても最初の取り組みだったのです。
それは、メディアが自分のことを取り上げる時、まったく自分を理解していないかのような内容であることに愛想をつかし、メディアを頼った情報発信に見切りをつけて始めたことでもありますが、それを20歳代前半にして始めてしまう先見性は目をみはるばかりです。彼の不断の研究心がもたらしたものでもあります。
こうして自らが情報発信するようになってから、中田英寿選手のメディアへの露出、特にテレビ出演は明らかに変化しました。
まず、自らがプロデュースした番組を2000年7月からCS(スカイパーフェクTV!)チャンネルに開設しました。「nakata.net TV」と題して、月1回ペースで自身の近況報告やプライベートなことを発信するインタビュー、あるいは親しい人との対談などの内容で、さしずめ「元祖・個人チャンネル開局=ユーチューバー」といったところです。
ですから、地上波のテレビ出演の必要がなくなった形となり、地上波出演をほとんど受け付けない時期もありましたが、次第に信頼のおけるキャスター、例えばテレ朝・ニュースステーションの久米宏氏などの番組、あるいは作家の村上龍氏がインタビュアーを務めるような番組には、ある程度の間隔で定期的に出演するという向き合い方に変えていったようです。
それ以外の、いわゆるバラエティ番組やワイドショー系の番組には一切出ないという姿勢を貫いたようです。
「先見性」については、もう一つ特筆すべき点があります。
それは彼が「サッカー選手である自分という存在が、一つの知的財産である」という認識を持っていたという点です。
中田英寿選手があまりファンとの写真撮影やサインに応じないのは有名でしたが、これも彼が気難しいからとか、面倒くさがり屋からと言った理由ではなく、それらが安易に使用されたりすることを嫌ったからと言われています。
こうした「肖像権の無断使用」など、知的財産権を侵害する行為に対する高い防衛意識をもって、考えをはっきりと主張したことにより、他の多くの選手、他のスポーツのアスリートたちも、その重要性を認識するようになったという点でも、彼は先駆者であり「先見性」を持った選手だったのです。
次に「技(ぎ)」について見ていきたいと思います。
中田英寿選手が16歳でU-17世界選手権の舞台にたった当時、彼のピッチにおける主戦場は、サイドハーフというかウィングにあたるポジションでした。
そこで彼は、国際舞台でも十分通用するスピード(走力)を披露します。ドリブルやクロスの精度といった技の部分も、大会までの長期間にわたる合宿や自主練習でかなり向上しています。
次に彼は、ベルマーレ平塚で、いわゆるトップ下のポジションに求められるスキルを磨きます。広い視野を確保するための姿勢をとり、常に周りの状況を首を細かく振りながら確認するプレースタイル、そこで得た状況判断から繰り出されるスルーパス。
中田英寿選手の凄いところは、常に動きながらも、そうした周りの確認、状況判断を怠らずに続け、その精度をあげていこうとする向上心です。
中田英寿選手が繰り出すスルーパスは「キラーパス」と呼ばれます。平塚時代に出す彼のパスは、決してJリーグ仕様の、緩いものではなく、世界のトップリーグレベルの試合で求められる国際仕様の高速パスなのです。
それは、いずれ自分が海外でプレーした際に通用するパス精度を磨くという意味と、Jリーグや日本代表も、これぐらいの高速パスを普通に繰ることができなければ、国際舞台では通用しないというメッセージがこもったものでした。
スピードの遅い日本人選手の速度に合わせたパスを出すという選択はしませんので、その高速パスが、もし通れば、まさに相手を仕留めることができるキラーパスなのですが、受け手がなかなか追いついてくれない場面が出てきます。
それでも、受け手が誰であろうと「このパススピードが世界基準なんだから、受けてくれ」と言わんばかりのキラーバスが繰り出されます。
平塚でも日本代表でも、受け手の選手からは泣き言が出されましたが、その一貫したプレースタイルはペルージャ移籍以降の海外での経験に活きていきます。
このスルーバスについては、よく相手のスピードに合わせた、ほど良いパスを繰り出す選手と比較されることがあります。
代表的なのは小野伸二選手です。彼が繰り出すパスは、相手の欲しいところにピタリを収まることが多く、それは「エンジェルパス」とか「ベルベットパス」と評される、相手に優しいパスということだと思います。
どちらが良い悪いという見方はまったく無意味です。けれども、大きな違いが一つあります。パス一つでチームが盛り上がり、まとまって勝利を目指せる力を与えるのはどちらか、と言えば、これは小野伸二選手のパスだと思います。
「キラーパス」は相手を一発で仕留める効果も持ちますが、追いつけなかった味方の士気を削ぐリスクもはらみます。それは、チームのまとまり感、盛り上がり感の強さにも影響を与えます。
1999年ワールドユース選手権で、小野伸二選手が果たした役割は、まさに自分のバスで見方を盛り上げ、まとまって勝利を目指す力を与えたものだったと思います。
中田英寿選手の「キラーパス」を語る時、それが日本代表や所属クラブを国際基準に引き上げるためのメッセージを込めたパスではあったと思いますが、目の前の試合、目の前の大会を勝ち進む手段として、果たしてどうだったのでしょう。
特に2006年ドイツW杯の日本代表チームが、1戦毎にチームとしての「まとまり」を失っていったのではないかと思われる様子を見た時、イレブンの思いが「司令塔の中田英寿選手を中心に戦い抜くぞ」という結束力とは縁遠いものになっていたのではないでしょうか。その見方は穿ち過ぎでしょうか。
次に「プレースキック」に触れたいと思います。
中田英寿選手が「日本代表の別格の存在」になる1997年夏あたりまで、彼がプレースキックを任されることは、さほど多くなかったと思います。
けれども、日本代表でも、ペルージャでも、彼の存在が大きくなるにつれ、プレースキックを任される場面が増え、その経験をもとに精度も少しづつあげていきます。
のちに日本代表では中村俊輔選手と言う稀代のプレースキッカーが現れたことから、中田英寿選手はあっさりと、彼にその座を譲ります。
最後に「シュート」の技についても触れておきたいと思います。
中田英寿選手は、もともとFWポジションが長い選手ではありませんから、そのシュートが注目される機会は少なかったのですが「日本代表の別格の存在」になってからは、常に得点に絡むことが求められ、また海外でプレーを始めてからは、攻撃陣であれば点に絡まなければ失格とさえ評価される厳しい環境の中で、得点に対する意識を相当高めたようです。
ベルマーレ平塚でプロ選手としてのキャリアを始めた頃、同僚で大先輩のGK・小島伸幸選手が、中田英寿選手の練習における意識の高さに舌を巻いたそうです。
中田英寿選手が練習後、自主練習の形で誰もいないゴールマウスに向かってシュート練習をしていたそうです。ところが、ほとんど枠に飛ばないことから小島選手が「こいつ、へたくそだなぁ」とあきれていたそうです。すると中田英寿選手のシュート練習につきあっていたコーチも、小島選手と同じ思いで怒声を浴びせたそうです。
すると、中田英寿選手は「何言ってんですか、試合中はGKがいるんですよ、それを考えたらポストの内側20センチじゃなかったら決まるわけないでしょ」と言い返したそうです。
それを聴いた小島選手は「とことん、思い知らされましたよ、中田英寿ってのは、ホントに目標設定が高い男なんだなぁって」
そのような意識の高い練習の積み重ねの延長線上に、オーバーヘッドキックでゴールを決めて見せたり、強烈なミドルシュートでゴールを奪うなどの結果があり、まさに万能型のゴールゲッターに成長しています。
このように「ドリブル」「パス」「プレースキック」「シュート」のどれをとっても非常に高いレベルまで自分のスキルを磨き、上達していったのは、彼の「あくなき向上心」があったからだと思います。
16~17歳の頃は、走力と身体の強さだけが国際レベルでも通用する選手でしたが、その後の練習と研究で、「視野の広さと一瞬の状況判断」「ドリブル」「パス」「プレースキック」「シュート」どの技も国際レベルまで引き上げていったことがわかります。
チームの司令塔としての役割も、これらのスキルが高まるとともに強まったと言えます。まだ10代の頃、チームの司令塔は常に別の選手が務めていました。それが、21歳になる頃には、クラブでも日本代表でも、チームの司令塔と言えば彼のことを指すようになりました。
日本代表での中田英寿選手が、まさに司令塔としての地位を確立したことを示す象徴的な記事があります。2000年1月1日付のスポーツ紙各紙は、この年のスポーツの中心的なイベントであるシドニー五輪に関する特集を組みました。
その中で「スポーツ報知」紙は、サッカー五輪代表が中田英寿選手に率いられ32年ぶりのメダル獲得が期待できるとして「中田を感じる 中田で変わる 中田が勇気に」という見出しを打ちました。

彼が五輪代表の中心選手として、いかに圧倒的存在であるかをよく表現している見出しだと思います。
「司令塔」は、彼が飽くなき努力を積み重ねて自分の「技」を磨き、その結果に得たポジションです。
最後に「体(たい)」について見ていきます。
すでに書きましたが、1993年にU-17世界選手権に出場した日本代表は、その2年前から強化が始まっていますが、当時、中学2年生だった中田英寿選手は、関東選抜の一員に選ばれています。そこから日本代表候補の選考が行われたわけですが、当初、彼を送り出した指導者の方は、日本代表候補に残るのは難しいのではないかと感じていたそうです。
ところが、日本代表候補にピックアップされたので、指導者の方は理由をたずねたそうです。その答えは「確かに彼は技術的には不十分ですが、走力、敏捷性などのフィジカル面で秀でており国際試合で通用するだけの素質を持っていますので」というものでした。
当時まだ中学生でしたから体は細かったのですが、走るスピードと、身のこなしの素早いムチのような身体を持っていたようです。
その身体に、少しづつ筋肉をつけ、当たり負けしない体幹を鍛え、日本代表での国際試合でも、海外クラブでの試合でも、少々では倒れない強靭な身体を作っていったわけです。
中田英寿選手の「体(たい)」を語る上でもう一つ大切なことは、長期離脱を強いられるような大きなアクシデントに見舞われることがなかった点です。
それは持って生まれた骨格の強靭さと、選手生活の中での徹底した自己管理、ケアの賜物なのですが、実は食生活という点では、やや苦労したようです。
実は大変な野菜嫌いで通っていて、頑なに野菜を食べない理由としては、「野菜を食べて得られるものより嫌いなものを無理して食べるストレスの方が影響が大きい」と話してしたそうです。
身体づくりの上でハンディとなったことと言えばそれぐらいで、2004年春あたりまでは、海外クラブ在籍中も含めて、長期離脱せずに日本代表を支え続けた「体」は、驚異的ですらあります。
サッカー選手にケガはつきものと言われるほど、ケガのリスクを抱えながらプレーすることになるわけですが、中田英寿選手の凄いところは「技(ぎ)」のところでも触れましたが、常に相手の状況を把握し続けながらプレーすることで、後方からのタックルや激しい接触プレーなどの不測の事態になるべく巻き込まれないようにしてきたことです。
それも中田英寿選手を「日本代表の別格の存在」たらしめ、それを長きにわたり維持し続けられた大きな要因だと思います。
ケガには強い中田英寿選手も勝てないアクシデントはありました。それはサッカー選手の職業病とも言われている、通称・恥骨炎になったことです。
2003~2004年シーズン終盤、2004年春あたり、ボローニャ在籍当時に発症したそうですが、痛みをおしてシーズンを戦いボローニャの1部残留に貢献しました。
シーズン終了後のオフ、2ケ月間は治療に専念して2004~2005年シーズンはフィオレンティーナに移籍、新シーズン当初から復帰しましたが、オフのトレーニング不足がたたりパフォーマンスが上がらず、日本代表の招集も約1年間にわたり見送られました。
2005年3月、約1年ぶりに日本代表に召集されましたが、この日本代表での1年のブランクは、実は、中田英寿選手抜きで、ドイツW杯アジア予選を戦ってきた他の選手たちとの心理的な距離を広げてしまった不幸な1年間だったようです。
特に日本代表ジーコ監督が、あたかも中田英寿選手にポジションを用意してあげるかのような布陣をとったことが火に油を注ぐことになったようです。
恥骨炎が癒えてまもない中田英寿選手のパフォーマンスが、目に見えて低調なのを見た他の選手たちは、不満を募らせていき、以前のように別格の存在としては見ず、一人だけ浮いている存在として見る選手が増えてしまいました。
「中田英寿選手の「心・技・体」」の「心(しん)」の部分でも書きましたが、自分のサッカー人生の集大成にしたかった最後の大会、2006年ドイツW杯において、チームメートの共感を得られないという破綻をきたしてしまいましたが、その破綻を招くことになったのが、2004年春から2005年3月までの恥骨炎という「体」の異変による日本代表からの離脱でした。
ドイツW杯グループリーグ敗退を見届けて、あっけなく選手生活の幕を閉じた中田英寿選手ですが、「心・技・体」のすべてをハイレベルな状態に鍛え上げ、維持し続けて10歳代後半から20歳代の長きにわたり疾走し続けたことを思えば、完全燃焼して精魂尽き果ててしまっても、何ら不思議ではないことなのかも知れません。
しかし、最後の最後は、不幸な終わり方だったなぁと思います。ドルトムントの空を見上げて「これが最後の試合だ」と中田英寿選手が思っていたことを、チームメートの誰一人知らずにいたのですから。
選手時代の中田英寿選手は、一般受けするようなリップサービスや愛想のいいふるまいなどを意識的に避けてきたようにも思います。
本来はとてもフレンドリーなオープンな人柄でも、メディアからの自己防衛本能や、平静で動じない性格もあって、一般のサッカーファンから見た場合、例えばカズ選手やゴン・中山雅史選手などに対して抱く選手像とは対極にあるタイプの選手に映ったことでしょう。
それでも「何もそこまでしなくても」と思うようなエピソードもあります。
1997年11月、マレーシア・ジョホールバルの奇跡を起こした試合後、ピッチ上ではお祭り騒ぎのようにしてイレブンが集合写真やTVカメラ撮影に応じていますが、なぜか中田英寿選手だけは、写真やTVカメラに映りこもうとせず、ひたすら最後方をウロウロしているように見える姿が残っています。
まさに「何もそこまでしなくても」と思うような行動ですが、一種の照れ隠しだったのかも知れません。この試合のヒーローが中田英寿選手であることは誰の目にも明らかなのですが、それ故、彼は「そんなに自分をクローズアップしないでください」という気持ちになっていたのではないかと思います。
一方で、自分が得点を決めた時はなおのこと、味方の得点や勝利の瞬間にもクールに、控えめにしか喜びを表さない中田英寿選手にも、長い選手生活の中で、こんなに喜びを爆発させたことがあるんだ、という場面のスポーツ紙の記事もあります。
2002年W杯のグループリーグ第2戦、ロシアとの試合でゴールを決めた稲本選手を祝福するため、多くの選手が飛びつくようにして輪を作りましたが、その輪に中田英寿選手も喜びを爆発させながら、少し遅れ気味ではありますが、飛びついた場面です。
このような表情の中田英寿選手は本当に珍しく、普段はどう考えても控えめにしか喜びを表に出さない選手ですが、この場面を見ると、中田英寿選手も「喜びを爆発させることがある」普通の選手だとわかって、グンと親しみが増します。
今後、サッカー日本代表の中心となるような選手で、中田英寿選手のようなタイプの選手が、また現れるだろうかと自問した場合、なかなか現れる予感がしないタイプであるように思います。
おそらく、この時代だからこそ出現したカリスマではないかと思います。
理由は二つ、この1993年から2006年までの時代が日本サッカーが国際舞台に駆け上がる時代であり、中田英寿選手はまさに、その時代と歩調を合わせて成長した選手だからというのが一つ。
もう一つは、一般のサッカーファンに伝わる中田英寿選手のイメージがメディアを通すことによって少し歪められることがあり、それを嫌った中田英寿選手が、いち早く自らの手で情報発信するというアスリートとしては初めての取り組みをした選手であること、です。
これは、まさに時代的な背景が生んだ選手ということであり、今後の日本代表選手には、むしろ生まれにくい選手だからかも知れません。
しかし、中田英寿選手ほど若くして、しかも長期にわたり「日本代表における別格の存在」であったことは、Jリーグ以降の日本サッカーの30年における輝かしい偉業であることも事実です。
中田英寿選手が世界最高峰と言われるイタリアリーグで、堂々たるプレーを見せ続け、その割には大言壮語を吐くでもなく、終始、謙虚にふるまい続けたことにより、日本人プレーヤーに対する世界の評価を格段にあげてくれて、その後の多くの日本人選手の海外挑戦の道を拓いた功績は、称賛して余りあります。
この神秘的なカリスマのことは、これからも長きにわたって、いろいろな角度、切り口から語られていくと思いますし、すでに選手生活を終えて久しい中田英寿氏が、それら一つ一つに反応することは、これからもないと思います。
なぜなら中田英寿氏自身が、若い頃よく「「サッカーは人生のすべて」といった考え方でサッカーをやっているわけではない」と話していたものの、やはり14年間のサッカー人生から得たものも大きく、現在は「FIFA親善大使」を務めるほど、世界のサッカー界から見ても著名な存在になったことからも窺えるように、いろいろな角度、切り口から語られるだけの価値のある存在になっているからです。
当ブログも含めて私たちが意を用いなければならないのは、中田英寿選手を語る場合、それが例えば間違っても「名誉棄損」にあたるようなこととか「肖像権の無断使用」にあたるようなことなどについては、細心の注意を払わなければならないということです。すなわち「安易な考え方で」中田英寿選手を語ってはならないという「戒め」を持ち続ける必要があります。
中田英寿選手を近くで長い間ウォッチし続け、濃密なコミュニケーションをとり続けたことで、中田英寿選手も信頼を寄せ心を開いてきたジャーナリストが何人かいます。
もっと中田英寿選手に迫りたいと思えば、そうしたジャーナリストが残したテキスト、著作を丹念にひも解くのがいいのではないかと思います。
ただ、通算14年間という時間軸全体を通して「別格の存在となった日本代表」中田英寿選手を語っているのは、おそらく、当ブログの今回の2回シリーズしかないと思いますし、その核心部分が非常に高いレベルに鍛え上げられた「心・技・体」の部分であることに切り込んでいるテキストも、今回の2回シリーズしかないと思います。
それは、今回のシリーズが「Jリーグがスタートして以降の日本サッカー30年の記録から」というテーマであり、後世に残す記録としての価値を最重要視しているからに他なりません。
何十年後かに、この記録を読んだ方が、1993年のJリーグ草創期から進化・発展を遂げた2006年までの間「日本代表の別格の存在」であった中田英寿選手のことを伝える内容として、もっとも適切ではないかと思っています。
ご愛読、ありがとうございました。
【本稿は、1月22日(日)17時から書き始めていますが、最初の仕上がりは1月23日(月)21時過ぎです】
【1月24日(火)には、テレビ出演の件やジョホールバルでの集合写真の件などのところを一部加筆しています。】
【1月25日(水)には、ASローマでのリーグ制覇を決めた試合のところや、その後の日本人選手の海外挑戦の道を拓いた部分などを加筆しています】
【1月28日(土)には、「心」の部分にドイツW杯での夕食会の部分や、「体」の部分の恥骨炎の部分などを加筆しています】
【1月29日(日)には、「心」の部分の最後のところに、nakata.net書籍版からの引用など、「技」の部分のところに平塚時代のシュート練習のエピソードなどを加筆しています】
【2月2日(木)には、nakata.netTVのことなどを加筆しています】
【2月4日(土)には、「技」の部分に2000年1月1日付スポーツ報知特集記事のことを加筆しました】
【3月28日(火)には、2002年W杯のロシア戦で見せた、喜びを爆発させた中田選手の表情を捉えた記事などのことを加筆しています】
【6月28日(水)には、「体」の部分で野菜嫌いについて紹介して、発疹のため記者会見に少し色の入ったメガネをかけてきた話を記述しましたが、発疹は別の理由であることが判明しましたので削除しました。合わせて「心」の部分で、強靭な彼でも心折れかねない糾弾行為を受けた経験のことを追加しました。】
【加筆前にお読みになった方は、再度、完成稿をお読みいだたければと思います】
2006年6月22日、ドルトムントのホームスタジアムでのブラジル戦の終了ホイッスルが鳴ると、ピッチ中央に仰向けに横たわり、まるで精も根も尽き果てたかのように選手生活に幕を閉じた、中田英寿選手。
1993年、16歳の時から日本代表のユニフォームを身にまとって国際舞台に立ち続け、弱冠21歳にして日本代表の「別格の存在」となって9年のも長きにわたって日本代表を牽引してきた中田英寿選手。
中田英寿選手は、何故、それほど若くして「別格の存在」となり得て、何故、9年のも長きにわたって牽引し続けてこれたのでしょうか?
そのことに思う時、中田英寿選手の「心・技・体」のすべてが、まさに当時の代表選手たちに比べて1歩も2歩も先を行く高いレベルにあったからではないかと感じました。
つまり中田英寿選手は、早くから自らの「心・技・体」を鍛錬し続け、20歳代になろうかという頃には、そのすべてを高いレベルまで鍛え上げたが故、若くして「別格の存在」となり得たのであり、その後も「心・技・体」の鍛錬を怠らなかったが故、長きにわたって日本代表を牽引できたのだと思うのです。
今回は「早くから「心・技・体」を鍛錬し続けた中田英寿選手」について記録に留めておきたいと思います。それが中田英寿選手のことを後世に語り伝える上で、欠かせないと確信しています。
まず、その「心(しん)」。
中田英寿選手はメンタル面で、当時の他の選手より抜きん出ている点がいくつかあります。
一つは平常心というか、どんなことにも動じない、感情の起伏の少ない、強い精神力です。前回も書きましたが「W杯なんて一つの大会に過ぎない」と捉えるマインド自体が驚異的です。サッカー選手なら最高峰の舞台でプレーすることは夢でありも目標であるのが一般的な捉え方ですが、中田英寿選手はそうではありません。
そもそも、中田英寿選手は「「サッカーは人生のすべて」といった考え方でサッカーをやっているわけではない」と常々話している選手です。
たまたま、今のこの時期、サッカーでさまざまな経験を積めるし、自分も成長できるからサッカーをやっているだけ、といったフラットな気持ちでサッカーを捉えている人です。
そのことは平常心として肩に力の入らない精神状態をもたらしますが、反面、こだわりのない淡白な気持ちにも陥りやすいものです。シドニー五輪のベスト4を賭けたアメリカ戦、日韓W杯のベスト8を賭けたトルコ戦、中田英寿選手も悔しかったには違いないでしょうけれど、他の選手ほど悔しい気持ちには見えませんでした。
かと言って、すべての場面で淡々と、淡白にプレーする選手かと言えば違います。ジョホールバルの奇跡を生んだ獅子奮迅のプレーぶり、衝撃的なデビューを飾ったセリエA開幕戦のユベントス戦のプレーぶり、2001年コンフェデ杯準決勝・土砂降りの豪州戦で見せた地を這うようなFK、さらにはASローマがシーズン制覇を決めたユベントス戦で途中出場ながら1ゴール1アシストをあげたプレーなど、ここ一番に持てる力を出し切る集中力も、どんなことにも動じない平常心と強い精神力の延長上にあるメンタルだと思います。
どんなことにも動じない平常心、強い精神力は、特に対外的な発信の場面でも顕著です。
中田英寿選手は、実はとてもフレンドリーな人だということを、少しでも接点のある人ならば口を揃えて言います。
そのフレンドリーさは、身近な人だけに示されるものではなく、一国の首相などを相手にした場合にも、動じない平常心と精神力に支えられて発揮されます。
セリエA・ペルージャでプレーしていた時、欧州歴訪中の小渕恵三首相がイタリアを訪問しました。
その時、小渕首相とイタリアの首相との昼食会に、イタリアで活躍する日本人として中田英寿選手が単独で招待されました。
普通であれば、一国の首脳の昼食会に単独で出席するなど、ビビる以外の何物でもない体験でしょうけれど、中田英寿選手はまったく違いました。
臆することなく堂々と二人の首脳との昼食会をこなしたのです。彼がいかに動じない平常心と精神力を持った人かを物語るエピソードです。
けれども、多くのメディアを通じて発信される自分のことや、日本代表に関する喧騒にも似た報道に対しては、常にクールにというか、フレンドリーさとは無縁の、時として冷淡と思えるほど起伏の少ない姿勢を貫きます。
その姿勢は、メディア側から見ると「この年代で、そういう態度をとり続けるのは考えられない」とばかり、時にはバッシングの対象にしたり、時には記事の中で皮肉たっぷりな見出しをつけたりしてきました。
例えば、こういうことがありました。中田英寿選手は「ピッチの上では対等」という考え方が特に強い選手で、日本代表での練習でも試合でも、必要なコミュニケーションをとる際「さん」づけなどの敬称をつけることは決してしません。
これは試合中の瞬時、瞬時の状況の中で必要なことを伝えるのに、いちいち長い名前を呼んだりしない、スポーツ競技なら常識でもあり、ピッチ上では「ヒデ !」「カズ !」「ナナ !」などと呼び合います。
ところがキャプテン・井原正巳選手は「イハラ」と呼ばれていたのでしょう。ある時、中田英寿選手が大声で「イハラーー!」と指示を出している姿と音声がテレビカメラに捉えられました。マスコミはすぐ飛びつきました。
決して否定的な論調ではないにしても「中田選手は井原正巳選手を堂々と呼び捨てにして指示していました」というコメントがつけば「へぇ~、中田選手は平気でそういう言葉遣いをする人間なんだ」という印象をもたれる可能性は十分あるわけです。
ですから、中田英寿選手の胸の内、心の内を知り得ない一般人の多くがメディアの論調を真に受けて中田英寿選手のイメージを抱いていました。
そのことで、中田英寿選手がずいぶん損をしたのではないかとも思いますが、中田英寿選手は、それに頓着することなく「どうせメディアが勝手に作っているだけだから」と受け流してきました。
20歳代前半の青年が、メディアという巨大な力に対しても、なんら怯むことなく、臆することなく堂々とした姿勢を取り続けていたというのは、驚異的であり、他の同世代の選手たちと比べて、はるかに抜きんでたマインド、精神力の持ち主だということを示しています。
しかし、それほどに強靭な精神力の持ち主の中田英寿選手も、全国紙のインタビュー記事が発端となって、いわゆる右翼団体からの執拗な糾弾行為にさらされたことがありました。当時、若干21歳の青年に対するものです。
彼がいかに強靭とはいえ、糾弾行為から身の安全を確保するために取らざるを得なかった日々は、どれほど恐怖だったことか。事情を知らないメディアなどは、いい加減なことを書きたてました。しかし、彼は医師の診断で「極度のストレスが原因」と言われるほどの症状を呈するほどに追い詰められていました。
この時、中田英寿選手はフランスW杯のため日本を離れることができたため、致命的なことにならずに済みましたが、これが日本から離れられない状況がもっと続いたならと考えると、暗澹たるものがあります。
この「どんなことにも動じない平常心、強い精神力」は「非常に明晰な頭脳」と合わせ持っている、中田英寿選手の「資質」にほかなりませんが、それは、日本代表チームの一員として他の選手たちと同じ目線に立とうとする場合、自分の精神的強さ、頭脳明晰さがあまりにも抜きん出ているが故に、かなり他の選手たちと相和するのが難しいというハンディを背負うことになります。
チームの中で若い方に属する20歳代半ばまでは、自分がマイペースで他の選手たちとつるむことがなくても、せいぜい「変わったヤツ」と見られるだけで、そのハンディはさほど表面化しませんでしたが、20歳代後半、特に自分が自他ともにチームリーダーとして見られる、2006年ドイツW杯に向けたチームの中では、その強い精神力が邪魔をして、チームメイトから反発を買うことになっていきます。
すべからく団体競技のチームは、いわゆる「チームとしてまとまり」「チーム全員がお互いに助け合って」勝利にまい進することが基本であり、強いチームというのは「まとまり」や「互いに助け合う」マインドが他のチームより勝っているのが普通です。
そんな中で、リーダー格の選手に対する他の選手の意識が違う方向を向いていれば、いわゆるベクトルが合わないわけで「まとまり」や「互いに助け合う」マインドが他のチームより勝るのは難しくなります。
中田英寿選手の「心」の部分で唯一、残念なのは、そのあまりに強い精神力、平常心に加え、人とつるむことを好まないマイペースな性格が、チームの他の選手たちを遠ざける結果となったことです。
中田英寿選手は平塚に入団した理由の一つに「タテ社会ではないみたいだから」というチーム内の風通しのよさをあげ「ピッチの上では皆、対等」という考え方を貫いてきました。しかし、年月を経て、自分がチームの中で先輩と呼ばれる立場になり、若い選手たちから「こうして欲しい」と要求されたり「自分たちはこう思う」と意見される立場になった時、自分が若い時に望んでいた「タテ社会ではない関係」とか「ピッチの上では対等」といった考え方で、後輩選手たちにも接したかどうか・・・。
逆に「ヒデさんはタテ社会の先輩」であり「ヒデさんの前では対等たり得ない」と思われるようなふるまいになっていなかったのかどうか、もし、そうだとしたら、若き日に先輩たちに対して行なっていたふるまいがブーメランのように自分に返ってきたのではないかとすら思ってしまいます。
それでも中田英寿選手は、彼なりに全力を尽くしています。2006年ドイツW杯の第一戦・豪州戦に逆転負けした後、次戦クロアチア戦を3日後に控えた夜、中田英寿選手は選手だけの夕食会を提案して実現させています。
日本代表の歴史には、選手だけのミーティングや食事会で徹底的に議論を戦わせたことがターニングポイントとなって、チームが劇的にまとまり快進撃を続けたケースが幾つかあります。
中田英寿選手もそうした「チームとしてのまとまり」を取り戻したい一心で提案して実現した夕食会だったに違いありません。
でも結局それは夕食会以上のものにはなりませんでした。中田英寿選手と他のすべての選手、その間に生じた溝は埋まることなく大会は終わりました。
ブラジル戦終了後、ピッチ中央に仰向けに横たわった中田英寿選手のもとに近づく選手が一人としていなかったという現実が、その溝の深さを物語っていました。
これは「ないものねだり」なのかも知れませんが、もし中田英寿選手が、その食事会で、自分の思いをすべてさらけ出し「まとまって戦いたい」「そのために自分がどうすればいいか教えて欲しい」といった趣旨のスピーチでもしていたらと思います。
中田英寿選手ではなく「中田英寿氏」となった今、聡明な氏のことですから、いろいろと思うところはあると思います。けれども、当時の自分の考え方やふるまいを、決して後悔することはないと思います。
中田英寿選手が自ら発信したインターネットでの記録は、「nakata.net」という書籍になっています。欧州のサッカーシーズンである秋から春まで毎にまとめられているのではないかと思いますが、05-06、すなわち現役生活最後となったシーズンの本を読んでみますと、2005年11月16日に国立競技場で行われたアンゴラとの試合について、とても興味深い記述があります。
少し引用します。「実は今回ほど、やっていて虚しさや寂しさを感じた試合も初めてだと思う。
特に、後半の途中、試合中なのにもかかわらず、まるで俺自身が第三者かのように試合を感じた瞬間があった。
その時、観客席をふっと見上げたら、両ゴール裏のサポーター席を除いた正面スタンドとバックスタンドは、まるで誰も試合を楽しんでいないかのように静けさが漂っていた。
そして、その視線をグラウンド上に落としてみた。そしたら案の定、ピッチの上にも同じような静けさが漂っていた。試合中にもかかわらず・・・・。
それを見た瞬間、恥ずかしながら俺はそのピッチ上の状況を打開する術が、思い浮かばなかったし、何のために試合をやっているのか混乱してしまった。そして、他の選手たちは一体どういう気持ちでやっているんだろうか、何を目的でサッカーをやっているんだろうか、と考えてしまった。
チームとしてこの試合で何をやりたいのか、それぞれ個人として何をやりたいのかが見えなかったんだよね。
〈中略〉
日本代表が今のレベルからもう一つ上のレベルに行くには、相手が強い時や跡が無いような厳しい状態の時に、出来るサッカーを常時やる "集中力と精神面の強さ"を手に入れるだけでいいと思う。
それは、本当に個人個人の気持ち次第。
味方に要求できる強さ、味方を信じて走れる強さ、味方を助ける声を出せる強さ、そんなちょっとした強さが今の日本代表に一番欠けている事だと思う。」
以上が引用部分ですが、この日の記述について編集者のコメントだと思いますが、「翌年7月3日のメールには『半年前に引退を決意した』と綴られているが、引退決意は実はこのころから徐々に本格的なものに固まりつつあったのかもしれない」というコメントがついています。
今回のテーマである「21歳にして日本代表の別格の存在となった中田英寿選手の「心・技・体」」のうち「心」の部分は、そのあまりに強靭な精神力、他を寄せ付けないマイペースな性格ゆえに、自分のサッカー人生の集大成にしたかった最後の大会にきて、チームメートの共感を得られないという破綻をきたしてしまいました。
引用した記述にもあるように、中田英寿選手が指摘している「日本代表に欠けている点」は、まさに「もっとも」なことです。ですから、何年経過しようが、後年の中田英寿氏は、何一つ悔いがないわけです。
当時も、このことに異論を挟む代表選手はいなかったと思います。
にもかかわらず、実際は、他の選手たちに、その思いは伝わりませんでした。
中田英寿選手も、さきに引用した日の最後にこう記述しています。
「ただ、これらはすべて他人が助けてくれる事ではなくて、自分で変えるしかないのだけれど・・。」
つまり、中田選手の思いが伝わらなくても、それは仕方のないこと、各自が自分で変えるしかないことなので、変わらなければ仕方のないこと、と思い定めていたようで、あとは自分が現役を辞めることしか選択の余地がないと心に決めたのだと思います。
さて、中田英寿選手の「心」の部分の大きな特徴として「どんなことにも動じない平常心、強い精神力」について述べてきましたが、もう一つの特徴は「非常に明晰な頭脳」です。その具体的な要素として「語学力」「研究心」「先見性」があげられます。
まず「語学力」。私たちが舌を巻いたのは、セリエA・ペルージャに移籍して現地で開いた最初の記者会見です。現地の記者から「何かイタリア語で一言」と問われ、即座に流暢なイタリア語で「もうお腹がすいたので勘弁してよ、パスタでも食べにいきたいな」と返したのです。
21歳のサッカー青年が、実は大変な勉強家で、イタリア語会見に耐えられるだけのボキャブラリーを習得していたことを、まざまざと知った場面でした。
「研究心」でも、数々のエピソードがあります。中学時代に中田英寿選手にサッカーを指導した方は、何かを教えた時、他の選手からはさほど質問が出なくとも中田英寿選手だけは、先生があきれるほど質問してきたといいます。自分が納得いくまで探求する、その姿勢も彼の持つ資質です。
その「自分が納得いくまで探求する」姿勢は、Jリーグ入りした時、そして欧州挑戦を決めた時のクラブ選びでも如何なく発揮されました。
山梨・韮崎高校からJリーグ入りする際、(その1)でもご紹介したとおり当時の12クラブ中、11クラブから誘いを受けるという高評価の中、横浜M、横浜F、ベルマーレ平塚の練習にそれぞれ参加しています。
中田英寿選手は、選ぶ基準を明確に持っていました。それは「自分が活きるポジションですぐ試合に出られる可能性があるクラプ」というものでした。その結果、平塚を選んだわけです。「タテ社会ではないみたいだから」つまり、先輩の言うこと、目上の人が言うことが絶対みたいなチームではなさそうというのも中田英寿選手の判断の決め手だったようです。
そして欧州挑戦を決めた時の選択基準もほぼ同じでした。当時、欧州のビッグクラブといわれるチームからのオファーも幾つかありました。
サッカー選手であればビッグクラブの一員になることは、W杯でプレーすることと同様、夢であり目標です。しかし、中田選手は「ビッグクラブの一員になっても、すぐ試合に出られなければ意味がない」という考えのもと、例え小さなクラブでも、自分をキチンと評価してくれて試合に出られる可能性の高いクラブ、ということでセリエAに昇格したばかりのペルージャを選んだのです。
このように、自分がキチンとして基準を持ち、それに合うクラブを納得いくまで調べて、確認して、その上で決めるという確固たる姿勢を、若くして貫いたことが、彼の成功の大きな要因だと思います。
選ぶクラブがビッグクラブで「常勝軍団」であることなど、彼にとっては不必要だったようですが、それは逆に、そういうクラブの一員が持つ「勝者のメンタリティ」を涵養する機会を得られなかったのではないかという、ある意味の「悲劇」でもあったのではないかと当ブログは指摘しておきたいと思います。
日本に来た大物外国人選手、あるいは指導者の中で、ジーコやドゥンガ、あるいはベンゲルといった人たちはサッカープレーヤーの持つべき大切なマインドに「勝者のメンタリティー」をあげています。
「勝者のメンタリティー」を分かりやすく言えば、それは「負け犬根性を持つな」「勝負には絶対勝つんだ」というマインドをチームを構成するすべての選手が共有していなければ、試合には勝てないんだ、ということのようです。
そして、「勝利」を重ね続けているビッグクラブ、常勝軍団と呼ばれるクラブには、長い間に培われてきた、その「勝者のメンタリティー」が備わっており、どのクラブも、そこを目指していくべきだ、ということのようです。
中田英寿選手が選んだクラブは、対照的に、まだ「勝者のメンタリティー」が備わっているとは言い難いクラブだったと思います。
そこで自分が常に試合に出続け、スキルと経験を積むことはできたと思いますが、チームがタイトルを取るとか、王者と呼ばれることはありませんでした。
「どんなことにも動じない、感情の起伏の少ない平常心」のところでも書きましたが、シドニー五輪のベスト4を賭けたアメリカ戦、日韓W杯のベスト8を賭けたトルコ戦、中田英寿選手も悔しかったには違いないでしょうけれど、他の選手ほど悔しい気持ちには見えなかったのは、この「勝者のメンタリティー」と無縁ではないのではないか、そう思えてならないのです。
中田英寿選手の持つメンタリティーの3つ目の要素「先見性」で特筆すべきは、当時のアスリートとして初めてといえる「インターネットを通じた独自の情報発信を始めた」という点です。
自分の公式サイトを開設して、情報発信するというスタイルはサッカー選手のみならず、当時の日本のスポーツ界を見渡しても最初の取り組みだったのです。
それは、メディアが自分のことを取り上げる時、まったく自分を理解していないかのような内容であることに愛想をつかし、メディアを頼った情報発信に見切りをつけて始めたことでもありますが、それを20歳代前半にして始めてしまう先見性は目をみはるばかりです。彼の不断の研究心がもたらしたものでもあります。
こうして自らが情報発信するようになってから、中田英寿選手のメディアへの露出、特にテレビ出演は明らかに変化しました。
まず、自らがプロデュースした番組を2000年7月からCS(スカイパーフェクTV!)チャンネルに開設しました。「nakata.net TV」と題して、月1回ペースで自身の近況報告やプライベートなことを発信するインタビュー、あるいは親しい人との対談などの内容で、さしずめ「元祖・個人チャンネル開局=ユーチューバー」といったところです。
ですから、地上波のテレビ出演の必要がなくなった形となり、地上波出演をほとんど受け付けない時期もありましたが、次第に信頼のおけるキャスター、例えばテレ朝・ニュースステーションの久米宏氏などの番組、あるいは作家の村上龍氏がインタビュアーを務めるような番組には、ある程度の間隔で定期的に出演するという向き合い方に変えていったようです。
それ以外の、いわゆるバラエティ番組やワイドショー系の番組には一切出ないという姿勢を貫いたようです。
「先見性」については、もう一つ特筆すべき点があります。
それは彼が「サッカー選手である自分という存在が、一つの知的財産である」という認識を持っていたという点です。
中田英寿選手があまりファンとの写真撮影やサインに応じないのは有名でしたが、これも彼が気難しいからとか、面倒くさがり屋からと言った理由ではなく、それらが安易に使用されたりすることを嫌ったからと言われています。
こうした「肖像権の無断使用」など、知的財産権を侵害する行為に対する高い防衛意識をもって、考えをはっきりと主張したことにより、他の多くの選手、他のスポーツのアスリートたちも、その重要性を認識するようになったという点でも、彼は先駆者であり「先見性」を持った選手だったのです。
次に「技(ぎ)」について見ていきたいと思います。
中田英寿選手が16歳でU-17世界選手権の舞台にたった当時、彼のピッチにおける主戦場は、サイドハーフというかウィングにあたるポジションでした。
そこで彼は、国際舞台でも十分通用するスピード(走力)を披露します。ドリブルやクロスの精度といった技の部分も、大会までの長期間にわたる合宿や自主練習でかなり向上しています。
次に彼は、ベルマーレ平塚で、いわゆるトップ下のポジションに求められるスキルを磨きます。広い視野を確保するための姿勢をとり、常に周りの状況を首を細かく振りながら確認するプレースタイル、そこで得た状況判断から繰り出されるスルーパス。
中田英寿選手の凄いところは、常に動きながらも、そうした周りの確認、状況判断を怠らずに続け、その精度をあげていこうとする向上心です。
中田英寿選手が繰り出すスルーパスは「キラーパス」と呼ばれます。平塚時代に出す彼のパスは、決してJリーグ仕様の、緩いものではなく、世界のトップリーグレベルの試合で求められる国際仕様の高速パスなのです。
それは、いずれ自分が海外でプレーした際に通用するパス精度を磨くという意味と、Jリーグや日本代表も、これぐらいの高速パスを普通に繰ることができなければ、国際舞台では通用しないというメッセージがこもったものでした。
スピードの遅い日本人選手の速度に合わせたパスを出すという選択はしませんので、その高速パスが、もし通れば、まさに相手を仕留めることができるキラーパスなのですが、受け手がなかなか追いついてくれない場面が出てきます。
それでも、受け手が誰であろうと「このパススピードが世界基準なんだから、受けてくれ」と言わんばかりのキラーバスが繰り出されます。
平塚でも日本代表でも、受け手の選手からは泣き言が出されましたが、その一貫したプレースタイルはペルージャ移籍以降の海外での経験に活きていきます。
このスルーバスについては、よく相手のスピードに合わせた、ほど良いパスを繰り出す選手と比較されることがあります。
代表的なのは小野伸二選手です。彼が繰り出すパスは、相手の欲しいところにピタリを収まることが多く、それは「エンジェルパス」とか「ベルベットパス」と評される、相手に優しいパスということだと思います。
どちらが良い悪いという見方はまったく無意味です。けれども、大きな違いが一つあります。パス一つでチームが盛り上がり、まとまって勝利を目指せる力を与えるのはどちらか、と言えば、これは小野伸二選手のパスだと思います。
「キラーパス」は相手を一発で仕留める効果も持ちますが、追いつけなかった味方の士気を削ぐリスクもはらみます。それは、チームのまとまり感、盛り上がり感の強さにも影響を与えます。
1999年ワールドユース選手権で、小野伸二選手が果たした役割は、まさに自分のバスで見方を盛り上げ、まとまって勝利を目指す力を与えたものだったと思います。
中田英寿選手の「キラーパス」を語る時、それが日本代表や所属クラブを国際基準に引き上げるためのメッセージを込めたパスではあったと思いますが、目の前の試合、目の前の大会を勝ち進む手段として、果たしてどうだったのでしょう。
特に2006年ドイツW杯の日本代表チームが、1戦毎にチームとしての「まとまり」を失っていったのではないかと思われる様子を見た時、イレブンの思いが「司令塔の中田英寿選手を中心に戦い抜くぞ」という結束力とは縁遠いものになっていたのではないでしょうか。その見方は穿ち過ぎでしょうか。
次に「プレースキック」に触れたいと思います。
中田英寿選手が「日本代表の別格の存在」になる1997年夏あたりまで、彼がプレースキックを任されることは、さほど多くなかったと思います。
けれども、日本代表でも、ペルージャでも、彼の存在が大きくなるにつれ、プレースキックを任される場面が増え、その経験をもとに精度も少しづつあげていきます。
のちに日本代表では中村俊輔選手と言う稀代のプレースキッカーが現れたことから、中田英寿選手はあっさりと、彼にその座を譲ります。
最後に「シュート」の技についても触れておきたいと思います。
中田英寿選手は、もともとFWポジションが長い選手ではありませんから、そのシュートが注目される機会は少なかったのですが「日本代表の別格の存在」になってからは、常に得点に絡むことが求められ、また海外でプレーを始めてからは、攻撃陣であれば点に絡まなければ失格とさえ評価される厳しい環境の中で、得点に対する意識を相当高めたようです。
ベルマーレ平塚でプロ選手としてのキャリアを始めた頃、同僚で大先輩のGK・小島伸幸選手が、中田英寿選手の練習における意識の高さに舌を巻いたそうです。
中田英寿選手が練習後、自主練習の形で誰もいないゴールマウスに向かってシュート練習をしていたそうです。ところが、ほとんど枠に飛ばないことから小島選手が「こいつ、へたくそだなぁ」とあきれていたそうです。すると中田英寿選手のシュート練習につきあっていたコーチも、小島選手と同じ思いで怒声を浴びせたそうです。
すると、中田英寿選手は「何言ってんですか、試合中はGKがいるんですよ、それを考えたらポストの内側20センチじゃなかったら決まるわけないでしょ」と言い返したそうです。
それを聴いた小島選手は「とことん、思い知らされましたよ、中田英寿ってのは、ホントに目標設定が高い男なんだなぁって」
そのような意識の高い練習の積み重ねの延長線上に、オーバーヘッドキックでゴールを決めて見せたり、強烈なミドルシュートでゴールを奪うなどの結果があり、まさに万能型のゴールゲッターに成長しています。
このように「ドリブル」「パス」「プレースキック」「シュート」のどれをとっても非常に高いレベルまで自分のスキルを磨き、上達していったのは、彼の「あくなき向上心」があったからだと思います。
16~17歳の頃は、走力と身体の強さだけが国際レベルでも通用する選手でしたが、その後の練習と研究で、「視野の広さと一瞬の状況判断」「ドリブル」「パス」「プレースキック」「シュート」どの技も国際レベルまで引き上げていったことがわかります。
チームの司令塔としての役割も、これらのスキルが高まるとともに強まったと言えます。まだ10代の頃、チームの司令塔は常に別の選手が務めていました。それが、21歳になる頃には、クラブでも日本代表でも、チームの司令塔と言えば彼のことを指すようになりました。
日本代表での中田英寿選手が、まさに司令塔としての地位を確立したことを示す象徴的な記事があります。2000年1月1日付のスポーツ紙各紙は、この年のスポーツの中心的なイベントであるシドニー五輪に関する特集を組みました。
その中で「スポーツ報知」紙は、サッカー五輪代表が中田英寿選手に率いられ32年ぶりのメダル獲得が期待できるとして「中田を感じる 中田で変わる 中田が勇気に」という見出しを打ちました。

彼が五輪代表の中心選手として、いかに圧倒的存在であるかをよく表現している見出しだと思います。
「司令塔」は、彼が飽くなき努力を積み重ねて自分の「技」を磨き、その結果に得たポジションです。
最後に「体(たい)」について見ていきます。
すでに書きましたが、1993年にU-17世界選手権に出場した日本代表は、その2年前から強化が始まっていますが、当時、中学2年生だった中田英寿選手は、関東選抜の一員に選ばれています。そこから日本代表候補の選考が行われたわけですが、当初、彼を送り出した指導者の方は、日本代表候補に残るのは難しいのではないかと感じていたそうです。
ところが、日本代表候補にピックアップされたので、指導者の方は理由をたずねたそうです。その答えは「確かに彼は技術的には不十分ですが、走力、敏捷性などのフィジカル面で秀でており国際試合で通用するだけの素質を持っていますので」というものでした。
当時まだ中学生でしたから体は細かったのですが、走るスピードと、身のこなしの素早いムチのような身体を持っていたようです。
その身体に、少しづつ筋肉をつけ、当たり負けしない体幹を鍛え、日本代表での国際試合でも、海外クラブでの試合でも、少々では倒れない強靭な身体を作っていったわけです。
中田英寿選手の「体(たい)」を語る上でもう一つ大切なことは、長期離脱を強いられるような大きなアクシデントに見舞われることがなかった点です。
それは持って生まれた骨格の強靭さと、選手生活の中での徹底した自己管理、ケアの賜物なのですが、実は食生活という点では、やや苦労したようです。
実は大変な野菜嫌いで通っていて、頑なに野菜を食べない理由としては、「野菜を食べて得られるものより嫌いなものを無理して食べるストレスの方が影響が大きい」と話してしたそうです。
身体づくりの上でハンディとなったことと言えばそれぐらいで、2004年春あたりまでは、海外クラブ在籍中も含めて、長期離脱せずに日本代表を支え続けた「体」は、驚異的ですらあります。
サッカー選手にケガはつきものと言われるほど、ケガのリスクを抱えながらプレーすることになるわけですが、中田英寿選手の凄いところは「技(ぎ)」のところでも触れましたが、常に相手の状況を把握し続けながらプレーすることで、後方からのタックルや激しい接触プレーなどの不測の事態になるべく巻き込まれないようにしてきたことです。
それも中田英寿選手を「日本代表の別格の存在」たらしめ、それを長きにわたり維持し続けられた大きな要因だと思います。
ケガには強い中田英寿選手も勝てないアクシデントはありました。それはサッカー選手の職業病とも言われている、通称・恥骨炎になったことです。
2003~2004年シーズン終盤、2004年春あたり、ボローニャ在籍当時に発症したそうですが、痛みをおしてシーズンを戦いボローニャの1部残留に貢献しました。
シーズン終了後のオフ、2ケ月間は治療に専念して2004~2005年シーズンはフィオレンティーナに移籍、新シーズン当初から復帰しましたが、オフのトレーニング不足がたたりパフォーマンスが上がらず、日本代表の招集も約1年間にわたり見送られました。
2005年3月、約1年ぶりに日本代表に召集されましたが、この日本代表での1年のブランクは、実は、中田英寿選手抜きで、ドイツW杯アジア予選を戦ってきた他の選手たちとの心理的な距離を広げてしまった不幸な1年間だったようです。
特に日本代表ジーコ監督が、あたかも中田英寿選手にポジションを用意してあげるかのような布陣をとったことが火に油を注ぐことになったようです。
恥骨炎が癒えてまもない中田英寿選手のパフォーマンスが、目に見えて低調なのを見た他の選手たちは、不満を募らせていき、以前のように別格の存在としては見ず、一人だけ浮いている存在として見る選手が増えてしまいました。
「中田英寿選手の「心・技・体」」の「心(しん)」の部分でも書きましたが、自分のサッカー人生の集大成にしたかった最後の大会、2006年ドイツW杯において、チームメートの共感を得られないという破綻をきたしてしまいましたが、その破綻を招くことになったのが、2004年春から2005年3月までの恥骨炎という「体」の異変による日本代表からの離脱でした。
ドイツW杯グループリーグ敗退を見届けて、あっけなく選手生活の幕を閉じた中田英寿選手ですが、「心・技・体」のすべてをハイレベルな状態に鍛え上げ、維持し続けて10歳代後半から20歳代の長きにわたり疾走し続けたことを思えば、完全燃焼して精魂尽き果ててしまっても、何ら不思議ではないことなのかも知れません。
しかし、最後の最後は、不幸な終わり方だったなぁと思います。ドルトムントの空を見上げて「これが最後の試合だ」と中田英寿選手が思っていたことを、チームメートの誰一人知らずにいたのですから。
選手時代の中田英寿選手は、一般受けするようなリップサービスや愛想のいいふるまいなどを意識的に避けてきたようにも思います。
本来はとてもフレンドリーなオープンな人柄でも、メディアからの自己防衛本能や、平静で動じない性格もあって、一般のサッカーファンから見た場合、例えばカズ選手やゴン・中山雅史選手などに対して抱く選手像とは対極にあるタイプの選手に映ったことでしょう。
それでも「何もそこまでしなくても」と思うようなエピソードもあります。
1997年11月、マレーシア・ジョホールバルの奇跡を起こした試合後、ピッチ上ではお祭り騒ぎのようにしてイレブンが集合写真やTVカメラ撮影に応じていますが、なぜか中田英寿選手だけは、写真やTVカメラに映りこもうとせず、ひたすら最後方をウロウロしているように見える姿が残っています。
まさに「何もそこまでしなくても」と思うような行動ですが、一種の照れ隠しだったのかも知れません。この試合のヒーローが中田英寿選手であることは誰の目にも明らかなのですが、それ故、彼は「そんなに自分をクローズアップしないでください」という気持ちになっていたのではないかと思います。
一方で、自分が得点を決めた時はなおのこと、味方の得点や勝利の瞬間にもクールに、控えめにしか喜びを表さない中田英寿選手にも、長い選手生活の中で、こんなに喜びを爆発させたことがあるんだ、という場面のスポーツ紙の記事もあります。
2002年W杯のグループリーグ第2戦、ロシアとの試合でゴールを決めた稲本選手を祝福するため、多くの選手が飛びつくようにして輪を作りましたが、その輪に中田英寿選手も喜びを爆発させながら、少し遅れ気味ではありますが、飛びついた場面です。
このような表情の中田英寿選手は本当に珍しく、普段はどう考えても控えめにしか喜びを表に出さない選手ですが、この場面を見ると、中田英寿選手も「喜びを爆発させることがある」普通の選手だとわかって、グンと親しみが増します。
今後、サッカー日本代表の中心となるような選手で、中田英寿選手のようなタイプの選手が、また現れるだろうかと自問した場合、なかなか現れる予感がしないタイプであるように思います。
おそらく、この時代だからこそ出現したカリスマではないかと思います。
理由は二つ、この1993年から2006年までの時代が日本サッカーが国際舞台に駆け上がる時代であり、中田英寿選手はまさに、その時代と歩調を合わせて成長した選手だからというのが一つ。
もう一つは、一般のサッカーファンに伝わる中田英寿選手のイメージがメディアを通すことによって少し歪められることがあり、それを嫌った中田英寿選手が、いち早く自らの手で情報発信するというアスリートとしては初めての取り組みをした選手であること、です。
これは、まさに時代的な背景が生んだ選手ということであり、今後の日本代表選手には、むしろ生まれにくい選手だからかも知れません。
しかし、中田英寿選手ほど若くして、しかも長期にわたり「日本代表における別格の存在」であったことは、Jリーグ以降の日本サッカーの30年における輝かしい偉業であることも事実です。
中田英寿選手が世界最高峰と言われるイタリアリーグで、堂々たるプレーを見せ続け、その割には大言壮語を吐くでもなく、終始、謙虚にふるまい続けたことにより、日本人プレーヤーに対する世界の評価を格段にあげてくれて、その後の多くの日本人選手の海外挑戦の道を拓いた功績は、称賛して余りあります。
この神秘的なカリスマのことは、これからも長きにわたって、いろいろな角度、切り口から語られていくと思いますし、すでに選手生活を終えて久しい中田英寿氏が、それら一つ一つに反応することは、これからもないと思います。
なぜなら中田英寿氏自身が、若い頃よく「「サッカーは人生のすべて」といった考え方でサッカーをやっているわけではない」と話していたものの、やはり14年間のサッカー人生から得たものも大きく、現在は「FIFA親善大使」を務めるほど、世界のサッカー界から見ても著名な存在になったことからも窺えるように、いろいろな角度、切り口から語られるだけの価値のある存在になっているからです。
当ブログも含めて私たちが意を用いなければならないのは、中田英寿選手を語る場合、それが例えば間違っても「名誉棄損」にあたるようなこととか「肖像権の無断使用」にあたるようなことなどについては、細心の注意を払わなければならないということです。すなわち「安易な考え方で」中田英寿選手を語ってはならないという「戒め」を持ち続ける必要があります。
中田英寿選手を近くで長い間ウォッチし続け、濃密なコミュニケーションをとり続けたことで、中田英寿選手も信頼を寄せ心を開いてきたジャーナリストが何人かいます。
もっと中田英寿選手に迫りたいと思えば、そうしたジャーナリストが残したテキスト、著作を丹念にひも解くのがいいのではないかと思います。
ただ、通算14年間という時間軸全体を通して「別格の存在となった日本代表」中田英寿選手を語っているのは、おそらく、当ブログの今回の2回シリーズしかないと思いますし、その核心部分が非常に高いレベルに鍛え上げられた「心・技・体」の部分であることに切り込んでいるテキストも、今回の2回シリーズしかないと思います。
それは、今回のシリーズが「Jリーグがスタートして以降の日本サッカー30年の記録から」というテーマであり、後世に残す記録としての価値を最重要視しているからに他なりません。
何十年後かに、この記録を読んだ方が、1993年のJリーグ草創期から進化・発展を遂げた2006年までの間「日本代表の別格の存在」であった中田英寿選手のことを伝える内容として、もっとも適切ではないかと思っています。
ご愛読、ありがとうございました。
【本稿は、1月22日(日)17時から書き始めていますが、最初の仕上がりは1月23日(月)21時過ぎです】
【1月24日(火)には、テレビ出演の件やジョホールバルでの集合写真の件などのところを一部加筆しています。】
【1月25日(水)には、ASローマでのリーグ制覇を決めた試合のところや、その後の日本人選手の海外挑戦の道を拓いた部分などを加筆しています】
【1月28日(土)には、「心」の部分にドイツW杯での夕食会の部分や、「体」の部分の恥骨炎の部分などを加筆しています】
【1月29日(日)には、「心」の部分の最後のところに、nakata.net書籍版からの引用など、「技」の部分のところに平塚時代のシュート練習のエピソードなどを加筆しています】
【2月2日(木)には、nakata.netTVのことなどを加筆しています】
【2月4日(土)には、「技」の部分に2000年1月1日付スポーツ報知特集記事のことを加筆しました】
【3月28日(火)には、2002年W杯のロシア戦で見せた、喜びを爆発させた中田選手の表情を捉えた記事などのことを加筆しています】
【6月28日(水)には、「体」の部分で野菜嫌いについて紹介して、発疹のため記者会見に少し色の入ったメガネをかけてきた話を記述しましたが、発疹は別の理由であることが判明しましたので削除しました。合わせて「心」の部分で、強靭な彼でも心折れかねない糾弾行為を受けた経験のことを追加しました。】
【加筆前にお読みになった方は、再度、完成稿をお読みいだたければと思います】