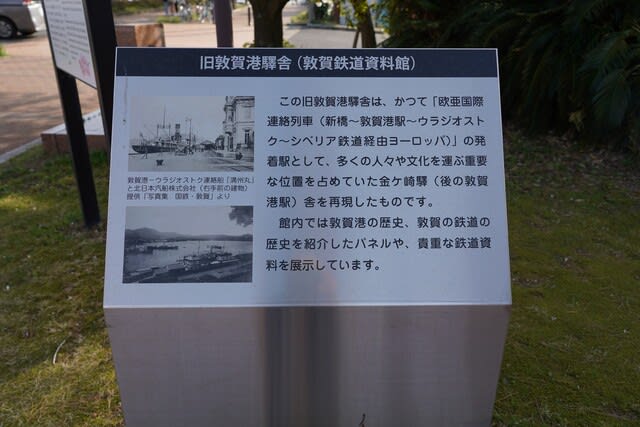かねてからブログのトップ画面で表示されているとおり、今秋「goo blog」はサービス終了することとなっている。これに伴い、「行き先不明人の時刻表」は、このたびブログ記事の引っ越し作業を行った。
引っ越し先は「Ameba ブログ」である。→ https://ameblo.jp/jikokuhyou485/
実はこのブログデータの引っ越し作業、今回で二回目となる。いずれもプロバイダーのサービス終了に伴うもの。(OCNブログ → goo blog → Ameba ブログ)
時代の流れか、昨今はYouTubeをはじめとした動画で直接メッセージを伝えるサイトが人気。もちろん自分も時間があるときは自分もついつい見てしまうのだが、これからも「まち歩き」しながら写真と文章でその土地の魅力を探っていきたいと考えての今回の引っ越しとなった。
開設18年間で二回引っ越しは多いか少ないか分からないが、その間、実に年齢を重ねた管理者にとって、かなり作業は大変であり勇気もいる作業であった。(かなりアップロードに時間を要するとのことだったが、一両日で完了した。)
ブログが最初に引っ越しをした時に数字「2」を付したが、今回は「3」ということになる。上記のURL、または「行き先不明人の時刻表3」で検索し、お気に入り登録、今後もフォローをよろしくお願いします。


引っ越し先は「Ameba ブログ」である。→ https://ameblo.jp/jikokuhyou485/
実はこのブログデータの引っ越し作業、今回で二回目となる。いずれもプロバイダーのサービス終了に伴うもの。(OCNブログ → goo blog → Ameba ブログ)
時代の流れか、昨今はYouTubeをはじめとした動画で直接メッセージを伝えるサイトが人気。もちろん自分も時間があるときは自分もついつい見てしまうのだが、これからも「まち歩き」しながら写真と文章でその土地の魅力を探っていきたいと考えての今回の引っ越しとなった。
開設18年間で二回引っ越しは多いか少ないか分からないが、その間、実に年齢を重ねた管理者にとって、かなり作業は大変であり勇気もいる作業であった。(かなりアップロードに時間を要するとのことだったが、一両日で完了した。)
ブログが最初に引っ越しをした時に数字「2」を付したが、今回は「3」ということになる。上記のURL、または「行き先不明人の時刻表3」で検索し、お気に入り登録、今後もフォローをよろしくお願いします。