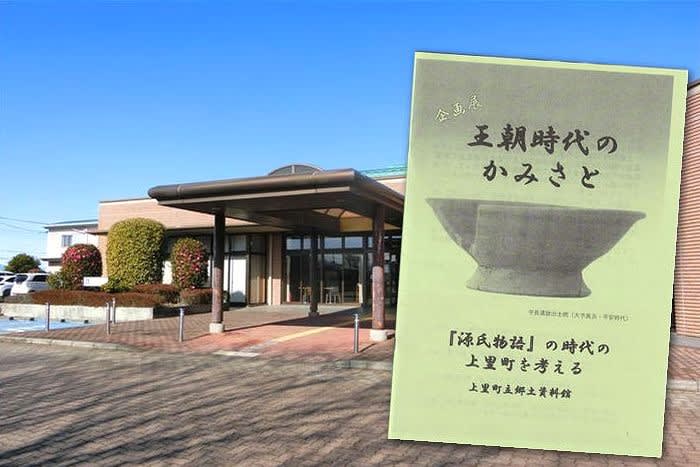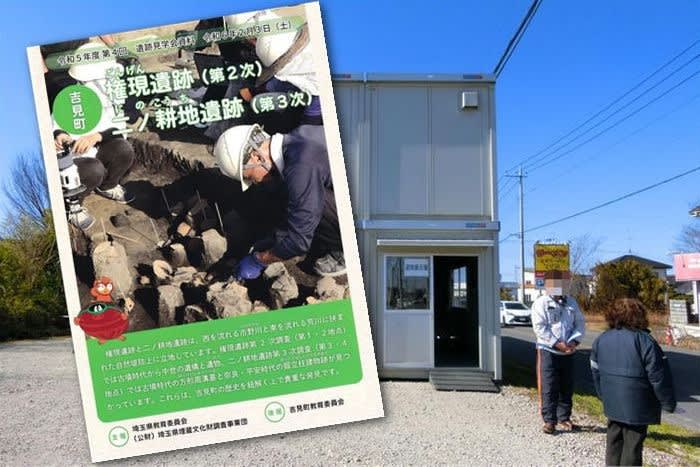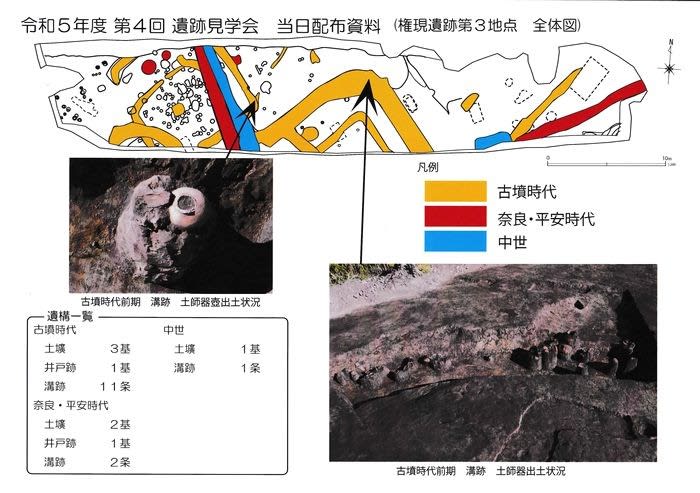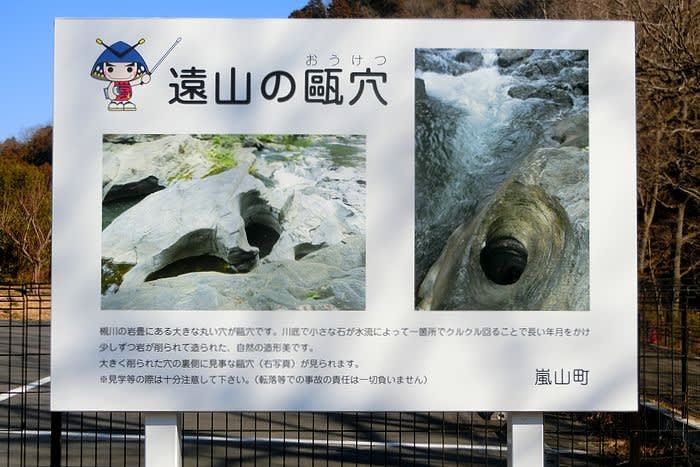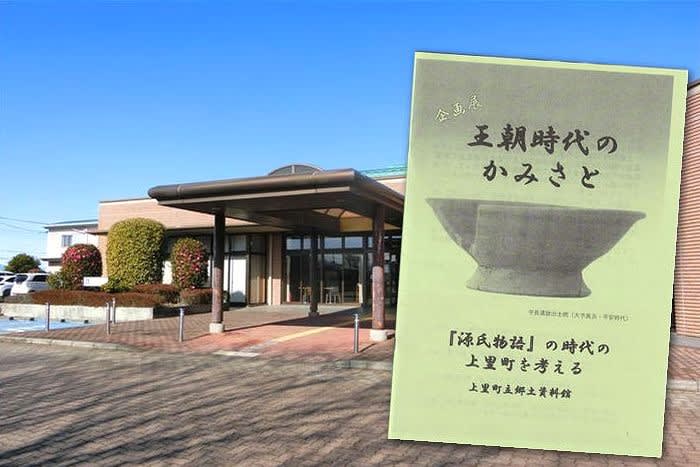 上里町立図書館・郷土資料館 と 企画展展示解説書
上里町立図書館・郷土資料館 と 企画展展示解説書
上里町立郷土資料館企画展
「王朝時代のかみさと-『源氏物語』の時代の上里町を考える-」
会 期:令和6年1月11日(木)~2月21日(水)
※展示解説書には2月18日までとあります
会 場:上里町立郷土資料館特別展示室 (児玉郡上里町七本木67)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上里町内では、これまでに大小合わせて、150か所以上もの遺跡が確認されており、部分的ではありますが現在
まで発掘調査が行われてきました。これら遺跡の調査によって、かつて町に暮らした人々の様子が今、少しづつで
すが明らかになってきています。
本展は、今から1,000年ほど前の平安時代(744~1192)の人々を特集します。特にこの時期の9世紀~12世紀に
かけては、平安時代の半ばから後半にあたり、歴史学では「王朝時代」とも呼ばれます。
この頃、上里町はどのような時代で、そこに暮らした人々はどんな日々を過ごしていたのでしょうか。これまで
の調査結果から考えたいと思います。 上里町立郷土資料館
《あいさつ文から抜粋引用》
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
を観覧してきました。
今年のNHK大河ドラマは『光る君へ』であり、この主人公である紫式部が『源氏物語』を書き上げたのも
この時期ですので、この時代に合わせた企画展とも言えるかも知れません。
本企画展は、
はじめに
第1章 王朝時代以前のかみさと
1-1奈良時代から平安時代初めの集落
(1)田通遺跡
(2)北稲塚遺跡
(3)寺西遺跡
(4)油免遺跡)
1-2王朝以前の集落の特徴
(1)土師器と須恵器の利用
(2)武蔵型甕の使用
(3)円面硯と帯金具の出土と地方役人の影
(4)古墳と埴輪の出土 集落の人々のご先祖様?
第2章 王朝時代のかみさと
2-1王朝時代の遺跡群
(1)田中に志遺跡
(2)日月遺跡)
(3)水引塚遺跡
(4)中長遺跡
(5)長幡部周辺出土土器
2-2王朝時代とは、どんな時代だったのか 王朝時代の特徴
(1)条里制水田の開発
(2)灰釉陶器の流入
(3)羽釜の登場
(4)須恵器の色彩と変化
(5)碗の変化」
(6)「ての字皿」の登場とその謎
第3章 まとめ 王朝時代の以前と以後
(1)集落の立地と支配者の変化
(2)流通 モノの動きの変化
(3)都の文化・思想の流入
おわりに 上里町の王朝時代の主人公
から構成されていて、沢山の解説パネル・写真と出土品が展示されていました。
観覧日:令和6年(2024)2月8日(木)